2010年02月19日 (金)
先月の27日、アメリカの作家のジェローム・デイヴィッド・サリンジャーが亡くなりました。91歳でした。代表作である『ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライ』は、日本でも『ライ麦畑でつかまえて』という野崎孝さんのみごとな邦題で知られていて、たいへんひろく読まれてきましたし、いまなお読まれています。作家の村上春樹さんが数年前に新訳を出してこれまた話題になったことは記憶に新しいことです。
『ライ麦畑』という本は、大きな社会的な事件のなかでも、話題を集めてきました。いちばんのスキャンダルは、ジョン・レノンを暗殺した青年がこの本を所持していたことです。愛読書で、犯行の直前まで読んでいました。1980年のことでした。また、レーガン大統領の暗殺をはかった青年もこの本の愛読者でした。1981年のことでした。
ふつうに考えれば、この本が熱狂的なファンの多いロングセラーであることの証拠にすぎないのですが、事件が事件ですし、そんなに危険な本なのか、という疑いの目で見るひともアメリカにはいまなお少なからず存在しています。
では、著者のサリンジャーは、自分の書いた小説がこんなようなとんでもない影響力をもってしまっていることをどう思っていたのでしょう。そもそも広く読まれていることをどう考えていたのでしょうか。
じつは、それが、ほとんどわからないのです。なぜなら、インタビューなどはもちろんのこと、サリンジャーは人前に出ることを嫌い、かなり早くに、自分の屋敷にひきこもってしまったからです。現代アメリカ文学の世界には、おもしろいことに、姿を見せようとしない作家が何人かいますが、サリンジャーはその筆頭格であり、先駆者であった、と言っていいかもしれません。
なぜ人前に出たがらないのか? なぜひきこもろうとするのか? どうして世間との接触を絶つのか?
これは、かれの作品を読むと、わかってきます。そして、それがかれの作品の現代的なところでもあれば、また、魅力の源にもなっています。いまなお多くのファンが誕生しつづけているのも、そんへんに理由があるように思われます。
ロングセラーである『ライ麦畑』ですが、語り手は16歳の高校生の少年です。この少年のいかにも若者らしい口調で話は進んでいきます。
本が出たのは1951年ですが、当時だんぜん新鮮だったのは、そのいかにも若者らしい口調でした。こんな自然な話し言葉で小説を書いてもかまわないのか、とみんなたいへんおどろきました。
はやりの若者のスラングを散りばめていたわけではありません。じつに自然な若者らしい口調で書かれていたのです。たとえば、いちばん印象に残るのは、しょっちゅう口にだされる「kind of」という言葉です。日本語にすると、「なんか」、になるこの言葉が頻繁につかわれています。
「ここにいてもおもしろくない」と言うかわりに、「ここにいても、なんか、おもしろくない」と言うのです。
「なんか」が入ると、文章は、断定の度合いが、だんぜん弱まってきます。ですから、自分が言っていることにいまひとつ自信がない、あるいは、自分が言っていることをすこし曖昧にしておきたい、自分が言っていることに責任を持ちたくない、というときには、この「なんか」という言葉は、重宝なスパイスのような役割を果たしてくれます。
『ライ麦畑』の語り手は16歳の高校生ですから、じぶんの発言にいまひとつ自信がないかんじが出てくる「kind of」という言葉の混じった話し方はとてもリアルだったのです。
しかし、この主人公には言いたいことがたくさんあります。不満がいっぱいです。不満の塊だと言ってもいいくらいです。
たとえば、『ライ麦畑』で印象的なもうひとつの言葉「phony」には、少年の不満や憤懣がぎっしり詰めこまれています。「phony」とは、「ニセモノ」「インチキ」という意味ですが、この16歳の少年は、自分の周囲のいろんなもの、いろんな人物を、この言葉で罵倒するのです。あんなのインチキだ、あいつはニセモノだ、という具合にです。サリンジャーが『ライ麦畑』でたくさんつかったおかげで、この言葉は流行語にさえなりました。
でも、不満がいっぱいのこの少年は、それを人前ではっきりと表明して怒りをぶつけるようなことはほとんどしません。言いたいことはあるし、不満はあるのですが、それをぶちまけることはしないのです。「kind of」という言葉を散りばめながら、不満を言いつづけるばかりです。そしてそのうち、その不満は溜まり、少年の心のなかには、別な確信のようなものが生まれてきます。
どうせわかってもらえない。
みんなは誤解する。
みんなは曲解する。
なにしろ、みんな「ニセモノ」なんだし。
『ライ麦畑』の危険な、と言ってもいいような魅力は、語り手のこのような思いがひしひしと伝わってくるところにあります。
おまけに、この語り手は、その悩みをだれにも打ち明けません。それはそうでしょう、だって、みんな、「ニセモノ」なのですから。
サリンジャーの小説には、神経過敏な若者がたくさん出てきますが、共通しているのは、ひとりで苦しんでいることです。他人と接触しようとしないことです。そして、そのままに突き進んでいくことです。
サリンジャー以前にも、若者を主人公にした小説は、言うまでもなく、たくさんありました。しかし、そのほとんどは、成長小説です。若者が悩みを抱えながら、いろんな経験をし、だんだん成長して大人の仲間入りをしていくという類のものです。「ニセモノ」ばかりかもしれない大人の世界に、社会に入っていくという類のものです。「ニセモノ」を受けいれることも、ときには、大人になるためには重要な手続きになったりもしました。優先順位としては、大人と社会がまず最終目標としてあって、若者は、「そこへ至るプロセスの一部」にすぎませんでした。
しかし、『ライ麦畑』は、その「若者」を最優先したのです。「大人」の予備軍ではない、それ自体独立した価値観をもった人間として、つかまえたのです。「若者」という独立したジャンルを発見した、と言ってもいいでしょう。
サリンジャーの作品は、成長小説からもっとも遠いところにあります。『ライ麦畑』が、イギリスの成長小説の名作であるディケンズの『デーヴィッド・カパフィールド』を、あんなの、くだらないよ、と罵倒するところからはじまるのも象徴的です。
サリンジャーは、成長を拒否するのです。「大人」になる必要なんかない、「ニセモノ」になんかなる必要はない、と言うのです。そして、さらには、「社会」におもねる必要などない、とも。
サリンジャーの人嫌いぶりには、そんな「若者」の純粋さがうかがえます。
「若者」というものが「独立した大きなジャンル」として台頭してきて「若者文化」という「カウンターカルチャー」を形成するようになるのは1960年代になってからのことです。そのころにはもうサリンジャーは作品の発表をやめていました。しかし、本の人気はダントツでした。
NHKオンラインより/投稿者:管理人 | 投稿時間:23:05

















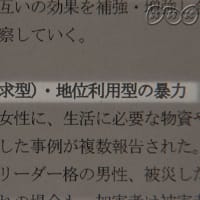

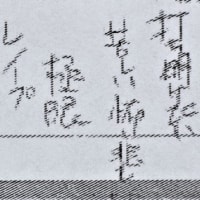






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます