2012年イタリア・エミリア地震の避難所(フィナーレ・エミリア市)

日本では大規模災害が起きると、学校の体育館が避難所に転用されるケースが多い。しかし、先進国ではこうした対応はあり得ない。新潟大学大学院の榛沢和彦特任教授は「日本の避難所は欧米からみればハラスメント状態だ。『避難所の生活を改善すると、被災者の自立が遅れる』という主張がされるなど、根本的な誤解がある」という――。(聞き手・構成=ノンフィクションライター・山川徹)
■環境を改善しないと災害関連死は減らない
――榛沢先生は、災害関連死や災害関連病を防ぐために避難所の環境改善を訴えてきました。災害関連死は、適切な医療や支援によって0にできると言われています。しかし災害が発生するたびに、災害関連死の事例が報告されます。なぜ、状況は改善しないのでしょうか。
災害が発生すると、一般的に急性期(発災から1週間程度)の医療が重視されがちです。しかし急性期だけに力を入れても、根本的に何も解決しません。何よりも、改善すべきは避難所の環境です。
例えば、交通事故が頻繁に起きる道路があったとします。救急車の数を増やしても、事故は減りません。急性期の医療を重視する災害支援は、救急車をたくさん走らせている状況と言えばいいでしょうか。でも、本来なら道路状態や交通状況などを早急に見直す必要があります。そう考えると、災害関連死を減らすためにも、いち早く環境改善に取り組まなければならないのが、いわゆる「雑魚寝の避難所」です。その風景は、約100年前の関東大震災から何も変わっていないのですから。
■イタリアでは家族ごとにテントで生活していた
――避難所に対して問題意識を持ったきっかけを教えてください。
私が災害医療にかかわるようになったのは、2004年の新潟県中越地震からです。避難所での生活や車中泊などが、エコノミークラス症候群のリスクを高めると初めて気づきました。その後、07年の新潟県中越沖地震、08年の岩手・宮城内陸地震、3.11、2016年の熊本地震などで避難所の医療支援に入りました。
本当の意味で、日本の避難所が抱える問題を突きつけられたのは、2012年です。5月にイタリア北部を大地震がおそいました。その2カ月後、イタリアを訪れて、避難所を視察し、驚きました。広場に大型テントが整然と並んでいる。歩いて入れるほど屋根が高いテントは被災した家族ごとに割り当てられていました。カーペットが敷かれ、人数分のベッドや冷暖房装置も設置されていました。「雑魚寝の避難所」との差に目を見張りました。
■「非常食」があるのは日本だけ
トイレやシャワーは、移動のコンテナ式でスタッフによって清潔に保たれていました。なかにはコインランドリーや子どもの遊具を備えた避難所もありました。食堂も、巨大テントで、キッチンコンテナで調理したばかりの料理を口にできる。欧米では被災者に温かい食事を提供するのが、当たり前になっていました。「非常食」があるのは日本だけなんですよ。
コンテナ製トイレ外観(フィナーレ・エミリア避難所、2012年7月)

コンテナ製トイレ内部(フィナーレ・エミリア避難所、2012年7月)

日本では、避難所で、被災者が並んでおにぎりや弁当を受け取るケースをよく目にしますが、イタリアでは避難所のスタッフが配膳などを担当していました。担当者の言葉が忘れられません。「温かくておいしいものを食べれば元気になるだろう。それが、生活を立て直す上ではもっとも大事なんだ」と。その数カ月前まで3.11の避難所の実態を目の当たりにしたせいか、本当に衝撃を受けました。
(2016年アマトリーチェ避難所の食事。イタリアでは被災地でもできたての料理が食べられる。)

――日本の避難所とは根本的になにかが違う気がしますね。
避難所は、被災したすべての人が安心し、健康的に過ごせて、生活再建へ向けて力を蓄えてもらう場――ヨーロッパやアメリカでは、そうした意識が共有されているのです。日本は災害大国とよく言われますが、避難所運営だけを見てもアメリカやヨーロッパの方が格段に進んでいます。イタリアも災害が多い国です。地震だけではなく、山火事も水害もひんぱんに起きます。アメリカもそう。毎年のように、ハリケーンやトルネードにおそわれています。そうしたなかで、避難所の環境改善や災害対策が進みました。イタリアでは全人口の0.5%にあたる人たちに必要なテントやキッチン、トイレ、ベッドを備蓄しています。10年以内に津波地震が予想されているシチリアでは今後は3%まで増やす予定だそうです。
■日本での「美談」が欧米では「人権侵害」
またイタリアでは、災害が発生すると政府から州の市民保護局に対して、72時間以内に避難所を設置するよう指令が下ります。ここでのポイントは、指令を受けるのは、被災した自治体の市民保護局ではなく、その周辺で被害をまぬがれた自治体の市民保護局という点です。日本では被災した自治体の職員が避難所に寝泊まりして、管理、運営を担当するでしょう。当然ですが、被災自治体の職員も、被災者なんです。避難所運営に奔走する自治体職員の姿が、日本では美談として取り上げられますが、アメリカやヨーロッパなら、人権侵害、あるいはハラスメントとして問題になるでしょうね。
――なるほど。避難所のあり方がハラスメントに該当する場合もあるんですね……。
避難所が、被災者の立場や人格を尊重しないハラスメント状態になっていることを支援者だけでなく、被災者自身も気づいていません。なかには、食事などの環境をよくすると被災者が自立せずに避難所に居着いてしまうと口にする運営者もいます。
■海外にとって雑魚寝の避難所は「クレイジー」
2018年の西日本豪雨では4カ月、毎日朝に冷たいおにぎり、お昼に同じ菓子パンを出し続けた避難所もありました。被災した人にとっては、要望を出したり、毎日出るおにぎりや菓子パンを断ったりしたら、もう支援がこないかもしれないという不安感もあり、泣き寝入りするしかない。被災者がガマンを強いられるのは食事だけではありません。寒くて広い体育館で、冷たい床の上にあり合わせの畳やマット……なかには段ボールやビニールシートを敷いて眠る。これでは身体を休めることができません。3.11の避難所を撮影した写真をアメリカやヨーロッパの支援者に見せたところ「クレイジー……」と絶句された経験があります。
「雑魚寝の避難所」の改善には、簡易ベッドを導入すべきなのですが、まだまだ進んでいません。自宅では畳に布団を敷いて寝ているから、避難所でも簡易ベッドは必要ないと考えている人が多いのです。もちろん平時なら問題ありませんが、硬い床に一日中すわって過ごすと足腰に想像以上の負担がかかります。3.11のある避難所では、1000人中、30人の高齢者が歩行困難になりました。足腰が痛んでトイレに立つのがおっくうになり、水分を控える被災者も少なくなかった。そうなると脱水状態で血液が濃くなり、エコノミークラス症候群や脳梗塞、心筋梗塞を発症しやすくなるという悪循環に陥ってしまう。それに、雑魚寝は床にたまった埃にウイルスや細菌が付着し、感染症のリスクも高くなる。
■市町村には問題意識が蓄積されにくい
避難所改善などの問題意識は、県の防災担当者には、少しずつ浸透してきたように感じます。しかし被災者支援の中心となる市町村の職員にまでそうした意識が共有できているかと言えば、疑問です。市町村の職員はたいてい3年程度で部署を異動する。経験や問題意識が蓄積されにくい上に、市町村には予算もない。
以前、ある自治体でベッドやトイレ、キッチンを48時間以内に避難所に届ける仕組み作りをしましょうと提案したところ「予算がない」「水や食べ物が先だろう」という反応でした。もちろん水や食べ物も大切ですが、同時にベッドやトイレの導入、温かい食べ物の提供も進めていかなければ、災害関連死は防げないのですが……。
――とはいえ、西日本豪雨や北海道胆振地震の避難所には、簡易ベッドが速やかに導入されたと聞きました。環境改善が進んでいるのではないですか。
うーん……。まだ簡易ベッド導入のシステムが構築されたとは言えませんね。
例えば、北海道胆振東部地震では、その前年に北見市にある日本赤十字北海道看護大学が研究用に400台の段ボールベッドを購入していました。加えて、発災当日、北海道の危機管理にたずさわり、寒冷地の避難所の危険性を訴え続けてきた北海道赤十字看護大学の根本昌宏先生が偶然、札幌にいたんです。根本先生がすぐに道庁で簡易ベッド導入を提言し、保管していたベッドを避難所に送ることができた。災害時の危機管理の専門家で、道庁の災害対策職員とも顔見知りだった根本先生だから、簡易ベッドの早期導入を実現できたと言えるかもしれません。非常に幸運な事例だったと言えるでしょう。
■災害専門省庁の設立が急務
一方で、私はうまくいかなかったケースも目の当たりにしました。2019年の台風19号では、総務省は発災後かなり速やかに福島、長野、茨城、千葉の4県の担当部署に連絡し、段ボールベッドがどのくらい必要か聞きとりを行いました。その結果、各県とも2000台の希望があったそうです。そして発災4日後ごろには段ボールベッド会社から送付してもらったそうなのですが、その保管場所は自衛隊基地などでした。県の担当者も保管場所や送付先を把握していなかったらしいんです。災害対策の問題点のひとつとして、避難所の設置部署と運営部署が違うことがあげられます。発災するまでの事前の準備は、総務省の管轄で、発災後は厚労省に代わる。
――縦割り行政の弊害ですね。
その最たるものですね。だからこそ、その弊害をなくすためにも災害専門省庁の設立が急務です。専門省庁がないから、いつも発災後に補正予算をつけて対応するしかない。一方イタリアでは災害関連の国家予算は約3000億円。この予算で、テントやトイレ、キッチンなどを備蓄し、搬送用のトレーラーやトラックのメンテナンスを行っています。
ただこうしたイタリアの仕組みがつくられたのも、最近の話なんです。イタリアで災害対策を行う市民保護庁が発足したのが、約40年前。それまでは、現在の日本のように、災害支援は市町村に丸投げでした。しかし1980年に、イルピニア大地震が発生し、建物の倒壊などで約3000人が亡くなりました。被害はそれだけに止まらずに、災害対応の遅れで、約1万人が避難生活で、病気を発症し、なかには命を落とす被災者も出ました。そうした反省から、市民保護庁が誕生したんです。
■「生命を守る」だけでなく「生活を早く戻す」
――イタリアは“災害関連死”を教訓として、災害専門省庁をつくったということですね。
そうとも言えますね。もうひとつ日本の災害対策から抜け落ちている視点が“市民社会保護”という考え方です。災害後に人々の暮らし、地域コミュニティーをできるだけ早く戻すこと。つまり生命を守るだけでなく、市民生活の復旧を第一に考えた災害対応です。
(山川徹『最期の声 ドキュメント災害関連死』(KADOKAWA)山川徹『最期の声 ドキュメント災害関連死』(KADOKAWA)

実は、これは戦争と切り離せない考え方でもあるんです。相手から攻められたとき、市民の生命をどのように守り、暮らしをどう復旧させるのか……。それに、戦争はたくさんの物を消費しますよね。消費ばかりでは戦争は続けられない。だからこそ、被害にあった市民に早く日常生活に復帰してもらって、物を生産して経済を回してもらう必要がありました。市民生活の復旧、復興があり、初めて戦争が続けられる。
こうした考え方が、欧米では災害対応にも生かされている。まずは市民の命を助ける。その後、いち早く社会復帰を果たしてもらう。それが、市民生活の保障や経済の早期復旧につながり、被災者自身のためになると受け止められています。
現状のまま、南海トラフ地震や首都直下地震が発生したらどうなるのか……。新型コロナでは、高齢者や基礎疾患を持つ人のリスクが明らかになりました。それは災害でも同じでしょう。このままでは避難所で、高齢者や基礎疾患を持つ人は過酷な生活を強いられてしまいます。災害時の被災者支援は、個人救済ではなく、公共の福祉です。だからこそ、何よりも避難所の環境改善を急ぐ必要があるのです。
榛沢 和彦
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 特任教授
(聞き手・構成=ノンフィクションライター・山川徹)
2022/03/10 17:00
PRESIDENT Online

















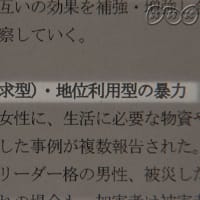

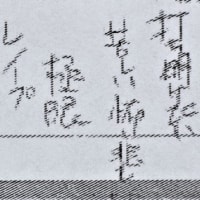






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます