『徒然草』を書いた作者には、「吉田兼好(よしだ けんこう)」の他に「兼好法師(けんこう ほうし)」という呼び方がある。
「兼好法師」の「法師」ってなんなのだろう?
法師は、『西遊記』の「三蔵法師」だとか、『耳なし芳一』の「琵琶法師」なんかで有名な例のソレで、ようするにお坊さんの事だ。
ところで、「法師」とは仏教のお坊さんに対する尊称であるのだが、お坊さんそのものを指し示す場合にも使われた。
「法師」は、現代語で言うなら「先生」という呼び名と似ている。
学校の先生の正式な職業名は「教員」である。「先生」は職業名ではない。
例えば、学校の先生がレンタルビデオ屋の会員になる時。職業欄に自分の職業を記入しなきゃいけない場合は『学校の先生』なんてには、まずマトモな先生なら記入しないはず、「教員」と記入するだろう。
「先生」はあくまで基本的には「尊称」で、他人がその地位にある人を尊敬して用いる言葉だ。だけど、教職につく人達をカンタンに指し示す場合にも「先生」は使われる。
吉田って教師がいたら、当然に生徒はその人を「吉田先生」と呼ぶだろう。
そして、昼の職員室で弁当食ってんのは「先生たち」だ。
現代風に例えて言うなら、「法師」とは「先生」である。
法師の正式な職業名は特定できないけど、「僧」か「仏僧」あたりが適当だろう。
そもそも僧には、座りが悪いけど正式な個人名なんか本来ない。「釈迦の弟子のだれそれ」としか言えない連中なのだ。名前すら捨ててる連中の本名を問題にするのすら馬鹿らしい。
だから、『西遊記』の「三蔵法師」がレンタルビデオを借りる時は、「玄奘三蔵」と名のるべきで、「三蔵法師」と名のるなら、自分で自分は「三蔵先生」だと言っているのに等しい。たぶん、マトモな僧なら自分で自分を「法師」とは名のらないはずなんだけど、調査不足で確証はない。
だから、「兼好法師」という呼び方も、じつは「吉田兼好」と同じで、あくまで他人からの「呼び名」なのだ。
じゃあ、『徒然草」の著者を現代の我々はなんと呼べば良いのか?
好きに呼べばいい。
「吉田兼好」でも「兼好法師」でもマルだ。
ただ、それじゃあまりに乱暴なので、正解らしき事を言うなら「兼好(けんこう)」と名のっていた僧が『徒然草』の作者だ。
でも、それはそれだけの話で、だから『徒然草』の作者は「兼好」だとも言い切れないのが古典の辛いところ。書いた本人が自分をなんて呼んでもらいたかったのかが、すっかり抜け落ちている。










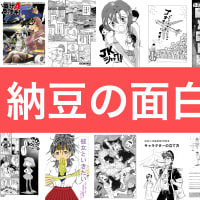

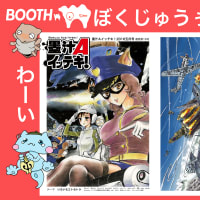
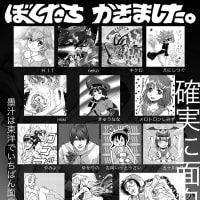


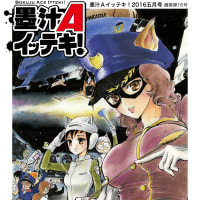



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます