〔一部引用。全文は「かわむらひさこのHP」から(リンク)〕
弁護人の主張する控訴の趣意の要旨及び控訴の趣意の補充は次のとおりである。
1 はじめに
控訴審の冒頭にあたり、控訴趣意書及び控訴趣意補充書の要旨を陳述する前に、原判決の基本的問題点について述べることする。
被告人は、30数年間、教育一筋に携わり、定年の年、都立板橋高校で社会科、生活指導などを行っていた元教員であるが、本件においては、平成16(2004)年3月11日に行われた都立板橋高校における午前10時開式予定の卒業式開式前の午前9時42分ころから同9時45分ころまでの間の被告人の行為が問題とされている。
この短い時間の、被告人の保護者に対する語りかけ、教頭、校長らの制止、退場要求にすぐに従わず抗議した行為が卒業式の遂行業務を妨害したとして問題とされている。
原判決は、被告人の上記行為に対して威力業務妨害にあたるとして有罪とした。
しかしながら、原判決の認定は、次のような問題点が存すると考える。
第1に、被告人の上記行為に対し、刑罰法規を適用して有罪としたことについてである。このことは、原判決が、本事件において、真に守られるべき保護法益が何かということについての深い考察を欠いたためと考えられる。
この3月11日の都立板橋高校の卒業式は、10時少し過ぎに始まり、式次第に従って予定どおり進行し、終了している。都立板橋高校を含め都立高校においては、開式が少し遅れることはよくあることで、この板橋高校の卒業式においては卒業式に参加した保護者を含め、卒業生も式が遅れたという認識すらなかったのである。
また、卒業式の最後に卒業生らが選んだ「旅立ちの歌」を盲人の卒業生のピアノ伴奏で、卒業生全員で合唱したこともあって、卒業生、保護者、教員にとっても近年にない感動的な卒業式であったと言われたものであった。
卒業式の意義は、高校3年間の教育課程を学び終え、卒業し旅立っていく卒業生を、その卒業生と共に3年間教えた教員と家庭で育ててきた保護者とで祝福し合うところにあると考えられる。その意味で、卒業式の主役はあくまでも卒業生であるといえる。被告人は、この卒業式が開式する前に、既に板橋高校の校舎からも離れており、卒業式そのものの遂行業務を妨害するというようなことは全くなかったのである。また、被告人が卒業式の開式前、保護者に対して呼びかけた内容も、「国歌斉唱の時、できたら着席お願いします。」と述べたもので、卒業式そのものの進行を妨害するものではなかったのである。このような実態を有した卒業式に対して、「卒業式典の遂行業務を妨害した」ものとして、刑罰法規を適用し有罪としたことに対し、多くのマスコミが厳しく批判したところである。
以上のことは、原判決が、卒業式開式前に行われる行為に関して、守るべき保護法益が何かについての詰めた検討を欠いたためと考えられる。すなわち、本件で被告人が保護者に語りかけを行った時間は、私語が禁止される時間ではない。現に被告人が保護者に語りかけを行った時間は、既に体育館の中に入った保護者の中には、隣の保護者と語り合ったり、知り合いの保護者と語りかけるため、席を立ったりしていたのである。仮に被告人でなく、卒業式に出席するために参加していた保護者の一人が被告人と同じように他の保護者に語りかけを行い、教頭、校長らの制止、退場要求にすぐに従わず、抗議した場合を考えてみれば、午前10時開式予定の卒業式の約15分も前に終わっている行為に対して、「卒業式典の遂行業務を妨害」したとして、処罰の対象とすることの不当性はより鮮明になると考える。現に、原審公判においても、北爪校長は、被告人を体育館から出した後、警察を呼ばなかった理由について、新聞社から取材を受け、「既に、要求に従って体育館から出ていたので、呼ぶ必要がないと考えた」旨答えている。このことは、卒業式当日の時点では、管理職である校長自身が、被告人が卒業式開式前に体育館を出たことにより、被告人が卒業式典そのものの進行を妨害することはないと考えたことを意味すると考えられるのである。このことは、また、本件についての公訴提起そのものに対する疑問に繋がっていくものと考えられるのである。
第2に、原判決は、起訴事実、すなわち、被告人の保護者に対する語りかけ、教頭、校長らの制止、退場要求にすぐに従わず抗議した行為すべてを有罪としたことにより、通常表現の自由の範疇に考えられる行為をも処罰対象としたことを意味し、表現の自由に属する行為を不当に制限する内容となっている。
被告人の保護者に対する短い時間の語りかけの内容は、平成15(2003)年10月23日に都教委が教職員に対して一律に国歌斉唱時の起立、斉唱を命じ、従わなかった場合は懲戒処分に付するとした通達(以下、「10・23」通達)に関する説明であり、また、最後は保護者に対して「国歌斉唱の時、できたら着席お願いします。」と呼びかけたものである。この発言自体は、校長ら管理職の意に添わないものであったとしても、当然に表現の自由の保障の範疇に入るものである。
なお、校長が板橋高校の卒業式の実施要項を作成するにあって基になった10・23通達に関しては、昨年9月21日、東京地方裁判所で憲法19条で保障された思想、良心の自由を侵害するとともに、教育基本法10条1項で禁止する不当な支配に当たるとの判断が示されているところである。また、10・23通達そのものは、校長、そして教職員に対して向けられたもので、保護者らはその対象となっていないことも留意されるべきである。
第3に、原判決は上記判断と関連する事実として、卒業式開式前に被告人が保護者に対してサンデー毎日の記事のコピーを配布していたのを教頭が制止し、その後、教頭が被告人が保護者席と卒業生席との間の中央付近に行くのについていき、被告人が保護者に対する語りかけをした最初からその制止を行っていた旨認定している。これは、起訴段階で、検察官が被告人の行為を刑事罰の対象とするため、構成された事実を含んでいると考えられる。被告人の保護者に対するコピー配布そのものを教頭が制止したとする事実認定、及び被告人が保護者に対する語りかけを行った最初の時点では、被告人の側にはだれもおらず、被告人はそのような中で話しており、教頭ないし校長が被告人の側にきたのは、被告人が最後に保護者に対する呼びかけを行った直後か、その終りのころであったのであり、これと異なる原判決の事実認定は誤っていると言わなければならない。
被告人の保護者に対する語りかけが、教頭なりからの制止がないところでなされたということになれば、その語りかけ自体が、何ら問題となるものでなかったことがより明らかになるといわければならない。その意味で、この点に関する事実認定の誤りは、法令適用の誤りと密接に結びついていると言わなければならない。
さらに、このことは、問題とされた被告人の行為、すなわち、第1点として、被告人の保護者に対する語りかけ、呼びかけが正当か否か、第2点として、教頭、校長らの被告人を制止したことの意味、制止、退場要求が妥当か否か、第3点として、被告人が校長らの退場要求にすぐに従わず抗議した行為が正当か否か、それぞれについて具体的に検討することの必要性を示していると言わなければならない。
本控訴審においては、以上の点を踏まえて、慎重に審理されることを切望する次第である。
2 法令適用の誤り
弁護人が主張する第1の控訴理由は、原判決の認定事実(教頭による被告人の週刊誌コピー配布の制止及び保護者への呼びかけの制止の存在を含む)を前提とする法令適用の誤りである。これには、①構成要件該当性判断の誤り②違法性阻却事由に関する判断の誤り③憲法21条違反が並列的に含まれる。
控訴趣意補充書(3)
2007(平成19)年10月2日
弁護人の主張する控訴の趣意の要旨及び控訴の趣意の補充は次のとおりである。
1 はじめに
控訴審の冒頭にあたり、控訴趣意書及び控訴趣意補充書の要旨を陳述する前に、原判決の基本的問題点について述べることする。
被告人は、30数年間、教育一筋に携わり、定年の年、都立板橋高校で社会科、生活指導などを行っていた元教員であるが、本件においては、平成16(2004)年3月11日に行われた都立板橋高校における午前10時開式予定の卒業式開式前の午前9時42分ころから同9時45分ころまでの間の被告人の行為が問題とされている。
この短い時間の、被告人の保護者に対する語りかけ、教頭、校長らの制止、退場要求にすぐに従わず抗議した行為が卒業式の遂行業務を妨害したとして問題とされている。
原判決は、被告人の上記行為に対して威力業務妨害にあたるとして有罪とした。
しかしながら、原判決の認定は、次のような問題点が存すると考える。
第1に、被告人の上記行為に対し、刑罰法規を適用して有罪としたことについてである。このことは、原判決が、本事件において、真に守られるべき保護法益が何かということについての深い考察を欠いたためと考えられる。
この3月11日の都立板橋高校の卒業式は、10時少し過ぎに始まり、式次第に従って予定どおり進行し、終了している。都立板橋高校を含め都立高校においては、開式が少し遅れることはよくあることで、この板橋高校の卒業式においては卒業式に参加した保護者を含め、卒業生も式が遅れたという認識すらなかったのである。
また、卒業式の最後に卒業生らが選んだ「旅立ちの歌」を盲人の卒業生のピアノ伴奏で、卒業生全員で合唱したこともあって、卒業生、保護者、教員にとっても近年にない感動的な卒業式であったと言われたものであった。
卒業式の意義は、高校3年間の教育課程を学び終え、卒業し旅立っていく卒業生を、その卒業生と共に3年間教えた教員と家庭で育ててきた保護者とで祝福し合うところにあると考えられる。その意味で、卒業式の主役はあくまでも卒業生であるといえる。被告人は、この卒業式が開式する前に、既に板橋高校の校舎からも離れており、卒業式そのものの遂行業務を妨害するというようなことは全くなかったのである。また、被告人が卒業式の開式前、保護者に対して呼びかけた内容も、「国歌斉唱の時、できたら着席お願いします。」と述べたもので、卒業式そのものの進行を妨害するものではなかったのである。このような実態を有した卒業式に対して、「卒業式典の遂行業務を妨害した」ものとして、刑罰法規を適用し有罪としたことに対し、多くのマスコミが厳しく批判したところである。
以上のことは、原判決が、卒業式開式前に行われる行為に関して、守るべき保護法益が何かについての詰めた検討を欠いたためと考えられる。すなわち、本件で被告人が保護者に語りかけを行った時間は、私語が禁止される時間ではない。現に被告人が保護者に語りかけを行った時間は、既に体育館の中に入った保護者の中には、隣の保護者と語り合ったり、知り合いの保護者と語りかけるため、席を立ったりしていたのである。仮に被告人でなく、卒業式に出席するために参加していた保護者の一人が被告人と同じように他の保護者に語りかけを行い、教頭、校長らの制止、退場要求にすぐに従わず、抗議した場合を考えてみれば、午前10時開式予定の卒業式の約15分も前に終わっている行為に対して、「卒業式典の遂行業務を妨害」したとして、処罰の対象とすることの不当性はより鮮明になると考える。現に、原審公判においても、北爪校長は、被告人を体育館から出した後、警察を呼ばなかった理由について、新聞社から取材を受け、「既に、要求に従って体育館から出ていたので、呼ぶ必要がないと考えた」旨答えている。このことは、卒業式当日の時点では、管理職である校長自身が、被告人が卒業式開式前に体育館を出たことにより、被告人が卒業式典そのものの進行を妨害することはないと考えたことを意味すると考えられるのである。このことは、また、本件についての公訴提起そのものに対する疑問に繋がっていくものと考えられるのである。
第2に、原判決は、起訴事実、すなわち、被告人の保護者に対する語りかけ、教頭、校長らの制止、退場要求にすぐに従わず抗議した行為すべてを有罪としたことにより、通常表現の自由の範疇に考えられる行為をも処罰対象としたことを意味し、表現の自由に属する行為を不当に制限する内容となっている。
被告人の保護者に対する短い時間の語りかけの内容は、平成15(2003)年10月23日に都教委が教職員に対して一律に国歌斉唱時の起立、斉唱を命じ、従わなかった場合は懲戒処分に付するとした通達(以下、「10・23」通達)に関する説明であり、また、最後は保護者に対して「国歌斉唱の時、できたら着席お願いします。」と呼びかけたものである。この発言自体は、校長ら管理職の意に添わないものであったとしても、当然に表現の自由の保障の範疇に入るものである。
なお、校長が板橋高校の卒業式の実施要項を作成するにあって基になった10・23通達に関しては、昨年9月21日、東京地方裁判所で憲法19条で保障された思想、良心の自由を侵害するとともに、教育基本法10条1項で禁止する不当な支配に当たるとの判断が示されているところである。また、10・23通達そのものは、校長、そして教職員に対して向けられたもので、保護者らはその対象となっていないことも留意されるべきである。
第3に、原判決は上記判断と関連する事実として、卒業式開式前に被告人が保護者に対してサンデー毎日の記事のコピーを配布していたのを教頭が制止し、その後、教頭が被告人が保護者席と卒業生席との間の中央付近に行くのについていき、被告人が保護者に対する語りかけをした最初からその制止を行っていた旨認定している。これは、起訴段階で、検察官が被告人の行為を刑事罰の対象とするため、構成された事実を含んでいると考えられる。被告人の保護者に対するコピー配布そのものを教頭が制止したとする事実認定、及び被告人が保護者に対する語りかけを行った最初の時点では、被告人の側にはだれもおらず、被告人はそのような中で話しており、教頭ないし校長が被告人の側にきたのは、被告人が最後に保護者に対する呼びかけを行った直後か、その終りのころであったのであり、これと異なる原判決の事実認定は誤っていると言わなければならない。
被告人の保護者に対する語りかけが、教頭なりからの制止がないところでなされたということになれば、その語りかけ自体が、何ら問題となるものでなかったことがより明らかになるといわければならない。その意味で、この点に関する事実認定の誤りは、法令適用の誤りと密接に結びついていると言わなければならない。
さらに、このことは、問題とされた被告人の行為、すなわち、第1点として、被告人の保護者に対する語りかけ、呼びかけが正当か否か、第2点として、教頭、校長らの被告人を制止したことの意味、制止、退場要求が妥当か否か、第3点として、被告人が校長らの退場要求にすぐに従わず抗議した行為が正当か否か、それぞれについて具体的に検討することの必要性を示していると言わなければならない。
本控訴審においては、以上の点を踏まえて、慎重に審理されることを切望する次第である。
2 法令適用の誤り
弁護人が主張する第1の控訴理由は、原判決の認定事実(教頭による被告人の週刊誌コピー配布の制止及び保護者への呼びかけの制止の存在を含む)を前提とする法令適用の誤りである。これには、①構成要件該当性判断の誤り②違法性阻却事由に関する判断の誤り③憲法21条違反が並列的に含まれる。











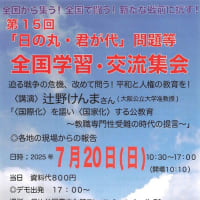

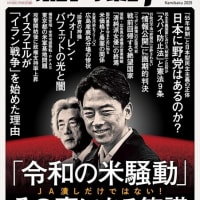
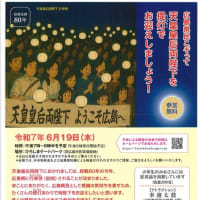


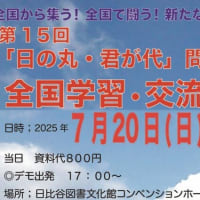





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます