=高校学習指導要領改訂と教科書(出版労連 教科書レポート) 2 各教科ごとの分析=
◆ (4)数学の特徴
1.内容増による負担増
現行の学習指導要領でも、内容が多く、消化しきれないという生徒・教員の声があったがも今回の改訂では、単位数を変更しても内容削減を行っていない。
むしろ、「期待値」や「仮説検定」、日常場面での数学的活動などが明記され、内容は確実に増えている。
これは、現場の実態に即していないのではないだろうか。高校生・教師にとっては、負担が増え、結果、内容の未消化となる危険性があると言える。
2.コンピュータの使用の明記
たとえば、数学Ⅰの(3)二次関数の中に、「(ア)二次関数の式とグラフとの関係について、コンピュータなどの情報機器を用いてグラフをかくなどして多面的に考察すること」とあり、コンピュータの活用を明示している箇所が随所に書かれている。
数学でコンピュータを活用することは確かに有効であるが、一方で、コンピュータが普段の数学の授業で使える学校はどれくらいあるのだろうか。
コンピュータルームは情報の授業等で常に埋まっており、また、プロジェクタやWi-Fi環境の設備も整っていない学校も多いのではないだろうか。また、タブレットPCの普及も遅れている感が否めない。
そのような状況の中で、解説書ならともかく、学習指導要領でコンピュータの活用を随所でうたうのはいかがなものか。家庭の経済格差が、学力格差を生む危険性すらはらんでいる。
3.統計偏重よりも自由度を
今回の改訂で、ベクトルが数学Cに移動した。
大学入学共通テストの出題範囲が、数学Ⅰ・数学Aと数学Ⅱ・数学Bであるから、ベクトルは実質、理系に移ったことになる。
そして、数学Bには「統計的な推測」が残り、統計の履修率を上げようというねらいが透けて見える。
統計も大切な分野であるが、ベクトルも同じく大切な分野である。これまで文系の生徒もベクトルを学んだのは何のためだったのだろうかという疑問が残る。
もっと生徒一人ひとりの興味にあった、自由度の高い学習指導要領であってほしいと切に願うものである。
『出版労連 教科書レポート No.61』(2018)
◆ (4)数学の特徴
1.内容増による負担増
現行の学習指導要領でも、内容が多く、消化しきれないという生徒・教員の声があったがも今回の改訂では、単位数を変更しても内容削減を行っていない。
むしろ、「期待値」や「仮説検定」、日常場面での数学的活動などが明記され、内容は確実に増えている。
これは、現場の実態に即していないのではないだろうか。高校生・教師にとっては、負担が増え、結果、内容の未消化となる危険性があると言える。
2.コンピュータの使用の明記
たとえば、数学Ⅰの(3)二次関数の中に、「(ア)二次関数の式とグラフとの関係について、コンピュータなどの情報機器を用いてグラフをかくなどして多面的に考察すること」とあり、コンピュータの活用を明示している箇所が随所に書かれている。
数学でコンピュータを活用することは確かに有効であるが、一方で、コンピュータが普段の数学の授業で使える学校はどれくらいあるのだろうか。
コンピュータルームは情報の授業等で常に埋まっており、また、プロジェクタやWi-Fi環境の設備も整っていない学校も多いのではないだろうか。また、タブレットPCの普及も遅れている感が否めない。
そのような状況の中で、解説書ならともかく、学習指導要領でコンピュータの活用を随所でうたうのはいかがなものか。家庭の経済格差が、学力格差を生む危険性すらはらんでいる。
3.統計偏重よりも自由度を
今回の改訂で、ベクトルが数学Cに移動した。
大学入学共通テストの出題範囲が、数学Ⅰ・数学Aと数学Ⅱ・数学Bであるから、ベクトルは実質、理系に移ったことになる。
そして、数学Bには「統計的な推測」が残り、統計の履修率を上げようというねらいが透けて見える。
統計も大切な分野であるが、ベクトルも同じく大切な分野である。これまで文系の生徒もベクトルを学んだのは何のためだったのだろうかという疑問が残る。
もっと生徒一人ひとりの興味にあった、自由度の高い学習指導要領であってほしいと切に願うものである。
『出版労連 教科書レポート No.61』(2018)



















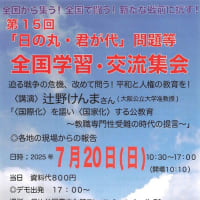




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます