
大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」とコラボした展示会に国立博物館に出かけました。この時代に浮世絵だけでなく、青本や黄表紙などの娯楽本が売れたということは、いかに識字率が高かったかわかります。特に、貸本屋や瓦版の普及により庶民が情報を得る機会が多かったことは、他の都市と比べても特筆すべき点だと考えられます。黄表紙の発行部数は、蔦重が活躍を始めた当初は250部程度だったそうですが、時代とともに拡大し、5千部から7千部に達する作品もあったということですから、驚きです。
江戸時代後期の江戸の人口は約100万人とされ、同時期のロンドンは約86万人、パリは約55万人、北京は110万人と推定され世界有数の都市の一つでした。また、江戸の町人の識字率は 70~80%に達していたとする研究もあります 。同時期のヨーロッパでは都市部でも50%以下の地域が多く、庶民が書物を読む機会は限られていたということです。
江戸は識字率の高さだけでなく、上下水道の整備や商業の発展、文化の成熟など、非常に高度な都市機能を持っていたということです。あらためて日本という国の素晴らしさを感じました。
江戸時代後期の江戸の人口は約100万人とされ、同時期のロンドンは約86万人、パリは約55万人、北京は110万人と推定され世界有数の都市の一つでした。また、江戸の町人の識字率は 70~80%に達していたとする研究もあります 。同時期のヨーロッパでは都市部でも50%以下の地域が多く、庶民が書物を読む機会は限られていたということです。
江戸は識字率の高さだけでなく、上下水道の整備や商業の発展、文化の成熟など、非常に高度な都市機能を持っていたということです。あらためて日本という国の素晴らしさを感じました。











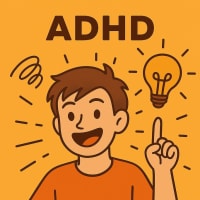
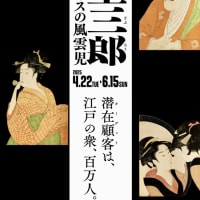













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます