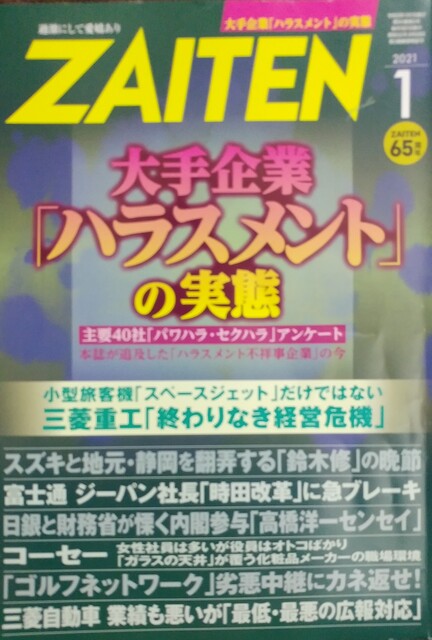●クビ切りは組合で選ぶ
そこに国鉄の不祥事が追い打ちをかけた。ヤミ手当の受給に、機関士の酒気帯び運転……。マスコミは国鉄の批判キャンペーンを展開。分割民営化に世論もなびいた。一方、国鉄では毎年1兆円の赤字が出て、出血が止まらない。こうして国鉄はついに解体されることになった。
誰を国鉄に残し、誰に転職を促すか──。国鉄内で「選別」が始まり、水面下で「リスト」作りが行われた。
民営化前、関西で列車乗務の仕事をしていた男性は、「50歳以上は会社を辞めてほしい」と圧力をかけられた、と振り返る。彼は辞め、残った同僚もすぐにJRを去った。最近、その理由を教えてくれたという。
「乗務が終わって職場に戻ったら、上司になった後輩から『ぼちぼち辞めたらどうや』と毎日言われる。みじめやった、と振り返っていました」
国鉄の内部事情に詳しい国鉄OB(60代)はこう証言した。
「社員を選別する際、その一つにどの労働組合に所属しているかが重要な要素だった」
このOBによれば、管理部門の人事担当には「K、D、T」という隠語があったという。Kは国労、Dは動労、Tは鉄労の意。隠語は元々、駅長や助役など現場責任者や管理者が使っていた。組合への直接介入は、不当労働行為に当たるからだ。声に出して言えない時は、指で“影絵のキツネ”を作った。逆にすると「K」に見えた。
「分割民営化の1年くらい前から『〇〇はKだ』『△△はDだ』という言葉が人事担当者間で露骨に飛び交ってた。なぜ労働組合で選別するかって? それが一番分かりやすいからですよ」
また別の国鉄OB(70代)はこう言った。
「優秀な社員と組合運動ばかりしている人だったら、どっちを残しますか」
●総評つぶしが狙い
国鉄改革は、何のための「改革」だったのか。首相として国鉄改革に政治生命をかけた中曽根康弘氏は、国鉄解体の狙いをかつて本誌でこう語った。
「総評を崩壊させようと思ったからね。国労が崩壊すれば、総評も崩壊するということを明確に意識してやったわけです」(96年12月30日号)
ルポライターで、86年に『国鉄処分』の著書を出した鎌田慧さん(78)は、国鉄解体の本質は(1)民活(民間活力)(2)国労つぶし──この2点にあったと指摘する。
「『民活』という名で公共性をなくし、大企業が国鉄財産を乗っ取ることを考えた。そのためには、国労という最強の抵抗勢力であった労働組合が邪魔だった。そこで楔を打ち込み、壊滅を図ったのです」
国鉄当局は86年7月、全国に「人材活用センター」を設置。余剰人員と見なされた1万5千人の職員を送り込むと、草刈りやペンキ塗りなど本業とは関係のない仕事をさせた。センターは「首切りセンター」とも呼ばれ、将来への不安を抱いた職員が何人も自殺した。JRが発足すると、7628人を「清算事業団」に回し、3年後、最後までJR復帰を訴えた1047人のクビを切った。うち、国労組合員は966人を占めた。・・・・続きはこちら
そこに国鉄の不祥事が追い打ちをかけた。ヤミ手当の受給に、機関士の酒気帯び運転……。マスコミは国鉄の批判キャンペーンを展開。分割民営化に世論もなびいた。一方、国鉄では毎年1兆円の赤字が出て、出血が止まらない。こうして国鉄はついに解体されることになった。
誰を国鉄に残し、誰に転職を促すか──。国鉄内で「選別」が始まり、水面下で「リスト」作りが行われた。
民営化前、関西で列車乗務の仕事をしていた男性は、「50歳以上は会社を辞めてほしい」と圧力をかけられた、と振り返る。彼は辞め、残った同僚もすぐにJRを去った。最近、その理由を教えてくれたという。
「乗務が終わって職場に戻ったら、上司になった後輩から『ぼちぼち辞めたらどうや』と毎日言われる。みじめやった、と振り返っていました」
国鉄の内部事情に詳しい国鉄OB(60代)はこう証言した。
「社員を選別する際、その一つにどの労働組合に所属しているかが重要な要素だった」
このOBによれば、管理部門の人事担当には「K、D、T」という隠語があったという。Kは国労、Dは動労、Tは鉄労の意。隠語は元々、駅長や助役など現場責任者や管理者が使っていた。組合への直接介入は、不当労働行為に当たるからだ。声に出して言えない時は、指で“影絵のキツネ”を作った。逆にすると「K」に見えた。
「分割民営化の1年くらい前から『〇〇はKだ』『△△はDだ』という言葉が人事担当者間で露骨に飛び交ってた。なぜ労働組合で選別するかって? それが一番分かりやすいからですよ」
また別の国鉄OB(70代)はこう言った。
「優秀な社員と組合運動ばかりしている人だったら、どっちを残しますか」
●総評つぶしが狙い
国鉄改革は、何のための「改革」だったのか。首相として国鉄改革に政治生命をかけた中曽根康弘氏は、国鉄解体の狙いをかつて本誌でこう語った。
「総評を崩壊させようと思ったからね。国労が崩壊すれば、総評も崩壊するということを明確に意識してやったわけです」(96年12月30日号)
ルポライターで、86年に『国鉄処分』の著書を出した鎌田慧さん(78)は、国鉄解体の本質は(1)民活(民間活力)(2)国労つぶし──この2点にあったと指摘する。
「『民活』という名で公共性をなくし、大企業が国鉄財産を乗っ取ることを考えた。そのためには、国労という最強の抵抗勢力であった労働組合が邪魔だった。そこで楔を打ち込み、壊滅を図ったのです」
国鉄当局は86年7月、全国に「人材活用センター」を設置。余剰人員と見なされた1万5千人の職員を送り込むと、草刈りやペンキ塗りなど本業とは関係のない仕事をさせた。センターは「首切りセンター」とも呼ばれ、将来への不安を抱いた職員が何人も自殺した。JRが発足すると、7628人を「清算事業団」に回し、3年後、最後までJR復帰を訴えた1047人のクビを切った。うち、国労組合員は966人を占めた。・・・・続きはこちら