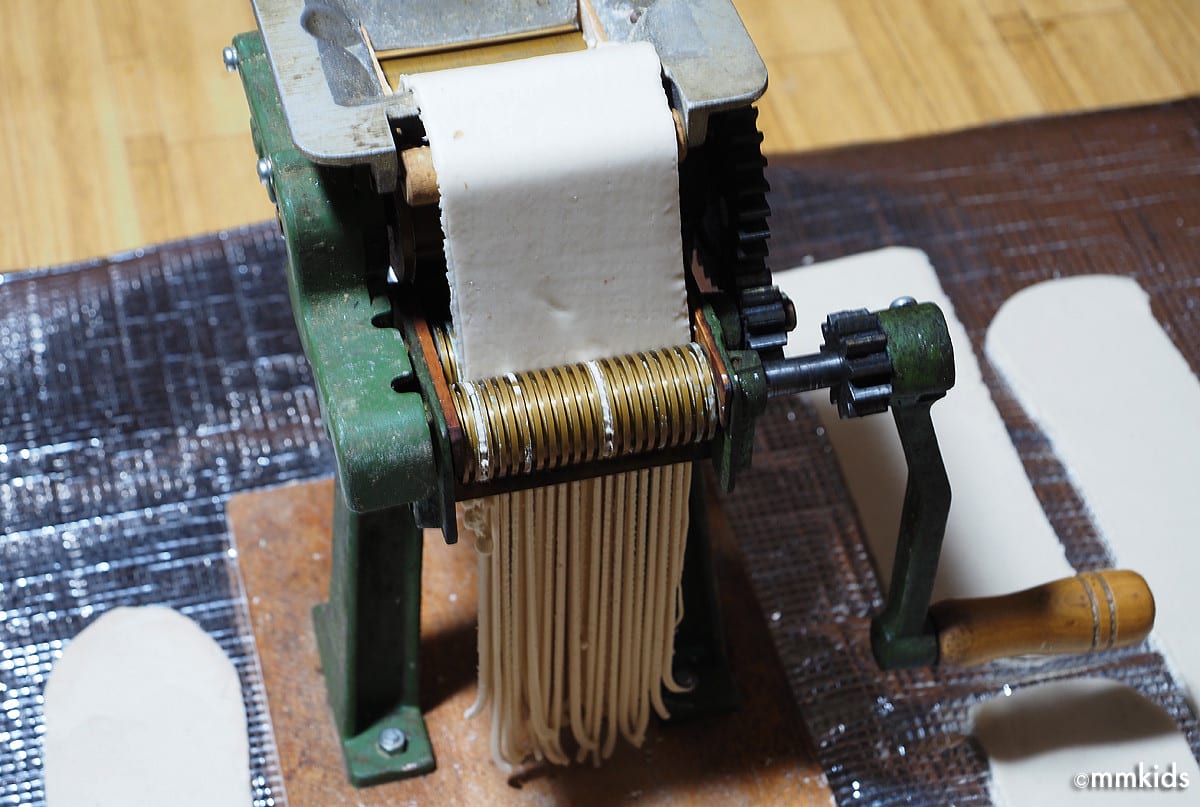朝窓を開けると東はうろこ雲でしたが西は快晴。これはピーカンになると10時頃に晴れ渡ったのを見届けて妻女山に登りました。週末に行う今年最後の妻女山里山デザイン・プロジェクトの作業と納会の下見も兼ねています。

仁科三山の爺ヶ岳(2670m)。南峰と本峰の間の白沢の上部には、春に種蒔きをする老爺の雪形が見られ、山名の由来となりました。雷鳥も生息します。爺ヶ岳には、栂山・栂谷ノ峯・後立山・五六ヶ岳・爺岳・爺子岳とたくさんの別称があります。手前の里山は、茶臼山などがある西山。

鹿島槍ヶ岳(2889m)。山頂の右手の陰になっている谷には、平家の落人が隠れたというかくね里があり、上部の雪渓は2018年に長野県初の氷河であると認定されました。かくね里の人々は、やがて大川沢を下り鹿島川の辺りに住み、それが今の鹿島集落とか。ただ、鹿島神社には807年(大同2年)には集落があった記述があるそうで、平家追討以前にすでに集落があったことになります。戦国時代の天文年間の大地震で鹿島槍が大崩壊し、麓が大被害を受けたため、地震の神様である鹿島神社を勧請したともいわれています。

北へ。白馬三山の左から白馬鑓ヶ岳(2903.11m)、杓子岳(2812m)。信里小学校とJAの建物や民家が見えます。最近ワイナリーの建物ができました。周囲には葡萄畑が広がっています。

白馬三山全景。手前右は茶臼山の崩れた南峰。中腹から下には林檎畑が広がっています。サンふじなどの収穫は終わっていると思います。今年は猛暑で贈答用のリンゴが充分に集まらなかったそうです。

これらの写真はこの妻女山展望台から撮影しています。411mと低いのですが、北アルプス、戸隠連峰、信越トレイル、笠ヶ岳、四阿山までの大パノラマが見られます。

左斜め後方には斎場山(旧妻女山)。これから撮影機材と山仕事の道具を積んで林道を登ります。

陣場平へ。第四次川中島の戦いで上杉軍が本陣の陣城を建てた場所です。先日、SBCの「ずくだせテレビ」に出演した時に島田秀平さんを案内しました。週末はチカラシバの除去作業をします。来春の貝母の開花が楽しみです。満開の様子は各年の4月の記事をアーカーイブでご覧ください。それは見事です。満開は4月10〜20日頃。手前の樫の木で作ったベンチに腰を掛けてゆっくりと鑑賞してください。高句麗人の積石塚古墳の横にも3つあります。下の駐車場から歩いて30〜40分ぐらいです。保育園児でも登れます。開花状況はこのブログでお知らせします。

陣場平の中央にあるクマノミズキ。樹冠にはまだ実が残っています。実がついている枝の赤が鮮やか。小鳥の餌になります。ここで顔見知りの鳥に非常に詳しいご夫婦と邂逅。鳥談義をしているとイカルが来てきれいな鳴き声を聞かせてくれました。冬鳥がたくさんいてあちこちから鳴き声が聞こえます。

先週から長野森林組合が松枯れ病対策で赤松の伐採と薬品の燻蒸をあちこちで行っています。被せてあるビニールは昔と違って自然分解性です。

陣場平の入り口から林道。落ち葉で分からなくなりましたが、ベンチの手前は左右にニホンカモシカの獣道があります。時間が合えば見られます。左の三角のものは昆虫が冬ごもりするためのインセクトホテル。右手前の緑はゴヨウアケビでニホンカモシカの冬の餌になります。

堂平大塚古墳のログハウスへ。週末使わせてもらうので掃除をしました。逆光の紅葉が美しい。麓は13度になった様ですが、山上は4度でした。寒風がないのが何よりでした。

長坂峠に戻って歩いて斎場山へ。クヌギの枯れ葉と手前下にはヤマコウバシの枯れ葉。ヤマコウバシは春の新葉が出るまで落ちないので、受験生のお守りになっています。

「ずくだせテレビ」でも紹介した斎場山(旧妻女山)上杉謙信が最初に本陣としたと伝わる山。山頂は古代科野のクニの古墳です。

円墳なので山頂は平で円形です。ここに盾を敷き床几を置いて陣幕を張って本陣とし、鼓を奏でたといわれています。ただ信玄が全軍を海津城にいれてしまったので、本陣を陣場平に移したと伝わっています。

鮮やかなアオツヅラフジ(青葛藤)の青い実。毒草ですが、漢方では利尿、鎮痛薬として、民間薬では神経痛やリウマチ、通風、むくみ、膀胱炎などに用いられます。アルカロイドの一種が含まれるため、多量に接種すると呼吸不全、心臓麻痺、腎機能障害になる危険があります。クリスマスリースを作る時にも用いられます。
万葉集では黒葛(つづら)という名で登場します。
「駿河の海 おしへに生(お)ふる 浜つづら 汝(いまし)を頼み 母に違(たが)ひぬ」東歌
(駿河の海に生えている浜つづらのように、長くいつまでもそなたを頼りにしていて母と仲違いしてしまった)

ノイバラ(野茨)の赤い実。いわゆる野薔薇で芳香のある白い小さな花を咲かせます。しかし繁殖力が強く地下茎をのばすため、陣場平では貝母のために有害なので除去しています。また、これが登山道を塞ぐと登れなくなってしまいます。この赤い実は食べられますが。下剤としてつかわれる生薬なので過食は禁物です。アオツヅラフジもノイバラの実も食べる小鳥がいます。

妻女山松代招魂社。戊辰戦争以降の戦没者を祀っています。瓦が落ちたりしたので屋根を葺き替える様です。
●「戊辰戦争」の戦没者を祀る妻女山松代招魂社と松代藩の戦没者名簿(妻女山里山通信):戊辰戦争以降の経緯と明治時代の招魂社の貴重な写真も掲載。

展望台に戻って北方の別名戸隠富士の高妻山(2,353m)。左奥に乙妻山。手前の戸隠山の崖が見応えがあります。その手前は富士ノ塔山の尾根です。

飯縄山(1917m)。山頂は右の頂きです。左の南峰には飯縄神社の奥宮があります。祭神の飯縄権現(飯綱大明神)は、管狐(くがきつね)を使って術を行う飯縄遣(いいづなつかい)の仏神。山岳信仰が発祥といわれる神仏習合の神です。その姿は白狐に乗った烏天狗で、大日如来の化身の不動明王のさらなる化身といわれています。上杉謙信の兜の前立てにもあります。冬山登山は雪がしまる2月中旬以降がおすすめです。もちろん冬山装備は必須。アイゼンも必要です。手前の里山の左下に見える大きな四角いものは電波反射板です。

東方には根子岳(2207m)と四阿山(2354m)。四阿山は真田の修験の山で、山頂には麓の山家神社の奥宮が二つあります。麓の神社には、真田幸隆が奉納した奥宮の漆塗りの扉が現存します。拙書では四阿山と真田の関係を詳細に記しています。菅平牧場から四阿山、根子岳をまわるループコースは拙書でも紹介していますが、大人気です。
●インスタグラムはこちらをクリック。ツイッターはこちらをクリック。YouTubeはこちらをクリック。もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。
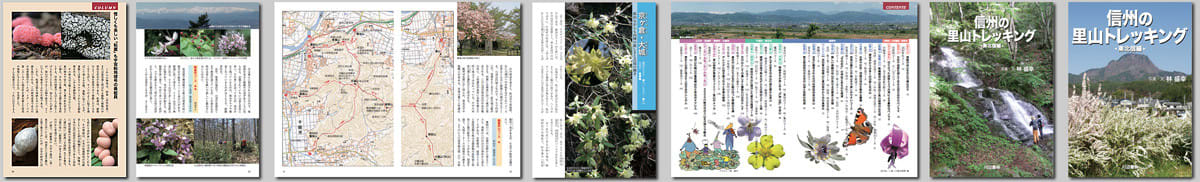
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

仁科三山の爺ヶ岳(2670m)。南峰と本峰の間の白沢の上部には、春に種蒔きをする老爺の雪形が見られ、山名の由来となりました。雷鳥も生息します。爺ヶ岳には、栂山・栂谷ノ峯・後立山・五六ヶ岳・爺岳・爺子岳とたくさんの別称があります。手前の里山は、茶臼山などがある西山。

鹿島槍ヶ岳(2889m)。山頂の右手の陰になっている谷には、平家の落人が隠れたというかくね里があり、上部の雪渓は2018年に長野県初の氷河であると認定されました。かくね里の人々は、やがて大川沢を下り鹿島川の辺りに住み、それが今の鹿島集落とか。ただ、鹿島神社には807年(大同2年)には集落があった記述があるそうで、平家追討以前にすでに集落があったことになります。戦国時代の天文年間の大地震で鹿島槍が大崩壊し、麓が大被害を受けたため、地震の神様である鹿島神社を勧請したともいわれています。

北へ。白馬三山の左から白馬鑓ヶ岳(2903.11m)、杓子岳(2812m)。信里小学校とJAの建物や民家が見えます。最近ワイナリーの建物ができました。周囲には葡萄畑が広がっています。

白馬三山全景。手前右は茶臼山の崩れた南峰。中腹から下には林檎畑が広がっています。サンふじなどの収穫は終わっていると思います。今年は猛暑で贈答用のリンゴが充分に集まらなかったそうです。

これらの写真はこの妻女山展望台から撮影しています。411mと低いのですが、北アルプス、戸隠連峰、信越トレイル、笠ヶ岳、四阿山までの大パノラマが見られます。

左斜め後方には斎場山(旧妻女山)。これから撮影機材と山仕事の道具を積んで林道を登ります。

陣場平へ。第四次川中島の戦いで上杉軍が本陣の陣城を建てた場所です。先日、SBCの「ずくだせテレビ」に出演した時に島田秀平さんを案内しました。週末はチカラシバの除去作業をします。来春の貝母の開花が楽しみです。満開の様子は各年の4月の記事をアーカーイブでご覧ください。それは見事です。満開は4月10〜20日頃。手前の樫の木で作ったベンチに腰を掛けてゆっくりと鑑賞してください。高句麗人の積石塚古墳の横にも3つあります。下の駐車場から歩いて30〜40分ぐらいです。保育園児でも登れます。開花状況はこのブログでお知らせします。

陣場平の中央にあるクマノミズキ。樹冠にはまだ実が残っています。実がついている枝の赤が鮮やか。小鳥の餌になります。ここで顔見知りの鳥に非常に詳しいご夫婦と邂逅。鳥談義をしているとイカルが来てきれいな鳴き声を聞かせてくれました。冬鳥がたくさんいてあちこちから鳴き声が聞こえます。

先週から長野森林組合が松枯れ病対策で赤松の伐採と薬品の燻蒸をあちこちで行っています。被せてあるビニールは昔と違って自然分解性です。

陣場平の入り口から林道。落ち葉で分からなくなりましたが、ベンチの手前は左右にニホンカモシカの獣道があります。時間が合えば見られます。左の三角のものは昆虫が冬ごもりするためのインセクトホテル。右手前の緑はゴヨウアケビでニホンカモシカの冬の餌になります。

堂平大塚古墳のログハウスへ。週末使わせてもらうので掃除をしました。逆光の紅葉が美しい。麓は13度になった様ですが、山上は4度でした。寒風がないのが何よりでした。

長坂峠に戻って歩いて斎場山へ。クヌギの枯れ葉と手前下にはヤマコウバシの枯れ葉。ヤマコウバシは春の新葉が出るまで落ちないので、受験生のお守りになっています。

「ずくだせテレビ」でも紹介した斎場山(旧妻女山)上杉謙信が最初に本陣としたと伝わる山。山頂は古代科野のクニの古墳です。

円墳なので山頂は平で円形です。ここに盾を敷き床几を置いて陣幕を張って本陣とし、鼓を奏でたといわれています。ただ信玄が全軍を海津城にいれてしまったので、本陣を陣場平に移したと伝わっています。

鮮やかなアオツヅラフジ(青葛藤)の青い実。毒草ですが、漢方では利尿、鎮痛薬として、民間薬では神経痛やリウマチ、通風、むくみ、膀胱炎などに用いられます。アルカロイドの一種が含まれるため、多量に接種すると呼吸不全、心臓麻痺、腎機能障害になる危険があります。クリスマスリースを作る時にも用いられます。
万葉集では黒葛(つづら)という名で登場します。
「駿河の海 おしへに生(お)ふる 浜つづら 汝(いまし)を頼み 母に違(たが)ひぬ」東歌
(駿河の海に生えている浜つづらのように、長くいつまでもそなたを頼りにしていて母と仲違いしてしまった)

ノイバラ(野茨)の赤い実。いわゆる野薔薇で芳香のある白い小さな花を咲かせます。しかし繁殖力が強く地下茎をのばすため、陣場平では貝母のために有害なので除去しています。また、これが登山道を塞ぐと登れなくなってしまいます。この赤い実は食べられますが。下剤としてつかわれる生薬なので過食は禁物です。アオツヅラフジもノイバラの実も食べる小鳥がいます。

妻女山松代招魂社。戊辰戦争以降の戦没者を祀っています。瓦が落ちたりしたので屋根を葺き替える様です。
●「戊辰戦争」の戦没者を祀る妻女山松代招魂社と松代藩の戦没者名簿(妻女山里山通信):戊辰戦争以降の経緯と明治時代の招魂社の貴重な写真も掲載。

展望台に戻って北方の別名戸隠富士の高妻山(2,353m)。左奥に乙妻山。手前の戸隠山の崖が見応えがあります。その手前は富士ノ塔山の尾根です。

飯縄山(1917m)。山頂は右の頂きです。左の南峰には飯縄神社の奥宮があります。祭神の飯縄権現(飯綱大明神)は、管狐(くがきつね)を使って術を行う飯縄遣(いいづなつかい)の仏神。山岳信仰が発祥といわれる神仏習合の神です。その姿は白狐に乗った烏天狗で、大日如来の化身の不動明王のさらなる化身といわれています。上杉謙信の兜の前立てにもあります。冬山登山は雪がしまる2月中旬以降がおすすめです。もちろん冬山装備は必須。アイゼンも必要です。手前の里山の左下に見える大きな四角いものは電波反射板です。

東方には根子岳(2207m)と四阿山(2354m)。四阿山は真田の修験の山で、山頂には麓の山家神社の奥宮が二つあります。麓の神社には、真田幸隆が奉納した奥宮の漆塗りの扉が現存します。拙書では四阿山と真田の関係を詳細に記しています。菅平牧場から四阿山、根子岳をまわるループコースは拙書でも紹介していますが、大人気です。
●インスタグラムはこちらをクリック。ツイッターはこちらをクリック。YouTubeはこちらをクリック。もう一つの古いチャンネルはこちら。76本のトレッキングやネイチャーフォト(昆虫や粘菌など)、ブラジル・アマゾン・アンデスのスライドショー。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。
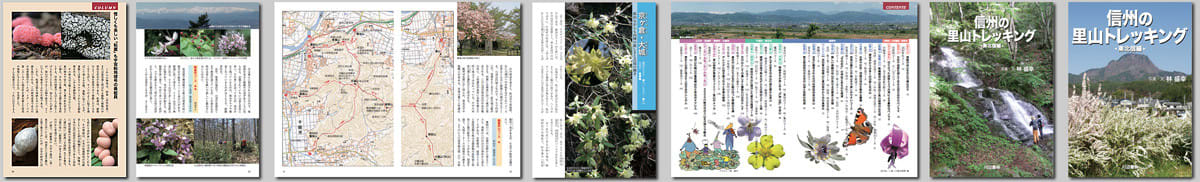
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。