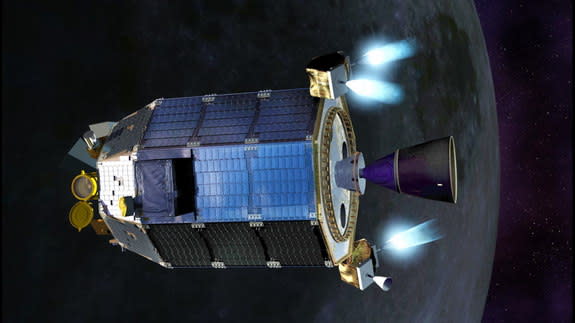月の形は完全な球形からかけ離れていて、
地球に面している側と、その反対側が高く出っ張った奇妙な形をしています。
でも理論上では、約44億年前に形成されて以降、
回転力によって完全な球形に成形されているはずなんですねー

満月の時に見える丸い形の月は、
地球上にいる私たちには、ひじょうになじみ深い光景です。
でも天文学者によると、
別の角度から見れば、わずかにレモン形をしているそうです。
月の地形上にある、この2つの巨大な出っ張り部分は、
地球方向の軸上に並ぶ、こぶだらけの頂点を形成しています。
では、この出っ張りはどのようにして形成されたのでしょうか?
その答えとして、
「月が超高温状態だった形成初期に、地球から及ばされた強力な重力にある」
とする研究論文が発表されました。
火星サイズの浮遊惑星と地球との衝突で、
月が形成されたと考えられています。
当初は溶岩の塊だったのですが、じょじょに冷えて固まり始めることに…
月の重力が海の満ち引きを起こすのと同様に、
月の6倍の質量をもつ地球は、
新たに誕生した衛星である月が固まり始める時期に、
強力な潮汐力を及ぼすことになります。
潮汐力は月を伸縮させるのですが、
この伸縮プロセスで摩擦による熱が発生します。
伴流動体だった月は、表面が冷えている間にこの熱で暖められ、
この動的プロセスで生じた熱が不均一に伝わり、
月の地殻の形成に影響を及ぼしたんですねー
初期に及ぼされた潮汐力により、
月の地殻はさまざまな場所で熱を受けることに…
こうして、さまざまな場所で受けた熱の差によって、
月の形状の対部分が形成されます。
その後、月は冷えている間に、この潮汐力によって外側がゆがみ、
そのゆがんだ形のまま凍り付くことになります。
要は、潮汐力が月に「わずかにレモンの形」の形状を与え、
この形は、地殻が冷えた後に固定化したということです。
地球に面している側と、その反対側が高く出っ張った奇妙な形をしています。
でも理論上では、約44億年前に形成されて以降、
回転力によって完全な球形に成形されているはずなんですねー

満月の時に見える丸い形の月は、
地球上にいる私たちには、ひじょうになじみ深い光景です。
でも天文学者によると、
別の角度から見れば、わずかにレモン形をしているそうです。
月の地形上にある、この2つの巨大な出っ張り部分は、
地球方向の軸上に並ぶ、こぶだらけの頂点を形成しています。
では、この出っ張りはどのようにして形成されたのでしょうか?
その答えとして、
「月が超高温状態だった形成初期に、地球から及ばされた強力な重力にある」
とする研究論文が発表されました。
火星サイズの浮遊惑星と地球との衝突で、
月が形成されたと考えられています。
当初は溶岩の塊だったのですが、じょじょに冷えて固まり始めることに…
月の重力が海の満ち引きを起こすのと同様に、
月の6倍の質量をもつ地球は、
新たに誕生した衛星である月が固まり始める時期に、
強力な潮汐力を及ぼすことになります。
潮汐力は月を伸縮させるのですが、
この伸縮プロセスで摩擦による熱が発生します。
伴流動体だった月は、表面が冷えている間にこの熱で暖められ、
この動的プロセスで生じた熱が不均一に伝わり、
月の地殻の形成に影響を及ぼしたんですねー
初期に及ぼされた潮汐力により、
月の地殻はさまざまな場所で熱を受けることに…
こうして、さまざまな場所で受けた熱の差によって、
月の形状の対部分が形成されます。
その後、月は冷えている間に、この潮汐力によって外側がゆがみ、
そのゆがんだ形のまま凍り付くことになります。
要は、潮汐力が月に「わずかにレモンの形」の形状を与え、
この形は、地殻が冷えた後に固定化したということです。