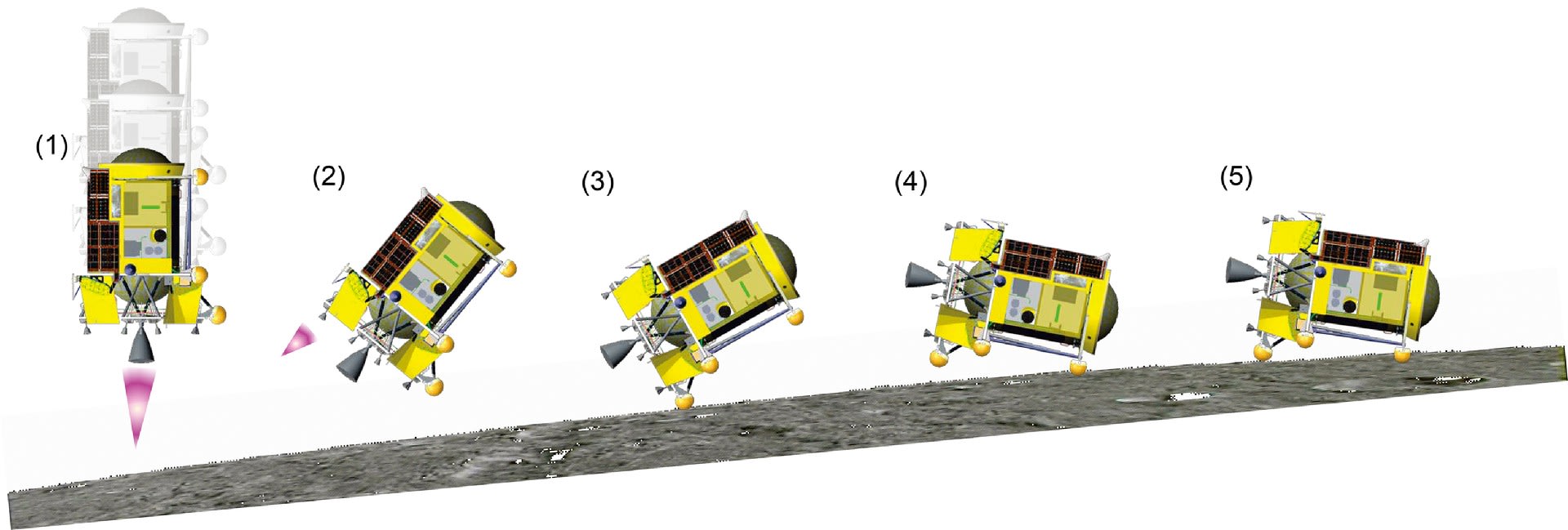今回の研究では、月の裏側にある“コンプトン-ベルコヴィッチ”という放射性物質が特異的に多いことで知られる地域からのマイクロ波放射を計測し、地下に熱源が存在することを突き止めています。
この成果から分かってきたこと、それはコンプトン-ベルコヴィッチは35億年前に月の火山活動で形成されたということでした。
2種類の地殻は厚さだけでなく組成も異なっていて、例えば大陸地殻は主に花崗岩、海洋地殻は主に玄武岩で構成されています。
陸地に存在する花崗岩は、地上で暮らす私たちにとって最もなじみ深い火成岩の1つで、その頑丈さや美しさから建築物の基礎や外壁、墓石などに利用されています。
でも、地球以外の天体ではとても珍しく、逆に言えば地球では例外的に豊富な岩石と言えます。
花崗岩は地下の奥深くでマグマが固まって作られる岩石で、水には岩石が溶けるために必要な温度を下げる性質があります。
そう、マグマになる過程では水の存在が重要になるんですねー
なので、表面に海が広がり、水を地下に送り込む役割を果たすプレートテクトニクスが存在する地球は、花崗岩が作り出されやすい条件を備えた惑星と言えます。
例えば、月の裏側にある幅約50キロの“コンプトン-ベルコヴィッチ”と名付けられた地域には、起源は不明ながらも花崗岩が豊富に存在することが知られています。
ガンマ線の分析から、放射線源は花崗岩に含まれる放射性元素のトリウムだと推定されています。
このため、コンプトン-ベルコヴィッチは“太古に存在した月の火山が固まった跡である”と推定。
でも、仮説を裏付ける他の証拠は、まだ見つかっていませんでした。
もし、本当にコンプトン-ベルコヴィッチが花崗岩の豊富な地域だとすると、トリウムなどの放射性物質が崩壊することで熱が発生します。
発生した熱は地下深部から宇宙空間にマイクロ波の形で逃げていくので、マイクロ波の強度から地下の熱源分布を推定できるはずです。
“嫦娥1号”と“嫦娥2号”には、月を周回する探査機として初めてマイクロ波測定器が搭載されていたので、このような研究が可能になりました。
熱放射の特徴をとらえることができる3~37GHzのマイクロ波の強度を分析した結果、コンプトン-ベルコヴィッチは月の裏側における高地の平均値と比べて、マイクロ波の強度が約20倍も高い値になる、1平方メートル当たり180mWの熱流束が計測されました。
この結果は、コンプトン-ベルコヴィッチの地下には確実に熱源が存在していて、それは放射性物質を豊富に含んだ巨大な花崗岩である可能性が高いことを示していました。
研究チームが考えているのは、コンプトン-ベルコヴィッチは約35億年前に存在した月の火山が固まったことによって形成されたということ。
ただ、今回の研究はコンプトン-ベルコヴィッチにまつわる数多くの謎の1つを解決したにすぎません。
水もプレートテクトニクスも存在しない月で、これほど巨大な花崗岩の塊が形成されるには、地球よりも極端なマグマ生成環境が必要になるはずです。
たとえば、他の地域とは異なりコンプトン-ベルコヴィッチには水が豊富に存在していたのでしょうか?
あるいは、温度が非常に高かったなどの特別な条件が整っていたのかもしれません。
この謎の解決に必要なのはさらに研究を進めること。
そのための研究は、コンプトン-ベルコヴィッチに留まらず、月全体がどのように形成・進化していったのかを理解することに繋がるはずです。
こちらの記事もどうぞ
この成果から分かってきたこと、それはコンプトン-ベルコヴィッチは35億年前に月の火山活動で形成されたということでした。
この研究は、惑星科学研究所(PSI)のMatthew A. Sieglerさんたちの研究チームが進めています。
花崗岩が作り出されやすい条件
地球の表面は分厚い“大陸地殻”と薄い“海洋地殻”に覆われています。2種類の地殻は厚さだけでなく組成も異なっていて、例えば大陸地殻は主に花崗岩、海洋地殻は主に玄武岩で構成されています。
陸地に存在する花崗岩は、地上で暮らす私たちにとって最もなじみ深い火成岩の1つで、その頑丈さや美しさから建築物の基礎や外壁、墓石などに利用されています。
石材としての花崗岩(とその別名になる御影石)という名称は、学術的な意味での花崗岩を指していない場合がある。
このように身近な存在の花崗岩。でも、地球以外の天体ではとても珍しく、逆に言えば地球では例外的に豊富な岩石と言えます。
花崗岩は地下の奥深くでマグマが固まって作られる岩石で、水には岩石が溶けるために必要な温度を下げる性質があります。
そう、マグマになる過程では水の存在が重要になるんですねー
なので、表面に海が広がり、水を地下に送り込む役割を果たすプレートテクトニクスが存在する地球は、花崗岩が作り出されやすい条件を備えた惑星と言えます。
起源が不明な花崗岩の塊
地球以外の天体に、花崗岩が一切存在しないわけではありません。例えば、月の裏側にある幅約50キロの“コンプトン-ベルコヴィッチ”と名付けられた地域には、起源は不明ながらも花崗岩が豊富に存在することが知られています。
コンプトン-ベルコヴィッチという名称は、コンプトン・クレーターとベルコヴィッチ・クレーターの間に位置することから名付けられた。
コンプトン-ベルコヴィッチは、NASAの月探査機“ルナ・プロスペクター”によって、1998年にガンマ線量の多い地域として特定されたことで注目されるようになりました。ガンマ線の分析から、放射線源は花崗岩に含まれる放射性元素のトリウムだと推定されています。
このため、コンプトン-ベルコヴィッチは“太古に存在した月の火山が固まった跡である”と推定。
でも、仮説を裏付ける他の証拠は、まだ見つかっていませんでした。
 |
| NASAの月探査機“ルナ・プロスペクター”で観測された北極点付近のガンマ線量。月の裏側は放射性元素が少ないが、コンプトン-ベルコヴィッチは例外的に豊富な地域の1つである。(Credit: NASA, GSFC, ASU, WUSTL & B. Jolliff) |
 |
| NASAの月探査機“ルナー・リコネサンス・オービター”で撮影されたコンプトン-ベルコヴィッチ。見た目に白っぽいことは、白っぽい岩石である花崗岩が存在すると推定する上で1つの根拠になる。(Credit: NASA) |
約35億年前に存在した月の火山の跡
今回の研究では、中国国家航天局の月探査機“嫦娥1号”と“嫦娥2号”の観測データを用いて、コンプトン-ベルコヴィッチが本当に巨大な花崗岩の塊なのかを分析しています。もし、本当にコンプトン-ベルコヴィッチが花崗岩の豊富な地域だとすると、トリウムなどの放射性物質が崩壊することで熱が発生します。
発生した熱は地下深部から宇宙空間にマイクロ波の形で逃げていくので、マイクロ波の強度から地下の熱源分布を推定できるはずです。
“嫦娥1号”と“嫦娥2号”には、月を周回する探査機として初めてマイクロ波測定器が搭載されていたので、このような研究が可能になりました。
熱放射の特徴をとらえることができる3~37GHzのマイクロ波の強度を分析した結果、コンプトン-ベルコヴィッチは月の裏側における高地の平均値と比べて、マイクロ波の強度が約20倍も高い値になる、1平方メートル当たり180mWの熱流束が計測されました。
 |
| コンプトン-ベルコヴィッチはマイクロ波の放射量が多いことかが今回明らかにされた。これは地下に熱源が存在することの強い証拠になる。(Credit: Siegler, et.al.) |
研究チームが考えているのは、コンプトン-ベルコヴィッチは約35億年前に存在した月の火山が固まったことによって形成されたということ。
ただ、今回の研究はコンプトン-ベルコヴィッチにまつわる数多くの謎の1つを解決したにすぎません。
水もプレートテクトニクスも存在しない月で、これほど巨大な花崗岩の塊が形成されるには、地球よりも極端なマグマ生成環境が必要になるはずです。
たとえば、他の地域とは異なりコンプトン-ベルコヴィッチには水が豊富に存在していたのでしょうか?
あるいは、温度が非常に高かったなどの特別な条件が整っていたのかもしれません。
この謎の解決に必要なのはさらに研究を進めること。
そのための研究は、コンプトン-ベルコヴィッチに留まらず、月全体がどのように形成・進化していったのかを理解することに繋がるはずです。
こちらの記事もどうぞ