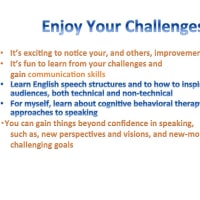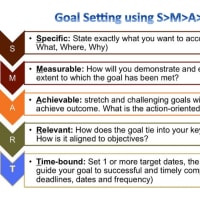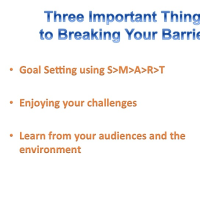つい一週間前に、山中先生の「STAP細胞のノウハウ教えて」という変なコメント、が気になって懸念したこと(ものづくりのための研究ノート020:STAP細胞と再現性)が残念ながら本当だったらしい。STAP細胞の再現性(再現率というべきかもしれないが)がきわめて低いらしいのだ。
昨日でたNatureのニュース記事「Acid-bath stem-cell study under investigation」によると(英文は同記事から引用)、
1)10人の有力幹細胞研究者にNatureが問い合わせてところ、どこも再現が取れていない。
(None of ten prominent stem-cell scientists who responded to a questionnaire from Nature has had success.)
2)懐疑的な研究者のブログサイトでは、失敗報告が8例出ている(*)
(A blog soliciting reports from scientists in the field reports eight failures)
3)共同研究者の若山先生が理研時代に小保方さんの協力をえて、独立に再現性を確認したが、山梨大学に移ってからは成功していない。
(The protocol might just be complicated ― even Wakayama has been having trouble reproducing the results. He and a student in his laboratory did replicate the experiment independently before publication, after being well coached by Obokata. But since he moved to Yamanashi, he has had no luck. )
ということが述べられている。
確かに同一条件でおこなっておらず、多くは成体(adult)の細胞をつかっているようであるが、
彼らがOct4GFPマウスを利用した逆流性食道炎モデルで酸の多い食道上皮でoct4+細胞が出現するという報告をSTAP細胞のNature論文でしているのをみると、
成体(adult)の細胞を使って、そんなに条件に気を配らなくても(生体内(in vivo)の逆流性食道炎モデルの方が試験管内より(in vitro)条件がコントロールできない気がする)、少なくともoct4+までは行く気がするのだが、それもかなわないようだ(**)。
上の引用にもあるように、実際のプロトコールは複雑であるようで、隠されたノウハウがあるのかもしれない。あるサイトにも指摘のあるように、「再現性と再現率はわけて議論すべきなのかもしれない。」
いずれにせよ、安定した技術とは言えないようである(***)。
知的財産のからみや競争性の維持など理由から公開していなかったのかもいしれないが、詳しいプロトコールは公開せざるをえなくなるのではないだろうか?(****)
日本人としては、何らかのピットフォールがあって再現率が低いだけで、再現性のある技術であってほしい。
(*)このサイトものづくりのための研究ノート020:STAP細胞と再現性でも紹介してました。
なおこのサイトに今文章だけですが、ドイツ人の研究者が再現に成功したとのコメントを載せています。
その一つは成体ラットからの作成。ホンマかいな??
Rat Spleens from 6 month rats, LSM separated lymphocytes, treated exactly as published, cultured in DMEM/F12,2%B27,Lif. Oct4 detected after 7 days by western Blot.
(**)(3月4日追記)
Oct4までは行くのでないかというのが、その後3月3日あたりに出てきたようである。
Biotechinicalフォーラム掲示板によると、qqさんという人が、
「私の知る限り2つの独立したラボによりある程度のところまで再現できているようです。
そのうちの一つはOct4の遺伝子、タンパク質の発現上昇とsphere形成を確認したとのことです。
もう一つのラボでは現在論文投稿中とのことのようです。
私が実際に確認したわけではないので、本当のところはわかりませんが、この2つのラボ(一つは海外)もstem cellの著明なラボなので報告を待ちたいです。
私の想像ですが、現象としてはおそらく真実で、ただ早急に論文にするためにデータの取り扱いを誤ってしまったのではと思います。日本人として、真実であってほしいです。」
と述べている。
また上記懐疑的な研究者ノープラーさんのブログでも3月3日同様の彼自身の情報として以下のコメントがでてきた。
「I’ve heard several reports now that labs can sometimes see some kind of either Oct4-GFP reporter activity or pluripotency gene expression in acid treated cells, but the scientists do not seem particularly encouraged.
(いくつかのラボで酸に浸した細胞で、ある程度のOct4-GFPリポーター活性や多能性関連遺伝子の発現が見られるうることを耳にした。しかし研究者たちは特に前向きにとらえているわけではないようである)」
まあOct4発現までは何とか行くのかしら?
(***)技術の安定性に問題があるなら、発表のタイミングは今でないといけなかったのか疑問である。もう少し安定するまで待ってもよかったのではないだろうか?
(****)再現性とともにデーターの利用の仕方にも問題があったようで事態は複雑な感じになってきているが、ここでは再現性のみの問題に特化して議論した。今後幻のマウスクローン作製としてしられるイルメンゼ―事件のような展開にならないことを祈りたい。
(以下3月5日追記)
結局3月5日理研が詳細プロトコールをprotocol exchangeと理研HP上で発表。
ぱっと見た感じでは、温度管理を厳格にして、pH管理を厳格にしたところと、LIFの加えるタイミングがコツの模様。またこれだけで、若山先生が山梨で再現できない理由が説明できるとは思えない。おそらく血清のロットの問題他、ピットフォールがこれ以外にあるのではないだろうか?
なお丹羽先生がコレスポでプロトコールを発表しているところをみると、理研内では再現がとれたということなのだろうか?
ちなみにマウス胎児線維芽細胞(MEF)の場合は、継代したものは初期化できないらしいので、これまで成功例がない理由(多くがMEFを利用)も一応説明がつくのだろうか?
まだまだ目が離せない。
(追記)2016年3月1日追記。
個人的にはもはや興味を失っていたのだけれど、未だにこのブログのSTAP関連の項目を目にされている方が多い様なので、追記しておく。
2015年9月24日同様の趣旨からなる論文をNatureが掲載した。
1報目"Failure to replicate the STAP cell phenomenon"はボストンを中心とした幹細胞分野の大御所たちのチームによるもの
2報目"STAP cells are derived from ES cells"は理研のグループによるもの
の二つで、1はほぼ全てのSTAPのprotocolを検証し、作成できないことを示すとともに、バイオインフォマテッィクスを利用してSTAP細胞とされていたものに、ESが混ざっていることを証明したもの、2もバイオインフォマティックスを用いてESのまざりを証明したものである。
STAPの論文は途中から基本的に無理筋な感じを呈してきたが、これで完全に決着がついた。残念ながら、おそらく誰かがES細胞を混ぜて虚構の細胞を作ったことになる(結局それが誰かわからないのであるが。。)。ただこの一件で日本のサイエンスに大きな傷跡が残り、一人の偉大な科学者を失ったことは悔やまれる。
昨日でたNatureのニュース記事「Acid-bath stem-cell study under investigation」によると(英文は同記事から引用)、
1)10人の有力幹細胞研究者にNatureが問い合わせてところ、どこも再現が取れていない。
(None of ten prominent stem-cell scientists who responded to a questionnaire from Nature has had success.)
2)懐疑的な研究者のブログサイトでは、失敗報告が8例出ている(*)
(A blog soliciting reports from scientists in the field reports eight failures)
3)共同研究者の若山先生が理研時代に小保方さんの協力をえて、独立に再現性を確認したが、山梨大学に移ってからは成功していない。
(The protocol might just be complicated ― even Wakayama has been having trouble reproducing the results. He and a student in his laboratory did replicate the experiment independently before publication, after being well coached by Obokata. But since he moved to Yamanashi, he has had no luck. )
ということが述べられている。
確かに同一条件でおこなっておらず、多くは成体(adult)の細胞をつかっているようであるが、
彼らがOct4GFPマウスを利用した逆流性食道炎モデルで酸の多い食道上皮でoct4+細胞が出現するという報告をSTAP細胞のNature論文でしているのをみると、
成体(adult)の細胞を使って、そんなに条件に気を配らなくても(生体内(in vivo)の逆流性食道炎モデルの方が試験管内より(in vitro)条件がコントロールできない気がする)、少なくともoct4+までは行く気がするのだが、それもかなわないようだ(**)。
上の引用にもあるように、実際のプロトコールは複雑であるようで、隠されたノウハウがあるのかもしれない。あるサイトにも指摘のあるように、「再現性と再現率はわけて議論すべきなのかもしれない。」
いずれにせよ、安定した技術とは言えないようである(***)。
知的財産のからみや競争性の維持など理由から公開していなかったのかもいしれないが、詳しいプロトコールは公開せざるをえなくなるのではないだろうか?(****)
日本人としては、何らかのピットフォールがあって再現率が低いだけで、再現性のある技術であってほしい。
(*)このサイトものづくりのための研究ノート020:STAP細胞と再現性でも紹介してました。
なおこのサイトに今文章だけですが、ドイツ人の研究者が再現に成功したとのコメントを載せています。
その一つは成体ラットからの作成。ホンマかいな??
Rat Spleens from 6 month rats, LSM separated lymphocytes, treated exactly as published, cultured in DMEM/F12,2%B27,Lif. Oct4 detected after 7 days by western Blot.
(**)(3月4日追記)
Oct4までは行くのでないかというのが、その後3月3日あたりに出てきたようである。
Biotechinicalフォーラム掲示板によると、qqさんという人が、
「私の知る限り2つの独立したラボによりある程度のところまで再現できているようです。
そのうちの一つはOct4の遺伝子、タンパク質の発現上昇とsphere形成を確認したとのことです。
もう一つのラボでは現在論文投稿中とのことのようです。
私が実際に確認したわけではないので、本当のところはわかりませんが、この2つのラボ(一つは海外)もstem cellの著明なラボなので報告を待ちたいです。
私の想像ですが、現象としてはおそらく真実で、ただ早急に論文にするためにデータの取り扱いを誤ってしまったのではと思います。日本人として、真実であってほしいです。」
と述べている。
また上記懐疑的な研究者ノープラーさんのブログでも3月3日同様の彼自身の情報として以下のコメントがでてきた。
「I’ve heard several reports now that labs can sometimes see some kind of either Oct4-GFP reporter activity or pluripotency gene expression in acid treated cells, but the scientists do not seem particularly encouraged.
(いくつかのラボで酸に浸した細胞で、ある程度のOct4-GFPリポーター活性や多能性関連遺伝子の発現が見られるうることを耳にした。しかし研究者たちは特に前向きにとらえているわけではないようである)」
まあOct4発現までは何とか行くのかしら?
(***)技術の安定性に問題があるなら、発表のタイミングは今でないといけなかったのか疑問である。もう少し安定するまで待ってもよかったのではないだろうか?
(****)再現性とともにデーターの利用の仕方にも問題があったようで事態は複雑な感じになってきているが、ここでは再現性のみの問題に特化して議論した。今後幻のマウスクローン作製としてしられるイルメンゼ―事件のような展開にならないことを祈りたい。
(以下3月5日追記)
結局3月5日理研が詳細プロトコールをprotocol exchangeと理研HP上で発表。
ぱっと見た感じでは、温度管理を厳格にして、pH管理を厳格にしたところと、LIFの加えるタイミングがコツの模様。またこれだけで、若山先生が山梨で再現できない理由が説明できるとは思えない。おそらく血清のロットの問題他、ピットフォールがこれ以外にあるのではないだろうか?
なお丹羽先生がコレスポでプロトコールを発表しているところをみると、理研内では再現がとれたということなのだろうか?
ちなみにマウス胎児線維芽細胞(MEF)の場合は、継代したものは初期化できないらしいので、これまで成功例がない理由(多くがMEFを利用)も一応説明がつくのだろうか?
まだまだ目が離せない。
(追記)2016年3月1日追記。
個人的にはもはや興味を失っていたのだけれど、未だにこのブログのSTAP関連の項目を目にされている方が多い様なので、追記しておく。
2015年9月24日同様の趣旨からなる論文をNatureが掲載した。
1報目"Failure to replicate the STAP cell phenomenon"はボストンを中心とした幹細胞分野の大御所たちのチームによるもの
2報目"STAP cells are derived from ES cells"は理研のグループによるもの
の二つで、1はほぼ全てのSTAPのprotocolを検証し、作成できないことを示すとともに、バイオインフォマテッィクスを利用してSTAP細胞とされていたものに、ESが混ざっていることを証明したもの、2もバイオインフォマティックスを用いてESのまざりを証明したものである。
STAPの論文は途中から基本的に無理筋な感じを呈してきたが、これで完全に決着がついた。残念ながら、おそらく誰かがES細胞を混ぜて虚構の細胞を作ったことになる(結局それが誰かわからないのであるが。。)。ただこの一件で日本のサイエンスに大きな傷跡が残り、一人の偉大な科学者を失ったことは悔やまれる。