
昨年、ドミンゴがバリトン・ロールの最高峰の一つにチャレンジするというので話題になり、
メトの公演もHDを経由してDVD化までされることになった『シモン・ボッカネグラ』が、
指揮だけは同じレヴァインのまま、主要キャストは総とっかえで今シーズンも再演です。
昨年の『シモン』は、声の老化が激しいモリスのずっこけフィエスコ、いつも通りわんわん喚いているだけのジョルダーニのアドルノといった問題もありましたが、
ドミンゴの、年齢やテノール声というハンデを越える、役作りの素晴らしさと舞台プレゼンスの強烈さなどには大いに感銘を受けましたし、
そもそもドミンゴがバリトンの役を歌うという、そのスタート地点そのものにヘッズからの批判も多かったですが、
私自身は”優れた舞台人とは何か?”ということを問う、HDやDVD化の意義のある公演だったのでは、と思っています。
しかし、そんな私でも、今日のシーズン初日の『シモン』を観て、素直にこう思うのでした。HDは一年早かったかも、、。
今日の座席はグランド・ティアーのサイド・ボックス中、二番目に舞台に近いボックスで、
この座席は、舞台の一方の端が観づらいのと、音響面での若干の問題はあるのですが、
一方で、歌手の演技や表情、そして、もう殆ど目の前のすぐ下にいる指揮者やオケの様子もはっきりと見えるので、なかなか面白く、私の好きな座席の一つです。

毎回毎回、もう今度こそは駄目かも、とヘッズに思わせつつ、シーズン初日やHDと言った肝心の場は、
文字通り死んでも指揮台に這い上がって来そうな勢いのレヴァインですが、その通りで、やっぱり今日も這い上がって来ました。
以前にも書きました通り、もはやメトでは”本当に現れた!”というような、珍獣的ポジションに近づきつつあるレヴァインなので、
開演前の拍手はものすごく、ごおおおおっ!!という地鳴りのような喝采があがって、それが一旦静まりかけたと思うと、
どこぞのヘッドが劇場の後ろの方から、”Bravo, Maestro!”と檄を飛ばし、
その後に再び巻きあがった観客からの拍手に本物の温かさがあって、レヴァインの嬉しそうな表情についほろりと来てしまいます。
今シーズン、タイトル・ロールを歌うのは、ディミトリ・ホロストフスキー。
70に手が届かんというドミンゴと比べてしまうと、誰でもそうなのでしょうが、彼のシモンは若々しく、
残りの幕より、プロローグでの設定(つまり、一幕の20年ほど前)の方がぴったり来る位。
彼の声が作品の中でどのように聴こえるか、という点については、大体こういう風になるのではないかな、と予想していたのに近く、
というのも、私は彼の声質自体は非常に美しいと思うし、好きか嫌いかと聞かれれば間違いなく好きな方に入りますが、
彼の声にはヴェルディが書いたオーケストレーションをカットスルーような、もしくはそれを包んで上に広がってくるようなクオリティはなくて、
それが、私が彼はヴェルディ・バリトンでは決してないと思う一因です。
そして、それは今日の公演でも、アンサンブルが厚くなる箇所、特に他の歌手との重唱の場面で感じられました。
というのも、今日共演しているフリットリ、フルラネットはもちろん、デ・ビアジオに至るまで、イタリア勢の歌手達には、
ヴェルディのオーケストレーションを後ろにしても尚立ってくる声の響きがあるのです。
以前、『ドン・カルロ』を鑑賞した時、私はホロストフスキーは声量が少し足りないのかな、という風に思っていたのですが、
先シーズンに聴いたカーネギー・ホールでのラドヴァノフスキーとのジョイント・リサイタルや今日の公演を経て、
それは声量の問題ではなくて、響きの問題なんだと思うに至りました。
単純な声量の観点で言うと、今日の『シモン』でも、まずは十分なものがあったと思います。
(もちろん彼が声量豊かと言うつもりはありませんが、決して音量が少ない訳ではないと感じました。)
そのことは、オーケストレーションの厚みが薄くなったり、またほとんどオケの音を伴わないで歌う場面で、
あれ、こんなに声が出ているんだな、と、逆にはっとすることでも裏付けられると思います。
また、こういうオケの音がない場面での彼の歌は、彼の真骨頂とするところで、彼の声の美しさが際立つというか、
そういえば、リサイタルの時も、アンコールで歌ったアカペラのロシア民謡が一番彼の良さが出ていたのを思い出します。

少し前の、ヴェルディ・バリトン云々、の話に戻り、それでは真のヴェルディ・バリトンでなきゃシモンを歌っちゃいけないのか、
また、そうでなければ優れたシモンを歌えないのか?と問われれば、これはオペラが好きな方ならそれぞれにご自身の基準をお持ちと思いますが、
私自身は必ずしもそんなことはないと思っています。
もちろん、他が全て同じであれば、私も真性ヴェルディ・バリトンのサウンドを取りますが、他が同じでなければ、
結局は、総合して、どれだけ観客の心を動かすことが出来るか、ここに集約されるのではないかと思います。
逆にヴェルディ・バリトンのサウンドがあっても、それが出来なかったら、何の意味もありません。
(ホロストフスキーよりはヴェルディ・バリトン的資質があるメオーニが、味もしゃしゃりもないリゴレットを歌って心底がっかりさせられましたが、
その件は次にあげる1/22の記事まで待ちたいと思います。)
というわけで、全体の話をすると、今日のホロストフスキーの歌は音楽的には非常に良い内容だったと思います。
フレージングはよく考えられているし、スタミナの配分も申し分なく、この上演時間が決して短くない公演の、しかも、歌うパートがかなりに渡るこの役で、
全く疲れを感じさせないだけでなく、第一幕のシモンの演説シーン(”平民たちよ、貴族達よ Plebe! Patriazi! Popolo!”)と、
三幕(かつ全幕)のラストにあたる、フィエスコとの二重唱に、最も大きな波が来るよう、かつ、それらが前にある場面から曲線を描くように上手く盛り上がって行く、など、
非常に巧みなペース配分が行われていて、今回、彼がこの役をメトで歌うのは初なのですが、本当に良く準備して来たことがよくわかる歌唱です。

ただし、演技の方ではもうちょっと改善の余地があるかもしれません。
まあ、相手がドミンゴでは大概の歌手は勝ち目がないので、彼と比べてはいけないとは思うのですが、
この役の、演技や表現面での難しさは、シモンが持っているたくさんの側面、顔が作品の中に全て含まれている点にあって、
愛する女性(アメーリアの母)を思う情熱的な側面、娘思いの優しい父親としての顔、統治者としての厳しさと威厳、
義理の父親との確執に悩む息子としての側面、などなど、これらそれぞれを繊細さを持って演じつつ、かつ、一人の人間として無理なく統合できていなければなりません。
それを成し遂げている事実こそが、私がドミンゴのシモンはあれはあれですごかった、と思う理由になっているのですが、
ホロストフスキーはこれらの多面的なシモンの性質のある部分は巧みに演じているのですが、逆にある部分は弱い、、といったでこぼこがあるのが残念です。
彼が上手くこなしていたのは、怒りに燃える場面(一幕で、フィエスコとの和解を試みるも失敗、フィエスコが立ち去ったと見せかけた後の、
Oh, de' Fieschi implacata, orrida razza!といった言葉などは歌唱と合わせて、ぞっとさせられるような冷ややかさがありました。)や総督としての外の顔を見せている場面で、
逆に、苦手に見受けたのは娘を愛する父親としての慈愛の表現で、この作品の中で幸せの頂点と言っても良い、アメーリアとの、
お互いの素性がわかる、第一幕のあの感動的な二重唱の部分で、歌で手一杯で余裕がないのか、あるいはこういう場面の表現に照れがあるのか、
全然フリットリに自分から絡んで行かなくて、フリットリがとりつくしまなし、、という感じで立ちすくんでいました。
イタリア・オペラですからね、こういうところはもっともっと熱くてもいいんだけどな、、と思います。

後、彼の顔の表情は三つ位しかバリエーションがなくて、ニュートラルな顔、怒りの表情(目がぎろっと横を向く)、そしてニカッと笑った顔、
基本はこの三つだと思います。(実生活は知りませんけれど、少なくとも舞台では。)
特にニカッと笑った表情は、例えばカーテン・コールなんかでこれが出ると、ああ、ホロストフスキーって意外とお茶目なんだわ、と思い、好ましい表情なのですが、
公演の中で使用すると若干浮くというか、もう少し笑い顔のバリエーションを工夫する必要があるかな、と思います。
今回、面白いなと思ったのは、毒を飲んでしまった後、視力を失う、もしくは視界がぼやけて良く見えなくなっている、という設定で彼が演じていた点で、
それが最後に突然、彼の目にはアメーリアの母親の姿が浮かんでいるのでしょう、彼女に向かって歩きながら微笑みながら死んでいく、という演技付けになっていて、
ドミンゴの終始、獅子のような激しさを持った死に様とは全く対照的で、あの音楽と周りの人物たちが浮かべる重苦しい表情の中で、
突然、シモンの顔が天国に照らされているように柔和になるというのは、こちらも不意をつかれる演技で、すごく良いアイディアだと思うのですが、
その柔和になった、心に平和が訪れた時の表情が、突然、”ニカッ”になってしまう、これはあいたたた、、です。
ここで、愛する人と再び出会う喜び、というような、微妙な表情を微笑みに込められると、すごく効果的になると思います。
こうして細かい点をねちねち言うのは全体としては大変良かったからで、さらに優れたシモンへ!という思いの裏返しです。

ホロストフスキー単体でもなかなか聴きごたえがありましたが、それだけでは真にすごい公演にはならない。
今回、素晴らしかったのはアンサンブル・オペラとしての出来、つまり、他のキャストの一人一人も含めた出来です。
まず、フィエスコを歌ったフェルッチョ・フルラネット。『ドン・カルロ』初日での彼の表現力に目と耳が釘付けになったものですが、
彼の舞台での存在感というのは本当にすごいと思います。プロローグの、前景にシモンを取り囲む民衆が居て、舞台奥にある壁沿いの石段を上りながら、
フィエスコがその様子を眺めつつ去るという演技なんですが、こんな後景のはずの彼が、前に居るシモンのホロストフスキーよりも、
強い存在感を発しているのです。
去年、モリスが歌った時はこんな演技あったっけ?って感じなんですけど。(全然モリスに視線が向かなかった。)
フルラネットは、スカラの『シモン』のフィエスコが、”これ、どうしましょ!?”という出来だったのですが、
今回は歌唱もその時とは見違える位安定していて、声も本当に良く通っていましたので、あの日は余程不調だったのだと思われます。
それこそプロローグから最後の幕まで、演技と歌唱の両方で名人芸を繰り広げていたフルラネット。
第三幕で、パオロとの会話を通して、シモンに複雑な思いを抱き続ける彼のフィエスコの苦悩の表現にさすが、、と酔いしれ、
いよいよシモンと対峙する場面は、もうオケの素晴らしい演奏もあって、息詰まるような迫力だったんですが、
それまで頭巾付きの修道士が着るようなローブをつけたフィエスコがシモンの総督の椅子に、頭巾をかぶったままじっと座っているところに、
シモンが部屋に転がり込んで来て、自分は海で(海賊として)死んでしまっていた方が良かったのだ、、と嘆くシモンに、
背後から、”お前にはきっとその方が良かったろう。”と話しかけ、
”紛れ込んできたのはどこのどいつだ?”とシモンが答えると、椅子から立ち上がり、”お前を恐れぬものだ!”と歌いながら、ばっ!と、
着ていたローブを脱ぎ捨てて正体を現す、という、遠山の金さんもびっくり!のかっこいいシーンがあります。
フィエスコはこの修道士ローブの下に豪華なシルクの衣装を二枚重ね着していて、
すぐ下には袖つきの、床まである美しいシルクの上着(最後の写真を参照。)、
その更に下に、ノースリーブの床まで届くロング・ワンピースのようなものを身につけていて、
この下のワンピの布地がちらっと上着の下に見えて、衣装の豪華さを際立たせているのですが、
ばっ!とローブを脱ぎ捨て、”そうだ、わしはフィエスコだ!”と見得を切ったフルラネットを見て、私は目が点になり、固まってしまいました。
だって、フルラネット、ロング・ワンピの下に真っ白なコットンの半そでのTシャツを着て、ニの腕から下をまる出しで仁王立ちしているのですもの!!
もしかして、、、?
やっぱり!!フルラネット、修道士ローブだけを脱ぎ捨てなければならないところを、その下の上着まで脱ぎ捨ててしまったのね、、。
それにしても、シルクの長ワンピの下の白いTシャツがジャンカルロ・デル・モナコの超トラディショナルで豪華な舞台に嫌なくらい映えるーっ!!
すごい迫力でシモンをにらみつけながら立っているフィエスコ!でも、白いTシャツ!!だめ、、肩がひくひくして来た、、。
ホロストフスキーは幸い客席側に向かってひざまずきながら熱唱していて、全く気がついていないみたいなので、
つい私も、”そうよ、今は絶対に後ろを向いちゃ駄目よ!!”と心の中で叫び続ける。
と、フルラネットがやけに腕がスースーするな、と感じたのか、視線を自分の体に落として、目玉が飛び出さん位びっくりしているのが見えました。
自分のパートを歌いながら、蟹歩きでこっそりと自分の脱ぎ捨てた衣装の山に近づき、長袖の上着を探し当てこっそり着用するフルラネット、、。
こんなお茶目なフルラネット、初めて見ました。
白Tシャツなしで、直に衣装を身につけていれば、そのまま上着を着ないで押し通す手もあったのでしょうけれど、、、たかが白Tシャツ、されど白Tシャツ、です。

アメーリア役を歌ったバルバラ・フリットリに関しては、彼女の最高の歌唱の一つを聴いた、という気がします。
真っ直ぐに声が飛んで来る、あの美しい発声に、この役にぴったりの、楚々としていながら、かつ芯の強そうな雰囲気、、。
彼女の”星と海は微笑み Come in quest'ora bruna”は、生の全幕の舞台で、こんなにこの曲を上手く歌えるソプラノがいるのか?!と、
本当にびっくりするような素晴らしい出来でした。
舞台に登場したかと思ったらすぐに歌いださなければならないこのアリアは、本当に難しいと思うのですけれど、、。
昨シーズンのピエチェンカはあの冒頭の木管を前のめり気味に演奏させるレヴァインの指揮にきちんと乗れてなかったような部分があったのですが、
全く同じアプローチで指揮をしているレヴァインの意図を、フリットリの方は的確に摑んで、指揮との息もぴったり合っていました。
フリットリは現在レヴァインのお気に入りのソプラノのように見受けられるのですが、こういうのを聴くと、もっとも!と思います。
彼女の役作り、芝居のうまさは言わずもがな。
こういう役では、彼女は舞台上で非常に思い切ってゆっくり動くのですが(歩き方なんかほとんど摺り足みたいな部分もあります)、
それがアメーリアの高貴な身柄とか気性を本当に的確に表現しています。
重唱の部分での他の歌手への繊細な気配りのセンスもさすがで、三幕ラスト、シモンが息を引き取った直後に、
ガブリエーレ役のデ・ビアジオと歌った”Padre! 父上!”の一言は、もうあまりに美しくて失神するかと思いました。

ラン全部をラモン・ヴァルガスが歌う予定だったガブリエーレ役は、そのヴァルガスが初日の少し前から風邪を引き、
カバーをつとめているロベルト・デ・ビアジオが今日の代役をつとめました。
NYタイムズの評に、彼は現在42歳、元フルート奏者で、歌を歌い始めたのはたった4年前(!)ということになっているんですが、
2004年に京都のイタリア文化会館でピンカートン(『蝶々夫人』)をコンサート形式で歌っているみたいなので、劇場の全幕に立ったのは、という意味なのかもしれません。
また、日本では『ルチア』のエドガルドも歌ったことがあるようです。
デ・ビアジオは今日がメト・デビューになったんですが、レヴァインが指揮の、演目初日の公演の、しかも代役でデビューなんて、
どれだけプレッシャーが大きく、どれだけ度胸がいることでしょう!
相当緊張していたのか、もう最初の方は表情が顔に張り付いていると言う感じで、レヴァインがリラックスして!という感じで微笑むと、
それに答えて微笑んだ、その微笑んだ顔がまたそのまんま張り付いてしまって、なぜその歌詞の内容で今微笑む?という場面があったのは愛嬌です。
でも、彼の歌声は、一声目から、これは本当に綺麗!と思いました。音にピンがあって、基本的な発声に無理が無く、自然に音が出てくるので、
非常に耳に心地良い。
声質は、からっとして軽くはあるのですが、適度に男性的な音で、この役にはぴったりだと思います。
すらっとしていて身長もそこそこあるので、舞台姿も綺麗。
中盤で音色が少し浅くなったり、二幕のアリア(”我が心に炎が燃える Sento avvampar nell'anima”)で一箇所、
高音の音色が損なわれた部分がありましたが、そのまま崩れず、繰り返しの部分では同じ音をきっちりと出し、
終盤にはまた盛り返して、先ほども書いたPadreを非常に美しい音で聴かせるなど、全体的には非常に良い歌唱で、
何より彼はこの役に必要な高音を綺麗に出せる力があるので、ガブリエーレ役を聴く本来のスリルがあります。
この中盤の部分では、一幕の冒頭で見せていたような綺麗な発声が若干損なわれていた部分もあったり、
オケが厚い重唱部分で突然声が聴こえにくくなったりする箇所が数箇所あり(もしかして、休憩??)スタミナも含め、その辺りがこれからの課題かもしれません。
それにしても、ほんと、今年メト・デビューのテノールがこんな歌唱を聴かせるのですから、昨年のジョルダーニの歌唱は、今となってはほとんど冗談としか思えません。
更に、もしかすると、本キャストのヴァルガスよりも、デ・ビアジオの方がこの役には良いのではないか、という風に、私は思っています。
パオロ役は大事な役ゆえ、なかなか観客の期待が高く、今日のアライモは一部の観客からブーを受けていましたが、
私は昨シーズンに比べてそう悪いとは思いませんでした。
最後にオケですが、本当に素晴らしかった。
プロローグから何かがクリックしたのが明らかで、それはオケのメンバーの表情を見ていても伝わって来ました。
レヴァインは優れた指揮者ではありますが、このレベルの優れた演奏は、それだけではなくて、何か別の、
特別なマジックがあった時にしか生まれないような類の演奏で、とにかく至福でした。
こういう演奏に出会うと、”そうそう、これこそが私がメトに通い続けている理由じゃないか!”と思い出せてくれます。
ただ、今シーズンの『シモン』の演奏はプロローグと一幕が演奏され、たった1回のインターミッションの後、二幕と三幕が演奏されるという強行スケジュールで、
客が早く帰宅できるよう工夫するのもいいですけれど、レヴァインを殺す気か!と思います。
この日はカーテン・コールで舞台上にまで出てきてくれていましたが、指揮自体は相当辛かったようで、二日目の公演(1/24)は降板してしまいましたし、
長時間リハーサルをするので有名な彼が、メト・オケの演奏会のリハーサルを早めに切り上げるなど、
今の彼にとって長時間の指揮はかなりの負担になっているようです。
今日のような素晴らしい演奏を聴けるなら、1回多いインターミッションで少しでもレヴァインが楽になるというなら、
観客はほんの少しの不便を分かち合う位の優しさがあっても良いと思うのですけど、、。
Dmitri Hvorostovsky (Simon Boccanegra)
Barbara Frittoli (Maria / Amelia Grimaldi)
Roberto De Biasio replacing Ramón Vargas (Gabriele Adorno)
Ferruccio Furlanetto (Andrea / Jacopo Fiesco)
Nicola Alaimo (Paolo Albiani)
Richard Bernstein (Pietro)
Edyta Kulczak (Amelia's lady-in-waiting)
Adam Laurence Herskowitz (A captain)
Conductor: James Levine
Production: Giancarlo del Monaco
Set and Costume design: Michael Scott
Lighting design: Wayne Chouinard
Stage direction: Peter McClintock
Gr Tier Box 30 Front
SB
***ヴェルディ シモン・ボッカネグラ Verdi Simon Boccanegra***
メトの公演もHDを経由してDVD化までされることになった『シモン・ボッカネグラ』が、
指揮だけは同じレヴァインのまま、主要キャストは総とっかえで今シーズンも再演です。
昨年の『シモン』は、声の老化が激しいモリスのずっこけフィエスコ、いつも通りわんわん喚いているだけのジョルダーニのアドルノといった問題もありましたが、
ドミンゴの、年齢やテノール声というハンデを越える、役作りの素晴らしさと舞台プレゼンスの強烈さなどには大いに感銘を受けましたし、
そもそもドミンゴがバリトンの役を歌うという、そのスタート地点そのものにヘッズからの批判も多かったですが、
私自身は”優れた舞台人とは何か?”ということを問う、HDやDVD化の意義のある公演だったのでは、と思っています。
しかし、そんな私でも、今日のシーズン初日の『シモン』を観て、素直にこう思うのでした。HDは一年早かったかも、、。
今日の座席はグランド・ティアーのサイド・ボックス中、二番目に舞台に近いボックスで、
この座席は、舞台の一方の端が観づらいのと、音響面での若干の問題はあるのですが、
一方で、歌手の演技や表情、そして、もう殆ど目の前のすぐ下にいる指揮者やオケの様子もはっきりと見えるので、なかなか面白く、私の好きな座席の一つです。

毎回毎回、もう今度こそは駄目かも、とヘッズに思わせつつ、シーズン初日やHDと言った肝心の場は、
文字通り死んでも指揮台に這い上がって来そうな勢いのレヴァインですが、その通りで、やっぱり今日も這い上がって来ました。
以前にも書きました通り、もはやメトでは”本当に現れた!”というような、珍獣的ポジションに近づきつつあるレヴァインなので、
開演前の拍手はものすごく、ごおおおおっ!!という地鳴りのような喝采があがって、それが一旦静まりかけたと思うと、
どこぞのヘッドが劇場の後ろの方から、”Bravo, Maestro!”と檄を飛ばし、
その後に再び巻きあがった観客からの拍手に本物の温かさがあって、レヴァインの嬉しそうな表情についほろりと来てしまいます。
今シーズン、タイトル・ロールを歌うのは、ディミトリ・ホロストフスキー。
70に手が届かんというドミンゴと比べてしまうと、誰でもそうなのでしょうが、彼のシモンは若々しく、
残りの幕より、プロローグでの設定(つまり、一幕の20年ほど前)の方がぴったり来る位。
彼の声が作品の中でどのように聴こえるか、という点については、大体こういう風になるのではないかな、と予想していたのに近く、
というのも、私は彼の声質自体は非常に美しいと思うし、好きか嫌いかと聞かれれば間違いなく好きな方に入りますが、
彼の声にはヴェルディが書いたオーケストレーションをカットスルーような、もしくはそれを包んで上に広がってくるようなクオリティはなくて、
それが、私が彼はヴェルディ・バリトンでは決してないと思う一因です。
そして、それは今日の公演でも、アンサンブルが厚くなる箇所、特に他の歌手との重唱の場面で感じられました。
というのも、今日共演しているフリットリ、フルラネットはもちろん、デ・ビアジオに至るまで、イタリア勢の歌手達には、
ヴェルディのオーケストレーションを後ろにしても尚立ってくる声の響きがあるのです。
以前、『ドン・カルロ』を鑑賞した時、私はホロストフスキーは声量が少し足りないのかな、という風に思っていたのですが、
先シーズンに聴いたカーネギー・ホールでのラドヴァノフスキーとのジョイント・リサイタルや今日の公演を経て、
それは声量の問題ではなくて、響きの問題なんだと思うに至りました。
単純な声量の観点で言うと、今日の『シモン』でも、まずは十分なものがあったと思います。
(もちろん彼が声量豊かと言うつもりはありませんが、決して音量が少ない訳ではないと感じました。)
そのことは、オーケストレーションの厚みが薄くなったり、またほとんどオケの音を伴わないで歌う場面で、
あれ、こんなに声が出ているんだな、と、逆にはっとすることでも裏付けられると思います。
また、こういうオケの音がない場面での彼の歌は、彼の真骨頂とするところで、彼の声の美しさが際立つというか、
そういえば、リサイタルの時も、アンコールで歌ったアカペラのロシア民謡が一番彼の良さが出ていたのを思い出します。

少し前の、ヴェルディ・バリトン云々、の話に戻り、それでは真のヴェルディ・バリトンでなきゃシモンを歌っちゃいけないのか、
また、そうでなければ優れたシモンを歌えないのか?と問われれば、これはオペラが好きな方ならそれぞれにご自身の基準をお持ちと思いますが、
私自身は必ずしもそんなことはないと思っています。
もちろん、他が全て同じであれば、私も真性ヴェルディ・バリトンのサウンドを取りますが、他が同じでなければ、
結局は、総合して、どれだけ観客の心を動かすことが出来るか、ここに集約されるのではないかと思います。
逆にヴェルディ・バリトンのサウンドがあっても、それが出来なかったら、何の意味もありません。
(ホロストフスキーよりはヴェルディ・バリトン的資質があるメオーニが、味もしゃしゃりもないリゴレットを歌って心底がっかりさせられましたが、
その件は次にあげる1/22の記事まで待ちたいと思います。)
というわけで、全体の話をすると、今日のホロストフスキーの歌は音楽的には非常に良い内容だったと思います。
フレージングはよく考えられているし、スタミナの配分も申し分なく、この上演時間が決して短くない公演の、しかも、歌うパートがかなりに渡るこの役で、
全く疲れを感じさせないだけでなく、第一幕のシモンの演説シーン(”平民たちよ、貴族達よ Plebe! Patriazi! Popolo!”)と、
三幕(かつ全幕)のラストにあたる、フィエスコとの二重唱に、最も大きな波が来るよう、かつ、それらが前にある場面から曲線を描くように上手く盛り上がって行く、など、
非常に巧みなペース配分が行われていて、今回、彼がこの役をメトで歌うのは初なのですが、本当に良く準備して来たことがよくわかる歌唱です。

ただし、演技の方ではもうちょっと改善の余地があるかもしれません。
まあ、相手がドミンゴでは大概の歌手は勝ち目がないので、彼と比べてはいけないとは思うのですが、
この役の、演技や表現面での難しさは、シモンが持っているたくさんの側面、顔が作品の中に全て含まれている点にあって、
愛する女性(アメーリアの母)を思う情熱的な側面、娘思いの優しい父親としての顔、統治者としての厳しさと威厳、
義理の父親との確執に悩む息子としての側面、などなど、これらそれぞれを繊細さを持って演じつつ、かつ、一人の人間として無理なく統合できていなければなりません。
それを成し遂げている事実こそが、私がドミンゴのシモンはあれはあれですごかった、と思う理由になっているのですが、
ホロストフスキーはこれらの多面的なシモンの性質のある部分は巧みに演じているのですが、逆にある部分は弱い、、といったでこぼこがあるのが残念です。
彼が上手くこなしていたのは、怒りに燃える場面(一幕で、フィエスコとの和解を試みるも失敗、フィエスコが立ち去ったと見せかけた後の、
Oh, de' Fieschi implacata, orrida razza!といった言葉などは歌唱と合わせて、ぞっとさせられるような冷ややかさがありました。)や総督としての外の顔を見せている場面で、
逆に、苦手に見受けたのは娘を愛する父親としての慈愛の表現で、この作品の中で幸せの頂点と言っても良い、アメーリアとの、
お互いの素性がわかる、第一幕のあの感動的な二重唱の部分で、歌で手一杯で余裕がないのか、あるいはこういう場面の表現に照れがあるのか、
全然フリットリに自分から絡んで行かなくて、フリットリがとりつくしまなし、、という感じで立ちすくんでいました。
イタリア・オペラですからね、こういうところはもっともっと熱くてもいいんだけどな、、と思います。

後、彼の顔の表情は三つ位しかバリエーションがなくて、ニュートラルな顔、怒りの表情(目がぎろっと横を向く)、そしてニカッと笑った顔、
基本はこの三つだと思います。(実生活は知りませんけれど、少なくとも舞台では。)
特にニカッと笑った表情は、例えばカーテン・コールなんかでこれが出ると、ああ、ホロストフスキーって意外とお茶目なんだわ、と思い、好ましい表情なのですが、
公演の中で使用すると若干浮くというか、もう少し笑い顔のバリエーションを工夫する必要があるかな、と思います。
今回、面白いなと思ったのは、毒を飲んでしまった後、視力を失う、もしくは視界がぼやけて良く見えなくなっている、という設定で彼が演じていた点で、
それが最後に突然、彼の目にはアメーリアの母親の姿が浮かんでいるのでしょう、彼女に向かって歩きながら微笑みながら死んでいく、という演技付けになっていて、
ドミンゴの終始、獅子のような激しさを持った死に様とは全く対照的で、あの音楽と周りの人物たちが浮かべる重苦しい表情の中で、
突然、シモンの顔が天国に照らされているように柔和になるというのは、こちらも不意をつかれる演技で、すごく良いアイディアだと思うのですが、
その柔和になった、心に平和が訪れた時の表情が、突然、”ニカッ”になってしまう、これはあいたたた、、です。
ここで、愛する人と再び出会う喜び、というような、微妙な表情を微笑みに込められると、すごく効果的になると思います。
こうして細かい点をねちねち言うのは全体としては大変良かったからで、さらに優れたシモンへ!という思いの裏返しです。

ホロストフスキー単体でもなかなか聴きごたえがありましたが、それだけでは真にすごい公演にはならない。
今回、素晴らしかったのはアンサンブル・オペラとしての出来、つまり、他のキャストの一人一人も含めた出来です。
まず、フィエスコを歌ったフェルッチョ・フルラネット。『ドン・カルロ』初日での彼の表現力に目と耳が釘付けになったものですが、
彼の舞台での存在感というのは本当にすごいと思います。プロローグの、前景にシモンを取り囲む民衆が居て、舞台奥にある壁沿いの石段を上りながら、
フィエスコがその様子を眺めつつ去るという演技なんですが、こんな後景のはずの彼が、前に居るシモンのホロストフスキーよりも、
強い存在感を発しているのです。
去年、モリスが歌った時はこんな演技あったっけ?って感じなんですけど。(全然モリスに視線が向かなかった。)
フルラネットは、スカラの『シモン』のフィエスコが、”これ、どうしましょ!?”という出来だったのですが、
今回は歌唱もその時とは見違える位安定していて、声も本当に良く通っていましたので、あの日は余程不調だったのだと思われます。
それこそプロローグから最後の幕まで、演技と歌唱の両方で名人芸を繰り広げていたフルラネット。
第三幕で、パオロとの会話を通して、シモンに複雑な思いを抱き続ける彼のフィエスコの苦悩の表現にさすが、、と酔いしれ、
いよいよシモンと対峙する場面は、もうオケの素晴らしい演奏もあって、息詰まるような迫力だったんですが、
それまで頭巾付きの修道士が着るようなローブをつけたフィエスコがシモンの総督の椅子に、頭巾をかぶったままじっと座っているところに、
シモンが部屋に転がり込んで来て、自分は海で(海賊として)死んでしまっていた方が良かったのだ、、と嘆くシモンに、
背後から、”お前にはきっとその方が良かったろう。”と話しかけ、
”紛れ込んできたのはどこのどいつだ?”とシモンが答えると、椅子から立ち上がり、”お前を恐れぬものだ!”と歌いながら、ばっ!と、
着ていたローブを脱ぎ捨てて正体を現す、という、遠山の金さんもびっくり!のかっこいいシーンがあります。
フィエスコはこの修道士ローブの下に豪華なシルクの衣装を二枚重ね着していて、
すぐ下には袖つきの、床まである美しいシルクの上着(最後の写真を参照。)、
その更に下に、ノースリーブの床まで届くロング・ワンピースのようなものを身につけていて、
この下のワンピの布地がちらっと上着の下に見えて、衣装の豪華さを際立たせているのですが、
ばっ!とローブを脱ぎ捨て、”そうだ、わしはフィエスコだ!”と見得を切ったフルラネットを見て、私は目が点になり、固まってしまいました。
だって、フルラネット、ロング・ワンピの下に真っ白なコットンの半そでのTシャツを着て、ニの腕から下をまる出しで仁王立ちしているのですもの!!
もしかして、、、?
やっぱり!!フルラネット、修道士ローブだけを脱ぎ捨てなければならないところを、その下の上着まで脱ぎ捨ててしまったのね、、。
それにしても、シルクの長ワンピの下の白いTシャツがジャンカルロ・デル・モナコの超トラディショナルで豪華な舞台に嫌なくらい映えるーっ!!
すごい迫力でシモンをにらみつけながら立っているフィエスコ!でも、白いTシャツ!!だめ、、肩がひくひくして来た、、。
ホロストフスキーは幸い客席側に向かってひざまずきながら熱唱していて、全く気がついていないみたいなので、
つい私も、”そうよ、今は絶対に後ろを向いちゃ駄目よ!!”と心の中で叫び続ける。
と、フルラネットがやけに腕がスースーするな、と感じたのか、視線を自分の体に落として、目玉が飛び出さん位びっくりしているのが見えました。
自分のパートを歌いながら、蟹歩きでこっそりと自分の脱ぎ捨てた衣装の山に近づき、長袖の上着を探し当てこっそり着用するフルラネット、、。
こんなお茶目なフルラネット、初めて見ました。
白Tシャツなしで、直に衣装を身につけていれば、そのまま上着を着ないで押し通す手もあったのでしょうけれど、、、たかが白Tシャツ、されど白Tシャツ、です。

アメーリア役を歌ったバルバラ・フリットリに関しては、彼女の最高の歌唱の一つを聴いた、という気がします。
真っ直ぐに声が飛んで来る、あの美しい発声に、この役にぴったりの、楚々としていながら、かつ芯の強そうな雰囲気、、。
彼女の”星と海は微笑み Come in quest'ora bruna”は、生の全幕の舞台で、こんなにこの曲を上手く歌えるソプラノがいるのか?!と、
本当にびっくりするような素晴らしい出来でした。
舞台に登場したかと思ったらすぐに歌いださなければならないこのアリアは、本当に難しいと思うのですけれど、、。
昨シーズンのピエチェンカはあの冒頭の木管を前のめり気味に演奏させるレヴァインの指揮にきちんと乗れてなかったような部分があったのですが、
全く同じアプローチで指揮をしているレヴァインの意図を、フリットリの方は的確に摑んで、指揮との息もぴったり合っていました。
フリットリは現在レヴァインのお気に入りのソプラノのように見受けられるのですが、こういうのを聴くと、もっとも!と思います。
彼女の役作り、芝居のうまさは言わずもがな。
こういう役では、彼女は舞台上で非常に思い切ってゆっくり動くのですが(歩き方なんかほとんど摺り足みたいな部分もあります)、
それがアメーリアの高貴な身柄とか気性を本当に的確に表現しています。
重唱の部分での他の歌手への繊細な気配りのセンスもさすがで、三幕ラスト、シモンが息を引き取った直後に、
ガブリエーレ役のデ・ビアジオと歌った”Padre! 父上!”の一言は、もうあまりに美しくて失神するかと思いました。

ラン全部をラモン・ヴァルガスが歌う予定だったガブリエーレ役は、そのヴァルガスが初日の少し前から風邪を引き、
カバーをつとめているロベルト・デ・ビアジオが今日の代役をつとめました。
NYタイムズの評に、彼は現在42歳、元フルート奏者で、歌を歌い始めたのはたった4年前(!)ということになっているんですが、
2004年に京都のイタリア文化会館でピンカートン(『蝶々夫人』)をコンサート形式で歌っているみたいなので、劇場の全幕に立ったのは、という意味なのかもしれません。
また、日本では『ルチア』のエドガルドも歌ったことがあるようです。
デ・ビアジオは今日がメト・デビューになったんですが、レヴァインが指揮の、演目初日の公演の、しかも代役でデビューなんて、
どれだけプレッシャーが大きく、どれだけ度胸がいることでしょう!
相当緊張していたのか、もう最初の方は表情が顔に張り付いていると言う感じで、レヴァインがリラックスして!という感じで微笑むと、
それに答えて微笑んだ、その微笑んだ顔がまたそのまんま張り付いてしまって、なぜその歌詞の内容で今微笑む?という場面があったのは愛嬌です。
でも、彼の歌声は、一声目から、これは本当に綺麗!と思いました。音にピンがあって、基本的な発声に無理が無く、自然に音が出てくるので、
非常に耳に心地良い。
声質は、からっとして軽くはあるのですが、適度に男性的な音で、この役にはぴったりだと思います。
すらっとしていて身長もそこそこあるので、舞台姿も綺麗。
中盤で音色が少し浅くなったり、二幕のアリア(”我が心に炎が燃える Sento avvampar nell'anima”)で一箇所、
高音の音色が損なわれた部分がありましたが、そのまま崩れず、繰り返しの部分では同じ音をきっちりと出し、
終盤にはまた盛り返して、先ほども書いたPadreを非常に美しい音で聴かせるなど、全体的には非常に良い歌唱で、
何より彼はこの役に必要な高音を綺麗に出せる力があるので、ガブリエーレ役を聴く本来のスリルがあります。
この中盤の部分では、一幕の冒頭で見せていたような綺麗な発声が若干損なわれていた部分もあったり、
オケが厚い重唱部分で突然声が聴こえにくくなったりする箇所が数箇所あり(もしかして、休憩??)スタミナも含め、その辺りがこれからの課題かもしれません。
それにしても、ほんと、今年メト・デビューのテノールがこんな歌唱を聴かせるのですから、昨年のジョルダーニの歌唱は、今となってはほとんど冗談としか思えません。
更に、もしかすると、本キャストのヴァルガスよりも、デ・ビアジオの方がこの役には良いのではないか、という風に、私は思っています。
パオロ役は大事な役ゆえ、なかなか観客の期待が高く、今日のアライモは一部の観客からブーを受けていましたが、
私は昨シーズンに比べてそう悪いとは思いませんでした。
最後にオケですが、本当に素晴らしかった。
プロローグから何かがクリックしたのが明らかで、それはオケのメンバーの表情を見ていても伝わって来ました。
レヴァインは優れた指揮者ではありますが、このレベルの優れた演奏は、それだけではなくて、何か別の、
特別なマジックがあった時にしか生まれないような類の演奏で、とにかく至福でした。
こういう演奏に出会うと、”そうそう、これこそが私がメトに通い続けている理由じゃないか!”と思い出せてくれます。
ただ、今シーズンの『シモン』の演奏はプロローグと一幕が演奏され、たった1回のインターミッションの後、二幕と三幕が演奏されるという強行スケジュールで、
客が早く帰宅できるよう工夫するのもいいですけれど、レヴァインを殺す気か!と思います。
この日はカーテン・コールで舞台上にまで出てきてくれていましたが、指揮自体は相当辛かったようで、二日目の公演(1/24)は降板してしまいましたし、
長時間リハーサルをするので有名な彼が、メト・オケの演奏会のリハーサルを早めに切り上げるなど、
今の彼にとって長時間の指揮はかなりの負担になっているようです。
今日のような素晴らしい演奏を聴けるなら、1回多いインターミッションで少しでもレヴァインが楽になるというなら、
観客はほんの少しの不便を分かち合う位の優しさがあっても良いと思うのですけど、、。
Dmitri Hvorostovsky (Simon Boccanegra)
Barbara Frittoli (Maria / Amelia Grimaldi)
Roberto De Biasio replacing Ramón Vargas (Gabriele Adorno)
Ferruccio Furlanetto (Andrea / Jacopo Fiesco)
Nicola Alaimo (Paolo Albiani)
Richard Bernstein (Pietro)
Edyta Kulczak (Amelia's lady-in-waiting)
Adam Laurence Herskowitz (A captain)
Conductor: James Levine
Production: Giancarlo del Monaco
Set and Costume design: Michael Scott
Lighting design: Wayne Chouinard
Stage direction: Peter McClintock
Gr Tier Box 30 Front
SB
***ヴェルディ シモン・ボッカネグラ Verdi Simon Boccanegra***



















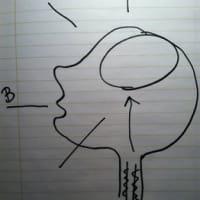
ホロストフスキーがMETで初めてシモンを歌うということは、私にとってすごく楽しみでもありましたが、彼がヴェルディ・バリトン最高峰の役を歌うことに拒否反応を示すオペラ・ファンも多いでしょうし、METで成功するのかとても心配でした。
初日のラジオ放送はライヴで聴くことができましたが、こちらがビックリさせられるほどの絶好調ぶり。
近年の彼のオペラステージでは1,2を争うほどの出来だったのではないでしょうか。
今思うと、2006年にヒューストンで初めてシモンを歌った時の録音は、めっちゃ力が入っていて、「張り切りすぎや~!」と突っ込みを入れたくなるほどだったのですが、ずいぶん自然に歌えるようになったと思います。
お陰さまでNYタイムズなどにもいい批評をいただけて、まずはホッと一息。
しかし、まだ安心はできませんでした。
そう!MadokakipさんのReviewがupされていなかったのであります!
正直に言わせていただくと、MadokakipさんのReviewはすごーーーーく怖かったです
自分がいいと思えば、ほかの人が何と言おうと関係ない!と自分に言い聞かせてはいるものの、Madokakipさんがホロストフスキーをメッタギリにする妄想がふくらみ、今日の今日までまたしても胃痛に悩まされていたのであります・・・。
(被害妄想強いんです、私
とりあえず、今はやっと楽になりました(笑)
常々私も言っておりますが、彼の声はオケ伴よりもピアノ、そしてピアノよりも無伴奏が一番良さが出ると思っています。
「なんだ、それじゃオペラ歌手じゃないじゃん」
そう言われるかもしれませんが
フリットリとのデュエットシーン・・・う~ん、彼は自称“Shy”なので苦手かもしれませんね。
過去、いろんな彼のラブシーン(というのかな?)を観てきましたが、そういうシャイなところは感じられます。
キスシーンはいつも寸止めで、キスしてるところはほとんど見たことない・・・ネトレプコにキスされて、ちょっと引いているのは見たことありますが(笑)
ニカッという笑顔・・・お許しください
これがプライベートでは彼のチャームポイントなのですが、舞台ではウィークポイントかもしれません。
ひとことで言うと、かわいいんです
ファンの間でも「笑うと少年のようになっちゃうんだよね~」とよく話題になります。
彼のFacebookに、前半の若い頃のシモンの衣装を身につけた舞台裏のビデオがupされていましたが、これがまた50前の男性とは思えないほど若くてカワイイ・・・。
この若さが、役柄の邪魔をすることがありますね。
白Tシャツ姿のフルラネットの話・・・笑わせていただきました。
それはホロストフスキー、見ていなくて幸いです。
彼のことだから、見てしまったらきっと笑いをこらえ切れなかったと思います
これは文句なしの名演ですね。フリットリとフルラネットはおっしゃる通り最高。
ホロストフスキーもいいシモンだったと思います。
レヴァインの指揮もプロローグからもの凄い迫力。
一回一回の指揮にすべてを賭けている、という感じが伝わってきて、今まで聴いた彼の指揮の中でも次元が違う感じです。
東京でもこの指揮が聴けるといいんですが
…。
ビアジオはいいテノールだと思います。ベルガモのオペラと来日した時のエドガルドは聴けませんでしたが、声も良いし、なにより様式感があります。
まだ少し不安定なところもありますが、代役で貴重なチャンスをものにしたというところでしょうね。
今後に期待したいと思います。
↑PCの前なので、普通に笑えばいいのですが。。
ホロストフスキーは、結局気づかずにすんだのでしょうか?大事なシーンですものね。
>Madokakipさんがホロストフスキーをメッタギリにする妄想がふくらみ
ええ、もう最近、メッタぎりが多かったですものね、、、ポプラフスカヤ、ラドヴァノフスキー、、(溜息)。
実を言いますと、今回の感想はこれでもちょっと厳しい方に入るかもしれません。
NYタイムズの批評よりも何よりも大切なヘッズの意見、これがもう圧倒的にホロストフスキーのシモンは良かった!というもので、
ネガティブな感想は私は今のところ、まだ一度も目にしていません。
それなのに厳しい目に感想を書いたのは、それは私が彼のシモンを気に入らなかったからではなく、むしろ逆で、想像以上に良かったので、
つい、欲が出て、ここを直せばもっと良くなる!と、あれこれ書いてしまったんですね。
この役はまだまだこれから長く歌って行くはずの役ですし、せっかく音楽(歌唱)の方が完成度が高いのですもの、
演技も目標は高く!彼が演技でドミンゴを越えられないなんて、誰が決めた?という勢いで、
色々と書いてしまったわけです。
これから彼の歌うこの役がどんどん進化して行くのが楽しみですね。
>ひとことで言うと、かわいいんです
わかりますよー。私もオフステージや終演後に出るあの表情は好きです!!
でも、あれだけルックスが良いのですもの、舞台上での表現の幅がもっと増えたら、鬼に金棒だと思います!
>それはホロストフスキー、見ていなくて幸いです。
ですよね(笑)あれ、振り向いていたら、絶対に笑うと思います。私なら笑いますもん!
(というか、実際笑っていたんですけど、、肩で 笑)
フルラネット、よくぞホロストフスキーが振り向く前に、気づいてくれた!!と思います。
次回からは白T厳禁!ですね。
本当に、メトでのシモン・デビューがこのような大成功に終わって、良かったです & おめでとうございます。
私もこのような素晴らしい公演を聴けて、最高に幸せでした!
これだけ出演している全員、そしてオケの演奏までが良い『シモン』というのは、そうそうないと思います。
最初は珍獣、いえ、レヴァインが本当に来た!という、どちらかというとイベント的な意味での盛大な拍手だったのが、
場、幕を重ねるにつれて、公演の中身自体への熱狂に変わっていったのもエキサイティングでした。
デ・ビアジオは2006年の『ルチア』の音源をYouTubeで聴きましたが、当時よりは間違いなく歌唱に安定感が増しましたし、
実際にオペラハウスで聴く声が、ピン(ping)と美しさを兼ね備えていて、とても良い素質を持ったテノールだと思います。
『ルチア』ではアンサンブルに問題があるように思いましたが、今回はレヴァインの指揮に良くついて行っていましたし、
スロー・スターターのため、年齢ももはや若くはないですが、良い指揮者や指導者に恵まれれば、
伸びる可能性もある人だと思います。
また、私もあまりにタイプの違うシモンなので、どちらかを選ぶことは出来ないのですが、
シモン以外の役に関しては、圧倒的に今シーズンの方が上ですね。
この日の初日はデ・ビアジオが興奮に花を添えていたと思うんですよ。
ヴァルガスも丁寧な歌を歌うテノールですし、ラジオですら、まだ彼のガブリエーレを聴く機会がないので、
彼を駄目だという気は毛頭ないのですが、メト・デビューの歌手があれだけの歌唱をこの役、
この舞台で披露した、というのは、それだけで、かなりスリリングなことでしたので、、。
そのうえに、フリットリとフルラネットがいて、オケが優れた演奏を繰り広げているのですから、、、
mamiさまの遠い目も納得というものです。
ええ、無事に(笑)
もうどきどきしてしまいましたよ、いつホロストフスキーが振り向いてしまうかと思って!
フルラネットのような大御所がこのピンチにどう対処するのか?と、そこもどきどきだったんですが、
彼も相当パニック・モードだったのか、かなり素の対処でした。
終演後に、レヴァインの頬を“良くやったな!”という感じで、
ぽんぽん!とフルラネットが平手で叩いていたんですが、レヴァインにあんなことが出来る人は、
もう現役のオペラ歌手ではそう多くはないはずです。
それにしても、良く考えてみれば、あの白Tはレヴァインの指揮しているところからははっきり見えていた筈なんですけどね、、
レヴァインもあまりにびっくりしたか、素通りでした、、、。
(特にレヴァインからは服が脱げてるぞ!というようなシグナルはなかったと思います。)
今回のシモンは本当に評判高いですね。いやKewGardensさまが言ってたんですけど…
私は初回の放送を聴き逃したので、次は週末のマチネのラジオ放送を今度こそ聴こうと、すごく楽しみにしています!シリウスは契約していないので…
MadokakipさまのおかげでMETの舞台が身近に感じられます。今後ともよろしくお願いします!
フィエスコ、むっちゃ健康的ですね(違)カツラまでしっかり作りこまれた衣装・美術の中のTシャツ姿を想像して、PCの前で大笑いさせていただきました。こんなアクシデントが起こったら、私は笑い上戸なので絶対噴出してしまいます~。流石に百戦錬磨のフルラネットも慌てたことでしょうね。
公演自体、非常にバランスの取れた「シモン」だったんですね。こういうMETらしい演出の公演がもっと復権してくれると良いんですが…無理でしょうかね。