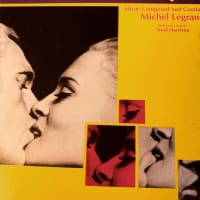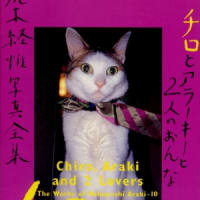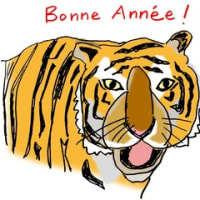今日は突然のお誘いにより
代官山へ出掛けた。
LANDというイベントで
若手のアーティストユニット(彼らはメオトだそう)
夫婦漫才ならぬ夫婦ペインティング。
HITOTZUKI
によるライヴペインティングと
percussion:DAISUKE IWAHARA(TOKYO NANGADEF)
DJ:KATSUYA TANIGUCHI
の面々が奏でる音楽とのライヴセッション。
とても面白かった。
ライヴペインティングの内容は
音楽に喩えればインプロビゼイション(即興)だった。
まさに実際の音楽のビートの中で
取り壊され、新たに恵比寿に引っ越すギャラリー
POINTの壁を使って描画は行われた。
以前観た展覧会で、
アーティスト磯崎道佳さんによる、
取り壊しされる家を使ったインスタレーション、
「横浜かくれんぼ/ずいっと野毛山あたり」の事をふと思い出す。
あ、そして、その前は
東恩納祐一さんが代官山で解体されるマンションのモデルルームで行った
インスタレーション
の事も思い出す。
とてもクールかつカラフルでゴージャス&ゴシックだったので
以来、印象に残っていた。
壊されゆく建物での創作は面白い
まさに破壊と創造なので
音楽創作のメソッドを齧り始めたせいか
観ていて前回行われた
「音楽の構造分析」
という特別講義で解説された『分節』の事が思い出された。
『分節→言葉の意味作用の変化によって構成される
全体における部分』と私は日記で定義したのだけど
こうしたライブペインティングという
行為はどこか音楽的だった。
モチロン、そこでライヴとして演奏されていた
音楽的グルーヴと自らの感覚を共鳴させながら
彼らは描いていた訳だけど。
そしてその中にも確かに
感覚的なグルーヴ&ビートや
それとは対照的である
意図的な技法も垣間みられた。
ただ滅茶苦茶にやっているわけではないという事(文脈)が
わかると観ていて俄然面白くなってくる。
それが若者を場内いっぱいにした動員力なのかな~
技術がどう、とか手法が新しいわけでもないのに
確かに観ていて面白いのだ。
お誘いくださったTOKYO SOURCE
編集長の近藤ヒデノリさん
が言っていた、
現代アートは表現の中の『ひずみ』を
どんどん増長させていく部分があるのだけれど
こうしたストリート寄りのアートが持つ
大衆への「伝染性」の早さのようなものは
どこから来るのだろう、といった言及は
音楽にもどちらかというと
あまり(敢えて?)解りやすくないものもあれば
『商業音楽(POPS)』という大衆の心を、『共感』を
掴みやすい傾向を(確信犯的に)持たせるものもあるわけで
(私はまさに今そのメソッドを学んでいるのだけど)
こういった対比は考えさせられる点があって興味深かった。
アートにおけるジャンルは違っていても
根本は繋がっているという事を
実感すると何だか世界は広がるのだった。
今宵はとても美しい満月の良い夜であった。
そして、明日は待ちに待った
ジムオルークによる特別講義、、、!
日記も長くなりそう(笑)
代官山へ出掛けた。
LANDというイベントで
若手のアーティストユニット(彼らはメオトだそう)
夫婦漫才ならぬ夫婦ペインティング。
HITOTZUKI
によるライヴペインティングと
percussion:DAISUKE IWAHARA(TOKYO NANGADEF)
DJ:KATSUYA TANIGUCHI
の面々が奏でる音楽とのライヴセッション。
とても面白かった。
ライヴペインティングの内容は
音楽に喩えればインプロビゼイション(即興)だった。
まさに実際の音楽のビートの中で
取り壊され、新たに恵比寿に引っ越すギャラリー
POINTの壁を使って描画は行われた。
以前観た展覧会で、
アーティスト磯崎道佳さんによる、
取り壊しされる家を使ったインスタレーション、
「横浜かくれんぼ/ずいっと野毛山あたり」の事をふと思い出す。
あ、そして、その前は
東恩納祐一さんが代官山で解体されるマンションのモデルルームで行った
インスタレーション
の事も思い出す。
とてもクールかつカラフルでゴージャス&ゴシックだったので
以来、印象に残っていた。
壊されゆく建物での創作は面白い
まさに破壊と創造なので
音楽創作のメソッドを齧り始めたせいか
観ていて前回行われた
「音楽の構造分析」
という特別講義で解説された『分節』の事が思い出された。
『分節→言葉の意味作用の変化によって構成される
全体における部分』と私は日記で定義したのだけど
こうしたライブペインティングという
行為はどこか音楽的だった。
モチロン、そこでライヴとして演奏されていた
音楽的グルーヴと自らの感覚を共鳴させながら
彼らは描いていた訳だけど。
そしてその中にも確かに
感覚的なグルーヴ&ビートや
それとは対照的である
意図的な技法も垣間みられた。
ただ滅茶苦茶にやっているわけではないという事(文脈)が
わかると観ていて俄然面白くなってくる。
それが若者を場内いっぱいにした動員力なのかな~
技術がどう、とか手法が新しいわけでもないのに
確かに観ていて面白いのだ。
お誘いくださったTOKYO SOURCE
編集長の近藤ヒデノリさん
が言っていた、
現代アートは表現の中の『ひずみ』を
どんどん増長させていく部分があるのだけれど
こうしたストリート寄りのアートが持つ
大衆への「伝染性」の早さのようなものは
どこから来るのだろう、といった言及は
音楽にもどちらかというと
あまり(敢えて?)解りやすくないものもあれば
『商業音楽(POPS)』という大衆の心を、『共感』を
掴みやすい傾向を(確信犯的に)持たせるものもあるわけで
(私はまさに今そのメソッドを学んでいるのだけど)
こういった対比は考えさせられる点があって興味深かった。
アートにおけるジャンルは違っていても
根本は繋がっているという事を
実感すると何だか世界は広がるのだった。
今宵はとても美しい満月の良い夜であった。
そして、明日は待ちに待った
ジムオルークによる特別講義、、、!
日記も長くなりそう(笑)