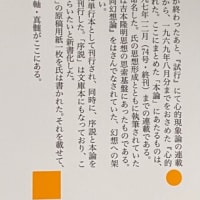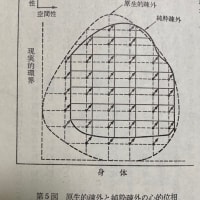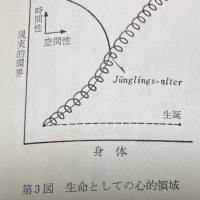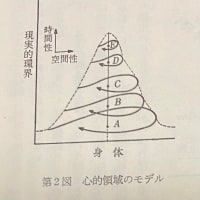言の葉綴り 142日本詩人選 12
源実朝(事実)の思想 その2
吉本隆明著
日本詩人選 12 源実朝
著者 吉本隆明
昭和四十六年八月二十八日発行
発行所 株式会社筑摩書房より抜粋
X I 〈事実〉の思想 その2
承前
承元三年(一二○九年)五月、頼朝以来の宿将のひとりであり、実朝が好意をよせていた和田左衛門尉義盛が、上総の国司に任じられるよう望んで内々に申し入れた。実朝はこの老将の望みをかなえてやりたいとかんがえ母政子にはかったが、頼朝の時代には武門の受領はこれを停止すべきよしの沙汰があり、このような例はゆるされなかった。いま、この願いをいれるのはあたらしい範例であり、女性の口を入れるべきことではないからとていよく拒否された。実朝はこの義盛の願いをかなえることはできなかった。
義盛は旬日をおいて、上総の国司を所望であるむねを、今度は陳情書をもって大江広元まで提出した。それには、治承以後の和田義盛一族の勲功をのべ、上総の国司の任を賜ることがこれからの余生にただひとつの望みであると記されていた。
いっぼう北条義時は、これより数ヵ月あとに、郎従のうち功あるものに侍に準じる位にとりたてる沙汰を賜りたいと申出た。実朝は無秩序にそういうことを許すのは後難のもとだとして、これを卻けた。また、おなじころ和田義盛の上総の国司所望の件について、内々に時をみてはからうから沙汰を期して待つようにとなだめた。義盛はよろこび感謝した。
このあたり実朝の決裁はさえている。たぶん、義時の所望もこのかぎりでは実朝の判断をこえるような不可解さはなかったのである。和田義盛と北条義時のちがいはなんであろうか。たぶん、義盛には〈制度〉としての武門という観点がなく、忠義一途の武将であったが、義時には〈制度〉も〈権力〉もなにを本質とするかがわかっていた。義盛が上総の国司を望んだのは、頼朝が蜂起してから忠誠と武勇をもってつくしてきた一族が、律令官制上の一国の国司を望むことは不当ではないというかんがえかたに基いている。だが、義時が郎従の功あるものを侍分にとりたててほしいと申出たとき、それは幕府国家の内部で処理しうるものだからという視点にたっていた。実朝はこのふたつの意味がよく判っていたはずである。
実朝は疱瘡のあとずっとそうであったといえばいえなくもないが、晩年にちかずくにつれて、神事•仏事に熱がはいらなくなって、おおくは代理を奉幣させるようになっている。ようやく青年にたっしたときには、実朝のこころは乾いてしまっていたかもしれない。なぜそういう憶測をくだすかといえば、実朝の〈景物〉はあたかも〈事実〉を叙するというよりほかないような独特な位相であらわれ、けっして〈物〉に寄せる〈心〉でも、〈心〉を叙するために〈景物〉をとらえる叙情でもないとしかいいようがないところがあるからである。
みな月廿日あまりのころ夕の風すだれうごかすをよめる
秋ちかくなるしるしにや玉すだれ
小簾の間とほし風の涼しさ
萩をよめる
秋はぎの下葉もいまだ移ろはぬに
けさ吹くかぜは袂さむしも
十月一日よめる
秋は去ぬ風に木の葉は散りはてて
やまさびしかる冬はきにけり
霰
もののふの矢並つくろふ籠手の上に
霰たばしる那須の篠原
同
笹の葉に霰さやぎてみ山べの
嶺の木がらししきりて吹きぬ
これらの〈景物〉を叙している歌は、八代集のどこにも場所をもうけることはできない。『万葉』後期にいれるには、あまりに〈和歌〉形式の初原的な形をうしないすぎているし、『古今』にいれるには、語法が不協和音をいれすぎている。『後拾遺』にさしこめば、あまりに古形を保存しすぎている。そうかといって『新古今』にさしこむには、もっと光線が不足している。この独自さは実朝の〈景物〉の描写が、〈景物〉をただ〈事実〉として叙して、かくべつの感情移入もなければ、そうかといって客観描写のなかに〈心〉を移入するという風にもなっていないところからきているようにみえる。実朝の〈心〉は冷えているわけではないが、けっして感情を籠めようともしていない。感情の動きがメタフィジックになってしまっている。実朝は青年期にたっしたとき、すでにこういう心を身につけなければならない境涯におかれていた。
〈夕べの風がすだれをうごかして透ってくる涼しさ〉という表現は、〈涼しいな〉という主観でもなく、〈涼しくわたってくる風〉という客観描写でもなく「風の涼しさ」という状態でとめられている。それだからどうしたということではない。この止め方は実朝の詩の方法のひとつの特徴である。この特徴が表象しているものは、「風の涼しさ」を感じているじぶんを、なんの感情もなく、じぶんの〈心〉がまた〈物〉をみるように眺めているという位相である。だから心情の表現が叙景の背後にかくされているのではなく、〈じぶんの心情をじっと眺めているじぶん〉というメタフィジックが歌の背後にあらわれてくる。このメタフィジックもまた詩人としての実朝に独特のものであるといってよい。
「けさ吹風は袂さむしも」というのは、まったく主観的に〈さむいことであるな〉といっているにもかかわらず、さむがっている作者ではなく、さむがっているじぶんという〈事実〉をながめている位相しかつたわってこないようにおもわれる。なぜこういうことになるのだろうか。たぶん実朝の〈心〉が、詩的な象徴というよりも、もっと奥深くの方に退いているからである。この独特の距離のとり方が実朝の詩の思想であった。「秋は去ぬ風に木の葉は散りはてて」の歌でもおなじなのだ。「山さびしかる冬はきにけり」を〈山はさびしき〉とか〈山ぞさびしき〉と表現すれば、並の叙情歌になったろうが「山さびしかる」と表現しているために、〈心〉は奥のほうに退いて〈山はさびしくなるだろうなとおもっているじぶんを視ているじぶん〉というようにうけとれることになる。
「ものゝふの矢並つくろふ」は真淵もあげ、子規も引用している周知の歌だが、かれらのいうこの万葉調の力強い歌は、けっしてそうはできていない。名目だけとはいえ征夷将軍あったものが、配下の武士たちの合戦の演習を写実した歌とみても、そういう情景の想像歌としてみても、あまりに無関心な〈事実〉を叙している歌にしかなっていない。冷静に武士たちの演習を眺めている将軍を、もうひとりの将軍が視ているとでもいうべきか。
「笹の葉に霰さやぎてみ山べの」も叙景のようにみえて、〈景物〉を叙しているじぶんの〈心〉を〈心〉がみているという位相があらわれざるをえない。
実朝の詩の思想をここまでもっていったものは、幕府の名目人として意にあわぬ事件や殺戮に立ちあいながら、祭祀の長者として振舞わねばならない境涯であった。
建暦元年(一二一一年)十二月二十日、和田義盛は上総の国司を所望した陳情書を、子息四郎兵衛尉を介して返却してもらいたい旨を大江広元に申入れた。業を煮やしたというべきであろうか。あまりに沙汰がないところから、義盛はいまはこれまでとかんがえたにちがいない。実朝は、しばらく余裕をみてうまくはからう旨つたえてあるのに、この挙におよんだことを心持よくおもわなかった旨を『吾妻鏡』は記している。しかし義盛にしてみれば、北条氏があれほど特権をうけながら、忠誠一途の宿将である和田一族にたいして、それくらいのことが握りつぶされていることが耐えがたかったにちがいない。おそらく母政子と北条一族のさしがねであった。実朝としては、この一徹の老将の心事をおもって心苦しかったにちがない。建暦二年も六月になって、実朝は和田義盛の邸を訪れてこの宿将を慰めねぎらっている。
さらに八月には、北面の三間所に伊賀前司朝光とともに和田義盛をつめさせるようにはかった。つまり近習なみにあつかおうとしたのである。宿将ではあるが、昔の物語などをききたいからだというのが実朝の名目であった。実朝は義盛がおもいつめている気配を感じて、これを慰めようとしたかもしれないし、この老将がじぶんの気ごころを理解する最後の生き残りとかんがえたかもしれなかった。実朝はよく気がつくやさしい心くばりをもっていた。
ところが、建保元年二月十五日、安念という僧侶が捕えられたのを期に、謀反の企てがあったことが発覚したと『吾妻鏡』はつたえている。そのなかに和田義盛の子息義直、義重の名があげられ、和田平太胤長もとらえられた。謀反といっても、もちろん北条氏を除こうとする企てであった。義盛は上総の伊北庄にいたが鎌倉にはせ参じ、わが子義直、義重らの助命をこうた。実朝は忠誠一途の老将の心にめでてこの二人を赦した。義盛は「老後の眉目を施して退出」したが、翌日、一族九十八人を引率して南庭に列座し、一族和田胤長の助命をも請うた。実朝は和田胤長が張本人とされているため、北条氏の手前、どうしても赦すわけにゆかなかった。そして和田一族の前で、胤長に縄をかけたまま奉行山城判官行村にひき渡させた。万事休すであり、この屈辱をうけた和田一族は、北条氏から実朝を奪うため蹶起する以外に道がなかった。胤長の屋敷領地は北条義時に拝領となり、もはや合戦よりほかに和田一族のなすべきことはのこされなくなったのである。
もちろん、実朝にはその帰すうはよくわかっていた。義盛には兵をあげるほかに道はのこされていないはずである。
すでに和田一族の蹶起は、幕下の諸将においても自明のこととしてうけとられるようになった。実朝の近習として信任の厚かった和田新兵衛尉朝盛は、父祖一党の蹶起が近くにあるのを知って蟄居していたが、実朝の下に参上して「公私互に蒙霧を散じ」(「吾妻鏡」)、心ゆくまで交歓を遂げたのち退出し、そのまま髪を切って蓮浄房の草庵で得度し、実阿弥陀仏と号して、郎党数人をつれて京都へ旅立った。板ばさみの苦しさを逃れるためである。朝盛の出家を知らせるため、郎党は義盛のもとに書状をたずさえていった。「叛逆の企ては、いまにおよんではとどめることもできません。しかし一族にしたがって実朝公に弓矢をむけることもできませんし、幕下に参じて父祖に敵することもできません。それよりも世を逃れて自他の苦しみを免れたいとおもいます。」とかかれていた。義盛はこれをきいて、僧体になっていても連れもどしてこいと四郎左衛門尉義直に命じた。朝盛は武勇にすぐれ、合戦のばあいに将としての器量をもっていることを惜しんだのである。実朝は、翌々日朝盛が出家したことをきいて、衝撃をうけ、人をやって「父祖の別涙を訪はしめ」た。
和田義直は朝盛入道を駿河国手越駅のあたりでつれもどしたが、義盛は朝盛を叱責した。また朝盛は黒衣のまま幕府に参上し実朝に挨拶した。これは実朝より慰撫のよびだしがあったためである。義盛は年来帰依するところ厚かった道房という僧を追放したが、人々は追放に名をかり、和田一族勝利の祈祷をなさしめるため大神宮へ遣わしたのだという風評をたて、ますます物情騒然となった。
実朝は、宮内兵衛尉公氏をつかわして和田邸におもむかせ、合戦の準備をしていると風聞があるが本当かどうかを問わせた。しばらくして義盛は寝殿からでてきて造あわせをとびこすとき、烏帽子がぬけて公氏のまえに落ちた。ちょうど人の首が打ち落されるのに似ていた。公氏は心中で、義盛は一族が叛乱にたつときはいさぎよく誅に服する志をあらわしているのだな、とうけとった。公氏は実朝からの問いただしの旨をのべた。
義盛はこたえた。頼朝将軍が在世のときは忠誠をはげみわれながら功をつとめた。そのために恩賞にあずかることも過分に過ぎるほどであった。頼朝将軍がなくなられたあとは、まだ二十年を経ないのに、おきわすれられたものの恨みをかこっている。たびたび陳情愁訴におよび、涙ながらに訴えるところがあったが実朝将軍の心にとどかない。これでは退いて家門の運つたなさを恥じるばかりであり、すこしも謀反の企てなどないーと。言葉がおわって保忠、義秀以下の勇士たちが列座して、兵具を開陳した。公氏は帰ってこの旨を報告した。その間、相州北条義時は参上して鎌倉在所の御家人たちを御所に呼んだ。そして義盛は日ごろ謀反の疑があり、蹶起の事はすでに決まっているかもしれないから、準備をおこたらぬよう指示した。ただし、まだ甲冑をつけるにはおよばないと申し伝えた。夕刻に、刑部丞忠季を使者にたて、和田義盛のもとにやった。和田氏反逆の風聞があるが驚いている。まず蜂起をやめて実朝将軍の裁可をまつべきであるとおもうーと。義盛はそれに答えていった。実朝将軍になんの恨みもいだくものではないが、相州北条義時の振舞いは、あまりに傍若無人でほかに人なきが如くであるので、問責のために鎌倉に発向しようとする群議が、近ごろ和田一族の若武者のあいだにある。義盛は度々これを諌めようとしたが、一切無効でもはや決意を交わしてしまっている。この期に望んでは老骨の力のとどかぬものとなってしまったーと。
かくして、いわゆる和田合戦の火ぶたはきられたことになる。和田一族の企図は、北条氏を打倒して、実朝将軍を奉ずるというところにおかれた。
和田義盛は兵を率いて将軍の幕下に攻め入った。同時に北条義時邸と大江広元邸を囲んだ。和田合戦の模様は、嘘も真もこきまぜて『吾妻鏡』が詳細に描写している。しかし、わたしにはそれほど興味がない。和田四郎左衛門尉義直が伊具馬太郎盛重のために討取られたのをきいて、義盛は、この愛する武勇の子のためにこそじぶんは上総の国司を所望したのだ、いまはもう合戦にはげんでも何の意味もなくなった、と声をあげて「悲哭」し、狂乱の態をなし、ついに江戸左衛門尉能範に撃たれたという。
実朝はもちろん、和田義盛をはじめ一族が、じぶんに謀反の気がなく、ただ北条義時一族の勢力をそぐのが目的であったことをよくしっていた。また、一途な宿老の心中もよく察していた。北条氏一族もまた、それをよく心得ていて、『吾妻鏡』は北条泰時に「義盛上に於て逆心を挿まず、只相州に阿当(あだ)せんが為」、謀反をおこしたのだ、といわせているくらいである。
実朝がついに父頼朝の代からの忠誠一途の老将たちのすべてを失ったことを悟ったに違いない。実朝の心にもはや何の希望もなくなったのは、たぶん和田合戦のあとであった。実朝の乾いた心は、そのまま冷えたといってよい。
(その3に続く)