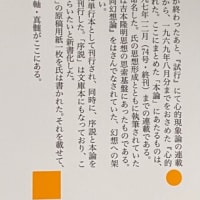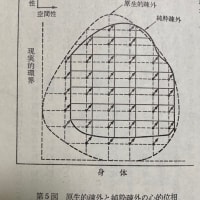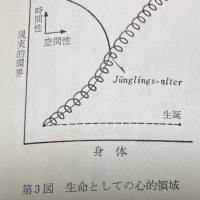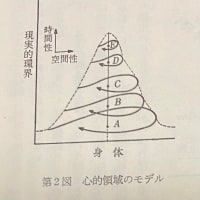123〈信〉の構造2 キリスト教論集成
吉本隆明
④マチウ書試論ーー反逆の倫理 その1
投稿者 古賀克之助

〈信〉の構造2 ——キリスト教論集成
ニ〇〇四年十一月三十日 新装版第一刷発行 著者ー吉本隆明 発行所ー株式会社春秋社
マチウ書試論ーー反逆の倫理より抜粋

マチウ書試論ーー反逆の倫理
1
(当方注 著者は、この著作では、キリスト教にたいする一種の畏敬の念もあって、言い方から何から全部変えたと述べている。例えば、マタイ伝をマチウ書、イエスをジュジユ、ヨハネをジャンなどと。)
マチウ書の作者は、メシア•ジュジユをヘブライ聖書のなかのたくさんの予約から、つくりあげている。この予約は、もともと予約としてあったわけではなく、作者がヘブライ聖書の予約としてひきしぼることによって、原始キリスト教の象徴的な教祖であるメシア•ジュジユの人物をつくりあげたと考えることができる。だから当然史観というべき性質のものであり、ジュジユはマチウ書の作者の史観が凝集してつくりあげた象徴的人物に外ならないと言える。マチウ書にあらわれた史観は、原始キリスト教の教義ときりはなすことができないが、おなじように当時のイスラエル民族がぶつかっていた混乱や危機というものと、きりはなすこともできない。教義、現実の危機、象徴的教祖ジュジユの性格、これらのあいだの強い結びつきのなかに原始キリスト教の思想的な特徴が鋭くあらわれている。マチウの作者が、ジュジユをあたかも実在の人物であるかのように描き出したという点だけからみれば、マチウ書はいまではほとんど読むにたえない幼稚な、仮構の書であるかも知れないが、ジュジユに象徴されるひとつの、強い思想の意味をとり出してくるとすると、いまでもそれを無視することはできないものである。マチウ書の仮構は、その発想を逆むきにたどることによって、容易にそのメカニスムをさらけ出してしまうが、マチウ書のもっている思想の意味は、まるでひとりの日人物が実在するように、たしかな、生々しい実感で、生きていると感じられる。
もともと、マチウ書は、第二世紀につくられたもので、ユダヤ教と原始キリスト教を、ただしく結びつける原典は、ヘブライ聖書、ジャンのアポカリプス、ポオル書簡のいくつか、であって、これも現在あるものにいたるまでに、たくさんの補正がくわえられていると信じられている。だいいちに、ジャンのアポカリプスは、ユダヤ教に属する原典で、この系列は、たとえば、エサイ書、ダニエル書、ザカリ書、ジャンのアポカリプスとなるべきものだ。したがって、まことに奇異な感じがするが、ポオルは、メシア•ジュジユを、実在の人物として考えていなかった。ポオルにあらわれたジュジユは、メシアとしてのジュジユであり、もとより、メシア宗としての原始キリスト教の、象徴的な教祖である。
このような見解をうらずけるためには、いまある新約聖書の配列をつくりかえ、神学者たちが、ジュジユを実在の人物であるかのように考えるために、見ぬふりをしてきた矛盾を、ひとつひとつほりかえしてゆかなければならないはずである。だが、意識的に配列したと思われる新約書の、福音伝、使徒伝、ポオル書簡、ジャンのアポカリプス、は互いに有機的つながりをもっていて、みたところ矛盾だらけにおもわれるにもかかわらず、その矛盾をつきつめていくと、言いようのない泥沼のなかにひきずりこまれてしまう。矛盾のいとぐちは至るところにころがっている。がその矛盾はほかの矛盾によって、強く保護されているのである。このような矛盾のつながりのなかには、本質的な意味で、原始キリスト教のたえてきた風雪のつよさがあるのだろう。資料の改ざんと付加とに、これほどたくさんの、かくれた天才と、宗教的な情熱とを、かけてきたキリスト教の歴史をかんがえると、それだけ大へん暗い感じがする。マチウ書が、人類最大のひょうせつ(当方注 4文字振り点(、)で強調 以下同じ。)書であって、ここで、うたれている原始キリスト教の芝居が、どんなに大きなものであるかについて、ことさらに述べる任ではないが、マチウ書の、じつに暗い印象だけは語るまいとしても語らざるを得ないだろう。ひとつの暗い影がとおり、その影はひとりの実在の人物が地上をとおり過ぎる影ではない。ひとつの思想の意味がぼくたちの心情を、とおり過ぎる影である。
アルトゥル•ドレウスは、その著「キリスト神話」のなかで、後期ユダヤのメシア観についてつぎのように書いている。
「ラビの徒即ちユダヤの教法学者達は、メシアについて二つの観念を有っていた。その一つによれば、メシアは、ダヴィデ王の後裔として、また強大な神の英雄として、ユダヤ人を現下の奴隷的屈辱の状態から解放し、約束された世界帝国を創建し、人間全体の審判を行うものだというのである。これがユダヤのメシア観であり、その理想はダヴィデ王であった。また他の観念に従えば、彼メシアは、ガリラヤにおける十支族を糾合してエルサレムに向って進軍し、アルミルムの引率するゴッグ及びマゴッグとの闘争において、イロベアムの罪、即ちイスラエル人がユダヤ人と分離した罪の故に陣没するのだというのである。」(原田瓊生訳)
マチウ書に描かれているジュジユは、このふたつのメシア観から、すこしも外れていない。ヘブライ書、ジャンのアポカリプス、およびマチウ書の物語の直接の原型であるマルク書を、当時の伝承や風習とおもわれるものと、注意ぶかく対象し、考えあわせることによって、原始キリスト教の象徴であるジュジユは、どのようにつくられたか、ドウレスはあきらかにしようとしている。ジュジユがダヴィデ王の子孫であるという系図は、メシア観のひとつからつくりあげられた。二章の二•二三にある、ジュジユがガリレ地方にしりぞき、ナザレト村に住んだというのは、他のメシア観からつくりあげられた。エドロ王に迫害の意思があるのをさっして、ジョゼフとマリがジュジユをつれてエジプトに逃げたとき、エドロは、大いに怒ってベトレム地方の二歳以下の男の子を、ことごとく殺したという物語は、ヘブライ聖書ののなかの、エジプトからの脱出記一の十五•十六にある、「エジプト王は、シラフおよびプアというヘブライの産婆に語り、言う。おまえたちがヘブライの女たちを出産させるとき、下半身を見て、もし男の子であれば、それを殺し、もし女の子であれば生かしておけ。」というところからつくりあげたものと思われている。ジュジユをベレトム生まれとしたことについて、マチウの作者は、「おまえユダの地のベレトムよ。おまえはユダの主だった村々のなかで、たしかに小さいものではない。おまえからひとりの長が生まれでて、わたしのイスラエルを養うだろうから、」というところからヒントをえたことを、あきらかにしているが、ミケ書五の一には、「おまえエフラタのベトレムよ。ユダ群村のなかの小さなものよ。おまえからわたしのためにイスラエルを支配するものが生まれでるだろう。」とあり、引用するにしても、マチウの作者の引用には、主観が入っているのか、異本がたくさんあったのか、どちらかである。
概してマチウの作者が、ジュジユを創作するやりかたは幼稚であり、ヘブライ聖書と、ジャンのアポカリプスを、こまかく検討して、そのなかの言葉を、当時のメシア観にあうように集め、一人の人間の出生と経歴と死をくみたてていったという、単純なことしかしていない。時間と空間についての觀念は、ほとんどないと言ってよい。生半可に進歩的な神学者のように、処女妊娠とか、出生譚とか、復活とかは伝説であるが、ジュジユの伝道や処刑が事実であったというのは、まったくくだらない見解であり、マチウ書のなかで、処女妊娠ということより確かであると思われるところはどこにもないと言ってよいだろう。それゆえ、ウルトラ•モンタンのように、処女妊娠も復活もまるのみに信ずるために、理神論のたすけをかりるか、またはジュジユを実在性を拒否するか、どちらかである。
また、ジュジユは、マリーとローマ兵士の間の私生児であったのでジョゼフこそいい面の皮だなどとかんぐって、リアリストぶる必要もない。すべてはヘブライ聖書の予約にのっとってつくられた架空の人物である。
ひとびとがここでつまずくのは、マチウ書をはじめ、福音書が神話として読まれるためには、あまりにも意識的につくられているからである。言わばマチウ書は、神話的条件からも、伝記的条件からも失格している。この失格の意味のなかに、原始キリスト教の異様な特徴があると言えるだろう。マチウの作者が、意識的に考えていたことは、ヘブライ聖書にあらわれている後期ユダヤ教のメシア観を、ひとりの人物の意味のなかに集成して、それによってユダヤ教を母屋に、原始キリスト教をすえると言うことであった。この詐術は史上最大の詐術にちがいないが、ユダヤ教が原始キリスト教との深刻な闘争にまけてからは、たしかに成功したのであり、ヘブライ聖書と、ジャンのアポカリプスは、あたかもキリスト教の遺産であるかのように変えられてしまった。原始キリスト教はひとりの架空の教祖をつくりあけることによって、イスラエル民族の史書であり、神話の書である、ヘブライ聖書にとどめを刺し、その思想の流れを、教義のなかにそそぎこんだのである。こういう詐術をささえたのは、ユダヤ教にたいする敵意と憎悪感であるが、かれらはその生理的とも言える憎悪感を、思想の型にまで普遍化し、ヘブライ聖書の特異な解釈として、それを定着させた。現在、原始キリスト教の思想の型とかんがえられているものは、ほとんとこの生理的な憎悪感として分解することができるもので、教義としてあるのは、ヘブライ聖書と、ユダヤ経典からのひょうせつである。マチウ書は、これをつきつめることによってひょうせつと深刻な憎悪感の倫理化という、ふたつの臓腑にふわけすることができることを立証している。
(中略)
マチウ書十六で、作者ははじめてジュジユの死のプランをあきらかにしている。シモン•ピエルはジュジユに、あなたはメシアであり、生きた神の子だという。ジュジユは自分がエルサレムにゆき、長老や祭司長や神学者から多くの苦しみをうけ、殺され、三日目に蘇生することを弟子達に語る。マチウ書の作者は、すでに十一の四〇で、ヨナ書のヨナ寓話をかりて、「それゆえヨナが、三日三夜大魚の腹中にあったように、人の子は三日三夜地中にあるだろう。」と注意ぶかい伏線をしいているが、作者の物語構成は、けっして巧みであるとは言えない。十七章ではすぐに、モイズとエリとの亡霊が、ジュジユと対話しながら弟子たちにあらわれたと書いて、そのあとで、かがやく雲が、かれらをおおい、雲のなかから、これはわたしの愛する子であり、わたしがまったき慈愛をそそぐものだ。かれに耳をかたむけよ。とひとつの声が語る。と書いて、ジュジユがメシアであることを、メシア再臨の教義といっしょにあきらかにしている。マチウの作者は、メシア教義をダニエル書からジャンのアポカリプスにいたる黙示録と関連させて、マチウ書のなかにはめこんだことが判るが、ジュジユの復活物語が、どんなに粗雑なものであるとしても、それをあたかも実在の人物のように描いてきた。ジュジユの死後につけくわえるためには、アポカリプスの系列にたいする作者の特別な関心がなければならないはずである。周知のように原始キリスト教は、ただひとつの黙示書、ジャンのアポカリプスをもっている。ところで、ジャンのアポカリプスは、ヘブライ聖書のなかの黙示書と対照させて読んでゆくと、その構成が意企的であり、複合的であり、そこから感じとられるものはマチウ書の印象と酷似している。急転して描かれているマチウ書の、ジュジユの死と復活の物語を解析してゆくまえに、ジャンのアポカリプスの性格について、触れておこうと思う。ジャンのアポカリプスのうち、もともとそのような形であったのは、大凡十四章から、十八章にわたるわずかな個処であると思う。語学の関係で、文体論的に照明をあててみるわけにはいかないが、ほとんど、とってつけたような黙示的な幻影と諸教会への脅迫とで、出来あがっているジャンのアポカリプスは、十四章あたりから突如見事なイメージを、コンパクトな文体で展開しはじめる。これは十八章あたりまでつづくが、それからはまた、ちぐはぐな印象しか与えなくなる。
(中略)
周知のように、マチウ書の廿三章には、パリサイ派の律法学者に対するジュジユの非難という名目で、原始キリスト教のユダヤ教派にたいする批判が、ほとんど憎悪をこめて述べられている。非情な、メカニカルな言葉で、批判というものの極限が、はっきりと生理的なとでも言いたいようなすがたであらわれている。と、読者はそのなかにつぎのような転調をきくことが出来ることをしっている。
「エルサレムよ、エルサレムよ、預言者たちを殺し、派遣されたものを石でうち殺すものよ。牝どりがそのつばさの下にあつめるように、いくたびわたしは、おまえの子らをあつめようとしたろう。だがおまえたちはそれを欲しなかったのだ!」
ドウレスによれば、この引用した個処がマルク書やマチウ書のなかの、ジュジユのたったひとつのモデルである。ぼくたちは、ジュジユをひとりの無名の狂信者のなかに見出そうとする推理の方法に習わされてきているが、これは逆かもしれぬ。ヨセフスの古代史のなかのひとりの狂信者は、恐らく、当時のユダヤにおける無数の宗教的な熱狂と、現実的な混迷とを象徴している。こういう風潮のなかで、無数にうまれた狂信者の記録から、原始キリスト教が、その教祖の実像をつくりあげるためのモデルをえらんだのかもしれない。それゆえ、ジュジユはひとりの無名の思想家だったのではなく、無名の思想家の記録から、ジュジユはつくりあげられたのである。マチウ書のなかで、読むに耐えるほどの章句にぶつかったら、それは一応、原典があると疑って大過ないとおもわれるが、マチウ書廿三のおわりにちかく、とつぜんあらわれるエルサレムへの嘆きの結滞のない流路は、マチウ書のなかでは、尊重されていいものだ。もしこのエルサレムへの嘆きのうしろに、紀元九〇年ころの歴史家に記録された、ひとりの熱狂的な思想家がいるとすればなおさらである。
マチウ書はすぐそのあとで、原始キリスト教の根本的な理念であるメシア再臨と審判の教義をのべているが、これはアポカリプスを俗化したものである。ジュジユはあと死ねだけである。よく知られているように、ジュジユの死は、ジュドの裏切りによって媒介される。人間心理の陰惨さに通じていた原始キリスト教は、迫害からくる被害感によって、裏切りの暗い心理をよく知っていて、それをジュドという架空の人物に負わせる。ぼくは、ジュジユを裏切るジュドの心理のなかに、人間の負わされている秩序からの被害心理をよみとり、それを造型化しようとする文学者の、甘ったれた根性を信じない。ジュドという人物はユダヤ教の象徴であり、マチウの作者の真意は、まず何よりも、原始キリスト教を迫害し、秩序にうりわたしたユダヤ教という周知の公式を造型することであった。原始キリスト教と、ユダヤ教との殺人的反目と相剋とを歴史的に理解しないかぎり、マチウの作者が、ジュドという人物に負わせた役割はけっして理解できない。
ジュジユは、エサイ書五三の言葉を立証せねばならない義務があるかのように、「わたしの魂はかなしくて死にそうだ」などと言い、それから捕らえられる。マチウ書の、ジュジユの処刑の描写には、エサイ書五三を心棒として、伝承の衣がきせられる。ドウレスによれば、当時、「ヘロデ王の孫に当たるユダヤ王アグリッパを嘲るために気の狂った貧乏なカラバスという名の男に、紙製の冠を被らせ、笏を持たせ、王様のようなマントを着せてアレクサンドリアの街中を練り歩いたというのである。ついでドウレスは書いている。「これはきっと、フレイザーやロバートスンが忖度するように、古い祭りの慣わしではあるまいか。カラバスというのは、どうやらバラバスの書き誤りらしく思われる。」と。
マチウ書は、ローマのユダヤ総督が、「おまえはユダヤの王であるか。」と問うのにたいし、ジュジユが「おまえの言うとおりだ。」とこたえたと書いている。つづいて、ニ七の十五に、「祭りごとに総督は群衆の要求するひとりの囚人を釈放する習しがあった。」と書き、「かれらは有名なバラバスという囚人をもっていた。」と書いている。マチウ書によれば、総督は群衆に、ジュジユを赦すか、バラバスを赦すかと問い、群衆はバラバスを許せとこたえる。ジュジユは十字架にかけられる。マチウの作者はこの当時の伝承的祭礼の慣わしを、そのままジュジユの処刑物語にあてはめて構成した。ジュジユとは、バラバスのことであり、バラバスとは例祭の立役者である。
マチウの作者は、ここでも、キリスト教を迫害するユダヤ教という、手なれた公式を、憎悪をこめた発想によって、この伝承のなかへ封じこめる。ローマのユダヤ総督は、群衆のまえで手をあらって言う。「わたしは、この正義の人の血について関知しない。おまえたちのせいである。」と。人々はこたえる。
「かれの血が、われわれと、われわれの子孫の責にきしてたまるものか。」
総督によって象徴されるローマ的秩序と、群衆によって象徴されるヘブライ的秩序とは、原始キリスト教の憎悪の造型によって脅迫されている。ニーチェをかんかんに瞋らせたキリスト教的な発想の根源というものであろう。血とか、契約とかいう言葉で、あの素朴なユダヤ教の倫理、神から生活のなかへおりてきた倫理とは全くちがった陰惨な内容を象徴させたのは、原始キリスト教のソシャルコムプレックスにほかならない。
十字架にかけられたジュジユは、息たえるにあたって、「エロイ•エロイ•ラマサバクタニ」(当方注 原文の文字下記の通り。)という。

「わが神、わが神、おまえはなぜわたしをすてたのか。」と。詩篇二十二の「暁の鹿」の曲にのせて唱人の長にうたわせたダヴィドの詩である。マチウの作者が、死に絶えるジュジユに、詩篇のなかのダヴィドの言葉を吐かせたら最後の引用をえて、その主人公を死なせる。ジュジユが死にあたって諳誦していたヘブライ聖書の文句を想いおこして口にしたのだと言った類の、神学者たちの解釈は不必要である。マチウには、すべて信仰によることは悪であるまいかとさえ考える。それは人間の思考をでなく、思考の意味を奪うからである。ヘブライ聖書を縦横に引用し、また人物構成の素材としてこなせるほど諳誦していたのは、ジュジユという教祖ではなく、それを制作した作者だ。
マチウ書には、ジュジユの死のあとに、復活物語がつけくわえられているが、それは当時のメシア再臨信仰(すなわち、原始キリスト教の根本理念)にのっとって、ダニエル書六の十四にわたる獅子の穴に封じこめられたダニエルが、無傷のまま、あなから出られたという物語をヒントとしてつくられたものだ。ぼくたちはもう、ジュジユのロギアという名目で、マチウ書のなかにばら撒かれている原始キリスト教の思想的箴言にたちむかうべきであろう。
(当方注 その2に続く)