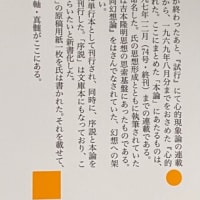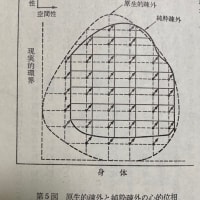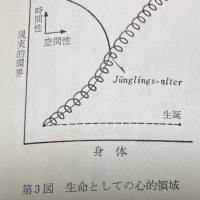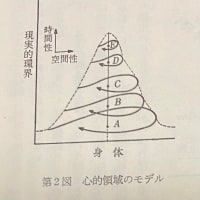言の葉 26 言語にとって美とはなにか ⑤ 文字・像と言語表現における像
言語にとって美とはなにか 第Ⅰ巻 著者吉本隆明 発行所 勁草書房 昭和40年5月20日発行
抜粋その1
同書第Ⅱ章言語の属性 3文字・像より
*当方注 像についての関連著書として、ここではサルトルの『想像力の問題』への言及がなされている。

(略)
たんなる遊吟であり、謡であり、語り伝えであり、また対話であった言語が、文字としてかきとめられるにいたったとき、言語の音声が共通に抽出された音韻の意識がはっきりと定着するまでに高度になったことを意味すると同時に、その意味伝達の意識がはっきりと固定化するまでに高度化したことを意味している。おそらく、文字は、たんに歌い、会話し、悲しみをのべていた古代人が、言語についての高度な抽出力を、手に入れたときはじめて表記されたのである。語り言葉、歌い言葉との分離と対立と浸透との最初のわかれは、文字の出現からはじまったということができる。
ここで、文字の成立は何を意味するかはっきりさせておかなければならない。
文字の成立によってほんとうの意味で、表出は、意識の表出と表現とに分離する。あるいは、表出過程が、表出と表現の二重の過程をもつともいってもよい。言語は意識の表出であるが、言語表現が意識に還元できない要素は、文字によってはじめて完全な意味でうまれるのである。文字にかかれることによって言語表出は、対象化された自己像が、自己の内ばかりでなく外に自己と対話するという二重の要素が可能となる。
(略)
言語には、自己表出にアクセントをおいてあらわれる自己表出語と、指示表出にアクセントをおいてあらわれる指示表出語があるように、言語本質の表記である文字にも自己表出文字と指示表出文字の区別があるだけで、これが本質的なのだ。
たとえば、(恋人)という文字は、指示表出文字である。これを表意的にではなく、表音的に(こいびと)または歴史的かなづかいで<こひびと>とかいても、その指示表出にかわりはない。(恋人)と表意文字でかけば、恋愛関係にある男、または女をさすが、<こいびと>とかな文字でかけば、それを指示しないということはありえない。なぜならば、それは言語本質によってきまるもので、文字によってきまるものではないからである。
しかし、たとえば<理性>という指示表出文字を、<りせい>という文字でかくとき、わたしたちが、あるためらいをおぼえるのは、現在の言語水準で、<りせい>は、ひとたび《理性》という表意を頭におもいうかべたうえで、<理性>のことであるとなったとするほかないからである。その手続きをはんざつとかんがえるならば、<りせい>というもじをつかって<かれはりせいがある>というような文章をかかずに、<彼はものごとをよくかんがえてきめるたちだ>というように表現するほかない。これは、漢字を意味形象としてつかうという伝統のなかに、わたしたちが身をひたして、書き言語の発達と伝達言語の発達のあいだにひき裂かれているからで、急激にこれを断絶させようとすれば、<りせい>→《理性》→<理性>という二段の手つづきをふむほかないからである。
こういう問題が真にやっかいな点は、わたしたちが、指示表出語に、意味や、対象の概念のほかに、それにまつわる像をあたえているし、またあたえうるとおもわれる。表意文字でかくことができるのは、もちろん指示表出語にかぎられる。現在では万葉仮名で、助詞や助動詞をかくことはなくなっている。そして、指示表出語だけでなく、言語の指示表出へのアクセントは大なり小なり像をあたえるという点に、言語表記の性格にとって最後のもんだいであり、また言語の美にとって最初のもんだいがあらわれる。
言語が意味や音のほかに像をもつというかんがえを、言語学者はみとめないかもしれない。しかし、<言語>というコトバを本質的な意味でつかうとき、わたしたちは言語学をふりきってもこの考えにつくほうがよい。言語学と言語の芸術論とが別れなければならないには、おそらくこの点からであり、言語における像という概念に根拠をあたえさえすれば、この別れは、可能なのだ。
言語における像が、言語の指示表出の強さに対応するらしいことは、わたしがいままで無造作に述べてきたところからも、推定できるはずだ。
しかし、言語の像が、<意味>とちがうことは、あたかも事物の<概念>と、事物の<象徴>とはちがうのとおなじようなものである。
言語は、その発生の初期に、視覚的反映にたいする反射的な音声という性格をすててしまった。わたしの考察では、音声が自己表出を手にいれたためである。これによって言語本質は、指示表出と自己表出とのないまぜられた構造となったのである。
もしも、言語の像を喚起したり、像を表象としたりできるものとすれば、意識の指示表出と自己表出とのふしぎな縫目に、その原因をもとめるしかない。
ここで、再び言語進化のところで考察したものを、新しい眼でたどってみなければならぬ。
音声は、現実界を視覚的に反映したときの反射的な音声であったとき、あきらかに知覚的な次元にあり、指示表出は現実界への直接の指示であった。しかし、音声の意識が自己表出としてはっせられるようになって、指示性は現実にたいするたんなる反射ではなく、対象性としての指示にかわった。いわば自己表出の意識は起重機のように有節音声を吊りあげたのである。
そのようにして、言語そのものは、知覚的な次元から離脱した。像は、人間が対象を知覚しているときには不可能な意識であることは、サルトルが『想像力の問題』(平井啓之訳)のなかで、指摘したとおりである。言語に像を表現したり喚起したりする力があるとすれば、言語が意識の自己表出をもつにいたったところに機動力をもとめざるをえないのである。
しかしそれとは逆に言語の像をつくる力は、指示表出の強い言語ほどたしかであるということができる。この意味で言語の像は、言語の指示表出に対応しており、また自己表出を機動力とする何かであるといわなければならない。
わたしが、いま、机の上の緑色の灰皿を眼でみながら、<ハイザラ>という言葉を発したとする。このとき灰皿の像をひきおこすことは不可能である。しかしいま、眼をとじて<ハイザラ>といったとすれば、灰皿の像を喚起することができる。ここで原始人たちが、海を目のまえでみながら、<海>といったとき、この語は反射音声だが、住居の洞穴にいながら<海>といって、なお海の概念をうることができるようになったとき、言語の条件は完成したことを想起しよう。像とは何かが、本質的にわからないとしても、それが対象的概念とも
対照的知覚とも違っているという理解さえあれば、言語構造の指示表出と自己表出の交錯した縫目にうみだされることは、了解することができるはずである。あたかも、意識の指示表出というレンズと自己表出というレンズが、ちょうどよくかさなったところに像がうまれるというように。
(略)
抜粋その2
同書第Ⅱ章言語の属性 4言語表現における像より
当方注 吉本隆明が語る戦後55年2 戦後文学と言語表現論のなかで、「言語にとって美とはなにか」の延長線上で、想像力の問題を理論的にやってみようと思ってはじめたのが、「ハイ・イメージ論」であると述べています。

言語の意味、価値、像などの概念から言語の芸術にふみこもうとするいま、言語の表出(Ausdrücken)を、表出(ausdrücke)と表現(produzieren)のふたつを分離して含むものとしてあつかうのが、適切であるとおもう。もちろん、文学的な表現もまた、意識の表出であるが、この表出はその内部で、<書く>という文字の表現の文学的な成立とともに、表出と表現に分裂する。言語の美のもんだいは、あきらかに意識の表出という概念を、固有の表出意識と、<書く>ことによって文学に固定せられた対象物への表現意識との二重の過程に拡張せられる。もちろん、その本質的な意味はかわらないのである。
このことは、いうまでもなく人間の自己意識の外化としての言語表出が、自己意識に反作用をおよぼし、戻ってくる過程と、外化せられた意識が、対象的に文学に固定されて、それが<実在>であるかのように自己意識の外に<作品>として生成され、生成されたものが自己意識に反作用をおよぼし、もどってくる過程の二重性が、無意識のうちに文学的表現(芸術としての言語表出)として前提されていることを意味している。それは文学が固定されて<書く>という文学的表現が成立して以後、文学作品は(書かれるもの)としてかんがえられているからだ。もちろん、語られる言語表現もまた文学、芸術でありうるし、現在も存在しつづけている。しかし、おこりうる誤解をさけるためにいえば、現在まで流布されている文学理論が、いちように<文学>とか<芸術>とか以上に、その構造に入ろうとせず、芸術と実生活とか、政治と文学とか、芸術と疎外とかいいならわせば、すんだつもりになるのは、表出という概念が固有の意識に還元される面と、生成(Produzieren)を経て表現そのものにしか還元されない面とを考察できなかったがためである。
(略)
A 彼はまだ年若い夫であった。(庄野潤三「生物」)
Bその部屋で二人はウイスキーを飲んでいた。(同)
ふたつは、いずれもひとつの文学作品のなかの文章で、意味はたれの眼にも、もっとも単純なものとしてみえる。
Aは「彼」という人物が年の若い夫であったという意味で、Bはあるひとつの部屋でふたりの人間がウイスキーを飲んでいたという意味である。もちろん「静物」という作品のなかでは、「彼」は主人公であり、作者と主人公とが微妙に未分化なものとして設定されている。またBの文章で「ふたり」というのは、作品のなかでは主人公と医者であるが、ここではべつに問題とする必要はない。
ここでいまはじめて当面しているのは、これらの文章を言語表現として、読むとは、いかなることを意味するのかというもんだいである。そのために、言語のおける意味、価値、像の概念をとりあげてきた。
わたしたちは、言語の価値を自己表出からみられた言語の全体的な関係としてかんがえてきた。したがって、Aという言語表現の価値は、「彼」という代名詞の自己表出、「は」という助詞の自己表出、「まだ」という副詞、「年若い」という形容詞、「夫」という名詞……の自己表出からみられた文章全体である。
Aという文章で、たんに文法的にみれば「彼」ということばは、第三者を意味する代名詞にすぎない。しかし、作者の意識の自己表出としてみるとき、この代名詞「彼」は作者との関係をふくむことになる。この文章を読んで「彼」ということばが、作者が自分を第三者のようにみたてた表現のようにもとれるし、また、作者とある密接な関係にある他人ともうけとれるような含みを感ずるのは、作者の自己表出として「彼」ということばを考えたうえで「彼」という意味をうけとっているからである。Aの文章で価値として「彼」ということばをかんがえるとは、このことをさしている。
「年若い」という形容詞のばあいもまったくおなじで、たんに<若い>と表現しても意味にはかわりないが、作者の意識に年齢としての強調があって、「年」という名詞と連合した表現をとらせたということができる。「夫」という名詞もおなじで、<男>とか<亭主」とかで意味としては代置できるもかかわらず、作者の自己表出が「夫」という語感をえらばせたのである。
このように、「彼」という人物が、まだ若い妻をもった男だったという意味の文章Aがふくんでいるニュアンスが、それぞれの語の自己表出からきていることが、たやすく了解される。このとき、わたしたちは、たんに意味としてではなく、価値としてこの表現をたどっているので、文章を言語表現としてみるとは、このことを意味している。
(略)
C しかし彼は、二三歩ふらふらと右に動き、休むでもなく、上の岩を調べるでもなく、ぼんやりと佇み、それからいきなり岩にとりついた。 (「岩尾根にて」北杜夫)
この文章から、あるはなれたところの岩にかこまれた場所で、ひとりの男が、なんの目的もなさそうに、だが、なにか意味ありげに岩の壁のしたをうろうろしたり、佇ちどまったりしていたかとおもうと、やがて岩に手足をかけて登ろうとした、という情景の像を、しかも、かなり遠方の感じでおもいうかべることができる。
そして、この像をうかべるとき、わたしたちは、この表現をたんに意味としてではなく、価値としてたどっているのである。これは「ふらふら」とか、「ぼんやり」とか、「いきなり」とかいう副詞のたくみな用法によって助長されているだろうが、何よりも、この文章を、作者の自己表出としてみるとき、その場面転換がすばやくおこなわれるところに、像をひきおこす要因がかくされている。たとえば、「右に動き、左に動き」というばあい、それは作者の意識との関係において右に動いたり、左に動いたりしていることであり、「休むでもなく、上の岩を調べるでもなく」というとき、作者の意識の判断との関係で休むでもなく、調べるのでもなく、ということにほかならない。
このように作者の自己表出からみられた指示表出はよくうごき、転換しその縫目に像があらわれる。
D 私が進むと、彼等(蠅―註)はだるそうに飛びあがり、すぐに舞いおりた。
(「岩尾根にて」北杜夫)
この文章は、ちょっとかんがえると作者である「私」が路をすすんでいくと、路のあたりにいた蠅が、にぶくとびあがって、またすぐ路のあたりにとまった、というようにうけとれるかもしれない。しかし、じっさいは、この文章の「私」は、作者の自己表出された像としての「私」であるから、像としての「私」が路をあるいてゆくという文章と、作者の自己表出としての「彼等」(蠅)がとびあがって、まいおりたという文章とが作者の意識の表現として二重に因果的にとらえられ、むすびつけられたものである。
この文章の含みは、「私」がすすむという表現が、途中で「彼等」(ハエ)がとびあがり、まいおりるという表現に転換し、それが「他」という助動詞でしめくくられることによっておわっている。いわば、文章のなかの「私」や「彼等」(蠅)と作者との関係の転換が、この表現の価値をたかめている例である。
言語の美にふみこむ道は、このような表現的なところから、複雑な過程へ、言語本質をみうしなうことなしに拡張してゆく道である。
言語にとって美とはなにか 第Ⅰ巻 著者吉本隆明 発行所 勁草書房 昭和40年5月20日発行
抜粋その1
同書第Ⅱ章言語の属性 3文字・像より
*当方注 像についての関連著書として、ここではサルトルの『想像力の問題』への言及がなされている。

(略)
たんなる遊吟であり、謡であり、語り伝えであり、また対話であった言語が、文字としてかきとめられるにいたったとき、言語の音声が共通に抽出された音韻の意識がはっきりと定着するまでに高度になったことを意味すると同時に、その意味伝達の意識がはっきりと固定化するまでに高度化したことを意味している。おそらく、文字は、たんに歌い、会話し、悲しみをのべていた古代人が、言語についての高度な抽出力を、手に入れたときはじめて表記されたのである。語り言葉、歌い言葉との分離と対立と浸透との最初のわかれは、文字の出現からはじまったということができる。
ここで、文字の成立は何を意味するかはっきりさせておかなければならない。
文字の成立によってほんとうの意味で、表出は、意識の表出と表現とに分離する。あるいは、表出過程が、表出と表現の二重の過程をもつともいってもよい。言語は意識の表出であるが、言語表現が意識に還元できない要素は、文字によってはじめて完全な意味でうまれるのである。文字にかかれることによって言語表出は、対象化された自己像が、自己の内ばかりでなく外に自己と対話するという二重の要素が可能となる。
(略)
言語には、自己表出にアクセントをおいてあらわれる自己表出語と、指示表出にアクセントをおいてあらわれる指示表出語があるように、言語本質の表記である文字にも自己表出文字と指示表出文字の区別があるだけで、これが本質的なのだ。
たとえば、(恋人)という文字は、指示表出文字である。これを表意的にではなく、表音的に(こいびと)または歴史的かなづかいで<こひびと>とかいても、その指示表出にかわりはない。(恋人)と表意文字でかけば、恋愛関係にある男、または女をさすが、<こいびと>とかな文字でかけば、それを指示しないということはありえない。なぜならば、それは言語本質によってきまるもので、文字によってきまるものではないからである。
しかし、たとえば<理性>という指示表出文字を、<りせい>という文字でかくとき、わたしたちが、あるためらいをおぼえるのは、現在の言語水準で、<りせい>は、ひとたび《理性》という表意を頭におもいうかべたうえで、<理性>のことであるとなったとするほかないからである。その手続きをはんざつとかんがえるならば、<りせい>というもじをつかって<かれはりせいがある>というような文章をかかずに、<彼はものごとをよくかんがえてきめるたちだ>というように表現するほかない。これは、漢字を意味形象としてつかうという伝統のなかに、わたしたちが身をひたして、書き言語の発達と伝達言語の発達のあいだにひき裂かれているからで、急激にこれを断絶させようとすれば、<りせい>→《理性》→<理性>という二段の手つづきをふむほかないからである。
こういう問題が真にやっかいな点は、わたしたちが、指示表出語に、意味や、対象の概念のほかに、それにまつわる像をあたえているし、またあたえうるとおもわれる。表意文字でかくことができるのは、もちろん指示表出語にかぎられる。現在では万葉仮名で、助詞や助動詞をかくことはなくなっている。そして、指示表出語だけでなく、言語の指示表出へのアクセントは大なり小なり像をあたえるという点に、言語表記の性格にとって最後のもんだいであり、また言語の美にとって最初のもんだいがあらわれる。
言語が意味や音のほかに像をもつというかんがえを、言語学者はみとめないかもしれない。しかし、<言語>というコトバを本質的な意味でつかうとき、わたしたちは言語学をふりきってもこの考えにつくほうがよい。言語学と言語の芸術論とが別れなければならないには、おそらくこの点からであり、言語における像という概念に根拠をあたえさえすれば、この別れは、可能なのだ。
言語における像が、言語の指示表出の強さに対応するらしいことは、わたしがいままで無造作に述べてきたところからも、推定できるはずだ。
しかし、言語の像が、<意味>とちがうことは、あたかも事物の<概念>と、事物の<象徴>とはちがうのとおなじようなものである。
言語は、その発生の初期に、視覚的反映にたいする反射的な音声という性格をすててしまった。わたしの考察では、音声が自己表出を手にいれたためである。これによって言語本質は、指示表出と自己表出とのないまぜられた構造となったのである。
もしも、言語の像を喚起したり、像を表象としたりできるものとすれば、意識の指示表出と自己表出とのふしぎな縫目に、その原因をもとめるしかない。
ここで、再び言語進化のところで考察したものを、新しい眼でたどってみなければならぬ。
音声は、現実界を視覚的に反映したときの反射的な音声であったとき、あきらかに知覚的な次元にあり、指示表出は現実界への直接の指示であった。しかし、音声の意識が自己表出としてはっせられるようになって、指示性は現実にたいするたんなる反射ではなく、対象性としての指示にかわった。いわば自己表出の意識は起重機のように有節音声を吊りあげたのである。
そのようにして、言語そのものは、知覚的な次元から離脱した。像は、人間が対象を知覚しているときには不可能な意識であることは、サルトルが『想像力の問題』(平井啓之訳)のなかで、指摘したとおりである。言語に像を表現したり喚起したりする力があるとすれば、言語が意識の自己表出をもつにいたったところに機動力をもとめざるをえないのである。
しかしそれとは逆に言語の像をつくる力は、指示表出の強い言語ほどたしかであるということができる。この意味で言語の像は、言語の指示表出に対応しており、また自己表出を機動力とする何かであるといわなければならない。
わたしが、いま、机の上の緑色の灰皿を眼でみながら、<ハイザラ>という言葉を発したとする。このとき灰皿の像をひきおこすことは不可能である。しかしいま、眼をとじて<ハイザラ>といったとすれば、灰皿の像を喚起することができる。ここで原始人たちが、海を目のまえでみながら、<海>といったとき、この語は反射音声だが、住居の洞穴にいながら<海>といって、なお海の概念をうることができるようになったとき、言語の条件は完成したことを想起しよう。像とは何かが、本質的にわからないとしても、それが対象的概念とも
対照的知覚とも違っているという理解さえあれば、言語構造の指示表出と自己表出の交錯した縫目にうみだされることは、了解することができるはずである。あたかも、意識の指示表出というレンズと自己表出というレンズが、ちょうどよくかさなったところに像がうまれるというように。
(略)
抜粋その2
同書第Ⅱ章言語の属性 4言語表現における像より
当方注 吉本隆明が語る戦後55年2 戦後文学と言語表現論のなかで、「言語にとって美とはなにか」の延長線上で、想像力の問題を理論的にやってみようと思ってはじめたのが、「ハイ・イメージ論」であると述べています。

言語の意味、価値、像などの概念から言語の芸術にふみこもうとするいま、言語の表出(Ausdrücken)を、表出(ausdrücke)と表現(produzieren)のふたつを分離して含むものとしてあつかうのが、適切であるとおもう。もちろん、文学的な表現もまた、意識の表出であるが、この表出はその内部で、<書く>という文字の表現の文学的な成立とともに、表出と表現に分裂する。言語の美のもんだいは、あきらかに意識の表出という概念を、固有の表出意識と、<書く>ことによって文学に固定せられた対象物への表現意識との二重の過程に拡張せられる。もちろん、その本質的な意味はかわらないのである。
このことは、いうまでもなく人間の自己意識の外化としての言語表出が、自己意識に反作用をおよぼし、戻ってくる過程と、外化せられた意識が、対象的に文学に固定されて、それが<実在>であるかのように自己意識の外に<作品>として生成され、生成されたものが自己意識に反作用をおよぼし、もどってくる過程の二重性が、無意識のうちに文学的表現(芸術としての言語表出)として前提されていることを意味している。それは文学が固定されて<書く>という文学的表現が成立して以後、文学作品は(書かれるもの)としてかんがえられているからだ。もちろん、語られる言語表現もまた文学、芸術でありうるし、現在も存在しつづけている。しかし、おこりうる誤解をさけるためにいえば、現在まで流布されている文学理論が、いちように<文学>とか<芸術>とか以上に、その構造に入ろうとせず、芸術と実生活とか、政治と文学とか、芸術と疎外とかいいならわせば、すんだつもりになるのは、表出という概念が固有の意識に還元される面と、生成(Produzieren)を経て表現そのものにしか還元されない面とを考察できなかったがためである。
(略)
A 彼はまだ年若い夫であった。(庄野潤三「生物」)
Bその部屋で二人はウイスキーを飲んでいた。(同)
ふたつは、いずれもひとつの文学作品のなかの文章で、意味はたれの眼にも、もっとも単純なものとしてみえる。
Aは「彼」という人物が年の若い夫であったという意味で、Bはあるひとつの部屋でふたりの人間がウイスキーを飲んでいたという意味である。もちろん「静物」という作品のなかでは、「彼」は主人公であり、作者と主人公とが微妙に未分化なものとして設定されている。またBの文章で「ふたり」というのは、作品のなかでは主人公と医者であるが、ここではべつに問題とする必要はない。
ここでいまはじめて当面しているのは、これらの文章を言語表現として、読むとは、いかなることを意味するのかというもんだいである。そのために、言語のおける意味、価値、像の概念をとりあげてきた。
わたしたちは、言語の価値を自己表出からみられた言語の全体的な関係としてかんがえてきた。したがって、Aという言語表現の価値は、「彼」という代名詞の自己表出、「は」という助詞の自己表出、「まだ」という副詞、「年若い」という形容詞、「夫」という名詞……の自己表出からみられた文章全体である。
Aという文章で、たんに文法的にみれば「彼」ということばは、第三者を意味する代名詞にすぎない。しかし、作者の意識の自己表出としてみるとき、この代名詞「彼」は作者との関係をふくむことになる。この文章を読んで「彼」ということばが、作者が自分を第三者のようにみたてた表現のようにもとれるし、また、作者とある密接な関係にある他人ともうけとれるような含みを感ずるのは、作者の自己表出として「彼」ということばを考えたうえで「彼」という意味をうけとっているからである。Aの文章で価値として「彼」ということばをかんがえるとは、このことをさしている。
「年若い」という形容詞のばあいもまったくおなじで、たんに<若い>と表現しても意味にはかわりないが、作者の意識に年齢としての強調があって、「年」という名詞と連合した表現をとらせたということができる。「夫」という名詞もおなじで、<男>とか<亭主」とかで意味としては代置できるもかかわらず、作者の自己表出が「夫」という語感をえらばせたのである。
このように、「彼」という人物が、まだ若い妻をもった男だったという意味の文章Aがふくんでいるニュアンスが、それぞれの語の自己表出からきていることが、たやすく了解される。このとき、わたしたちは、たんに意味としてではなく、価値としてこの表現をたどっているので、文章を言語表現としてみるとは、このことを意味している。
(略)
C しかし彼は、二三歩ふらふらと右に動き、休むでもなく、上の岩を調べるでもなく、ぼんやりと佇み、それからいきなり岩にとりついた。 (「岩尾根にて」北杜夫)
この文章から、あるはなれたところの岩にかこまれた場所で、ひとりの男が、なんの目的もなさそうに、だが、なにか意味ありげに岩の壁のしたをうろうろしたり、佇ちどまったりしていたかとおもうと、やがて岩に手足をかけて登ろうとした、という情景の像を、しかも、かなり遠方の感じでおもいうかべることができる。
そして、この像をうかべるとき、わたしたちは、この表現をたんに意味としてではなく、価値としてたどっているのである。これは「ふらふら」とか、「ぼんやり」とか、「いきなり」とかいう副詞のたくみな用法によって助長されているだろうが、何よりも、この文章を、作者の自己表出としてみるとき、その場面転換がすばやくおこなわれるところに、像をひきおこす要因がかくされている。たとえば、「右に動き、左に動き」というばあい、それは作者の意識との関係において右に動いたり、左に動いたりしていることであり、「休むでもなく、上の岩を調べるでもなく」というとき、作者の意識の判断との関係で休むでもなく、調べるのでもなく、ということにほかならない。
このように作者の自己表出からみられた指示表出はよくうごき、転換しその縫目に像があらわれる。
D 私が進むと、彼等(蠅―註)はだるそうに飛びあがり、すぐに舞いおりた。
(「岩尾根にて」北杜夫)
この文章は、ちょっとかんがえると作者である「私」が路をすすんでいくと、路のあたりにいた蠅が、にぶくとびあがって、またすぐ路のあたりにとまった、というようにうけとれるかもしれない。しかし、じっさいは、この文章の「私」は、作者の自己表出された像としての「私」であるから、像としての「私」が路をあるいてゆくという文章と、作者の自己表出としての「彼等」(蠅)がとびあがって、まいおりたという文章とが作者の意識の表現として二重に因果的にとらえられ、むすびつけられたものである。
この文章の含みは、「私」がすすむという表現が、途中で「彼等」(ハエ)がとびあがり、まいおりるという表現に転換し、それが「他」という助動詞でしめくくられることによっておわっている。いわば、文章のなかの「私」や「彼等」(蠅)と作者との関係の転換が、この表現の価値をたかめている例である。
言語の美にふみこむ道は、このような表現的なところから、複雑な過程へ、言語本質をみうしなうことなしに拡張してゆく道である。