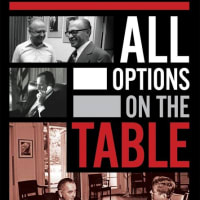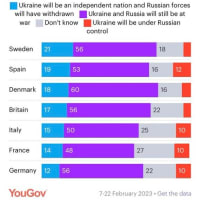服部龍二『高坂正堯―戦後日本と現実主義―』中央公論新社、2019年を読了しました。本書は、「国際政治」学界における知の巨人であり、論壇で「現実主義者」として活躍された故高坂氏を学問的業績はもちろんのこと、政策提言や時事評論、さらには人柄まで踏み込んで、その全体像を描き出した力作だと思います。新書ながら、400ページ近いボリュームがあり、読みごたえがあります。

この図書については、高坂氏のお弟子さんである戸部良一氏が、素晴らしい読書エッセー「恩師の評伝 『高坂正堯』を読む」を書いておられるので、関心のある方は、こちらもお読みになるとよいでしょう。
私が、本書を読んで感じた率直な疑問の1つは、高坂正堯氏は「国際政治学」者なのか、それとも「国際政治史」の学者なのか、ということです。この点に関連して、著者の服部氏は、こう述べています。「高坂の死は、総合的な魅力のある学問としての国際政治学の死であった」(379ページ)と。つまり、高坂氏は、国際政治学者であったと位置づけているようです。とはいえ、別の個所で、服部氏が「高坂の講義は、理論よりも歴史重視である」と書いているように、また、歴史学者の入江昭氏との深い親交や博士学位論文となった『古典外交の成熟と崩壊』(19世紀の外交史研究)が1つの主著であること、さらには、お弟子さんに「歴史学者」とみなされる人が目立つことを考慮すれば、高坂氏の研究は「歴史」に軸足を置いていたと理解するのが適切でしょう。なお、私はこれまでに高坂氏の主著をほぼ全て読み終えてます。そこから感じた高坂氏の国際政治へのアプローチは、「史学」専攻と違うものの、「歴史」に重きを置く分析手法でした。
ある学問が、学際的で総合的であるのは、必ずしも悪いことではありません。しかし、「総合的」であることは、ややもすれば「何でもあり」になりかねません。その結果、当該学問のアイデンティティが損なわれ、その体系があいまいになり、結果として継続的で持続的な科学的発展が難しくなる弊害は否定できないでしょう。私見では、残念ですが、高坂氏が京都大学で始めた「国際政治学」は、このトラップに嵌ったようです。端的に言えば、高坂「国際政治」学は、社会科学としての国際政治学なのか、それとも国際政治史なのか、判然としないのです。
「国際政治学」と「国際政治史(歴史学)」は、戦争や平和などを扱うこと等において共通していますが、それぞれは似て非なるものです。端的に言えば、社会科学としての政治学は概して理論化(単純化)や一般化を目指すのに対して、歴史学は、それをきらい(例外はありますが)、個別の歴史事象の特殊性や複雑性を重視します(詳しくは、コリン・エルマン、ミリアム・エルマン編『国際関係研究へのアプローチ―歴史学と政治学の対話―』東京大学出版会、2003年をお読みください)。つまり、政治学と歴史学は、方法論において、「水と油」なのです。そう簡単に混ざり合うものではありません。
こうした違いを乗り越えて、政治学と歴史学を融合させる試みは、研究者により何度も行われています。しかし、なかなかうまくいかないようです。両学問の統合しようとする優れた研究としては、川﨑剛『社会科学としての日本外交研究―理論と歴史の統合をめざして―』ミネルヴァ書房、2015年や保城広至『歴史から理論を創造する方法―社会科学と歴史学を統合する―』勁草書房、2015年などがあります。こうした知的営為や努力にもかかわらず、残念ながら、現時点では、こうした方法論が国際政治学界の研究者により、積極的に実践されて成果をだしているかとと問われれば、その結果は、心もとないと言わざるを得ないでしょう(政治学者と歴史学者が同じ事象を一緒に研究して、1つの統一した研究にまとめる試みは、管見の限り、大半が上手くいかずに終わっているようです)。もちろん、言うまでもなく、学問は必ずしも直線的に発展するわけではなりませんので、今後、両学問の長所を兼ね備えた画期的な研究成果が、次々と世に問われる日が来るのかもしれません。
さて、政治学と歴史学を兼ね備えた高坂「国際政治学」の意義や学問的遺産は、どのように評価できるでしょうか。服部氏は『高坂正堯』の終盤において、弟子たちの証言を引用しながら、「高坂が傑出した存在だっただけに、学問体系の継承は…不可能と見られた」(378ページ)と結んでいます。この「継承不可能性」にこそ、高坂「国際政治学」の1つの欠陥があると言ったら言い過ぎでしょうか。そもそも「学問」とは、ある体系や方法論、仮説などがあり、それを弟子や他の研究者が受け継いで、その欠点を補いながら修正して、その妥当性をエビデンスに照らして検証しながら、地道に時間をかけて発展するものです(「科学革命」が起こることもありますが)。国際政治学が単発の「時評」ではなく、「社会科学」と位置づけられるならば、誰も継承できない一個人のみの「秘伝」たる「国際政治学」では、発展しようがないでしょう。先行研究を乗り越えるのが、社会科学のエッセンスなのですから。
私は、誰も高坂「国際政治学」を継承できない1つの根本原因には、本書で指摘された「傑出」という彼の人間的属性を否定しませんが、それより、彼の学説に「政治学」と「歴史学」という、方法論上、相いれない学問体系が明確に整理されずに混然とした形で内在していたことにあると見た方が、より説得的だと思っています。批判を覚悟で大胆に述べれば、京都大学法学部で発祥した「国際政治学」は、それが誕生した1965年時点から、あるいは『国際政治―恐怖と希望―』(書名が国際政治「学」でないことに注意)が1966年に中央公論社から出版された時から、社会科学として発展する余地をほとんど残していなかったのではないでしょうか。他方、同時期に米国では、トーマス・シェリング『軍備と影響力』勁草書房、2018年(原書1966年)が出版され、それ以前にシェリングが世に問うた『紛争の戦略』(勁草書房、2008年〔原書1960年〕)とともに、その「学問体系」は数多くの研究者に「継承」され、核戦略研究やバーゲニング研究などの画期的な学問的成果の土台になり、国際政治学の進展に大きく寄与しました。
このような記事を書くと、読者から、日本の国際政治学には、理論のみならず歴史や地域研究などを包摂する総合的学問の良さがあるとお叱りを受けそうです。それはそれとしても、『高坂正堯』から日本の国際政治学の軌跡に思いをはせれば、その「社会科学としての発展」や「米国の国際政治学の展開」との比較から顧みると、日本の国際政治学の歩みは、全体として、あまりに属人的であり、科学的方法論に甘かったと思わざるを得ません(「自分の学問は自分で作るものだ」(高坂氏の発言、166ページ)。もちろん、その起源を高坂正堯氏個人だけに求めるわけではありません。学問を成り立たせる「批判的思考」を駆使して、高坂「国際政治学」に関する愚考を述べたにすぎませんので、この点は、読者の皆様にご理解をいただきたいと思います。

この図書については、高坂氏のお弟子さんである戸部良一氏が、素晴らしい読書エッセー「恩師の評伝 『高坂正堯』を読む」を書いておられるので、関心のある方は、こちらもお読みになるとよいでしょう。
私が、本書を読んで感じた率直な疑問の1つは、高坂正堯氏は「国際政治学」者なのか、それとも「国際政治史」の学者なのか、ということです。この点に関連して、著者の服部氏は、こう述べています。「高坂の死は、総合的な魅力のある学問としての国際政治学の死であった」(379ページ)と。つまり、高坂氏は、国際政治学者であったと位置づけているようです。とはいえ、別の個所で、服部氏が「高坂の講義は、理論よりも歴史重視である」と書いているように、また、歴史学者の入江昭氏との深い親交や博士学位論文となった『古典外交の成熟と崩壊』(19世紀の外交史研究)が1つの主著であること、さらには、お弟子さんに「歴史学者」とみなされる人が目立つことを考慮すれば、高坂氏の研究は「歴史」に軸足を置いていたと理解するのが適切でしょう。なお、私はこれまでに高坂氏の主著をほぼ全て読み終えてます。そこから感じた高坂氏の国際政治へのアプローチは、「史学」専攻と違うものの、「歴史」に重きを置く分析手法でした。
ある学問が、学際的で総合的であるのは、必ずしも悪いことではありません。しかし、「総合的」であることは、ややもすれば「何でもあり」になりかねません。その結果、当該学問のアイデンティティが損なわれ、その体系があいまいになり、結果として継続的で持続的な科学的発展が難しくなる弊害は否定できないでしょう。私見では、残念ですが、高坂氏が京都大学で始めた「国際政治学」は、このトラップに嵌ったようです。端的に言えば、高坂「国際政治」学は、社会科学としての国際政治学なのか、それとも国際政治史なのか、判然としないのです。
「国際政治学」と「国際政治史(歴史学)」は、戦争や平和などを扱うこと等において共通していますが、それぞれは似て非なるものです。端的に言えば、社会科学としての政治学は概して理論化(単純化)や一般化を目指すのに対して、歴史学は、それをきらい(例外はありますが)、個別の歴史事象の特殊性や複雑性を重視します(詳しくは、コリン・エルマン、ミリアム・エルマン編『国際関係研究へのアプローチ―歴史学と政治学の対話―』東京大学出版会、2003年をお読みください)。つまり、政治学と歴史学は、方法論において、「水と油」なのです。そう簡単に混ざり合うものではありません。
こうした違いを乗り越えて、政治学と歴史学を融合させる試みは、研究者により何度も行われています。しかし、なかなかうまくいかないようです。両学問の統合しようとする優れた研究としては、川﨑剛『社会科学としての日本外交研究―理論と歴史の統合をめざして―』ミネルヴァ書房、2015年や保城広至『歴史から理論を創造する方法―社会科学と歴史学を統合する―』勁草書房、2015年などがあります。こうした知的営為や努力にもかかわらず、残念ながら、現時点では、こうした方法論が国際政治学界の研究者により、積極的に実践されて成果をだしているかとと問われれば、その結果は、心もとないと言わざるを得ないでしょう(政治学者と歴史学者が同じ事象を一緒に研究して、1つの統一した研究にまとめる試みは、管見の限り、大半が上手くいかずに終わっているようです)。もちろん、言うまでもなく、学問は必ずしも直線的に発展するわけではなりませんので、今後、両学問の長所を兼ね備えた画期的な研究成果が、次々と世に問われる日が来るのかもしれません。
さて、政治学と歴史学を兼ね備えた高坂「国際政治学」の意義や学問的遺産は、どのように評価できるでしょうか。服部氏は『高坂正堯』の終盤において、弟子たちの証言を引用しながら、「高坂が傑出した存在だっただけに、学問体系の継承は…不可能と見られた」(378ページ)と結んでいます。この「継承不可能性」にこそ、高坂「国際政治学」の1つの欠陥があると言ったら言い過ぎでしょうか。そもそも「学問」とは、ある体系や方法論、仮説などがあり、それを弟子や他の研究者が受け継いで、その欠点を補いながら修正して、その妥当性をエビデンスに照らして検証しながら、地道に時間をかけて発展するものです(「科学革命」が起こることもありますが)。国際政治学が単発の「時評」ではなく、「社会科学」と位置づけられるならば、誰も継承できない一個人のみの「秘伝」たる「国際政治学」では、発展しようがないでしょう。先行研究を乗り越えるのが、社会科学のエッセンスなのですから。
私は、誰も高坂「国際政治学」を継承できない1つの根本原因には、本書で指摘された「傑出」という彼の人間的属性を否定しませんが、それより、彼の学説に「政治学」と「歴史学」という、方法論上、相いれない学問体系が明確に整理されずに混然とした形で内在していたことにあると見た方が、より説得的だと思っています。批判を覚悟で大胆に述べれば、京都大学法学部で発祥した「国際政治学」は、それが誕生した1965年時点から、あるいは『国際政治―恐怖と希望―』(書名が国際政治「学」でないことに注意)が1966年に中央公論社から出版された時から、社会科学として発展する余地をほとんど残していなかったのではないでしょうか。他方、同時期に米国では、トーマス・シェリング『軍備と影響力』勁草書房、2018年(原書1966年)が出版され、それ以前にシェリングが世に問うた『紛争の戦略』(勁草書房、2008年〔原書1960年〕)とともに、その「学問体系」は数多くの研究者に「継承」され、核戦略研究やバーゲニング研究などの画期的な学問的成果の土台になり、国際政治学の進展に大きく寄与しました。
このような記事を書くと、読者から、日本の国際政治学には、理論のみならず歴史や地域研究などを包摂する総合的学問の良さがあるとお叱りを受けそうです。それはそれとしても、『高坂正堯』から日本の国際政治学の軌跡に思いをはせれば、その「社会科学としての発展」や「米国の国際政治学の展開」との比較から顧みると、日本の国際政治学の歩みは、全体として、あまりに属人的であり、科学的方法論に甘かったと思わざるを得ません(「自分の学問は自分で作るものだ」(高坂氏の発言、166ページ)。もちろん、その起源を高坂正堯氏個人だけに求めるわけではありません。学問を成り立たせる「批判的思考」を駆使して、高坂「国際政治学」に関する愚考を述べたにすぎませんので、この点は、読者の皆様にご理解をいただきたいと思います。