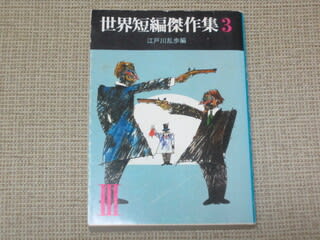江戸川乱歩編 1960年 創元推理文庫
ことし3月ころに買い求めた古本の文庫、シリーズは時代順に作品並べてってるらしいんで、こないだ読んだ第2集のあとから、ぼちぼち読んでった。
1925年から1929年の作品が収録されてんだけど、途中で編者の評として、1925年に発表された名作が多いことを「この年は本格短編にとって忘れえぬ年といえるだろう」と紹介してる、大正14年かあ。
古い時代のものだし、不勉強な私だし、読んだことないものばっかりなんだけど、蒸し風呂のなかで使われた凶器の話(「茶の葉」)とか、体育館みたいな密室のベッドの上で大金持ちが餓死した謀略の話(「密室の行者」)とかは、子どもん頃どっかで紹介されてんの見たことあった。
それだけアイデアが秀逸だっつーことなんだろう、もともとはこういう小説だったのねという発見ができて、なるほどねえと思うものあった。
収録作は以下のとおり。物語の序盤のうちから引用して何となくどんな話だったかのメモとして、あまりくわしく内容を書いたりしないようにしておく。
「キプロスの蜂」 The Cypryan Bees(1925) アントニー・ウイン
>ヘイリー博士は眼鏡をあげて、目にあわせた。
>「それは私も聞いている」博士はかぎたばこの箱をあけると、大きくつまんで鼻につめた。「もちろんバイルズ君、この小箱が蜂をいれるまえは何に使われたものか、ごぞんじだろうね」
>「いえ――知りませんね」(p.12)
ある晩、広場で自動車の運転席で死んでいる女が見つかる、窓は閉まっていて、女は蜂に刺されていた。車の床から見つかった死んだ蜂は、キプロス蜂という特殊な種類だという。
「堕天使の冒険」 The Adventure of the Fallen Angels(1925) パーシヴァル・ワイルド
>「どこかあやしい点があることはぼくにもわかっていたんだ」とトニイは意気揚々として始めた。「それもまえから、ずっとまえからだよ」
>「ぼくがあれほど言ったのにかい?」とビルは逆襲した。(p.54)
トランプで勝ち過ぎている相手に対して、カードに印をつけているだろとインチキを指摘したトニイだったが、彼よりそういうことに詳しいビルによって思いもよらぬ大きな問題に出くわすことになる。これが事実にもとづくストーリーだというのもちょっと驚き。
「茶の葉」 The Tea Leaf(1925) E・ジェブスン R・ユーステス
>ケルスタンは娘の破約にまったく機嫌を悪くしたようすだった。彼はウィラトンがルースを適当にからかった末、捨てたのだと思ったらしい。(略)ウィラトンのほうも、人柄がまえよりいっそうとっつきにくくなった。彼は永久に痛みつづける頭を持った熊のごとくに見えた。私は友人としてふたりの仲をもう一度和解させるようにつとめるのが自分の役目のような気がしたのだが、とりなしは見事に失敗した。(p.112)
ケルスタンとウィルトンは仲たがいをしたあとも、同じ曜日の同じ時刻に風呂通いをする習慣を意地でも変えようとしなかったので、浴室のなかで顔を合わせなければならないことが続いたが、そうしているある日のこと事件が起きる。
「偶然の審判」 The Avenging Chance(1925) アントニイ・バークリー
>ロジャー・シェリンガムは、あとになって考えてみて、新聞が「毒入りチョコレート事件」と呼んだ事件は、彼が出あったうちで、もっとも完全な計画的殺人だと思うようになった。動機は、捜すべき急所さえわかっていれば、きわめて明らかだったはずである――ところが、それがだれにもわからなかった。方法は、実際の要所さえつかめれば、まるで見当もつかないというほどでもなかった――ところが、それがだれにもつかめなかった。犯跡は、それをかくしているものに気づいたら、見やぶることも、そうむずかしいものではなかった――ところが、それにだれも気づかなかったのである。(p.139)
これ作者が長篇「毒入りチョコレート事件」 The Poisoned Chocolates Case 1929 を短篇に圧縮したものなんだという、編者が「そのみごとな構成は、同時代の作品中でも抜群である」としているけど、一読したなかでは私もこれがいちばんおもしろかった。トリックがどうこうとかぢゃなく、おもしろい。
「密室の行者」 Solved by Inspection(1925) ロナルド・A・ノックス
>不屈の精神をもって聞こえた秘密探偵、マイルズ・ブレドンは、仕事にはまったく無能だと、つねにみずから称していた。(略)ただし、あるとき一度だけは、ブレドンも、調べるだけで現実に問題を解決したと主張できることがあった。真相をみきわめるなんらの予備知識をもたずにである。実際、氏は、安っぽい新聞はほとんど読まないので、風変わりな百万長者、ハーバート・ジャービソンが、ベッドで死んでいるのを発見されるまで、彼のことなど耳にしたこともなかったといってもそう不思議ではない。ブレドンは、インデスクライバブル会社が、彼自身とほとんど同じくらいに高く買っている、高給とりの医師のシモンズ氏と、ウィルトシャーへ汽車で行く途中、その事件の状況を話してもらっただけだった。(p.171)
秘教的なものに凝っていた百万長者の死の謎を探偵があっという間に解決する、陰惨な事件のはずなのに、小説そのものはどっかユーモアが感じられるものがある。
「イギリス製濾過器」 English Filter(1926) C・E・ベチョファー・ロバーツ
>「ところでドルシー君」給仕がコーヒーをもってきて、一同が葉巻きに火をつけると、ホークスは口をひらいた。「わたしは三時にカスタンニ教授のところへ挨拶にいくつもりだったんだが、向こうのつごうはどうだろう? いいね? よろしい。そこで、わたしがどうしてもたずねてみたいのは、あとはリボッタ教授だけだ。教授の最近の仕事に、とても興味をもってね」
>「それはなんの造作もないことです」ドルシーは言った。「よかったら、いますぐでも――きっと研究室におられますよ。それに、あそこへいかれるなら、教授の助手にも会ってお話しされるようおすすめしますね」(p.195)
ローマの大学では昇進は年功順という組織になっていて、すぐれた助手の研究成果も上にいる教授のもので発表される、そんな研究室内で毒殺事件が起きる。
「ボーダー・ライン事件」 The Border-Line Case(1928) マージェリー・アリンガム
>新聞紙はそれを、石炭小路射殺事件と見出しでうたっていた。石炭小路というのは、ヴァケイション街を横に切れた狭い路地だった。事実はこうである――真夜中の一時、ヴァケイション街を巡回中の巡査が、人あしの途絶えた街頭で行き倒れを発見した。あまりの暑さに、うんざりしきっていた巡査は、その男の襟もとを弛めてやっただけで、ろくにあらためもしないで救急車を呼んだ。
>自動車が到着してみて、男がすでに絶命していることを知った。死体はそのまま死体置き場に運ばれた。検屍の結果、肩胛骨の下部からの盲貫銃創が死因。(p.221-222)
小路の突き当りはカフェになっていて通り抜けできない、ヴァケイション街では殺人現場を挟んで二人の巡査が巡回していて通りを見通せるんだが、誰にも見られずにどうやって男を撃ったのかという、閉め切ってないけど密室状態での事件。
「二壜のソース」 The Two Bottles of Relish(1928?) ロード・ダンセイニ
>私の名まえですか? スミザーズっていいまして、身分はほんのつまらぬ外交販売員なんですが、取り扱っています商品は、ナムヌモって商標の、肉だのから味の料理なんかにかけますソースなんです。これを食料品店に卸して歩くのが、私の仕事なんです。(略)(p.239)
>それというのは、このリンリイさんってひとが、じつにどうも、なんともいえない奇態な人物だったのです。奇人といいますか、天才といいますか。奇想天外な考えが、それこそ無尽蔵に飛び出してくるんです。(p.243)
ふとしたきっかけでルームメイトになったソースの販売員と、ロンドンに滞在して職を選ぼうとしているオックスフォードを卒業したばかりのリンリイ。新聞で話題になっている事件、ある男が貸別荘で少女と同棲を始めたが、少女が行方不明になってしまい、警視庁も捜し出すことができない、状況的には男が少女の金を奪って殺したと考えられる、そんな事件の真相をふたりが追究していく。推理がどうのこうのというより、異色作って言葉があてはまる。
「夜鶯荘」 Philomel Cottage(1928?) アガサ・クリスティ
>友人の家でジェラルド・マーティンに会ったのである。彼はむちゃくちゃに彼女に惚れこみ、一週間とたたないうちに、ふたりは婚約してしまった。かねがね、自分のことを「恋愛なんて柄にない女」だと思っていたアリクスは、完全に足をすくわれてしまったのである。
>意識せずに、彼女はまえの恋人の目をさまさせることになった。ディック。ウィンディフォードは怒りで口もきけないほどになって、彼女のところに来た。
>「あんなやつ、きみにとってはまるで見も知らない男じゃないか。どんな素性か、知れやしないじゃないか」(p.272)
アガサ・クリスティって有名なんだけど、私はあんまり読んでない、長いものはいくつか読んだけど、特に短篇はほとんど読んだことない、しかし、これはおもしろい、いままで読んだクリスティのなかでいちばんおもしろいんぢゃなかろうか。
「完全犯罪」 The Perfect Crime(1929) ベン・レイ・レドマン
>世界で最も偉大なこの探偵は、手にしたポートワインのグラスを満足げにすすりながら、テーブルごしに親友の顔をしげしげとながめた。彼はもう何年間も、友人たちと歓談するといった楽しみをもったことがなかったからだ。相手のグレゴリー・ヘアは、友の顔を見返しながら、耳をすませて、その言葉を待った。
>「このことには疑問の余地がないと思うね」トレヴァーは、グラスをおきながら、くりかえした。「完全犯罪は可能だよ。ただ、それには完全な犯人が必要なわけだ」(p.313)
犯罪者を専門的研究の対象にしてきて間違いをおかしたことのないハリスン・トレヴァー博士と、理想的な聞き手って感じの刑事弁護士のグレゴリー・ヘア、ふたりの完全犯罪論争は、思わぬ方向へころがっていく。
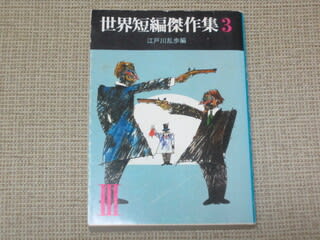
ことし3月ころに買い求めた古本の文庫、シリーズは時代順に作品並べてってるらしいんで、こないだ読んだ第2集のあとから、ぼちぼち読んでった。
1925年から1929年の作品が収録されてんだけど、途中で編者の評として、1925年に発表された名作が多いことを「この年は本格短編にとって忘れえぬ年といえるだろう」と紹介してる、大正14年かあ。
古い時代のものだし、不勉強な私だし、読んだことないものばっかりなんだけど、蒸し風呂のなかで使われた凶器の話(「茶の葉」)とか、体育館みたいな密室のベッドの上で大金持ちが餓死した謀略の話(「密室の行者」)とかは、子どもん頃どっかで紹介されてんの見たことあった。
それだけアイデアが秀逸だっつーことなんだろう、もともとはこういう小説だったのねという発見ができて、なるほどねえと思うものあった。
収録作は以下のとおり。物語の序盤のうちから引用して何となくどんな話だったかのメモとして、あまりくわしく内容を書いたりしないようにしておく。
「キプロスの蜂」 The Cypryan Bees(1925) アントニー・ウイン
>ヘイリー博士は眼鏡をあげて、目にあわせた。
>「それは私も聞いている」博士はかぎたばこの箱をあけると、大きくつまんで鼻につめた。「もちろんバイルズ君、この小箱が蜂をいれるまえは何に使われたものか、ごぞんじだろうね」
>「いえ――知りませんね」(p.12)
ある晩、広場で自動車の運転席で死んでいる女が見つかる、窓は閉まっていて、女は蜂に刺されていた。車の床から見つかった死んだ蜂は、キプロス蜂という特殊な種類だという。
「堕天使の冒険」 The Adventure of the Fallen Angels(1925) パーシヴァル・ワイルド
>「どこかあやしい点があることはぼくにもわかっていたんだ」とトニイは意気揚々として始めた。「それもまえから、ずっとまえからだよ」
>「ぼくがあれほど言ったのにかい?」とビルは逆襲した。(p.54)
トランプで勝ち過ぎている相手に対して、カードに印をつけているだろとインチキを指摘したトニイだったが、彼よりそういうことに詳しいビルによって思いもよらぬ大きな問題に出くわすことになる。これが事実にもとづくストーリーだというのもちょっと驚き。
「茶の葉」 The Tea Leaf(1925) E・ジェブスン R・ユーステス
>ケルスタンは娘の破約にまったく機嫌を悪くしたようすだった。彼はウィラトンがルースを適当にからかった末、捨てたのだと思ったらしい。(略)ウィラトンのほうも、人柄がまえよりいっそうとっつきにくくなった。彼は永久に痛みつづける頭を持った熊のごとくに見えた。私は友人としてふたりの仲をもう一度和解させるようにつとめるのが自分の役目のような気がしたのだが、とりなしは見事に失敗した。(p.112)
ケルスタンとウィルトンは仲たがいをしたあとも、同じ曜日の同じ時刻に風呂通いをする習慣を意地でも変えようとしなかったので、浴室のなかで顔を合わせなければならないことが続いたが、そうしているある日のこと事件が起きる。
「偶然の審判」 The Avenging Chance(1925) アントニイ・バークリー
>ロジャー・シェリンガムは、あとになって考えてみて、新聞が「毒入りチョコレート事件」と呼んだ事件は、彼が出あったうちで、もっとも完全な計画的殺人だと思うようになった。動機は、捜すべき急所さえわかっていれば、きわめて明らかだったはずである――ところが、それがだれにもわからなかった。方法は、実際の要所さえつかめれば、まるで見当もつかないというほどでもなかった――ところが、それがだれにもつかめなかった。犯跡は、それをかくしているものに気づいたら、見やぶることも、そうむずかしいものではなかった――ところが、それにだれも気づかなかったのである。(p.139)
これ作者が長篇「毒入りチョコレート事件」 The Poisoned Chocolates Case 1929 を短篇に圧縮したものなんだという、編者が「そのみごとな構成は、同時代の作品中でも抜群である」としているけど、一読したなかでは私もこれがいちばんおもしろかった。トリックがどうこうとかぢゃなく、おもしろい。
「密室の行者」 Solved by Inspection(1925) ロナルド・A・ノックス
>不屈の精神をもって聞こえた秘密探偵、マイルズ・ブレドンは、仕事にはまったく無能だと、つねにみずから称していた。(略)ただし、あるとき一度だけは、ブレドンも、調べるだけで現実に問題を解決したと主張できることがあった。真相をみきわめるなんらの予備知識をもたずにである。実際、氏は、安っぽい新聞はほとんど読まないので、風変わりな百万長者、ハーバート・ジャービソンが、ベッドで死んでいるのを発見されるまで、彼のことなど耳にしたこともなかったといってもそう不思議ではない。ブレドンは、インデスクライバブル会社が、彼自身とほとんど同じくらいに高く買っている、高給とりの医師のシモンズ氏と、ウィルトシャーへ汽車で行く途中、その事件の状況を話してもらっただけだった。(p.171)
秘教的なものに凝っていた百万長者の死の謎を探偵があっという間に解決する、陰惨な事件のはずなのに、小説そのものはどっかユーモアが感じられるものがある。
「イギリス製濾過器」 English Filter(1926) C・E・ベチョファー・ロバーツ
>「ところでドルシー君」給仕がコーヒーをもってきて、一同が葉巻きに火をつけると、ホークスは口をひらいた。「わたしは三時にカスタンニ教授のところへ挨拶にいくつもりだったんだが、向こうのつごうはどうだろう? いいね? よろしい。そこで、わたしがどうしてもたずねてみたいのは、あとはリボッタ教授だけだ。教授の最近の仕事に、とても興味をもってね」
>「それはなんの造作もないことです」ドルシーは言った。「よかったら、いますぐでも――きっと研究室におられますよ。それに、あそこへいかれるなら、教授の助手にも会ってお話しされるようおすすめしますね」(p.195)
ローマの大学では昇進は年功順という組織になっていて、すぐれた助手の研究成果も上にいる教授のもので発表される、そんな研究室内で毒殺事件が起きる。
「ボーダー・ライン事件」 The Border-Line Case(1928) マージェリー・アリンガム
>新聞紙はそれを、石炭小路射殺事件と見出しでうたっていた。石炭小路というのは、ヴァケイション街を横に切れた狭い路地だった。事実はこうである――真夜中の一時、ヴァケイション街を巡回中の巡査が、人あしの途絶えた街頭で行き倒れを発見した。あまりの暑さに、うんざりしきっていた巡査は、その男の襟もとを弛めてやっただけで、ろくにあらためもしないで救急車を呼んだ。
>自動車が到着してみて、男がすでに絶命していることを知った。死体はそのまま死体置き場に運ばれた。検屍の結果、肩胛骨の下部からの盲貫銃創が死因。(p.221-222)
小路の突き当りはカフェになっていて通り抜けできない、ヴァケイション街では殺人現場を挟んで二人の巡査が巡回していて通りを見通せるんだが、誰にも見られずにどうやって男を撃ったのかという、閉め切ってないけど密室状態での事件。
「二壜のソース」 The Two Bottles of Relish(1928?) ロード・ダンセイニ
>私の名まえですか? スミザーズっていいまして、身分はほんのつまらぬ外交販売員なんですが、取り扱っています商品は、ナムヌモって商標の、肉だのから味の料理なんかにかけますソースなんです。これを食料品店に卸して歩くのが、私の仕事なんです。(略)(p.239)
>それというのは、このリンリイさんってひとが、じつにどうも、なんともいえない奇態な人物だったのです。奇人といいますか、天才といいますか。奇想天外な考えが、それこそ無尽蔵に飛び出してくるんです。(p.243)
ふとしたきっかけでルームメイトになったソースの販売員と、ロンドンに滞在して職を選ぼうとしているオックスフォードを卒業したばかりのリンリイ。新聞で話題になっている事件、ある男が貸別荘で少女と同棲を始めたが、少女が行方不明になってしまい、警視庁も捜し出すことができない、状況的には男が少女の金を奪って殺したと考えられる、そんな事件の真相をふたりが追究していく。推理がどうのこうのというより、異色作って言葉があてはまる。
「夜鶯荘」 Philomel Cottage(1928?) アガサ・クリスティ
>友人の家でジェラルド・マーティンに会ったのである。彼はむちゃくちゃに彼女に惚れこみ、一週間とたたないうちに、ふたりは婚約してしまった。かねがね、自分のことを「恋愛なんて柄にない女」だと思っていたアリクスは、完全に足をすくわれてしまったのである。
>意識せずに、彼女はまえの恋人の目をさまさせることになった。ディック。ウィンディフォードは怒りで口もきけないほどになって、彼女のところに来た。
>「あんなやつ、きみにとってはまるで見も知らない男じゃないか。どんな素性か、知れやしないじゃないか」(p.272)
アガサ・クリスティって有名なんだけど、私はあんまり読んでない、長いものはいくつか読んだけど、特に短篇はほとんど読んだことない、しかし、これはおもしろい、いままで読んだクリスティのなかでいちばんおもしろいんぢゃなかろうか。
「完全犯罪」 The Perfect Crime(1929) ベン・レイ・レドマン
>世界で最も偉大なこの探偵は、手にしたポートワインのグラスを満足げにすすりながら、テーブルごしに親友の顔をしげしげとながめた。彼はもう何年間も、友人たちと歓談するといった楽しみをもったことがなかったからだ。相手のグレゴリー・ヘアは、友の顔を見返しながら、耳をすませて、その言葉を待った。
>「このことには疑問の余地がないと思うね」トレヴァーは、グラスをおきながら、くりかえした。「完全犯罪は可能だよ。ただ、それには完全な犯人が必要なわけだ」(p.313)
犯罪者を専門的研究の対象にしてきて間違いをおかしたことのないハリスン・トレヴァー博士と、理想的な聞き手って感じの刑事弁護士のグレゴリー・ヘア、ふたりの完全犯罪論争は、思わぬ方向へころがっていく。