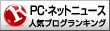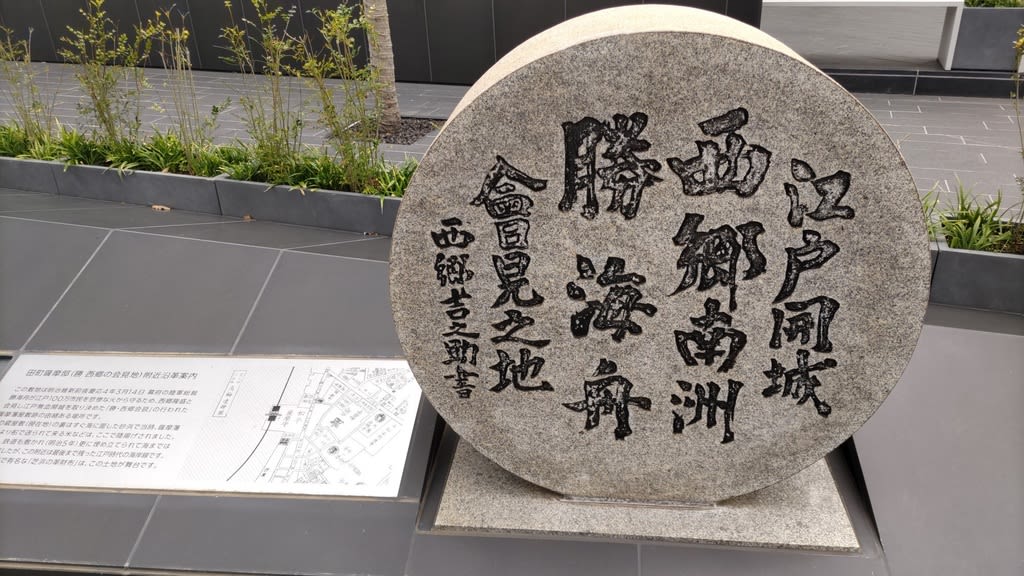皇居の由緒ある豊かな自然や歴史に思いをはせながら四季の変化や花々が見られるように、多様な樹木、草花が配置されています。
天守台は江戸城天守閣のあったところで三度建てられましたが、明暦(1657年)の大火で焼失した後は、再建されていません。
天守台から見える大芝生は大奥のあった場所です。本丸御殿のあった場所は、令和元年11月大嘗祭が執り行われました。
その一角には忠臣蔵でお馴染みの松の大廊下跡の石碑と案内板が設置されています。本丸御殿が豪華で凄かったであろうと想像できます。再建されたら良いと願っております。
中雀門跡から下っていくと大きな長い建物の百人番所があり、つつじの花がきれいに咲いております。大手門から出るとタイムスリップした世界から現実の社会に戻された感じがしました。