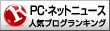海鮮焼きそば(桂宮)
横浜中華街で食事をするときは広東伝統創作料理店「桂宮」に行きます。
横浜中華街大通り沿いにあり、お店は清潔で広々とした店内は少人数から大 人数までどんな宴会にも対応してくれます。 本場シェフによる創作料理の数々と点心師が店内で手作りする点心をそろえたコースが人気です。
この日は海鮮焼きそばと春巻きを注文しました。ランチタイムには飲物がサービスとなっておりましたのでマンゴジュースを頼みました。焼きそばの量は具とともにとても多くて美味しくお腹いっぱいとなりました。
三遊亭圓朝のお墓
東京に「谷根千」と呼ばれる場所があります。谷中、根津、千駄木の地区を称しております。
千駄木駅から三崎坂を登っていくと全生庵というお寺があります。三遊亭圓朝のお墓があり毎年8月の命日には落語家の多くの皆さんが集まり供養参りをして、一般人との交流をするイベントが催されます。
三遊亭圓朝(1839~1900)は、2代目三遊亭円生の門に入りました。18歳で真打となり、芝居道具を用いて世話物を講じ、芝居囃と言われて大いに名を挙げてから落語に専念して創作落語の自作自演に新境地を開きました。
全生庵には圓朝が収集した幽霊図が所蔵されて毎年8月には一般公開をされています。明治時代の剣客で山岡鉄舟の筆で「三遊亭圓朝無舌居士」と墓石に記されています。山岡鉄舟のお墓も圓朝の墓の側にあります。
剣と笑いと涙のお芝居「ふたり傘」、豪華舞踊絵巻「歌謡舞踊」を繰り広げる章劇(座長・澤村蓮)公演を観覧しました。
章劇団は、芸達者な澤村章太郎が、2000年に旗揚げ、関東に新天地を求め一からスタート。2014年の浅草木馬館リニューアル特別公演では杮落しを任された人気劇団です。
2015年に、澤村章太郎は後見となり、澤村蓮が座長を襲名する。古典から現代劇、剣劇と幅広くこなす芸の力と和気藹々とした雰囲気が人気の秘訣。
篠原演芸場は200名客席で、観客のほどんどが女性たちで満席の状況。贔屓の役者が舞踊で出演をすると和服の着物の襟に扇形にした一万円札を大きなヘアピンで挟んでいきます。入場料は1800円なのに、役者の祝儀は万札がいっぱいなのにはビックリします。
 大衆演劇の役者たちは観客を常に大切にして応対をしています。
大衆演劇の役者たちは観客を常に大切にして応対をしています。高尾山のリフト
高尾山に登るには登山道とケーブルカーとリフトの3ルートがあります。
往復のチケットを購入して行きはケーブルカーを利用しました。このケーブルカーはかなり急坂のところを登っていきます。最高傾斜は31度の急勾配のところがあります。ケーブルカーは上りと下りの車両が交換するところが見所です。高尾山駅に到着すると茶店や土産物屋など賑わっています。見晴らし台からは遠くまで展望できます。
帰りはリフトを利用して降りました。遠くの景色を見ながら降りていくので写真撮影にはいいところです。途中かなり急勾配のところを下っていくのでスリルがあります。途中リフトに乗っている人の写真を撮影する人がおり、希望すれば写真を撮影してくれます。撮られた写真はリフトを降りた場所でプリントされたものが出来ていて記念の土産となります。わずか数分前に撮影した写真が出来上がっているとは凄いものです。
写真にはQRコードが付いていてスマホで読み取るとダウンロードできるようになっていました。12分間のリフトの空中散歩を楽しみました。
演題は「つれづれなるままに」でブログ掲載時のところから付けました。
最初はトークで、TAMCの歴史ある組織で研修したマジックをボランティア出演をした時の芸名「ハゲ山ひかる」の披露から、漫談を入れて客席の爆笑を誘いました。毎日思いついたことやエッセイを綴っているブログの説明から演技に入りました。
客席からステージに上がって頂いた客に手伝ってもらいました。ロープを取り出して椅子に座った状態で足と手をロープで固く縛ってもらう。共演者の出水博造さんが登場してきて幕を揚げて観客から姿が見えないようにしてもらう。その後、幕の内側から帽子、ピカチュウの人形、ネクタイ、アンパンマンの人形、背広の上着などが外へ投げ出される。幕を下ろすとロープで縛られたままである。客にロープをほどいてもらう。という摩訶不思議な作品でした。
友人たちが多く来場して観覧してくれました。そして貴重なコメントも頂き思い出に残るマジック演技でした。
東日本大震災復興支援として被災した宮城県、岩手県、福島県からも出店して特産品の販売をして賑わっております。石巻焼きそば、仙台からあげなども人気があり長い行列ができておりました。
埼玉県東松山の味噌ダレやきとりのブースからは、炭火焼きの煙がもうもうと出ております。集客効果もあり、こちらも長い行列です。人気のやきとりを50本も購入している人もおりました。東松山の味噌ダレやきとりは久し振りなので「かしら」を購入して家まで持ち帰りました。とても美味しかったです。
イベントプログラムでは、南口トランパル広場と北口イロノワヒロバで朝から夕方までスケジュールが組まれております。フラダンス、よさこいチーム、大塚阿波おどり、、合気道、歌謡曲などの披露がされていました。
新しく移転をしてオープンをした「おにぎり ぼんご」は相変わらず人気があり行列が絶えません。
大塚の発展は、街ぐるみで取り組みイベントを盛り上げている心意気が見られます。
最初に10月23日(日)に開催されるTAMC(東京アマチュア・マジシャンズ・クラブ)「マジック発表会」についての説明がありました。3年振りに開催されるステージマジックなので多くの来場者が見込まれる。
研修は、3枚のカードのうち客が選んだカードを予言しておくもの。27枚のカードを3列に9枚づつ並べて客が選んだカードを2回並べ替えることでずばり当てるもの。縦と横に3枚づづ並べた9枚のカードのうち客が選んだカード1枚を列単位にひっくり返していき当てるもの。15匹の魚のうちに客が選んだ一匹の魚をどこの水族館にいるかで当てるもの。宝くじが一瞬のうちに100万円に変身するもの等を行いました。
参加者は、研修したものの作品を習得しては覚えるのも早くなってきました。自分で復習していくとよく理解ができるようです。毎回、マジック教室に参加することが楽しみのようです。
TAMC(東京アマチュア・マジシャンズ・クラブ)の発表会は、今回で74回目となります。コロナ禍の為に2年間中止となり、3年振りの開催です。
10月23日(日曜日)有楽町「朝日ホール」午後2時開演
ご来場の皆様は、「入場券」の持参と「マスク」の着用をお願いいたします。おみやげマジック「TAMC水族館」のプレゼントがあります。
私は出水博造さんと共演して「つれづれなるままに」に出演します。
出演時間は、第1部の午後2時30分頃の予定となっています。
どうぞお楽しみください。お待ちしております。
幼児対象の母子16組が参加しておりました。今まで出演した観客の中では最も幼い子供たちでしたが、その若い母親たちも一緒に楽しめるものを披露しました。
最初は宝くじが百万円に変化するもの、次々にカラフルな花籠が出てくるラッキーバッグ、ロープと3色のシルクを利用した神田祭、新聞紙を活用した女の子たち、たけのこ、9つの数字が最後に8に集まる魔方陣などを披露しました。
12匹の動物のうち、選んだ動物を当てる時には、手伝ってくれた女の子が選んだ動物を思わず言ってしまったものだから、会場内爆笑となりました。いろいろとハプニングがあるものです。
マジックの後は、本の読み聞かせの時間で、ハロウィンに関するものでした。最後には参加した幼児たちにはお菓子のプレゼントがありました。
久し振りのマジックライブでしたが、観客の反応が直接分かりますのでとても良い体験で面白かったです。
中村 崇さん
中村 崇さんは「チーム渋谷888」のリーダーです。毎月8日、18日、28日の午後8時から、渋谷の名所となっているハチ公像の近辺や駅前広場、スクランブル交差点脇の喫煙所周りの清掃活動をしております。
渋谷駅前には多くの人が集まっておりました。ゴミや空き缶、ペットボトル、たばこの吸い殻などがとても多かったです。ゴミ清掃をしていると共感を持って話しかけてくる人たちがおります。
渋谷のゴミの多さは行政が立ち上がらないと少なくならない。ゴミ置き場の収集作業を多くすることで改善するだろう。などとコメントをしています。次回から一緒にゴミ清掃活動に加わりたい。と話しています。
中村 崇さんは清掃活動が終わるとファミリーレストランで打ち上げを兼ねた懇親会を開催します。いつも相手のことを思いやる心の優しい気持を持っている人です。
このチーム渋谷888の清掃活動は渋谷区でも認識しており、長谷部健渋谷区長から感謝状を授与されました。中村 崇さんはアイディアマンでもあります。文書能力も長けております。そして実行力のある素晴らしい方です。
昭和7年(1932年)10月1日、北豊島郡の巣鴨町・西巣鴨町・高田町・長崎町の4町が合併し、豊島区が誕生して今年で90年目を迎えています。
明治・大正から昭和・平成・令和へと大きく変貌をとげた豊島区のあゆみが展示されています。郷土資料、美術・文学作品とジオラマ・模型、映像等で豊島区の歴史と未来像を紹介しています。
第2章 豊島区の誕生と人々のくらし としまくのはじまり
第5章 輝く未来 としましんじだい
特別展 イケちゃんランド IKEBUS としまキッズパーク
それぞれのコーナーで懐かしい豊島や未来の池袋などが紹介されていてとても参考になりました。
開催期間は、令和5年3月26日まで。その期間中には、講演会、対談、朗読&対談、ジオラマ解説などの関連イベントが開催される案内がありました。
知久晴美さんが劇団ムジカフォンテを設立して33年が経過しております。今回の豊島区ミュージカル第8弾の舞台は、池袋駅東西を結ぶ「雑司が谷隧道」(通称ウイロード)がテーマとなっております。
大正14年(1925年)に開通し、戦後はヤミ市をつなぐ通路として活用され、その後は「ションベンガード」とも呼ばれ、暗く、汚く、怖い通路といわれていました。昭和61年の大改修でタイルが張られ「ウイロード」と名付けられました。さらに令和元年には、美術作家・植田志保さんにより筆と手で描かれた隧道は、明るく、きれいな、素晴らしいトンネルへと変身をしました。
ストーリーは、百鬼夜行のオープニングから、雑司が谷隧道の大正14年、昭和7年、昭和20年、戦後の闇市、昭和23年、昭和60年頃と展開していき、エピローグは百鬼夜行と盛り上がっていきました。出演者も80歳から3歳の幼児まで多数の方がおりまして、迫力満点のミュージカル公演でした。
今年で豊島区制施行90周年を迎えることで、お祝いとしての豊島区ミュージカル公演でした。劇団ムジカフォンテは10年前の豊島区制施行80周年より豊島区に関するテーマを採り上げて上演をしてきた実績があり、今回が8作目となります。
いつもながら、知久晴美代表と劇団員の方たちの情熱溢れる熱心な演技は、観客に楽しさと元気を与えてくれました。
トキワ荘のヒーローたち
南長崎花咲公園には、トキワ荘に住んでいたマンガ家のヒーローたちの記念碑があります。トキワ荘のモニュメント、マンガ家たちの似顔絵とサインが刻まれています。
同じ公園の敷地内に「トキワ荘マンガミュージアム」が出来る前までは、この記念碑がトキワ荘の思い出を語る主役であった。トキワ荘で過ごしていたマンガ家たちの意気込みがサインに表れています。
「トキワ荘マンガミュージアム」を見学するときには、このトキワ荘のヒーローたちの記念碑も見学するといいでしょう。
具体的には、内外商社貿易の第一線、大メーカーの国際部門に活躍する人材、官公庁各機関及び会社の駐在員、独立企業の経営マンを養成する。
従って語学に重点をおき専門科目の学習には、原書を教科書として使用することを強く推進する。会話は勿論、スピーチ等語学に絶対の自信を与える」
金子泰藏学長を知らない教員、職員も多くなっておりますが、基本となる原点を理解することは必要であります。早稲田大学は大隈重信氏、慶應義塾大学は福沢諭吉氏が創学者であると多くの人が認識しております。
総会では昨年度の活動報告がされましたが、コロナ禍の為に通常の活動がほとんど出来なかった。その中で、現役スポーツ部への支援活動は継続していた。役員では、足立尚陽支部長が退任され、新支部長に平井久雄氏が就任しました。審議の内容は全会一致で承認されました。
講演は、東京国際大学卒業、清水川ゼミ所属の同窓生で、宮城県栗原寺住職として活動をしている高橋俊英氏による演題「お葬儀と十三佛について」の法話でした。
日頃、私たちが知っているようで知らない「葬儀」について詳しく解説がありました。亡くなられてから葬儀までの流れを、枕経、通夜、火葬、戒名、葬儀についての説明がありました。
後半は、「十三佛」についてのしきたりのお話しでした。死んでから七日ごとに七回行う追善供養。49日の七七日忌までが「霊」で、その後は「佛」になっていく。十三佛と十三王との関係も教えてくれました。
先祖の人数、1代前(父母)は2人、2代前(祖父母)は4人、3代前(曾祖父母)は、8人。それが10代前になると1024人となる。自分が生きていることはたくさんの先祖がいたからである。先祖を大切にすることが必要であります。
日頃、知っているようで知らないお話を聞くことで、とても参考になる法話でありました。