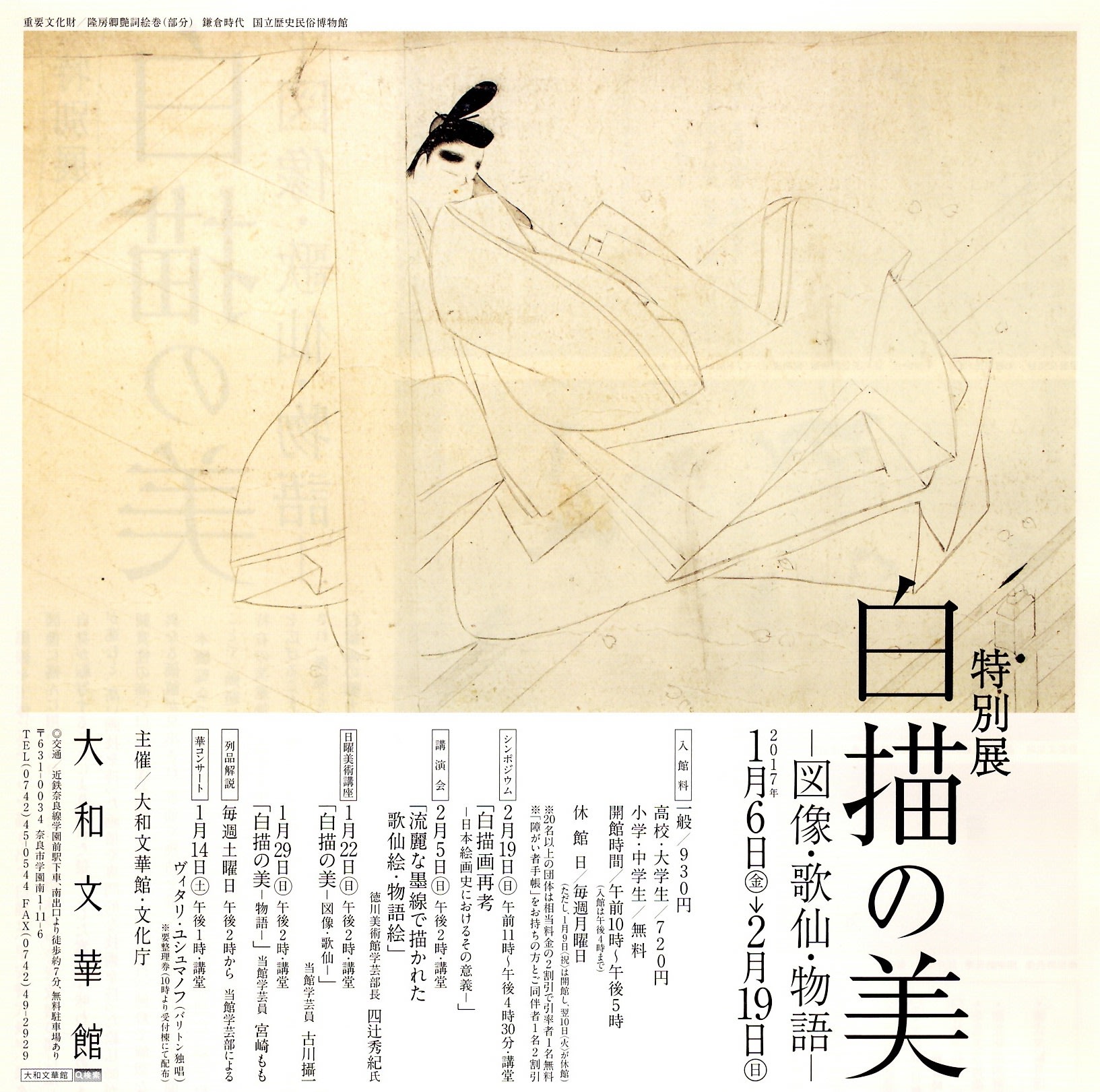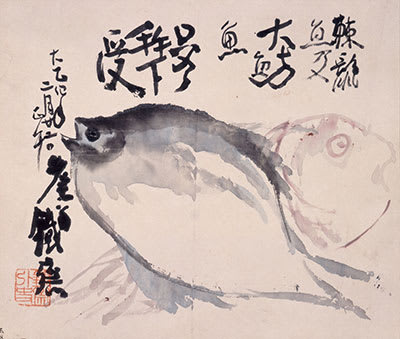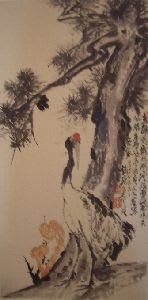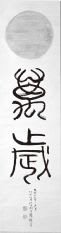今日は奈良は猛暑日の予想でしたが、なんとか34℃止まり、

「宴の器」展の大和文華館から家に戻った時刻でした。アツイ

古来「宴」を通して、神仏と人、人と人の交流が深められ、
この宴に置いて重要な役割を果たすのは器です。
季節、しきたりなど文化により取り合わせも異なり、
今回大和文華館所蔵108作品(重要美術品3含む)から、
食や酒、お茶に関わる様々な器を見てまいりました。
館内の中庭は開けはなられており、青々とした竹の色で
優しい光の中で、入り口の3作品が目に飛び込んできます。
左側は【根来塗、茶入と茶杓】室町時代
何とも言えない黒地が
中央は【蒔絵椿紫陽花文提重】江戸時代
花見などの宴会で手提げの中に四段お重や2つの酒器等が
 蒔絵椿紫陽花文提重
蒔絵椿紫陽花文提重
右側は【朱漆絵蓬莱文瓶子】江戸時代
中国瓶子よりもS字状の体でなまめかしく、
日本独自の美意識を感じます。
さあ4部門に分け展示されております。
Ⅰ.神仏の器・明器
【青磁多嘴壺】龍泉窯1080年、北宋 重要美術品
 青磁多嘴壺
青磁多嘴壺
【粉青双耳盃】堅手、朝鮮王朝
嵌入があり、堅手とは素地や釉や手触りが堅そうなところからで
反対は柔手になります。
【朱漆絵蓬莱文瓶子】既述
Ⅱ.水注・酒器
【二彩碗】奈良時代
唐三彩を模して金継ぎがほどこされています。
【金銅狩猟文脚盃】唐
ワインを入れる盃で青銅に鍍金で、狩猟図
馬に乗り、弓矢や投石で鹿や兎を狩っている
【赤絵市松文角瓶】景徳鎮窯、古染付手 明末期
口や角が釉薬の収縮率の違いで欠けており、官窯は×だが
民窯の作で日本の茶道では虫食いといい、景色を楽しむ
 赤絵市松文角瓶
赤絵市松文角瓶
【黒釉箶芦瓶】朝鮮・高麗 重要美術品
ロクロ成形で、黒釉が赤褐色を呈し、部分的に濃淡のムラが
 黒釉箶芦瓶
黒釉箶芦瓶
朝鮮半島からは三島手が、・・・
【東印度会社帆船図硝子酒盃】オランダ18世紀
 東印度会社帆船図硝子酒盃
東印度会社帆船図硝子酒盃
【黄瀬戸六角盃】【志野四方盃】【織部六角盃】美濃
【色絵更紗文盃】有田(鍋島)
【赤絵龍文盃】青木木米作‣京都⇐写⇐中国‣明【赤絵龍文盃】
【色絵花鳥文盃】ルイス・フィクトル作、デルフト窯、オランダ 1730年頃
まだ磁器が造れず、亜鉛の釉薬で造った白地に絵を
 色絵花鳥文盃
色絵花鳥文盃
Ⅲ.食器
【善教房絵詞摸本】岡田為恭筆1841年 紙本墨画
元はサントリー美術館蔵で、酒を盗み飲んでいる女性も
【文姫帰還図巻】明
匈奴にさらわれた姫が、南宋へ帰還する物語、宴の場面を
根来塗が実用的な作品
【志野柳文鉢】

 志野柳文鉢
志野柳文鉢
【色絵竜田川文向付】尾形乾山作、京都 江戸中期
【赤絵牡丹蓮華唐草文鉢】景徳鎮窯、明 重要美術品
民窯で赤と緑の釉で
 赤絵牡丹蓮華唐草文鉢
赤絵牡丹蓮華唐草文鉢
【青花富士山形平鉢】景徳鎮窯、古染付手 明末期
中国に注文して作られており、足は織部の足様です。
【蒔絵椿紫陽花文提重】既述
Ⅳ.茶器
【白天目茶碗】瀬戸、室町
【黒織部沓茶碗】美濃、桃山

 黒織部沓茶碗
黒織部沓茶碗
【色絵金彩菊草花文茶碗】薩摩 江戸後期
【色絵夕顔文茶碗】尾形乾山作、京都 江戸中期
 色絵夕顔文茶碗
色絵夕顔文茶碗
【赤楽宝珠文茶碗】青木木兎作、赤膚 江戸末期
楽焼になります。
【黒磁金彩碗】定窯 北宋
 黒磁金彩碗
黒磁金彩碗
【青磁五葉花形托】朝鮮・高麗
【青磁象嵌雲鶴文碗】朝鮮・高麗
【伊羅保手茶碗】朝鮮王朝
【青花山水人物碗】「大越国」銘、ベトナム16-17世紀
高い高台のチョコレートボトムで下部に蓮弁文、上部は
樹下を歩く人が柔らかな線で絵付けが
 青花山水人物碗
青花山水人物碗
茶器を観させていただき、中国で一番は青磁、二番は白磁
ところが日本では侘び茶に代表されるよう素朴さが
国民性による文化の違いが垣間見えました。

「宴の器」展の大和文華館から家に戻った時刻でした。アツイ

古来「宴」を通して、神仏と人、人と人の交流が深められ、
この宴に置いて重要な役割を果たすのは器です。
季節、しきたりなど文化により取り合わせも異なり、
今回大和文華館所蔵108作品(重要美術品3含む)から、
食や酒、お茶に関わる様々な器を見てまいりました。
館内の中庭は開けはなられており、青々とした竹の色で
優しい光の中で、入り口の3作品が目に飛び込んできます。
左側は【根来塗、茶入と茶杓】室町時代
何とも言えない黒地が
中央は【蒔絵椿紫陽花文提重】江戸時代
花見などの宴会で手提げの中に四段お重や2つの酒器等が
 蒔絵椿紫陽花文提重
蒔絵椿紫陽花文提重右側は【朱漆絵蓬莱文瓶子】江戸時代
中国瓶子よりもS字状の体でなまめかしく、
日本独自の美意識を感じます。
さあ4部門に分け展示されております。
Ⅰ.神仏の器・明器
【青磁多嘴壺】龍泉窯1080年、北宋 重要美術品
 青磁多嘴壺
青磁多嘴壺【粉青双耳盃】堅手、朝鮮王朝
嵌入があり、堅手とは素地や釉や手触りが堅そうなところからで
反対は柔手になります。
【朱漆絵蓬莱文瓶子】既述
Ⅱ.水注・酒器
【二彩碗】奈良時代
唐三彩を模して金継ぎがほどこされています。
【金銅狩猟文脚盃】唐
ワインを入れる盃で青銅に鍍金で、狩猟図
馬に乗り、弓矢や投石で鹿や兎を狩っている
【赤絵市松文角瓶】景徳鎮窯、古染付手 明末期
口や角が釉薬の収縮率の違いで欠けており、官窯は×だが
民窯の作で日本の茶道では虫食いといい、景色を楽しむ
 赤絵市松文角瓶
赤絵市松文角瓶【黒釉箶芦瓶】朝鮮・高麗 重要美術品
ロクロ成形で、黒釉が赤褐色を呈し、部分的に濃淡のムラが
 黒釉箶芦瓶
黒釉箶芦瓶朝鮮半島からは三島手が、・・・
【東印度会社帆船図硝子酒盃】オランダ18世紀
 東印度会社帆船図硝子酒盃
東印度会社帆船図硝子酒盃【黄瀬戸六角盃】【志野四方盃】【織部六角盃】美濃
【色絵更紗文盃】有田(鍋島)
【赤絵龍文盃】青木木米作‣京都⇐写⇐中国‣明【赤絵龍文盃】
【色絵花鳥文盃】ルイス・フィクトル作、デルフト窯、オランダ 1730年頃
まだ磁器が造れず、亜鉛の釉薬で造った白地に絵を
 色絵花鳥文盃
色絵花鳥文盃Ⅲ.食器
【善教房絵詞摸本】岡田為恭筆1841年 紙本墨画
元はサントリー美術館蔵で、酒を盗み飲んでいる女性も
【文姫帰還図巻】明
匈奴にさらわれた姫が、南宋へ帰還する物語、宴の場面を
根来塗が実用的な作品
【志野柳文鉢】

 志野柳文鉢
志野柳文鉢 【色絵竜田川文向付】尾形乾山作、京都 江戸中期
【赤絵牡丹蓮華唐草文鉢】景徳鎮窯、明 重要美術品
民窯で赤と緑の釉で
 赤絵牡丹蓮華唐草文鉢
赤絵牡丹蓮華唐草文鉢【青花富士山形平鉢】景徳鎮窯、古染付手 明末期
中国に注文して作られており、足は織部の足様です。
【蒔絵椿紫陽花文提重】既述
Ⅳ.茶器
【白天目茶碗】瀬戸、室町
【黒織部沓茶碗】美濃、桃山

 黒織部沓茶碗
黒織部沓茶碗【色絵金彩菊草花文茶碗】薩摩 江戸後期
【色絵夕顔文茶碗】尾形乾山作、京都 江戸中期
 色絵夕顔文茶碗
色絵夕顔文茶碗【赤楽宝珠文茶碗】青木木兎作、赤膚 江戸末期
楽焼になります。
【黒磁金彩碗】定窯 北宋
 黒磁金彩碗
黒磁金彩碗【青磁五葉花形托】朝鮮・高麗
【青磁象嵌雲鶴文碗】朝鮮・高麗
【伊羅保手茶碗】朝鮮王朝
【青花山水人物碗】「大越国」銘、ベトナム16-17世紀
高い高台のチョコレートボトムで下部に蓮弁文、上部は
樹下を歩く人が柔らかな線で絵付けが
 青花山水人物碗
青花山水人物碗茶器を観させていただき、中国で一番は青磁、二番は白磁
ところが日本では侘び茶に代表されるよう素朴さが
国民性による文化の違いが垣間見えました。