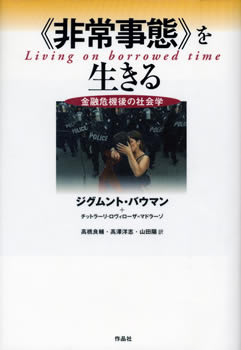
ジグムント・バウマン、チットラーリ・ロヴィローザ=マドラーゾ
(高橋良輔、高澤洋志、山田陽訳)
『《非常事態》を生きる ――金融危機後の社会学』
(作品社、2012年)
本書は、チットラーリ・ロヴィローザ=マドラーゾのインタビューに対して、ジグムント・バウマンが金融危機をめぐる資本主義の問題に答えたという形のタイトルになっているが、実際には金融危機ばかりではなく、バウマンがこれまで扱ってきた様々な社会学的主題についても議論されている。そういう点においては、バウマンの仕事についての良い概観を与えてくれる構成になっている。つまり、バウマンの本をそれほど読んでいない私にとって、本書は良いガイドと解説になっている。
バウマンの有名な社会学的概念に「ソリッド・モダニティ」と「リキッド・モダニティ」がある。ニューディール政策やフォーディズムから福祉国家(バウマン流に言えば社会国家)全盛の時代までのソリッド・モダニティは、流動化・液体化して現代に至った。社会のリキッド化に最も強く作用したのは、多くの論者が指摘するように、ネオ・リベラリズムによる資本主義経済のグローバルな展開である。ソリッド・モダニティの社会では労働者・生産者であった人びとは、リキッド・モダニティ社会では負債を抱えようが破綻しようが「消費者」として生き続けなければならない。
バウマンの著作はリキッド化した社会が持つ様々な問題を俎上にあげる。そのようなバウマンの仕事を、マドラーゾは[はじめに]で次のように評している。
逆説的な意味では、道徳的責任がバウマンの研究の唯一の動機である。彼は倫理的な読者に向けて書く非宗教的人間であり、超自然的な存在をはねつける社会思想家である。それにもかかわらず、その思いやりや道徳的品位、人間性への道徳的献身は、独善にはしる宗教的、世俗的人間の嫉妬を呼び起こしている。誠実に問題と向き合う用意のある信頼できる読者なら、誰でもジグムント・バウマンを読むことから何かを得るだろう。それは、逆説的にもそこに深い思いやりの言葉があるからである。同じように、凝り固まった政治的所属と独善的な見方にとらわれた読者は、歴史という要塞や城壁に苦しみながら向き合うことを覚悟しなければならない。それは確かに、近年の経済分野で起きてきたことを把握したければ、理解すべき課題なのである。 (p. 22-3)
本書は2部構成で、第1部の「液状化していく政治経済構造」では〔資本主義〕、〔福祉国家〕、〔民主主義と主権〕の三つのテーマについてバウマンが答える。「人間なるものの行方」と銘打った第2部では、さらにテーマは社会の広範な諸問題に拡大し、〔ジェノサイド〕、〔人口問題〕、〔原理主義〕、〔科学/技術〕、〔世代・ロスジェネ〕などに議論が及んでいる。主題が広範にわたりすぎているので、ここでは興味深かったいくつかに絞って取り上げてみたい。
これまでバウマンの著作を読んでいて個人的にとても印象深かったことがある。主題やその攻め口が(こういって良ければ)左翼的であると思えるにもかかわらず、共産主義(マルクス主義と言ってよいかどうかは難しいが)に極めて冷淡なのである。ここではどうしたって共産主義を引き合いに出して議論するのではないか、そう思える箇所でもほとんど何も語らずにスルーしてしまうという印象であった。
そのような私の疑問にあたかも直接に答えるような率直な記述がある。
私に言わせれば、共産主義は〈自由の王国への近道〉を強制するプロジェクトです。言葉の響きがどれほど魅力的で勇気づけるものだとしても、すでに実証されている通り、共産主義は実践に移される場合には必ず、奴隸制への近道、つまり自由の墓場への近道になってしまうのです。近道という考え自体、強制と同様、自由とはまったく相容れません。強制というのは自動的かつ自己増強的な事業です。いったん始めると、用心深く、決して緩められることのない不断の努力でもって、人々を従順で寡黙なままに強制し続けなければならなくなります。もし自由の名の下に強制が称賛されるならば(かつてジヤン=ジャック・ルソーが空想し、レーニンが断固として力説し、アルベール・カミュが、彼が生きていた当時着々と根を張りつつある二〇世紀の特性とみなして落胆したように)、本来の目的は台無しになってしまい、結局は強制を続けることだけが目的となってしまうでしょう。 (p. 31)
「すでに実証されている通り」というように、実現された共産主義としてのソ連や東欧の歴史を踏まえている発言だ。ハンナ・アーレントが証明したようにそれは全体主義国家であった。いわば、共産主義革命はまるで運命でもあるかのように全体主義国家へと転落した。ソ連指揮下のポーランド人民軍でナチスドイツと闘い、戦後のポーランドで反ユダヤ主義に苦しめられ、1968年にワルシャワ大学を解雇されたことを契機にポーランドを出国したというバウマンの経歴が刻印した思想なのだろうと、私は勝手に想像している。
バウマンは、「かつて共産主義を〈社会主義の短気な弟〉と呼んだこと」 (p. 30) があったという。そして、その「社会主義」あるいは「社会主義者としての姿勢」についてこう述べている。
私にとって社会主義とは、不平等や不正義、抑圧や差別、人の尊厳の汚辱や否定に対して、強い感受性を持つということです。〈社会主義者としての姿勢〉をとるということは、このような不正がいつどこで起きようと、どのような名目でなされようと、犠牲になっているのが誰であろうと、その全てに反対し抵抗することなのです。 (p. 31)
この「社会主義」は、「共産主義」と比較されるべき国家・社会制度を語る思想なのであろうか。バウマンの「社会主義」の「社会」は、私がずっと理解してきた「社会主義」の社会とはどうも意味合いが違う。国家・社会制度をめぐる思想と言うよりは、「人倫を重んじること」というような精神のありようのことに思える。バウマンは、「福祉国家」を「社会国家」と呼ぶべきだとしばしば記している。この「社会国家」の社会は、確かにバウマンの言う「社会主義」の「社会」、〈社会主義者としての姿勢〉の「社会」なのである。
さて、本書の標題にもなった金融危機(バウマンはそれを〈金融津波〉と呼ぶ)は、2007年夏頃からアメリカ合州国で表面化したサブプライムローンの焦げ付きに端を発した世界金融危機のことで、それは2008年9月15日にリーマンブラザーズ証券が連邦倒産法の適用を申請して倒産したことで決定的となった。
バウマンは、この世界金融危機は決して銀行や証券会社の経営の失敗として現われたわけではない、むしろそれは金融資本を中心とする資本主義の成功の帰結なのだと断言する。その論証のスタートに、バウマンはローザ・ルクセンブルグ(なつかしい!)を引き合いに出す。
彼女〔ローザ・ルクセンブルク〕によれば、資本主義は〈非資本主義〉もしくは〈前資本主義〉経済なしには存続できません。資本主義が己の原理と矛盾せずに発展できるのは、まだ手つかずで、経済進出と搾取の余地がある〈未開拓地〉がある限りにおいてなのです。ところが、その土地を制圧し、啓蒙という名目の下に搾取を行うことによって、前資本主義経済の未開拓地は収奪され、資本主義がさらに発展するために必要な資源はどんどん失われていきます。ありていに言えば、資本主義は本来、寄生的システムだということです。寄生者はみな、手つかずの宿主を見つければ一時はうまく繁栄できるかもしれませんが、それは〈宿主〉を食いものにしているということなので、遅かれ早かれ、自身の繁栄、さらにいえば生存の大前提である宿主を食い尽くしてしまいます。……資本主義は、いま寄生している種がやせ細り、あるいは絶滅しょうものなら、驚くべきほどの巧みさで新種の宿主を探し出します(実際、生み出しもします)。 (p. 32-3)
新しい〈寄生宿主〉となったのは、従来は借金もできないはずだった貧困層だったのである。つまり、「老若男女を問わず、とてつもなく多くの人々を債務者という人種に仕立て上げ」 (p. 37) ることに銀行は成功していたのだ。資本が食いものとしての〈宿主〉を新しく探し出そうとするとき、国家は陰に陽にそれに加担する。
過去に資本主義が変化した時と同様、今回も国家が新しい宿主を作り出し、資本主義の搾取に加担しました。まさにクリントン大統領のイニシアティブを基に、アメリカ政府の後押しで〈サブプライムローン〉が導入され、持ち家を購入するための信用貸付が、返済能力のない人々に提供されました。言い方を変えれば、これまでは信用貸付を媒介とした搾取の対象になり得なかった人々を借金族に引き込んだのです。 (p. 38)
歴史的には中南米諸国、中東諸国を食いもの・宿主としてきた(いる)アメリカ合州国(のネオ・リベ資本主義)は、新しい宿主として自国民に狙いを定めたということだ。資本主義がここまでやらざるを得なくなったという事実は、世界の資源を使い果たしてしまった資本主義そのものが「無意識に自殺しそうなくらい」危険な状態に陥っていたことを意味している。
バウマンは、資本主義の歴史を辿りつつ、つまり、ソリッド・モダニティと福祉国家の時代から振り返りつつ、ローザ・ルクセンブルグの言に基づいて次ぎのように資本主義の宿命を語る。
……資本主義の死は内的な崩壊から生じると考えられるということです。外的な爆発、ましてや外からの突然の攻撃による破壊などではありません(そういった攻擊は、もしあったとしても、とどめの一撃を与えるだけのものでしょう)。おそらく資本主義は、いかなる宿主も利用/存在/想像しつくしてしまった時に、飢えて死に絶えるのでしょう。耕作者や坑夫ならみないやというほど分かっていることですが、収穫逓減の法則によれば、有用で/利用可能で/利益を生む収穫物をほんの少し余分に手に入れようと努力すれば、法外な費用を支払わなければならなくなります。宿主の死滅へと近づいていくことになるのです。そして、さらなる耕作や採掘は愚かなこととなり、収獲ができなくなる前に放棄されるのがオチでしょう。 (p. 51)
資本主義がもつ実践への唯一のガイドラインは「利益の最大化」ですが、これが慢性的な無秩序と不合理な実践の元凶なのです。いまや手に余る証拠によって周知の事実となったのは、自己平衡化システムあるいは市場の〈見えざる(しかし巧妙で抜け目のない)手〉による制御など妄想に過ぎず、資本主義経済はいわば〈生来の傾向〉にのみ従い、はなはだしい不安定を生み出しているということです。この不安定は飼い馴らすことも制御することも、明らかに不可能です。遠慮なく言うならば資本主義は自身がもたらす破局を阻止できないし、その破局が与える損害を回復することもできません。まして予防など論外です。 (p. 52-3)
その例をアメリカ合州国に見るばかりではなく、ヨーロッパにおいて強烈なネオ・リベラリズム経済を推進したマーガレット・サッチャーのイギリスで起きたことにも言及している。
マーガレット・サッチャーは、よく知られているように、薬は苦くなければ効き目がないと主張しましたが言い落としたことは、その苦い薬(つまり、資本を解放する一方で、資本の過剰な振る舞いに対する潜在的な抑制力を一つずつ縛り上げていくこと)を飲むはめになるのは一部の人たちで、しかも他の人たちの不快感を取り除くために、ということです。さらに、彼女の場合は誤った預言者や近視眼的な教師に従って無視してしまったのですが、この手の療法は、遅かれ早かれ、様々な形の苦痛を引き起こして、あらゆる人々に影響を与えることになります。その結果、苦い薬を(ほとんど)皆が飲み込まなければならなくなるのです。この〈遅かれ早かれ〉はいまや〈いま〉になってしまいました。 (p. 57)
〈アンダークラス〉もバウマン社会学の欠かせない概念である。この社会を理解しようとするとき、社会思想や学的立場に応じて、社会構成員を様々な階層・クラスにカテゴライズすることができる。しかし、バウマンのいう「アンダークラス」はそうした階層・クラスから外れた人びとを指す。つまりは、この社会から不要と見なされた人びと、社会の構成員としては数え上げられず、常に排除の力が作用している人びとである。
例えば、金融危機の直接の原因となった〈サブプライムローン〉を焦げ付かせたアメリカ合州国の人びとは、金融資本が寄生する〈宿主〉なのであって、いかに貧しくても資本主義の搾取の対象として社会の階層・クラスに含まれている。したがって、彼らをアンダークラスとは呼びがたいのである。
〈貧困という問題〉は、かつては社会的な問題と考えられていたのですが、いまでは大幅に定義が修正され、法や秩序の問題と捉えられるようになりました。明らかに貧困を〈犯罪化する〉傾向があります。その証拠に、例えば〈アンダークラス〉という言葉が、〈下層〉階級あるいは〈労働者〉階級、〈極貧〉層といった言葉の代わりに用いられています(〈アンダークラス〉には、他の言葉にはない含意があります。それは、〈カテゴリーに値しない〉カテゴリー、つまり、他の階級の外部ではなく、階級システム自体――つまり社会――の外部に位置づけられわるカテゴリーを示しているのです)。国家が貧困に関心を払う時、その最も重要かつ明確な目的とは、もはや貧しい人々の健康維持ではなく、彼らを取り締まり、統制、監督、監視、訓練を施して、悪影響や厄介事を引き起こさないようにすることなのです。 (p. 65-6)
だから〈アンダークラス〉は、社会的事象の批判的切り口によっては、〈ディアスポラ〉であったり、〈サバルタン〉であったり、〈ナショナル・マイノリティ〉であったり、〈剥き出しの生〉であったり、〈移民〉であったりする。
〈アンダークラス〉は、モダニティが生み出した歴史的産物だとバウマンは主張する。
われわれの近代世界は、その最初から、強制的で執拗な近代化への衝動によって、大量に〈人間廃棄物〉を生み出す二つの大衆産業を発達させてきました……。その産業の一つは、秩序を構築する産業です(これは、拒否される人間、〈不適合者〉、適切で秩序立った――〈正常な〉――社会の領域から排除される人間を、大量に生み出さずにはおきません)。もう一つの産業は、〈経済発展〉と呼ばれているものです。これは、取り残される人間を大量に生み出します。取り残される人間というのは、〈経済〉において居場所を持てない人間、有効な役割を果たすことのない人間、生計を立てる機会のない人間のことです。彼らは、少なくとも合法的な手段では、つまり、推奨されている手段や、許容され得る手段では、取り残されてしまうのです。〈社会国家〉、〈福祉国家〉は、こうした二つの産業を段階的に撤廃しょうとする野心的な試みでした。それは、社会的排除の諸実践を段階的に撤廃し、最終的には除去することで、すべての人を包摂するという野心的な(おそらく野心的に過ぎた)プロジェクトだったのです。社会国家は、確かに欠点無しというわけにはいきませんが、多くの点で成功しました。しかしいま社会国家は自らを撒廃しようとしています――その一方で、人間廃棄物を生み出す二つの産業は、その機能を取り戻し、最高潮に達しています。第一の産業は〈よそ者〉(証明書を持たない人々、非合法な移民、庇護をもとめる人々、その他すべての〈好ましくない者〉)を生み出し、第二の産業は、〈傷ものの消費者〉を生み出しています。そしてこの両方が一緒になって〈アンダークラス〉を大量に生み出しているのです。この〈アンダークラス〉は、階級構造の底辺に位置する〈下層階級〉ではなく、〈正常な社会〉の階級システムの外部に投げ出された人々のことなのです。 (p. 115-6)
そして、ネオ・リベラリズムで武装した資本主義は、〈社会国家〉、〈福祉国家〉を崩壊させつつ、社会をリキッド化してしまった。現代ヨーロッパ社会で目立つのは〈アンダークラス〉としての移民である。
〈グローバルな諸力〉は、謎めいていて、見通すことができず、予測不可能なものであり、新たな方法で不確定性と不安定性を駆動させ続けていますが、移民は、そこで増殖され掻き立てられる不安と恐怖のあらゆる原因を、代表させられるのです。移民は、分かりやすく目に見えるかたちで、生活が破壊される恐怖や亡命を強制される恐怖、あるいは社会的転落や完全な排除への恐怖、また法と権利の世界の外部の〈どこでもない場所〉へと追いやられる恐怖を、身近なところで具現し表現しているというわけです。あるいはまた、移民は、液状化した近代社会で人々を苦しめる、半意識的な、あるいは意識下の、または無意識の実存的恐怖すべてを具体化しているというわけです。こうして(代理として)移民を追い散らすことで、謎めいたあらゆるグローバルな諸力に対抗するのです。しかし、このグローバルな諸力は、移民が経験している苦難の運命を、だれにでも差し向ける脅威です。ですからこうした移民を巡る幻想には、政治家や市場が巧妙に利用できる(そして、されている)多くの資本が存在しているのです。 (p. 118)
ここで注意すべきは、移民は決して資本の搾取の対象ではないことである。資本が利用しているのは、あくまで「移民を巡る幻想」なのであって移民ではないのだ。〈アンダークラス〉は、搾取-被搾取という社会関係からも排除されているのである。
〔福祉国家〕や〔民主主義と主権〕というテーマで「国家」を語るとき、バウマンは常に〈社会国家(福祉国家)〉を念頭に置いている。つまり、かつての〈社会国家〉は〈アンダークラス〉を生み出す産業を克服しようとした野心的な試みだった (p. 116) のだし、社会主義者として「不平等や不正義、抑圧や差別、人の尊厳の汚辱や否定に対して、強い感受性を持つ」 (p. 31) ということは、とりもなおさず新しい〈社会国家〉をイメージ、構想することに他ならないだろう。
「不平等や不正義、抑圧や差別、人の尊厳の汚辱や否定」に厳しい眼差しを向けるバウマンは、本書でもルター派の牧師でナチの迫害の犠牲者となったマルティン・ニーメーラーの詩を引用している [1] 。
最初、ナチが共産主義者を捕えていたとき、ニーメーラーは静かに考え――そうして、私は共産主義者ではない、だから黙っていよう、と思いました。しかしナチは次に、労働組合員を探し回りました。しかし、ニーメーラーは、労働組合員ではないということで、やはり黙っていました。さらに、ナチはユダヤ人を探し回りました。しかし、ニーメーラーはユダヤ人ではありませんでした。……さらにはカトリック信者が探されましたが、しかし、ニーメーラーはカトリック信者ではありませんでした。……次には、ナチはニーメーラーを探しに来ました。……しかし、その時には誰かの肩をもってくれる人などいなくなっていました。 (p. 121)
国家公務員を退職して年金暮らしの私は、貧しいとはいえ〈アンダークラス〉ではない。しかし、「政治家や市場が巧妙に利用」する「〈アンダークラス〉を巡る幻想」に私たちが取り込まれてしまえば、つまり自覚的であれ無自覚であれ〈アンダークラス〉の排除に加担してしまえば、私たちの運命はニーメーラーの運命そのものとなる。社会主義者であろうがなかろうが、「不平等や不正義、抑圧や差別、人の尊厳の汚辱や否定」に向けて感受性を際立たせておくことが必須だ、そう思う。
第2部で印象に残った話題は、「ジェノサイド」と「ホロコースト」の概念の違いである。インタビュアーのマドラーゾは、ホロコーストはジェノサイドの一つと考えるのに対して、バウマンは、その二つは異なるものだと主張する。
私は、あらゆる類似性は偶然的なもので、どんな比較も人を惑わし、表面的なものになると思っています……。ジェノサイドに匹敵するいくつもの大量殺人は、ナチ・ドイツの敗北やロシア共産主義の内部崩壊によって消え去ったわけではありません。この点ではあなたは正しいのでしょう。けれども、なんらかの不適切な人々に所属しているとか、都合の悪い場所や時代に生きているというだけの罪で数十万、数百万の人々を殺戮すること自体は、二〇世紀のいかなる全体主義の発明でもありませんでした。おそらくそうした殺戮は、あの世紀やその当時の全体主義と一緒くたにするわけにはいかないものです。むしろジェノサイドに匹敵する大量殺人は、いままで人間の歴史に付き物でした。しかしそれらは、別の役割を果たしていましたし、別の目的に役立てられ、異なった要因から引き起こされていたのです。
近代の全体主義体制を、人間に対する残虐行為のむごたらしい現れから隔てているものは、全体構想によって説明できます。殺戮は、一〇〇〇年ないし永遠に続く秩序をつくりあげる行為として行われました。社会の現実を全体構想の優雅さに合わせようと強制した結果が、殺戮だったのです。どうやってそんなに美しい像を彫ったのかという問いに、ミケランジェロは、簡単です、私はただ大理石の塊を手に入れて、いらない部分をすべて削っただけです、と答えたそうです。あの殺戮は、いくぶんこのやりとりを逆さまにしたようなものだと言えます。 (p. 174)
ホロコーストの殺戮は、歴史的に何度もあった大量殺人とは違うという。それは全体主義が国家を樹立しようとする全体構想の中で遂行された殺戮であると述べている。例えば、1994年にルワンダで起きたフツ族による少数民族ツチ族の大量虐殺にはいかなる社会構想も国家構想もない。つまり、歴史の中にしばしば現われたジェノサイドである。ホロコーストは、ソリッド・モダニティ社会の最も先端的な悪しき結末なのだ。
〔原理主義〕を巡る話題も興味深い。バウマンは、世俗的であれ宗教的であれ、原理主義の発生を心理学的にも解説してみせるが、人びとが憂えるような宗教原理主義の政治化よりも、政治原理主義の宗教化を憂えるのである。その一節を最後に挙げておく。
現在、〈宗教の政治化〉に関しては多くの議論がなされています。ところが、同時並行で起きている傾向、〈政治の宗教化〉には、ほぼ間違いなく、いっそう深刻な危険をはらみ、いっそう血なまぐさい結末をもたらす可能性が高いにもかかわらず、あまりに小さな関心しか払われていません。というのも、この傾向が進めば、交渉と妥協に委ねられるべき(政治にとつては日々の糧である)利益の衝突が善悪の最終対決に改変され、交渉による合意の余地が皆無となってしまうからです。敵対者の一方しかこの対決を生き残れません(まさに一神教の発端です)。この二つの傾向は、決して分離できないシャムの双生児〔密接な関係にある一対のもの〕だと言えるでしょう。そして、両者は内面に共有している悪魔を双子の片割れに投影してしまいがちなのです……。 (p. 225-6)
[1] ジグムント・バウマン(伊藤茂訳)『コラレテラル・ダメージ ――グローバル時代の巻き添え被害』(青土社、2011年) p. 37-8。










