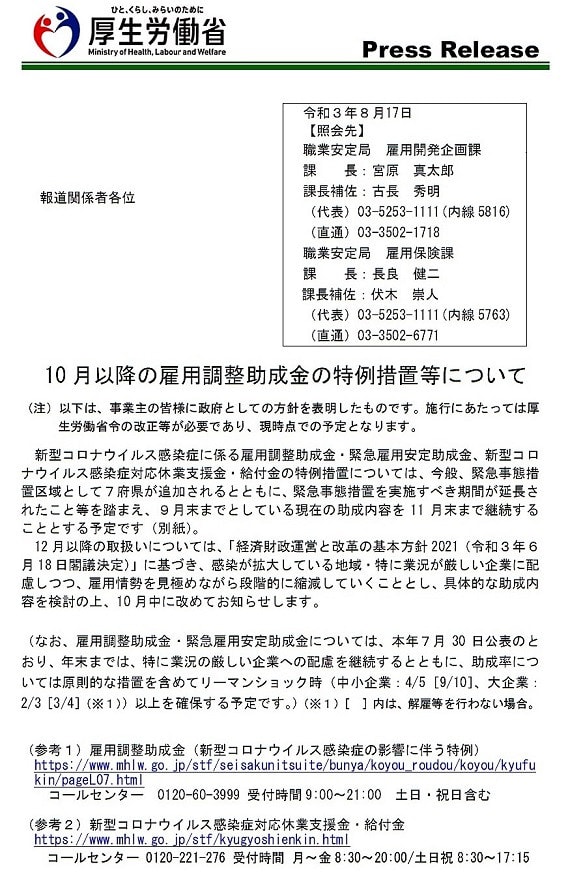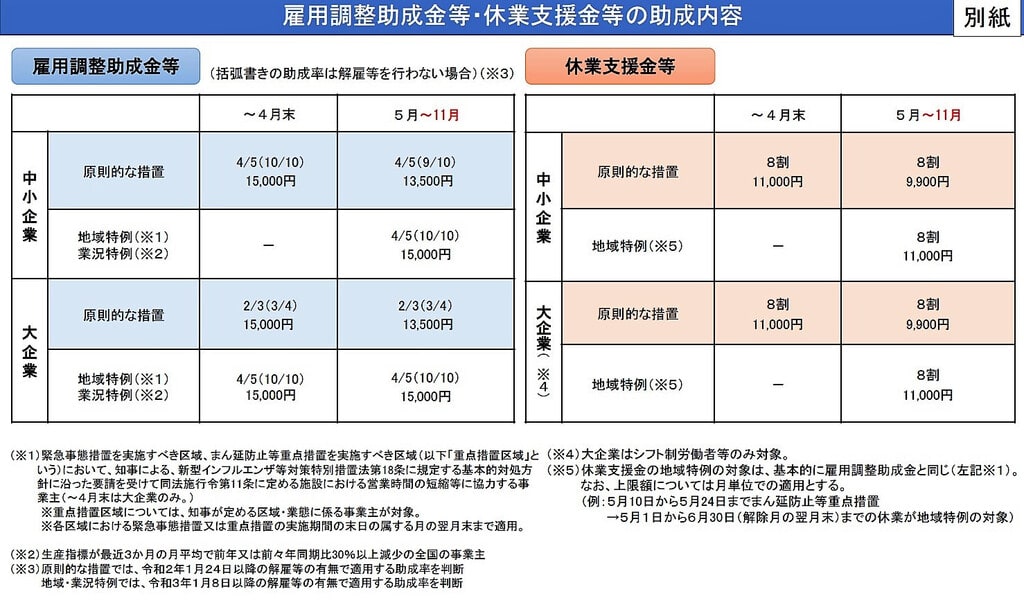改正育児休業法のうち2022(令和4)年10月1日施行された「男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」にともない、雇用保険法も改正され「出生時育児休業給付金」(第61条の8)が新設された。
(1) 支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間 を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
出生時育児休業給付金の対象は、以下のア及びイいずれにも該当する休業です。
ア 被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めた休業。
イ 「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に4週間(28日)までの範囲で取得されたもの。
・産後休業(出生日の翌日から8週間)は出生時育児休業給付金の対象外です。
・出生時育児休業給付金の対象となるには、出生時育児休業の初日から末日まで被保険者である必要があります。
・男性が出生時育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い日から出生時育児休業給付金の対象となります。⇒ 例1、2参照
・ 被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間) 以下であること。
「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。
休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
(期間を定めて雇用される方の場合)
④子の出生日※1から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間※2が満了することが明らかでないこと。
※1 出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日
※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの
休業中の就業可能日数/時間数の取扱い
出生時育児休業給付金の支給対象期間中、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで就業することが可能です。
休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。⇒ 例5・6参照
例:14日間の休業 ⇒ 最大5日(5日を超える場合は40時間)
10日間の休業 ⇒ 最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)
[10日×10/28≒3.57(端数切り上げ)⇒4日、80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし)]
出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。
また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。
(2) 支給申請期間
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。
• 出生時育児休業は、同一の子について2回に分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行います。
(3) 支給額
支給額 = 休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
休業開始時賃金日額の上限額
休業開始時賃金日額の上限額は15,190円となります(令和5年7月31日までの額)。
出生時育児休業給付金の支給上限額(休業28日):15,190円×28日×67%=284,964円
例:休業開始時の賃金日額は7,000円で、14日間の出生時育児休業を取得
この期間に賃金が支払われていない場合
支給額=7,000円×14日×67%=65,660円 =78,400円
この期間に3日就労して賃金21,000円が支払われた場合(支払われた賃金が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%~80%)。
支給額=78,400円-21,000円=57,400円
出生時育児休業期間を対象とした賃金の取扱い
「出生時育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」とは、出生時育児休業期間を含む 賃金月分として支払われた賃金のうち、次の額をいいます。
〇出生時育児休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額。
就労した場合の賃金のほか、出生時育児休業期間に応じて支払われる手当等を含みます。なお、通勤手当、家族手当、資格等に応じた手当等が、就労等した日数・時間にかかわらず一定額が支払われている場合は含みません。
〇就業規則等で月給制となっており、出生時育児休業期間を対象とした日数・時間が特定できない 場合は、日割計算(※)をして得られた額(小数点以下切り捨て)。
(※)「支払われた賃金額」×(「出生時育児休業取得日数」÷「出生時育児休業期間を含む賃金月の 賃金支払対象期間の日数(賃金支払基礎日数)」)

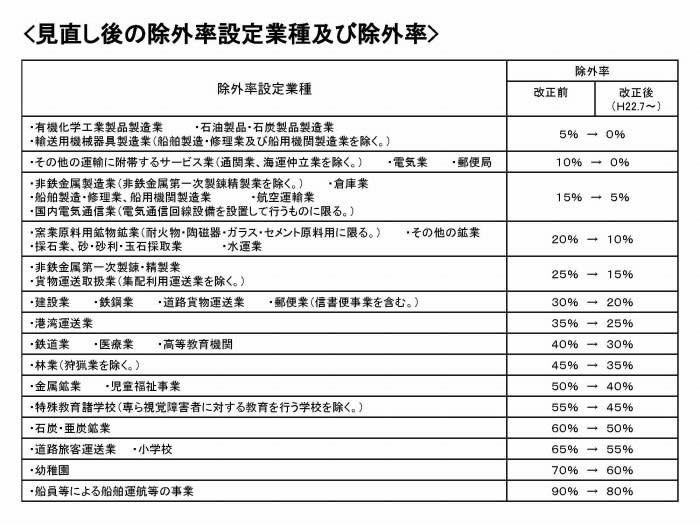














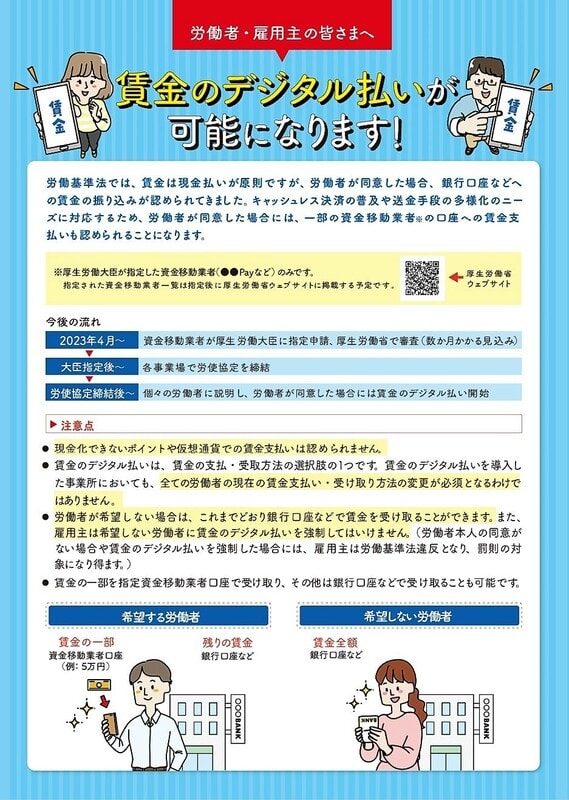
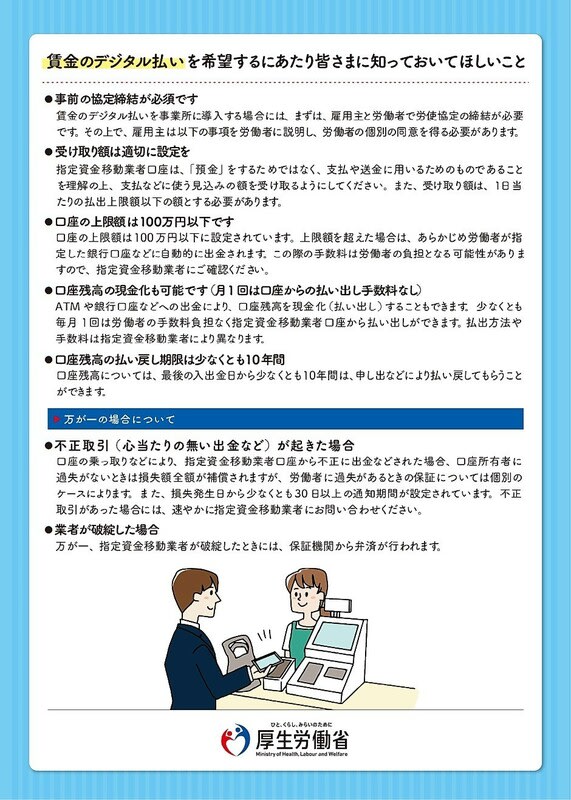
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3106f6c8.c9b3c94f.3106f6c9.2682cddd/?me_id=1332796&item_id=10000216&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkobucha-fuji%2Fcabinet%2F07528161%2Foutigohan20230304-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

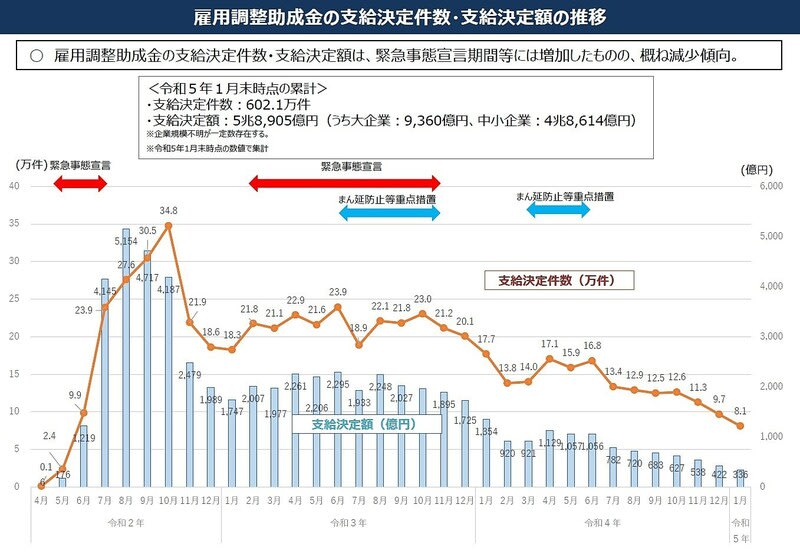





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bfa755.bb912127.18bfa756.dcb862a9/?me_id=1224379&item_id=10035875&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F2023_newitem%2F09726093%2F0203-0209-main-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
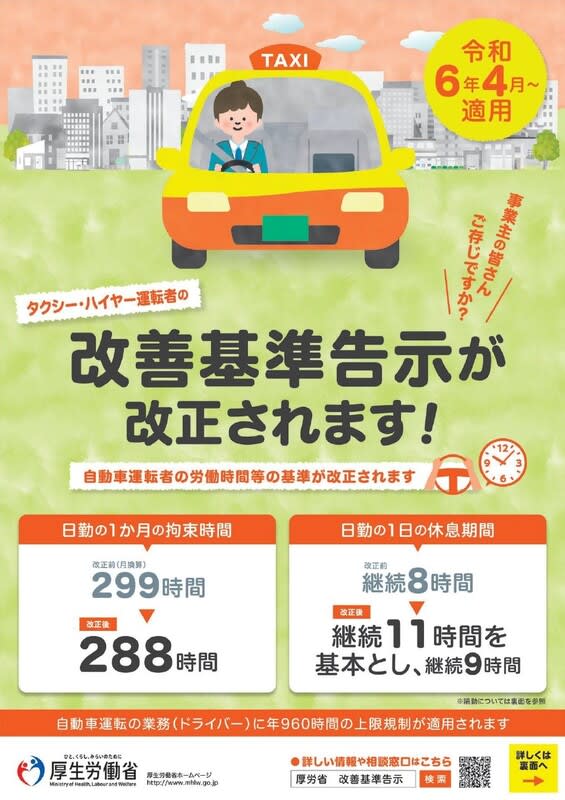



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23ecb40c.5e9cbb74.23ecb40d.9524f6c5/?me_id=1331692&item_id=10001570&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flindt-chocolate%2Fcabinet%2F9800606_02n.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d3cc8fb.1524f4c1.2d3cc8fc.f113179f/?me_id=1306287&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcraseed%2Fcabinet%2Frn%2Fdaki_thum1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)










![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1686efc9.82221094.1686efca.82938442/?me_id=1341714&item_id=10003211&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsaisondepapillon%2Fcabinet%2F14%2F10%2Fsdpxyf7042_1_1_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


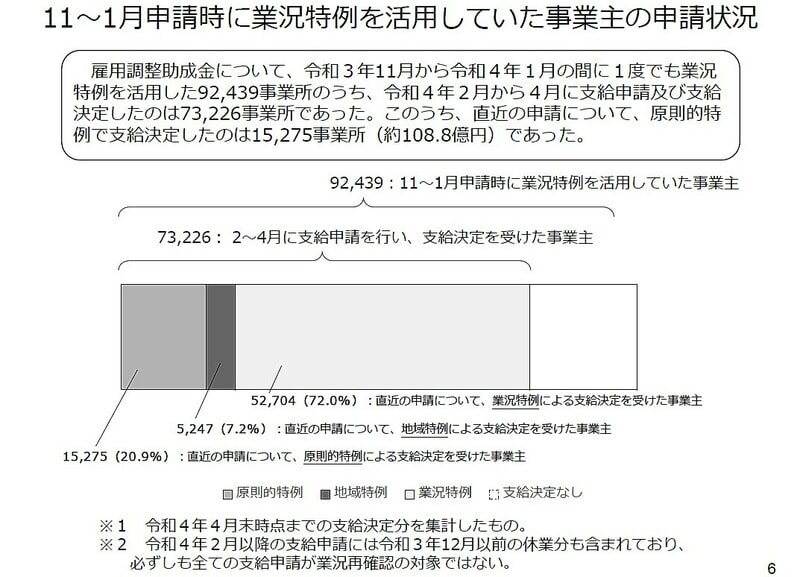



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23d6b196.53d31714.23d6b197.0040640b/?me_id=1367671&item_id=10000010&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgallershop%2Fcabinet%2Fvalentine%2F2022%2Fimgrc0078698502.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eff0ef9.3925a17e.1eff0efa.ff0355a7/?me_id=1269065&item_id=10000367&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkouragumi%2Fcabinet%2F07495043%2F07842125%2Fsyouhin12005970.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a042da.e1b690a8.20a042dc.580531d0/?me_id=1212232&item_id=10028976&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnetbaby%2Fcabinet%2F364%2F404364.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1928b83b.768fe50f.1928b83c.14957ad3/?me_id=1245129&item_id=10009756&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhaptic%2Fcabinet%2Fomnes%2F2021_2%2F7121-4053-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)