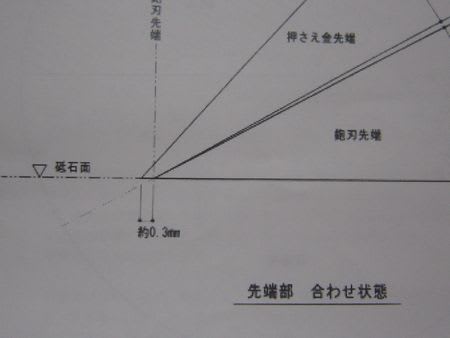知り合いの大工さんでロケットストーブにはまっている方がおられるので、
見学させていただいた。
ロケットストーブについては色々なサイトで紹介されているので、詳しくは
そちらを見て欲しい。
今回見せていただいたのは、ご自分で考案された試作品。外側は版築=土と石灰
を混ぜ合わせた物を突き固めていったもの。


温められた空気は通常、外壁と内側の断熱層の隙間に流していくのだが、この場合
後ろ側一箇所に集め下へ落とし込んでいる。




焚口の径を小さくされたことで、長い薪が入れにくい事や熱効率が思ったよりも
悪い等御本人は改善点を挙げられていたが、出てきた煙もほとんど水蒸気の湯気で
きちんと完全燃焼させておられた。見た目も変わっていてなかなか格好良い。
次にドラム缶で作ったタイプも試し焚きしていただいた。



着火後数分で外側のドラム缶がほんのり暖かくなり始める。


煙突を繋いでいなくても、排気口から出る煙はあんまり煙くない。
ロケットストーブの名前の由来になっている焚口の吸気音は全くと言っていい程
しなかった。
少ない燃料で暖も取れて天板を工夫すれば、湯をわかすくらいの調理が出来るので
ここ最近とても注目されている。
簡単な構造なので、素人でも作れてしまうというのも魅力の一つだ。
廃品利用を上手くすれば、大変安上がりに製作できる点もありがたい。
ここ信州では年間の半分はストーブが必要なので、もう少しきちんと勉強して
是非取り入れていこうと思う。
※御自分で作ろうと思われた方、ロケットストーブについての
基本が書かれた本がありますので、基本的なことを理解なさってからにして下さい。
自己流は火災の原因になりますので注意してください。