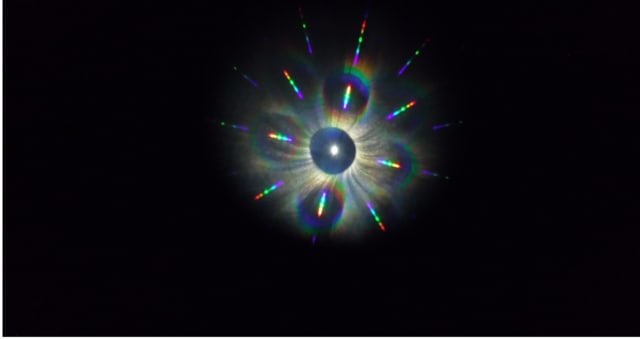「モグラ除け振動マシン」と、なるものを作りました。
ペットボトルを用いて羽根を切り出し風が吹くと羽根が回る仕組みです。
羽根が回るときに振動が起きます。
その振動が竹を通じて地面に伝わるものです。
それでは、材料からです。
1.ペットボトル(サントリーの特茶 伊右エ門 500mL が使いやすいです。) 1本
2.アルミ線(直径2mm、L≒40cm) 1本
3.細い竹(長さは適宜)今回は、1.2mの竹を用意しました。
3.アクリル絵の具・筆
道具は、
1.カッターナイフ
2.電気ドリル
3.ラジオペンチ
作り方は
1.ペットボトルの蓋と底にアルミ線を通す穴をあけます。
2.羽根を切ります。
・サントリーの特茶 伊右衛門 500mL は、胴体が羽にするのに丁度良いへっこみがありカッターナイフで切りやすいためです。
・カッターナイフで一度に切ろうとすると切り過ぎたり、ケガをし易いです。
・三回ぐらいできるようにすると綺麗に切りやすいです。
・羽根は、角度をつけるためカッターを入れる場所を差をつけて切ります。
3.羽根を切りしっかり折り目をつけます。
4.羽根の裏面にアクリル絵の具で色を付けます。(表面に塗ってしまうと色が取れやすい)
5.アルミ線を加工します。
・ラジオペンチで、アルミ線の先端を丸くしストッパーにします。
・ペットボトルの底から蓋に向けてアルミ線を通します。
・蓋から2cmほど離したところでほぼ直角に折ります。
最終的にペットボトルの底を水平より少し上にあげます。
・アルミ線の先端5cmほど折り返します。
6.折り返したらしの竹を差し込んで完成。
・切れたら羽根を曲げます。

エアコンの吹き出しを利用して、試運転開始。

上手く回りました。
こんな変わり物もいましたよ。

羽根が二重になっています。
よく考えています。
風を当ててみると、

羽根がダブルになるので良く回っています。





























 まずは、逆U字型にします。
まずは、逆U字型にします。 逆U字型にしたら、アルミパイプを斜めにセット。
逆U字型にしたら、アルミパイプを斜めにセット。