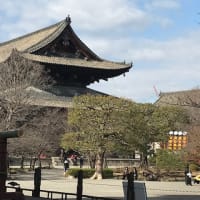みなづき、陰暦の名称で、6月の異名とする。
別名、旧名などと、異名の意味がわからないとして、このようなとらえ方で用いられてくるようになる。
異名を、月名の由来として解説するのは、新暦、旧暦と暦にかかわるので、困難なこともある。
水無月について、水の月とするのがわかりよいとされるようになってきた。
それはまた一方で、かんなづき、ともいう、有力な説というふうにして、神無月にも、連体助詞とする。
の、が、つ、助詞の原初的な性格という論文を想起する。
なし、として、な 単独で用いるのは、ない となる、現代語の打消し助動詞に見られる現象、いかなそうだ、という場合があって、形容詞の、なし そのものが縮約されるのはどうだろうか、つまり、みずなしづき が、みなづき と、短絡するのは、みずのつき が、みずなづき としてあったのだと、考えるより、成り立ちにくい。
水な月 というのも、水無月 というのも、水の月なのか、水無し月なのか、語構成からでは、説明が通るようである。
なによりも、無、無し、この語の意味するところ、水が梅雨だとするならば、そこで季節にあわせた民衆の知恵が働いたことになるのだろう。
6月 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/6月
>
水無月の由来には諸説ある。 文字通り、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されることが多いが、逆に田植が終わって田んぼに水を張る必要のある月「水張月(みづはりづき)」「水月(みなづき)」であるとする説も有力である。 他に、田植という大仕事を仕終えた月「皆仕尽(みなしつき)」であるとする説、水無月の「無」は「の」という意味の連体助詞「な」であり「水の月」であるとする説などがある。
無月(みなづき) - 語源由来辞典
gogen-allguide.com › 「み」から始まる言葉
水無月(みなづき)の意味・語源・由来を解説。 ... 水無月の「無」は、神無月の「な」と同じく「の」にあたる連体助詞「な」で、「水の月」という意味である。 陰暦六月は田に水を引く月であることから、水無月と言われるようになった。
> 社会・文化 >>6月の陰暦名称・別名・異名・旧名の一覧
http://ichiranya.com/society_culture/021-june_name.php
水無月 みなづき
田んぼに水を引き始める月であることから、水無月と呼ばれています。
水張月 みづはりづき
田んぼに水を張る月であることから、水張月と呼ばれています。
水月 みなづき・すいげつ
皆仕月 みなしつき
田植え等の農作業がも終わり、みな、しつくしたというという意味から、皆仕尽と呼ばれています。
弥涼暮月 いすずくれづき
松風月 まつかぜづき
風待月 かぜまちづき
季夏 きか
涼暮月 すずくれづき
涸月 こげつ
蝉羽月 せみのはつき
暑月 しょげつ
田無月 たなしづき
晩夏 ばんか
常夏月 とこなつづき
林鐘 りんしょう
鳴神月 なるかみつき・なるかみづき
炎陽 えんよう
建未月 けんびづき
「建」の文字は北斗七星の柄を意味し、その柄が旧暦で未の方位を向く為「建未月」と呼ばれています。
旦月 たんげつ
鳴雷月 なるかみづき
晩月 ばんげつ
伏月 ふくげつ
陽氷 ようひょう
別名、旧名などと、異名の意味がわからないとして、このようなとらえ方で用いられてくるようになる。
異名を、月名の由来として解説するのは、新暦、旧暦と暦にかかわるので、困難なこともある。
水無月について、水の月とするのがわかりよいとされるようになってきた。
それはまた一方で、かんなづき、ともいう、有力な説というふうにして、神無月にも、連体助詞とする。
の、が、つ、助詞の原初的な性格という論文を想起する。
なし、として、な 単独で用いるのは、ない となる、現代語の打消し助動詞に見られる現象、いかなそうだ、という場合があって、形容詞の、なし そのものが縮約されるのはどうだろうか、つまり、みずなしづき が、みなづき と、短絡するのは、みずのつき が、みずなづき としてあったのだと、考えるより、成り立ちにくい。
水な月 というのも、水無月 というのも、水の月なのか、水無し月なのか、語構成からでは、説明が通るようである。
なによりも、無、無し、この語の意味するところ、水が梅雨だとするならば、そこで季節にあわせた民衆の知恵が働いたことになるのだろう。
6月 - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/6月
>
水無月の由来には諸説ある。 文字通り、梅雨が明けて水が涸れてなくなる月であると解釈されることが多いが、逆に田植が終わって田んぼに水を張る必要のある月「水張月(みづはりづき)」「水月(みなづき)」であるとする説も有力である。 他に、田植という大仕事を仕終えた月「皆仕尽(みなしつき)」であるとする説、水無月の「無」は「の」という意味の連体助詞「な」であり「水の月」であるとする説などがある。
無月(みなづき) - 語源由来辞典
gogen-allguide.com › 「み」から始まる言葉
水無月(みなづき)の意味・語源・由来を解説。 ... 水無月の「無」は、神無月の「な」と同じく「の」にあたる連体助詞「な」で、「水の月」という意味である。 陰暦六月は田に水を引く月であることから、水無月と言われるようになった。
> 社会・文化 >>6月の陰暦名称・別名・異名・旧名の一覧
http://ichiranya.com/society_culture/021-june_name.php
水無月 みなづき
田んぼに水を引き始める月であることから、水無月と呼ばれています。
水張月 みづはりづき
田んぼに水を張る月であることから、水張月と呼ばれています。
水月 みなづき・すいげつ
皆仕月 みなしつき
田植え等の農作業がも終わり、みな、しつくしたというという意味から、皆仕尽と呼ばれています。
弥涼暮月 いすずくれづき
松風月 まつかぜづき
風待月 かぜまちづき
季夏 きか
涼暮月 すずくれづき
涸月 こげつ
蝉羽月 せみのはつき
暑月 しょげつ
田無月 たなしづき
晩夏 ばんか
常夏月 とこなつづき
林鐘 りんしょう
鳴神月 なるかみつき・なるかみづき
炎陽 えんよう
建未月 けんびづき
「建」の文字は北斗七星の柄を意味し、その柄が旧暦で未の方位を向く為「建未月」と呼ばれています。
旦月 たんげつ
鳴雷月 なるかみづき
晩月 ばんげつ
伏月 ふくげつ
陽氷 ようひょう