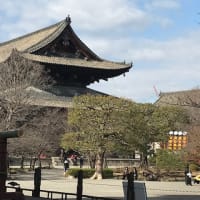現代日本語文法文章論 題材は、タイトルが、製鉄の謎掘れど尽きず とある。副題に、古代から近世まで、全国の遺跡を200カ所以上調査 とある。エッセイである。日本経済新聞の文化面、20141027付けである。執筆者は、 穴澤義功 氏である。なお、有料会員サイトであり、著作の全文をこのように言語分析に資料としているので、そのことをお断りするとともに、ここにお礼を申したい。
冒頭の文は、次である。
> 全国には鉄に関連する多くの遺跡がある。
末尾の文は、次である。
>日本古来の製鉄法たたらには、未解決の謎が数多く残っている。
書き出しの文段は、次のようである。
> 全国には鉄に関連する多くの遺跡がある。鉄塊、製鉄の際にできるスラグ(鉄滓(てっさい))、原料の鉄鉱石や砂鉄、木炭、炉の壁材など、鉄関連遺物の量は膨大だ。主な遺跡の年代は4、5世紀ごろから近世までで、1県で数百を数える例もある。私は鉄関連遺跡の調査・研究一筋に40年以上携わり、200以上の主要遺跡にかかわってきた。
末尾の文段は、次のようである。
> たたらというと、関心のある人のなかには山陰の出雲を中心とする箱形炉を想起する向きが多いだろう。が、長年鉄関連遺跡を調査してきて思うのは、踏みフイゴとセットで朝鮮半島から導入され生産性が高かった竪形炉の技術の方が、自給用としてはむしろ一般的だったのではないかということだ。日本古来の製鉄法たたらには、未解決の謎が数多く残っている。
段落は、見出しのもと、次のようである。
> 日本独自の発展過程
日本列島の鉄づくりは、中国に1000年以上、朝鮮半島に500年ほど後れて定着したと推定され、弥生時代からの鍛冶技術の長い伝統のもとに独自の発展過程を経た。鉄製錬の始まりは6世紀前半ごろと考えられ、当初は鉄鉱石を原料にしていた。しかし、日本列島では火山地帯特有の鉄原料である砂鉄が産出する。鉄鉱石を原料とした製鉄はほどなくして、砂鉄を原料とする製鉄に代わった。
> 実験考古学の手法試す
とはいえ、考古学では鉄関連遺跡を専門にする先生はいない。理系の先生に教えを請う一方、千葉県立房総風土記の丘(当時)や国立歴史民俗博物館の鉄に関する共同研究で様々な実験考古学の手法を試みた。その研究が、考古学や製鉄など異分野の研究者が一緒に議論し合う場となった日本鉄鋼協会の「鉄の技術と歴史」研究フォーラムにつながっている。
> 解析をマニュアル化
発掘関係者が判断に迷わないようにするため、解析のマニュアル化も図った。様々な指標から遺物を5段階評価するもので、遺物をどのように保存するかも決めてある。
春秋
2014/10/27付
日本経済新聞
必要なら守られねばならない。不要なら廃止されなければならない。規範とはそういうものだ。そんな当たり前が通じない日々は、かなり慣らされてきたとはいえ、居心地が悪い。鉄道などの優先席付近では携帯電話の電源を切る――破られている規範の代表格だろう。
心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響する恐れがある。これが規範の大義である。一方には「携帯が原因で機器に重大な事故が起きたとの報告は世界にない」(総務省)という事実がある。もちろん、携帯のせいと気づかぬまま体や機器の変調をやり過ごしているのかもしれない。少なくとも、不安を感じる人はいる。
先に、東京工業大の1年生が「技術者倫理」の授業でこの問題を取り上げたそうだ。学生からいろんな意見が出た。「嫌がる人がいるなら電源は切るべきだ」「車内放送を流し続ける意味はほとんどないと思う」。正解はない。世の中をよくする使命を持つ技術者は難題とどう向き合えばいいか、考えさせる狙いだという。
医療機器と携帯の間が3センチ以内だと影響が出ることがある、15センチ以内なら電源を切るのが望ましい。これが総務省の見解である。わずかな距離でもゼロでない限り規範はなくせない。安全なものをつくる使命は技術者に果たしてもらおう。それまでの間、携帯やスマホをいじくりたければ……優先席には近づかないことだ。
冒頭の文は、次である。
> 全国には鉄に関連する多くの遺跡がある。
末尾の文は、次である。
>日本古来の製鉄法たたらには、未解決の謎が数多く残っている。
書き出しの文段は、次のようである。
> 全国には鉄に関連する多くの遺跡がある。鉄塊、製鉄の際にできるスラグ(鉄滓(てっさい))、原料の鉄鉱石や砂鉄、木炭、炉の壁材など、鉄関連遺物の量は膨大だ。主な遺跡の年代は4、5世紀ごろから近世までで、1県で数百を数える例もある。私は鉄関連遺跡の調査・研究一筋に40年以上携わり、200以上の主要遺跡にかかわってきた。
末尾の文段は、次のようである。
> たたらというと、関心のある人のなかには山陰の出雲を中心とする箱形炉を想起する向きが多いだろう。が、長年鉄関連遺跡を調査してきて思うのは、踏みフイゴとセットで朝鮮半島から導入され生産性が高かった竪形炉の技術の方が、自給用としてはむしろ一般的だったのではないかということだ。日本古来の製鉄法たたらには、未解決の謎が数多く残っている。
段落は、見出しのもと、次のようである。
> 日本独自の発展過程
日本列島の鉄づくりは、中国に1000年以上、朝鮮半島に500年ほど後れて定着したと推定され、弥生時代からの鍛冶技術の長い伝統のもとに独自の発展過程を経た。鉄製錬の始まりは6世紀前半ごろと考えられ、当初は鉄鉱石を原料にしていた。しかし、日本列島では火山地帯特有の鉄原料である砂鉄が産出する。鉄鉱石を原料とした製鉄はほどなくして、砂鉄を原料とする製鉄に代わった。
> 実験考古学の手法試す
とはいえ、考古学では鉄関連遺跡を専門にする先生はいない。理系の先生に教えを請う一方、千葉県立房総風土記の丘(当時)や国立歴史民俗博物館の鉄に関する共同研究で様々な実験考古学の手法を試みた。その研究が、考古学や製鉄など異分野の研究者が一緒に議論し合う場となった日本鉄鋼協会の「鉄の技術と歴史」研究フォーラムにつながっている。
> 解析をマニュアル化
発掘関係者が判断に迷わないようにするため、解析のマニュアル化も図った。様々な指標から遺物を5段階評価するもので、遺物をどのように保存するかも決めてある。
春秋
2014/10/27付
日本経済新聞
必要なら守られねばならない。不要なら廃止されなければならない。規範とはそういうものだ。そんな当たり前が通じない日々は、かなり慣らされてきたとはいえ、居心地が悪い。鉄道などの優先席付近では携帯電話の電源を切る――破られている規範の代表格だろう。
心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響する恐れがある。これが規範の大義である。一方には「携帯が原因で機器に重大な事故が起きたとの報告は世界にない」(総務省)という事実がある。もちろん、携帯のせいと気づかぬまま体や機器の変調をやり過ごしているのかもしれない。少なくとも、不安を感じる人はいる。
先に、東京工業大の1年生が「技術者倫理」の授業でこの問題を取り上げたそうだ。学生からいろんな意見が出た。「嫌がる人がいるなら電源は切るべきだ」「車内放送を流し続ける意味はほとんどないと思う」。正解はない。世の中をよくする使命を持つ技術者は難題とどう向き合えばいいか、考えさせる狙いだという。
医療機器と携帯の間が3センチ以内だと影響が出ることがある、15センチ以内なら電源を切るのが望ましい。これが総務省の見解である。わずかな距離でもゼロでない限り規範はなくせない。安全なものをつくる使命は技術者に果たしてもらおう。それまでの間、携帯やスマホをいじくりたければ……優先席には近づかないことだ。