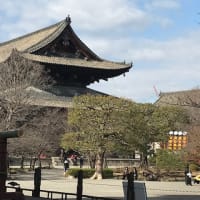甘んじる、わかりにくい語である。
それをわかりやすく言えば、受け入れるということである。
類語を検索すると、
受容れる ・ 丸呑み ・ 受容 ・ 鵜呑み ・ 受け入れる ・ 接受 ・ 受入れる ・ 迎え入れる ・ 受取る ・ 受け容れる ・ 丸呑 ・ 応ずる ・ 応じる ・ 入れる ・ まる呑み ・ 受けいれる など。
意義素に、許容するか、順応する、とある。
また、甘んじる ・ 甘受する ・ 仕方なく受け入れる ・ 不満ながら受け入れる ・ 不本意ながら受け入れる、など。
同じく意義素に、納得はできないもののやむを得ず認めること、とある。
あまんじる、あまんずる、そして、甘え、である。
あまんじる、とは、[動ザ上一]「あまんずる」(サ変)の上一段化、である。
例文には、薄給に―・じる。dictionary.goo.ne.jp › 国語辞書
この語を難しいと思うのは、許容することと、不満ながら受け入れるという、相反する語義を持つからである。
マラルメの生涯に、それを語るキーワードの一つが、甘んじた生活である。
マラルメ【Stéphane Mallarmé】ツイートする Facebook にシェア
[1842~1898]フランスの詩人。象徴派の代表者。ポー・ボードレールの影響を受け、独自の手法により純粋詩を追求。詩「エロディアード」「半獣神の午後」「骰子一擲(とうしいってき)」など。
http://poesie.hix05.com/Mallarme/mallarme00.html
>堀口大学のような翻訳の名手でさえも、マラルメの詩に関しては、まともな日本語に移しきれていない。
マラルメのこうした韜晦さはどこに由来するのだろうか
1864年、22歳のときマラルメはトゥルノンのリセの英語教師になった。その頃最初の本格的な詩 L’Azur を書いている。その後、ブザンソン、アヴィニョンのリセを歴任し、1971年の秋以降はパリのコンドルセ中学校の英語教師を勤めた。英語教師としての生活は1893年まで続けるが、高い収入は得られず、質素な生活に甘んじて生きた。
http://baudelai.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-9805.html
ドビュッシー歌曲集よりマラルメの詩「溜息』
溜息
マラルメ
私の魂はおまえの額に向かう、おお静かな妹よ、
そこでは茶褐色のしみをつけた秋が夢みているよ、
おまえの天使のような目が漂う空に向かって
私の魂は上って行くのだ、憂鬱な庭の中で、
白い噴水が〈蒼穹〉に向かって溜息つくように誠実に!
―〈蒼穹〉が青白く純粋な〈十月〉に感動し
巨大な水盤に映し出すのはその果てしない物憂さ。
澱んだ水面に黄褐色の臨終の落葉が
風に漂い冷たい水脈を穿っている、
黄色い太陽が長い光線を這わせている。
http://homepage2.nifty.com/182494/LiederhausUmegaoka/songs/R/Ravel/S1481.htm
「 溜息 」
ステファヌ・マラルメの3つの詩より
Soupir
from Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé
詩: ステファヌ・マラルメ
ぼくの魂は夢見る君の顔へと、おお静かな妹よ
そばかすでいっぱいの秋に
そして天使のような君の瞳の漂う空へと
向かっていく、まるで憂いに満ちた庭の中で
絶え間なく、白い噴水が青空に向かって溜息をつくように
-青空に向かって、青白く澄んだ十月の穏やかさは
大きな湖面に限りない憂鬱さを映し出し
そして漂わせる、死んだような水の上に褐色の苦悩を
枯葉の苦悩は風に乗って 冷たい轍を描く
黄色い太陽の長く伸びた光がその上をなぞっていく
http://blogs.yahoo.co.jp/kiichigobatake52/53135129.html
溜息
わが魂は、静かなる妹よ、はや朽ち葉色の木の葉に覆われた秋が
夢みることの少ないそなたの額と、
そなたの天使の眼に揺らめく空にむかって、
昇ってゆく、憂鬱の園の中の誠実な噴水が
白い溜息を吐きつつ蒼空に昇ってゆくのに似ている!
― 悲しみの十月が知った仄白く純なる蒼空へと、
ときに蒼空は果しない倦怠を水の深みに映し、
白い波間に苦悶する木の葉は、
風のまにまに漂って、冷たく薄暗い水脈を描き、
一筋の入り日のなごりと黄色の太陽のたゆたいつつも
(前川祐一訳)
もう一篇マラルメを。やはり前川祐一氏訳です。少しばかり長いです。
秋の歎き
マリアがわたしを棄てて他の星に行ってから――あれはオリオンだったか、牽牛星(アルタイル)だったか、それともお前、緑の金星だったか――わたしはいつも孤独を育んできた。 なんと永い一日一日を、私はひとり猫とだけ暮らしてきたことか。 ひとりでとは肉体を持つものがいないという意味で、わが猫は神秘の伴侶、一個の精霊。 だから永い毎日をただひとりわが猫と、ただひとり、ローマ頽廃期の最後の作家のひとりと暮らしたと言える。 あの純白の女がこの世を去ってから、不思議にもまた奇怪にも、わたしは「凋落」という語に要約されるあらゆるものを愛してきたからだ。 かくて一年のうちでわたしの好きな季節は、秋のまさに訪れんとするあのもの憂い夏の終わりの日々、一日のうちでわたしの散歩する時刻は、太陽が色褪せんとして、灰色の壁には黄銅色の、窓ガラスには赤銅色の光落としてたゆたう時刻。 さればこそわが魂が喜びを求める文学はローマの終焉期の死に絶えんとする詩歌であって、それも、異邦人どのも接触による回生の息吹を吸わず、初期キリスト教散文の稚拙なるラテン語を口ずさむことなきものばかりであった。
さればわたしは、これら愛誦の詩歌一篇を読んでいたが、その頬紅色の美しさは青春の燃える頬よりもわたしには魅力があった。 かくしつつわが片手でこの純粋な動物の柔毛を弄んでいるとき、窓の下で、手廻し風琴が
物憂げに心悲しい演奏を始めた。 そこはポプラ並木の小道で、マリアが還らぬ旅に蝋燭の炎に飾られてこの
道を去っていったから、あのポプラの葉は春でもわたしには悲しんでいるように思われる。 なるほど歎ける人たちの楽器というが、そのとおりで、ピアノはきらめく響、ヴァイオリンは引き裂かれた神経に光を与えるが、この手廻し風琴は、追憶の薄明かりのなかでわたしを絶望的な夢に誘いこんだ。 呟くように演奏する曲は陽気なほど俗悪な、場末の町の心臓を浮き浮きさせる流行遅れの軽っぽいやつだったが、その繰り返しのひと節がわたしの心に沁み透って、ロマンチックな小唄のようにわたしを泣かせたのはなぜか。 聞き惚れたわたしが、窓から一文も投げてやらなかったのは、折からのわが感動を掻き乱したくなかったし、楽器がひとりで唱っているのではないとわかるのが怖かったからだ。
>マラルメの家庭は今や、甘んじて必然の運命を受け入れており、彼. の未亡人になっ ...
>1871 年のこの夏、マラルメはまだ教師生活のこの物憂い単調さに完全に. 甘んじて従っていたわけではなかった。
>その思想圏内では、詩人は永遠に音楽家の下位に甘んじなければならないことになります。
>マラルメは 1862 年『芸術家』誌に投稿した記事「芸術の異端 ― 万人の芸術」において、次. のように後期ロマン主義的な .... のように、来るべき詩の壮麗さと大衆に甘んじた芸術の凡庸さという対比において変奏されている。
>『「マラルメ」という文字が私に思い出させるのは、最底辺の無知に甘んじている、あのころの心許なさである。