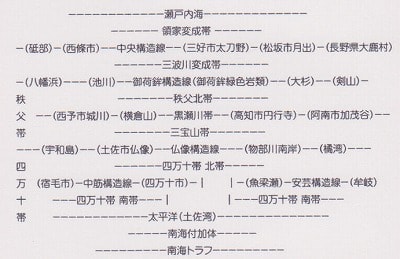インフラ、十年一昔、高知の変わり様
情報プラットフォーム、No.233、5月号、2012、掲載
高知に15年前に来た時と今とを比べる。前回の{納豆、十年一昔、高知の変わり様}(No.232、5月号、(2012))の続編である。
高知市内の東西の交通が、土電通りの他に、北環状道路、土佐道路と選択肢が増え、高速道も加わって便利さが増し、渋滞解消になっている。山田ま での「あけぼの街道」の開通が間近であり、「国道195号」の道標がすでに散見できる。南北方向の交通は、対面ではあるが五台山トンネルの完成 で、医療センターや高知新港へのアクセスが楽になった。高速道では、高知インターの開業があり、2008年の4車線化で川之江から南国までの19 のトンネル内の安全性が高まっている。また、県西部への延伸が少しづつ進んでいる。一方で、五台山の2本目のトンネル掘削は、高知龍馬空港へ、そ してさらに先への高規格道路の進捗を感じさせるに十分である。中山間地の道路整備も少しづつ進んでいる。
地形が急峻なこと、災害の多いこと、そして孤立しがちな地形であることなどの短所を長所に変えるように、多様な工夫の結果として高知県の土木技術が進んだ。地域に根ざした土建業者が各地に配置されている。沢筋の奥の集落に土建業者と自動車修理工場が一軒づつ必ずあるように思えた。「沢が崩れたと き、川下からだけではなく、上流からも復旧工事ができるようになっているのです」と
教えられた。公共投資が激減し、土建業の廃業や転業が相次ぐこ の頃では、こんなメリットも強調できなくなっていると思われる。
浦戸の渡し(御畳瀬-種崎間)は無料であるが、2002年から四輪は載せなくなった。県外客の案内の目玉としていたのだが残念である。浦戸大 橋、仁淀川河口大橋、宇佐大橋などが無料化された中で、高知桂浜道路は有料で残されている。
県内では10ヶ所だった道の駅は21ヶ所に倍増してい る。一方で、廃墟と化したドライブインが各地に散見される。
高知に来て最初に住んだのが知寄町のマンションの11階であった。高知港がよく見えた。停泊中の大阪高知特急フェリーや東京-那智勝浦-高知を結ぶ「さんふらわあ」を眺めたものである。船腹に太陽のマークを付けた「さんふらわあ」は2001年10月に、大阪特急フェリーは2005年4月に廃止と なってしまった。1998年に供用が始まった明石海峡大橋の影響が大きかった。JR四国の特急南風も苦戦をしているようである。高知と京阪神を結 ぶ高速バスの料金が安く、所要時間にも差が無くなっている。高知空港は2004年に滑走路が2500mに延伸され、着陸時の安定性や安全性は大き く増したと思われる。
県内中山間地で広く仕事をしている土木建設業の社長さんが携帯3社の電話をぶら下げていた。「圏外が多くてね」と嘆いていたのを思い出す。今で は何処を見ても、携帯3社の店舗が競い合い、丘の上には何処でも通信塔が立ち、圏外エリアは少なくなってきた。
一方で、高齢化率の上昇を示すかのように、養護老人ホーム、ケアハウスなど老人福祉施設が開設され、葬祭会館も次々とオープンしている。石材業 の新装の展示場も増えている。反面で、ホテルや大規模宴会場を持つ施設は苦しいようである。結婚式やお客(高知流の宴会)の在り方が変わってきて いる。閉鎖されたところも多い。高知に来た頃は2次会・3次会が普通だったが、高齢化のせいか、景気が悪いためか、めっきり減っている。飲酒運転 の取り締まり強化に伴って、代行が急速に増えてきたのもこの10年である。
大部分が外からの大きな力を受けながらの変わり様であるが、便利になったのか、不便なのか意見の分かれるところである。豊かさとは、幸せとは を、考え直す時に来ている。
ご感想、ご意見、耳寄りな情報をお聞かせ下さい。
鈴木朝夫(すずき ともお)
〒718-0054 高知県香美市土佐山田町植718
0887-52-5154、携帯 090-3461-6571 s-tomoo@diary.ocn.ne.jp