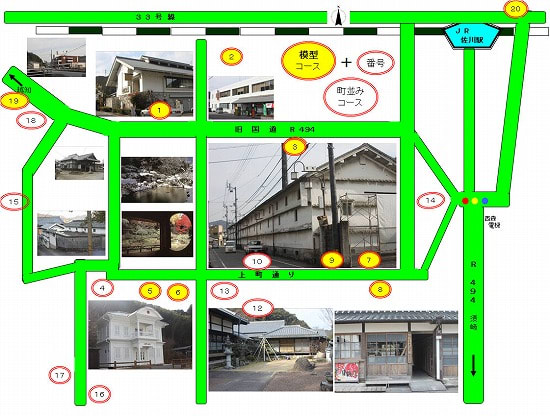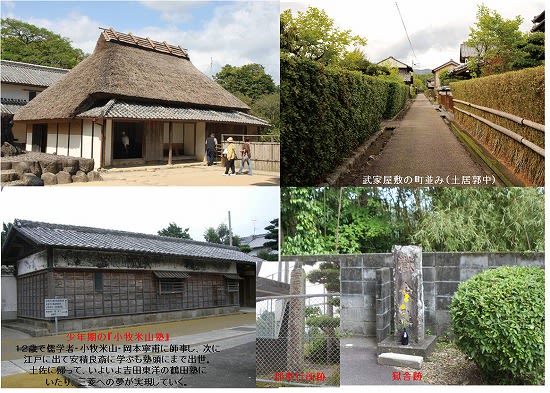羽迫博己さんの、土佐人の銅像20・・・板垣退助先生像

天保8年(1837)4月17日、土佐藩馬廻格
乾永六の長男として高知城下中島町に生れた。
少年時代から学問よりも相撲や闘犬などの勝負事を好み、
士格青年の社団組織「盛組」の中心人物として
乱暴を働き処分を受けている。
安政2年(1855)には1年間江戸勤番を勤めるが、安政
3年8月には総領職没収、城下四ヵ村禁足という重い
処分を受けて、3年間城西神田村で生活したこともある。
万延元年(1860)父の死去により、知行を50石削られて
220石で家督を継ぎ、時の仕置役 吉田東洋の
推薦を受けて藩政に携わり、騎兵術、蘭式兵学を学んだ。
慶応4年(1868)の戊辰戦争には東山道先鋒総督府参謀
として出征、その功績により、版籍奉還後は高知藩
山内豊範の補佐役大参事となった。
のち明治政府の参議となったが、明治6年征韓論に敗れて
西郷隆盛らとともに辞任した。
翌7年1月、同志とともに「愛国公党」を結成、民選議院
設立の建言を政府に提出、高知に帰って片岡健吉らと
立志社を設立して自由民権運動を展開した。
明治15年4月6日、自由党総理として遊説中、岐阜で
暴漢に刺されたとき、血まみれの中で口にした「板垣
死すとも自由は死せず」の一言が新聞その他で報道
され、この言葉が自由民権運動の合言葉になると
ともに、彼は一躍自由民権運動の英雄となった。
同年11月から7ヵ月にわたる欧州視察にあたっては、
その旅費の出所に疑惑が生じ、党内に亀裂を生じる
など、彼らの運動も曲折を重ねたが、明治22年の
憲法発布、翌年の国会開設への道を切り開いた。
その後、板垣は伊藤博文内閣の内務大臣などの要職に
つくも、明治33年引退後は社会改良運動に尽くした。
大正8年死亡 83歳。 あぞのに分骨堂がある。
板垣は角刀道振興にも力を尽くし、国技館の名付け親とも
言われるほどで、記念角刀興行をし、純益15,797円
が寄贈され、またそれ以外に募金が33,000円に上り
大正13年銅像が建設されたが、戦時中供出された。
除 幕: 昭和31年5月11日
題 字: 板垣退助先生像
規 模: 本体~2,2 ㍍ 台座~4,205 ㍍
総高~6,405 ㍍
事業費: 250万円