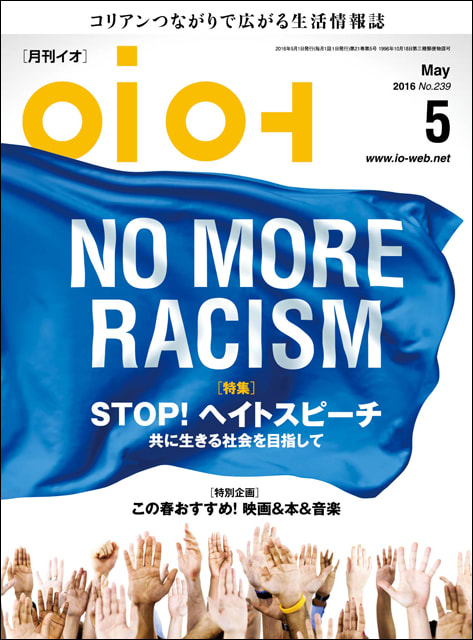今年7月、月刊イオが創刊20周年を迎える。
という事情で、7月号では「二十歳」の在日同胞青年たちを取り上げた。
正確には1996年生まれを対象にした。今年20歳になった・なる人たちだ。
二十歳といえば、歩んでいる道はさまざま。多くは大学生や専門学校生。高校卒業と同時に社会に出た人や、2年制の大学・専門学校を卒業し今年4月から働き出した人たちもいる。
私自身はこの間、6人の二十歳の同胞を取材したが、やはり「進路」という言葉をたくさん聞いた。
まず大きな選択を迫られるのが、高級部を卒業するときだろう。「進路」に迷いながらも、ぼーっとはしていられないし、受験や何らかの面接などの準備を進めなくてはいけない。徐々に進路が決まっていく周囲にプレッシャーを感じる人もいるはず。家族、友だち、教員と話し合うことで考えがまとまることもあるが、その逆もある。
そんな時期を葛藤と共に乗り越えたからだろうか、話を聞いた二十歳の人たちは皆、堂々と自身の考えを話してくれた。
一方で、やっと新しい生活をスタートさせたかと思うと、すでに次の「問題」が立ちはだかる。「次の進路はどうする?」「本当にこれでいいのか?」「こういう道もあるかも…」。「二十歳」はそんな時期だと感じた。高校卒業後に進学した人は、いざ「社会」が目の前にあるからこそ、高校のときとはまた違う覚悟がいるかもしれない。
年齢は私の3つ、4つ下になる。取材をする過程で、同世代として共感できたり、新鮮さを感じたり。また、数年前に自分が何に悩んでいたかも思い返してみた。
結局は、進学や就職後も「進路選択」の場面は何回も来る。新しい経験をすると、その経験をする前の自分とは少し違う自分がいるかもしれないし、進路を考える「材料」も以前とは違うかもしれない。二十歳のときの考えや決断が、数年後のかれ・かのじょらにとっても同じだとは限らない。「やっぱりこの道しかない!」と思うか、新しい考えが生まれるか、それはその時にまた分かることだと思う。
何かを「決める」ことは難しい。私もその時々に自分の考えや気持ちと向き合っていかなくてはいけない。迷った時、思い切って踏み出せる「勇気」を持っていたいと思う。(S)
という事情で、7月号では「二十歳」の在日同胞青年たちを取り上げた。
正確には1996年生まれを対象にした。今年20歳になった・なる人たちだ。
二十歳といえば、歩んでいる道はさまざま。多くは大学生や専門学校生。高校卒業と同時に社会に出た人や、2年制の大学・専門学校を卒業し今年4月から働き出した人たちもいる。
私自身はこの間、6人の二十歳の同胞を取材したが、やはり「進路」という言葉をたくさん聞いた。
まず大きな選択を迫られるのが、高級部を卒業するときだろう。「進路」に迷いながらも、ぼーっとはしていられないし、受験や何らかの面接などの準備を進めなくてはいけない。徐々に進路が決まっていく周囲にプレッシャーを感じる人もいるはず。家族、友だち、教員と話し合うことで考えがまとまることもあるが、その逆もある。
そんな時期を葛藤と共に乗り越えたからだろうか、話を聞いた二十歳の人たちは皆、堂々と自身の考えを話してくれた。
一方で、やっと新しい生活をスタートさせたかと思うと、すでに次の「問題」が立ちはだかる。「次の進路はどうする?」「本当にこれでいいのか?」「こういう道もあるかも…」。「二十歳」はそんな時期だと感じた。高校卒業後に進学した人は、いざ「社会」が目の前にあるからこそ、高校のときとはまた違う覚悟がいるかもしれない。
年齢は私の3つ、4つ下になる。取材をする過程で、同世代として共感できたり、新鮮さを感じたり。また、数年前に自分が何に悩んでいたかも思い返してみた。
結局は、進学や就職後も「進路選択」の場面は何回も来る。新しい経験をすると、その経験をする前の自分とは少し違う自分がいるかもしれないし、進路を考える「材料」も以前とは違うかもしれない。二十歳のときの考えや決断が、数年後のかれ・かのじょらにとっても同じだとは限らない。「やっぱりこの道しかない!」と思うか、新しい考えが生まれるか、それはその時にまた分かることだと思う。
何かを「決める」ことは難しい。私もその時々に自分の考えや気持ちと向き合っていかなくてはいけない。迷った時、思い切って踏み出せる「勇気」を持っていたいと思う。(S)