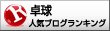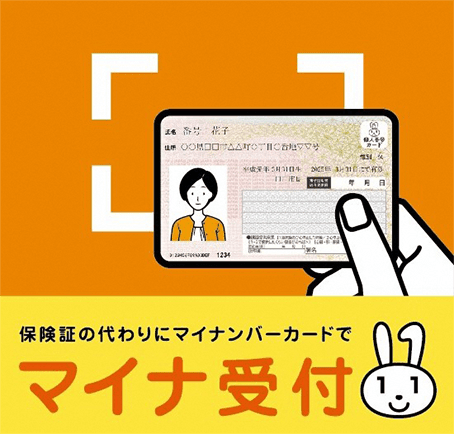2月1日に医療費控除の確定申告に税務署に行ってきました。確定申告期間は、2月16日~3月15日であるが、医療費控除の申請だけなら、1月から可能であるので、書類が整い次第、毎年1月下旬~2月上旬に手続きに出かけている。8時半の開門の15分前に税務署に行ったが、列が出来ていて6番目で、8時45分から受付が開始された。昨年までは、パソコンでの入力による申告であったが、今年からは、原則スマホによる申告で、マイナンバーカードを利用した手続きに変更されたとのことである。スマホの操作には不慣れなので、不安があったが、係員が付いてくれて、助けを借りての入力となった。収入所得、社会保険(健康保険)控除、生命保険控除、医療費控除、寄付金等入力する項目が多く、とても一人ではすべてを入力することは困難といえる。自宅でもe-Taxで申告できるという案内もあるが、正確を期すなら一人でやるのはとても無理との印象である。一人つきっきりなので、助かるが、マンパワー上、きわめて非効率といえる。
スマホを持たない人は、例外的にパソコンで申告することになるようである。また、マイナンバーカードを持っていない人は、カードを使わない方法で入力していくようである。年寄世代は、スマホを持たない人やマイナカード持たない人も少なくないので、スマホによる申告を原則とすることには疑問も感じる。今までは、申告書類をプリントにしてくれたが、今回は、スマホにデータが保存されるだけである。年寄世代は医療費がかさむので、医療費控除の申告は欠かせないが、申告手続方法は年寄りにはあまりにも優しくないので、断念している人も少なくないのではないか?2023年は、30万円近い医療費があったので、申告結果として9万円を越える還付金があった。医療費がかさむのは好ましくないが、還付金はありがたいお年玉となるので嬉しい思いである。
昨今、安倍派を中心とした自民党政治家の裏金問題が大騒ぎとなっているが、裏金の隠匿は脱税行為ともいえ、国民からも非難を浴びている。我々一般国民は、確定申告で国税庁からバッチリ税金を取られようとしている一方、政治家の何千万、何億円もの裏金が無税とは納得できない。国税庁は、「弱きをくじき強きを助ける」というのが基本のようで、一般国民には厳しく税を取り立てるが、政治家に対しては甘々状態で本来の業務をきちんとやっていない印象が強い。政治家は、特に自民党安倍政権は、検察も押さえ、税務当局も押さえてきたという驕りが見える。検察庁も国税庁も政権に忖度しているようで情ない話である。マスメディアも、厳しい税務調査を働きかけるべきであるが、グルになっている感があり、そのような声が聞こえてこないのは残念なかぎりである。残念ながら、我が国は、警察も検察も国税も本来の機能を果たしていない感がある。