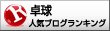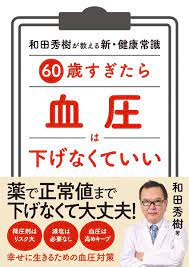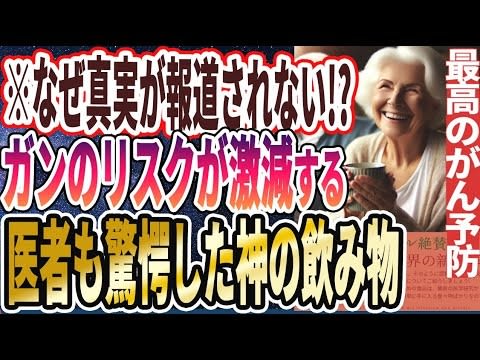ネット検索をしていたら、「本要約チャンネル」という健康関係のサイトに出会った。世界一わかりやすく要約が謳い文句で、その内容に説得性があるので、いろいろな切り口でのユーチューブに引き込まれる。いろいろあるので、個人的に興味が惹かれるものを随時紹介したいと思う。高齢者にとっては、健康のためには毎日どんなものを食べたらいいかしっかりした情報に疎いので、大変参考になる。
色々な情報がアップされているが、まずは、「万病が消え去り、ガンのリスクが激減する神飲料TOP5」というタイトルのユーチューブを最初に見た。紹介されている神飲料TOP5は下記の通りであった。
- しじみの味噌汁
味噌汁は塩分量が比較的高いにもかかわらず、胃がんのリスクを低下させ血圧 まで安定させてくれることがわ かっている。特に、しじみの味噌汁がおすすめ。冷凍しじみもいいようである。
- トマトジュース
トマトジュースはリコピン単体よりも大腸がん予防の効果が高い。ただし、無添加のもの選ぶことが重要である。
- 緑茶
緑茶には前立腺がんや女性の胃がんを予防する効果がある。
- コーヒー
コーヒーには肝臓がんや子宮体がんのリスクを下げる効果がある。
- エクストラバージンオリ-ブオイル
エクストラバージンオリーブオイルはがんだけでなく認知症まで予防してくれる。
逆に、飲めば飲むほどガンになる、一口たりとも飲んではいけない危険な飲み物2選は下記の通り。
- 糖分入りの飲み物
- アルコール
すべてのガンのリスクをあげる。但し、個人的には、適度なアルコールは食欲を増進するので、すべて悪いとは思えない。また、飲み物や食べ物については、すべてバランスだと思うので、参考にしながらバランスのよい摂取を心掛けたい。
「万病が消え去り、ガンのリスクが激減する神飲料TOP5」: https://www.youtube.com/watch?v=HcZxQRdTyBM
ネット検索していたら、Teaching Beauty鍼灸整骨院の院長が語る健康情報チャンネルを見つけ、早速チャンネル登録した。NHKやTBS等のテレビにも出演したことがある院長で、ユーチューブで健康に関するいろいろな情報を紹介してくれている。今回、気になったのは、「60歳以上の人が卵を毎日食べるとこうなります」というタイトルの卵に関する情報である。院長によると、卵には、①タンパク質 ②脂肪 ➂ビタミン ④ミネラル ⑤抗酸化物質 ⑥コレステロールがたっぷり含まれているので、栄養価満点の食品なので、できれば1日3個食べてほしいという。
院長によると、積極的に食べたほうがいい人として、①目の病気 ②骨粗しょう症 ➂心血管疾患 ④認知症予防 ⑤精神的不安がある人 ⑥高齢者をあげており、詳しく解説してくれている。個人的にも、加齢性黄斑変性症や不整脈を抱えており、認知症予防効果といい、精神的不安解消といい、高齢者というカテゴリーにピタリ該当するので、卵の重要性を改めて認識した。
普段の生活では、朝食時に卵は食べておらず、お昼に、うどんやラ-メンを食べる時に卵を1個入れる程度で、とても1日3個はとても無理。正直いって、卵の栄養価値がこんなにあるとは思ってもいなかった。旅行でホテルで朝食を食べる時は、必ず目玉焼き等の卵を食べるが、家ではほとんど食べていないので、これからは朝食メニューに卵料理を加えようかと思う。卵の値段は、一時値上がったが、ここにきて値段も下がってきて、安定して安く買うことができるので、ありがたい話である。日本では、生でも食べられるが、できれば調理したほうがいいようである。このチャンネルでは、他にもいろいろな健康情報を提供してくれているので、いろいろ覗いてみようと思う。
院長教えて!たまご(約19分): https://www.youtube.com/watch?v=uAJyJ-nLBwU
2002年から22年間も愛用していたマッサージチェアが故障気味となったため、新しく同じメーカーの後継機種と思われるものをネットで購入した。マッサージチェアは、安いものから何十万円するものまでピンからキリであるが、今まで使っていたのものは、安価なスライブの「くつろぎ指定席」というマッサージチェアだが、それで十分で、十分元を取った感がある。22年も経つとさすが廃版で、後継機と思われる、やはり「くつろぎ指定席」というマッサージチェアを購入した。大きな違いは、重さが従来のは49㎏もあったが、今回のは24.7㎏と軽量になった。また、叩くという機能は無くなったようであるが、フットレストが脚マッサージ機能とオットマン機能の両方を持っている。注文した翌日には届くというクイックデリバリーで2日に届いたが、見かけは大分コンパクトになった印象である。値段は、22年前は、79800円であったと記憶するが、今回は、ネットで販売各社を比較し、送料無料の一番安いところを選んだので、ほぼ5万円で済んだ。5年の長期保証も付けたが、それでも予想以上に安く買い替えることができた。ネットで簡単に買え、翌日には配達されるという便利な世の中になったものである。
我が家には、マッサージチェアとは別に、「若石式ローラー」というフットマッサージ機もある。これは単なる足裏マッサージ機ではなく、足ツボの反射区に回転ローラーで適度な刺激を与え、健康を増進しようという医療器具にも指定されている優れものである。足裏の反射区の図解があるので、それを見ながらツボに刺激を与えていくだけで簡単にマッサージ効果が得られる。詳しく覚えていないが、こちらは10万円近くしたと思う。やはり20年位前に台湾式の反射療法である「若石式足療法」の先生から勧められて購入したもので、いまだに健在である。健康効果を考えると決して高いものではない。自分のデスクの下に置いてあり、適宜ローラーで足つぼマッサージを行っている。ツボへの刺激が強く、街中の足裏マッサージ店に勝るとも劣らない効果が期待できる。ローラーに興味のある人は、下記のサイトに立ち寄ってみてください。
若石ローラーについて: https://www.jakuseki-rmr.com/?transactionid=1e75ad74f5ae93a61033613d3d7a11cab33ff975
2月3日に心臓・不整脈セミナーという市民公開講座に出席してきた。昨年6月に行われた同じ講師による「心房細動についてご存知ですか?~くすりとカテーテルアブレーション~」という同じプログラムだが、さらに理解を深めたいと思い、再度聴きに行ったものである。1年前に、心房細動の診断を受け、今は、薬による治療を続けているが、発生頻度が増えつつあり、カテーテル・アブレーション治療を受けることを検討中なので、様々な疑問を解決したいという思いからである。 講師は、心臓血管研究所付属病院の循環器内科医長の八木直治という先生である。セミナーの内容は全開とほぼ同じであったので、リマインドする形となった。参加定員は、50人と少ないので、満席として断られた人もいたようである。スライドによる説明だけで、配布資料がないため、メモ取る手間がかかり、話に集中できない恐れがあるが、自分の場合、前回のノートを持ち込んで聴いたので、特には問題なかった。セミナーは下記の項目に従い、説明が行われた。
- 心房細動とは
- 心房細動があると何が問題なのか
- 薬による治療
- カテーテルアブレーション治療
心房細動については、担当医からの説明だけでなく、友人から話しを聞いたり、本を読んだり、セミナーを聴いたりしているので、大分詳しくなった。薬による治療を卒業し、いつアブレーション治療を受けるべきかが悩ましく最大のポイントである。友人からは早く受けたほうがいいと強くアドバイスされているが、年令や症状の起伏考えると微妙な選択でもある。症状がひどければ、諦めもつくが、小康状態だとついつい先延ばしにしてしまう。今は、薬の服用で様子を見ている状況で、運動もスマートウォッチやオキシメーターで心拍数を常時チェックし、無理に心臓に負担をかけないように心がけながら、今まで通り実施している。薬療法も徐々に効果が薄れていくという話なので、年令と症状を見ながら、手術のタイミングを図ろうと考えている。講演後、質問を受けてくれたので、アブレーション治療を受けるタイミングのアドバイス、手術を担当する医師体制、携帯型心電計等について質問させてもらった。今治療を受けている医師から2月末に携帯型心電計を約一ヵ月貸してくれることになったので、不整脈の様子を見て、決断することにしたい。
区の胃がん検診の案内が来ていて、2年に1回、2000円の検査費用で、内視鏡検診が受けられるというものである。健康増進のためにも、この種のがん検診が安く受けられることはいいことだと思うが、その内容を見て疑問符が付いた。内視鏡検査は、近くのクリニックで毎年受けており、2年に1回は、区の検診制度を利用していた。今回、内視鏡検査対象の案内があったので、クリニックに行ったところ、血液を固まりにくくする薬を服用しているので、受診ができないと断られた。区の検診は利用できないが、一般の保険診療で検査を可能だといわれ、なんとなく釈然としなかったが、検査の予約も行った。家に戻って検診の案内書を読んでみたら、「受診できない方」として、13件の該当者がリストされており、その中に「血液を固まりにくくするお薬を服用中の方」があった。考えてみたら、不整脈の診断で血液サラサラの薬を飲み始めてから、初めての内視鏡検査である。高齢者の場合、脳梗塞や血栓防止のため、血液をさらさらする薬を服用している人も少なくない気がする。
同じ検査をするのに、区の検診では駄目だが、一般の保険適用では大丈夫というのも何か変なので、気になり本当はどうなのか少し調べてみた。1年前に大腸の内視鏡検査を受けた別のクリニックの担当医に訊いてみたら、区は、何か起こったら困るということで、危ない因子を持った人を受診者から排除しているようで、区の担当からも厳格に運用するよう言われているそうである。要するに、表向きがんの早期発見のためにがん検診の受診を薦めているが、危ない因子を持った人は排除するということで、実質的には健康増進というより、健康な人に限定して、高齢者等持病を持った人が検診を受けることを邪魔しているように見える。現場の担当医は、そのような薬を服用していても、問題なく検査できることを保証しているのに、何か変である。自分の理解では、血液をさらさらする薬が効いている期間は1日だけなので、毎日服用するよう言われている。言いかえれば、1回服用をやめれば、服用から24時間経った時点で検査する限り、元の状態に戻っているのだから、出血が止まらなくなる可能性はなくなるはずである。単に内視鏡による検査だけなら、出血の心配はないはずで、心配なら、区の検診では出血を招く恐れのある組織を切り取る生体検査をやめ、別途精密検査を勧告すればいいだけだと思う。区の検診による受診者排除は論理的根拠がなく、単に検診によるトラブルを回避したいという自己保全に過ぎないような気もする。担当医がそういう薬を服用していても、一般の保険診療は可能だというなら、区の検診も担当医の了解が得られることを条件として、門前払いとせず、できるだけ多くの人が安価な区の検診を受けられるように配慮してほしいものである。本当に危険があるなら、保険診療の場合もやめるべきであり、真実を知りたいところである。