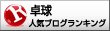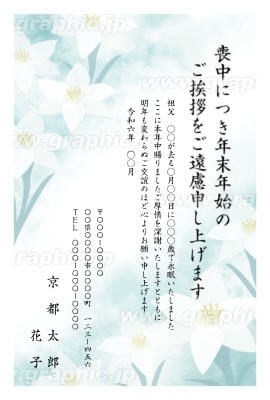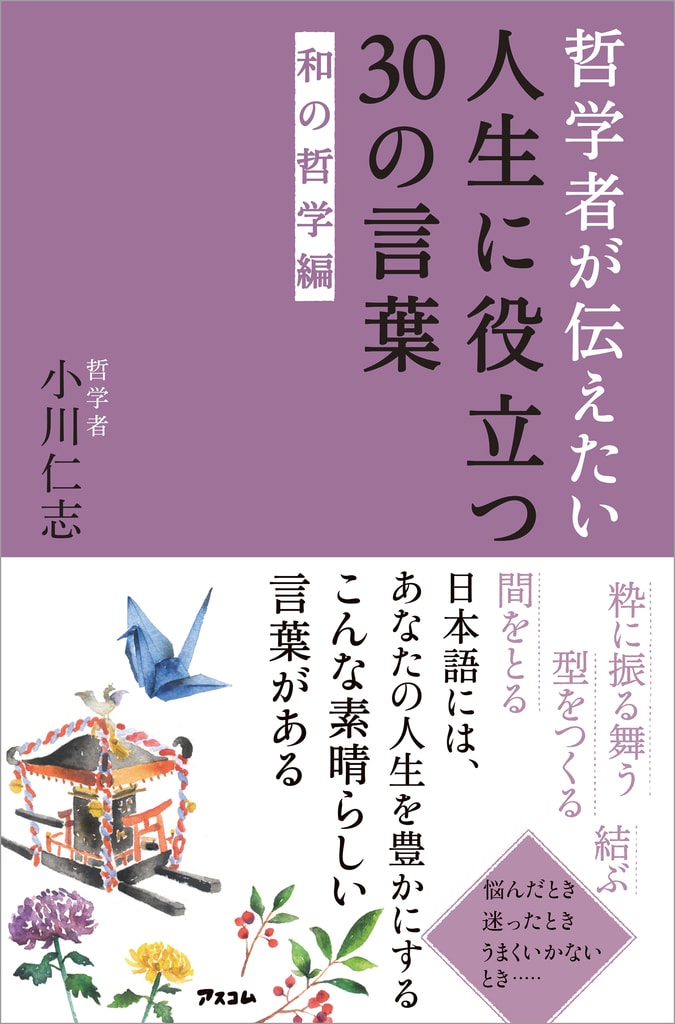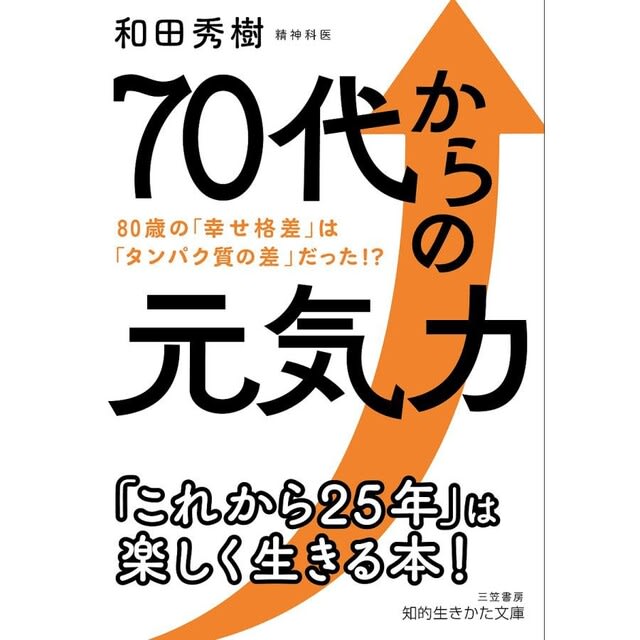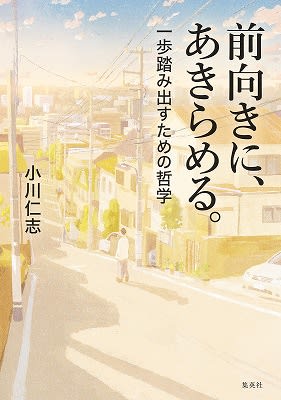高齢者専門の精神科医として活躍している和田秀樹氏が2022年9月に出版した「70代からの元気力」を図書館で借りて読み始めたが、自分にとってこれからの人生を生きていく上での手引書として、ピタリの内容が盛り込まれていたので、本自体を急遽購入することにして、しっかり読んでみた。サブタイトルは、「これからの25年」は楽しく生きる本!とあり、楽しく生きるヒントが盛りだくさんであった。プロローグで、「70代を楽しく生きれば、80代はもっと楽しくなる!」この人生観が「70代の人生」を充実させるという。とても読みやすい本で、項目ごとに具体的ノウハウが満載でヒントになる人生訓が述べられている。人生100年時代と考えれば、70代なんてまだまだ若い方とはいえ、「自分の人生も、あと何年?」と不安になることも多々あるので、大変参考になる。70代をはつらつと充実させたいものである。項目を列挙するだけで、どんな内容の本かよくわかると思うので、下に項目を列挙してみる。(項目は一部略)
1 65歳を過ぎたら,絶対「知っておきたいこと」
・日本人の「心理年齢」、20歳も若返っている。
・いまの「70歳」は、昔で言えば「50歳」
・70代の重要性に気づくと、元気が出る
・「団塊の世代が元気」になれば「日本も元気に」になる
・「若く見える人」ほど年齢を気にしないー70代の格差
・「70歳になる」とは「自由になる」ということ
・「何ごとも遊び半分」が、脳を老化させないコツ
・「胸を張って、無責任に生きる」は、70代の特権
・「外に出て町を歩く」だけでも必ず若返ります
2 「元気ある70代」は「元気ある食事」から作られる
・百寿者(100歳以上の人)ほど「肉」を食べている
・「健康数値が悪い人」のほうが、じつは長生き?
・「血圧を下げる」より「血管を強く太くする」のがいい
・70代の脳細胞は「若さ=肉」を求めています
・会社員の「食のバランス」が意外にいいワケー外食の効能
・肉を食べないから、体が動かなくなるのです
・「元気のある人」は当然、「元気のある食材」を食べています
3 70代から「脳の老化を防ぐ+遅らせる」食生活
略
4 80代が楽しみになる!70代からの「新しい習慣」
・「脳」も「感情」も使わないから老化するのです
・「食事を楽しむ」習慣が、前頭葉を刺激します
・70代の外食-家庭では摂れない栄養素を摂る知恵
・「孤独のグルメ」は、70代の体にも心にもいい
・前頭葉を刺激する「地元ランチ」のすすめ
・大好物を食べる「幸福感」を習慣にする効果
・65歳からの「見た目格差」は「タンパク質の差」
・65歳過ぎたら「むやみに健康になろうとしない」
・70歳過ぎたら「肉食男子・肉食女子になる」
5 人生は、70代からが「本当に面白くなる」
・「心が疲れているときに、体を休ませる」のは、逆効果
・70代の脳には「自然のリズム」が気持ちいい
・「70代からのゴルフ」という健康法
・「成果ゼロも楽しめる」のが、70代の楽しさ
・「動物と共に生きるセカンドライフ」の効能
・人生は「思い通りにいかない」から、面白くなる
6 70代から始めよう和田式「心と体」健康のコツ
・健康数値が悪くても「心が元気」なら、問題なし!
・「歳のことを考えない」のも、心の健康法
・「老い」はこっちが忘れてしまえば、追いかけてこない
・元気いい妻、元気ない夫―70代の「男女差」のなぜ?
・「歩数計を買って、ぶらぶらする」人生も、意外にいい
・幸せな70代は「早起き」から始まります
等々。