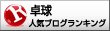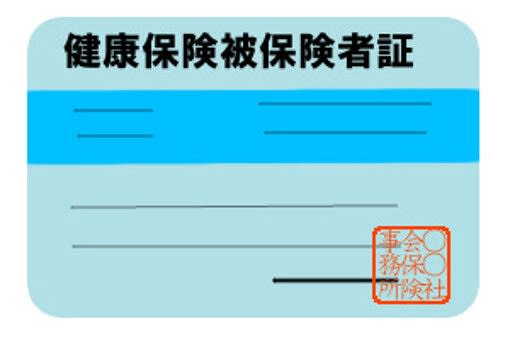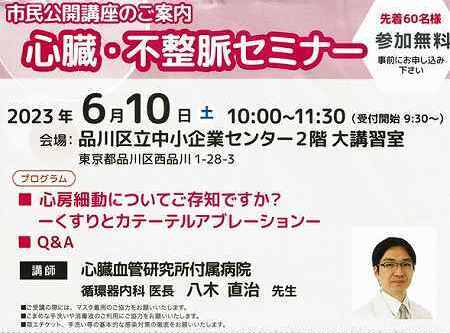令和5年度の後期高齢者医療保険料が決まったので、納付書で支払えという郵便物が届いた。7,8,9月分ということだが、一月分としては、理解していた年間の保険料を12で割った額より1万円近く多いので、疑問を感じ、区の担当部署に問い合わせをしたところ、いろいろなことがわかった。
まず、保険料のお知らせが入っており、そこには、「お支払いは7月からとなりますので、来年3月までの9回で月割りしています」と書いてあるが意味がよくわからなかった。問い合わせてわかったことは、3月に後期高齢者になったので、4~6月分は、未納になっており、その分を上乗せていることがわかった。一般的には、例年、保険料は7月に決まるので、4~6月分は前年実績に基づき、仮の徴収を行っており、7月分以降で、額の調整を行っているということがわかった。
今回、納付書が同封されており、それで保険料を支払えと案内されているが、口座振替も可能で、パソコンやスマホから手続きができる旨の案内文も記載されていた。口座振替の方が楽なので、手続きをしようかなと思ったが、問い合わせで、次のようなこともわかってビックリした。
今回の郵便物には保険料の算出方法等を記載したリーフレットも同封されていたが、保険料は、均等割額と所得割額の合計で算定されるという内容で、すでに知っていたことなので、すべてに目を通さなかった。問い合わせてわかったことは、保険料の徴収は、原則的には、「特別徴収」といって、年金から引き落とすことになっているが、介護保険料と後期高齢者保険料の合計額が、1回あたりに受け取る年金額の2分の1を「超えている場合とか新たに後期高齢者制度の対象となった場合は、特別徴収とならず、「普通徴収」(納付書又は口座振替)で保険料を納めてもらうと規定されていることが判明した。
保険料支払いの通知書には年金からの天引きの話しは一切案内されていないので、問い合わせて初めてわかった。皆、後期高齢者になって、初めて通知を受けるのであるから、わかりやすく丁寧に案内すべきである。年金からの天引きが原則なら、まずそのこと説明し、新規の対象者については、まとめて払うため初年度の保険額が高額となるので、納付書で対応する旨きちんと説明すべきである。
後期高齢者保険料は、均等割額と所得割額(年金等)の合計であるから、保険料が高い人は年金等の所得も高いはずだから、基本的に初年度以外は2分の1ルールが適用されるはずがないと思い、担当者に正したら、まさにその通りであった。マイナカードでデジタル化などと声高に議論されているが、後期高齢者の医療保険制度や保険証や保険料算出などはアナログ全開である。もっとすっきりとデジタル化できないか検討すべきであろう。