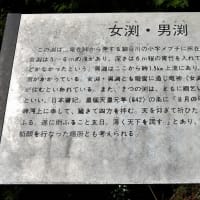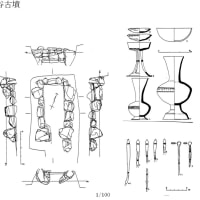僧侶だけでなく、一般の人も入浴したようです 撮影日;2008.9.25
創建の年代は不明です
治承4年(1180)の兵火で焼失
延応元年(1239)俊乗上人が再建
応永15年(1408)惣深上人が修復
東西八間・南北五間、西正面入母屋、東背面切妻造で、柱の上にある木組みの肘木が和様で、詰め組の中備えをなす丸みのある肘木が唐様です
国の重要文化財に指定されている建物です
★所在地;奈良市雑司町406
東大寺・二月堂から裏参道の坂を下りてくると左手に有ります
★入場料;非公開 (外観のみ見学可)
★問合せ;
湯屋内部の浴室入り口上部には唐風破が取り付けられているそうです
内部は3区分され、中央の浴室に建久8年(1197)に鋳物師草部是助(くさかべこれすけ)作の湯釜(口径231cm、深さ73cm)が据えられています(国重文)
別の釜で沸かした湯を運び入れて使用していたようです
「銭湯」の原型とされ、一般にも解放された「施し湯」としては、日本最古のもの
創建の年代は不明です
治承4年(1180)の兵火で焼失
延応元年(1239)俊乗上人が再建
応永15年(1408)惣深上人が修復
東西八間・南北五間、西正面入母屋、東背面切妻造で、柱の上にある木組みの肘木が和様で、詰め組の中備えをなす丸みのある肘木が唐様です
国の重要文化財に指定されている建物です
★所在地;奈良市雑司町406
東大寺・二月堂から裏参道の坂を下りてくると左手に有ります
★入場料;非公開 (外観のみ見学可)
★問合せ;
湯屋内部の浴室入り口上部には唐風破が取り付けられているそうです
内部は3区分され、中央の浴室に建久8年(1197)に鋳物師草部是助(くさかべこれすけ)作の湯釜(口径231cm、深さ73cm)が据えられています(国重文)
別の釜で沸かした湯を運び入れて使用していたようです
「銭湯」の原型とされ、一般にも解放された「施し湯」としては、日本最古のもの