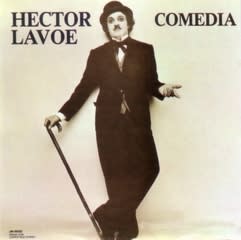当ブログ最多登場で、近日中にも登場予定だった、コンガの巨人、レイ・バレット(Ray Barretto)が亡くなった!!!
(
記事はコチラ。)
Cottonwoodhillさんという方からトラックバック頂きまして知りました。
2月17日、昨日だそうです。76歳。
奇しくも、プエンテ御大と同じ享年ではないですか。
う~ん・・・。唸るしか無いです。
2000年に入ってからも、名盤と呼ぶにふさわしいアルバムを出していたので、残念です。
ワタクシが在籍するラテン・スウィンガーズのフライヤーの中でも、リスペクトするヒトとしてワタシが挙げていたのは、ジョー・バターン(Joe Bataan)と、このレイ・バレットだったんでス。それくらい、好きなミュージシャンでした。ホントに偉大なミュージシャンでした。
冥福を祈ります。
実は、年齢が年齢だけに、何となくそろそろヤバイんじゃないのと思っていて、先週のラテン・スウィンガーズのライヴの時に、コンガのジン君とも「レイ・バレットって、まだ大丈夫なんだろかね?」くらいのハナシをしていたバカリだったんですよね。
とにかく、どれだけ言っても言い足りないくらい偉大な人だったんですが、一般にはそれほど知名度の高いヒトではないので、少し説明しますが、簡単に言うと、コンガ奏者です。と、同時に、バンド・リーダーとして、数々の名盤を作りまくって来た、ニューヨーク・ラテン界の張本勲のようなヒトです。(「~喝ッ!」とは言わないと思うが)
レイ・バレットの偉大なトコロは、まぁ、当たり前のハナシなんですが、カッコいい音楽を作り続けたトコロですね。50年以上!!!
ニューヨーク・ラテンの屋台骨。
(リスペクトと哀悼の意を込めて申し上げますが)ホントウにスゲェエエエエエッッ!!!!!ミュージシャンでした。
50年代はマンボを支え、同じ時期に、バード・バップ全盛のジャズ名盤にも多数参加し、60年代からは、NYラテンの牽引車。チャランガ、ブーガルーから、ラテン・ジャズまで。70年代には、ラテン・フュージョンや、ラテン・ファンクなんてやってしまうし、桁外れで旺盛な創作意欲。まさに巨人。
そして、モチロン、サルサの最前線で、強力なハード・サルサを量産し、ファニア・オールスターズ(Fania All Stars)の中心メンバーとして、世界にサルサを広めた立役者でもありまスね。
ヒット曲というコトで言うと、1962年の「El Watusi」が一番有名かもしれません。R&Bチャートで、20位以内とかいう、そんくらいのヒットなんですが、オリヴァー・ストーンの「JFK」でも、1963年の夏を回想するシーンで使われていたんで、62~63年のアメリカを象徴させるくらいには知られている曲ってコトでしょう。
レイ・バレットのリーダー・アルバムは、多分40~50枚くらいはあると思いますんで、全部集めるのは大変です。アタクシも20枚程度しか持ってないんですが、特にオススメなのを幾つか挙げておきます。
「Senor 007」(1965)

タイトル通り、「007」の音楽を粋でイナセなラテンで!
チャランガとマンボとジャズが混じって、その上でCTI的な感覚も在るような無いような。
いずれにしろCOOOOL!な一枚。
アホなジャケットも最高。
「Acid」(1967)

ラテン・ブーガルー・ニューヨーク!!!!!な一枚。
B級って言葉が似合うブーガルーなのに、叩き付ける如く鋭利な音楽性。
ありえないカッコ良さ!!!!!
ブーガルーの金字塔!!!
「Hard Hands」(1968)

JBっぽいラテン・ソウルとサルサが半々な構成。
しかし、コレまた、恐ろしいまでに鋭い、切れまくりの内容!!!
スっげぇーっぜ!!!
何というカッコ良さ!!!
息つくヒマなし!
本当に人間ワザなのか?
「Que Viva La Musica」(1972)

何と言っても、「Cocinando」を収録しているので、絶対外せない一枚。
サルサの絶頂期を象徴する一枚ってことで、さぁさ、ヨござんすね、お立ち会い。
「Indestructible」(1973)

サルサ王道ど真ん中名盤!!!
これがサルサじゃぁぁああああっっっ!!!な一枚。
ステキなジャケットに笑みもコボレますね。
「Can You Feel It」(1978)

ラテン・ディスコ・ソウル・ニューヨーク!!!
踊れぇぇえええッッ、なアルバム。
気持ちよか~!!!
「Rican/Struction」(1979)

アフロ・ラテン・ニューヨークなスゲぇ一枚!!!!!
ニューヨーク・ハード・サルサの最高峰。最高傑作。
とアタクシは思っております。
シャープなリズム! テンション・バリバリの尖った和声! 狂ったようなハイテンション!
聴かずに死ねるか!
いつもながらシュールなジャケット。
(手をケガしたから、こんなジャケットなんだそうで・・・)
「Handprints」(1991)

割と影の少ない、コンテンポラリー・アメリカなラテンジャズ・アルバム。
しかし、当然ながら鼻血ポイント多数!!!
気を付けて聴け!!!
「Trancedance」(2000)

コレぞラテンとジャズのイイトコ取り。
最高のラテン・ジャズ。
クール!スムース!エキサイティング!
陰影に富みまくった超絶COOOOOLミュージック!!!
なんて贅沢な音楽なんでしょ!
これだけじゃないのヨ、名盤の数々!!!!!
とにかく、スンげぇ音楽を作り続けた偉大なレイ・バレットに、黙祷ぉぉおおおッ!!!!!