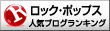ボビー・ヴァレンティン(Bobby Valentin)
「Rey Del Bajo」(1974)
クールなニューヨーク的佇まいと、お気楽ノリのカリブが見事に混在。
なんですが。
個人的にはニューヨーク的クール・ファンキー系サルサにイチコロよ、なのでありました。
こういうサルサからは、ニューヨーク・ラテンはジャズやソウルと物理的にも音楽的にも隣り合わせだという事を如実に感じ取れます。
ホーン・セクションでサックスが大活躍するのも、やはりジャズ的に都会感覚な感じがしますし、ピアノの、特にソロにおける和声はもっとハッキリと「ジャズ的」を感じると思います。ジャズ好きの友人にココラ辺を聴かせると、ピアノがカッコいいねぇ~、と大概シビレテ動かなくなります。(リズム的には、流石にラテンなのでもっとエグイ事をヤリマスが。)
しかし、かっこイーネっ!
特に好きなのが下記の二曲!
「Codazos」。クールに細かく刻むパーカッションに乗るダイナミックなホーンセクションと、ラッパやサックスのソロ。見事にクッキ~ン!ベース・ソロもかな~り痺れさせクレマス!
「Coco Seco」。ソウル・ラテン最高の一曲。ギターやドラムも入り、よりソウルなサウンド。大気圏離脱直前でスペイシー一歩手前のファンキー加減。最高。
そんな、スウィンギング・ファンキー・サルサ。貴方に捧げるアフロ・ヘアーとこの一枚。なモンで、よ~ろし~くね~。
「Rey Del Bajo」(1974)
クールなニューヨーク的佇まいと、お気楽ノリのカリブが見事に混在。
なんですが。
個人的にはニューヨーク的クール・ファンキー系サルサにイチコロよ、なのでありました。
こういうサルサからは、ニューヨーク・ラテンはジャズやソウルと物理的にも音楽的にも隣り合わせだという事を如実に感じ取れます。
ホーン・セクションでサックスが大活躍するのも、やはりジャズ的に都会感覚な感じがしますし、ピアノの、特にソロにおける和声はもっとハッキリと「ジャズ的」を感じると思います。ジャズ好きの友人にココラ辺を聴かせると、ピアノがカッコいいねぇ~、と大概シビレテ動かなくなります。(リズム的には、流石にラテンなのでもっとエグイ事をヤリマスが。)
しかし、かっこイーネっ!
特に好きなのが下記の二曲!
「Codazos」。クールに細かく刻むパーカッションに乗るダイナミックなホーンセクションと、ラッパやサックスのソロ。見事にクッキ~ン!ベース・ソロもかな~り痺れさせクレマス!
「Coco Seco」。ソウル・ラテン最高の一曲。ギターやドラムも入り、よりソウルなサウンド。大気圏離脱直前でスペイシー一歩手前のファンキー加減。最高。
そんな、スウィンギング・ファンキー・サルサ。貴方に捧げるアフロ・ヘアーとこの一枚。なモンで、よ~ろし~くね~。