人として生まれたからには、時に、フニャけたサルサを聴かねばなるまい。
そうだ!フニャけたサルサを聴こう!
ある日、そう思い立ちまして、ある時期のフニャけたサルサ(その筋の専門用語では「サルサ・ロマンティカ」と言います)の代表的シンガー、フランキー・ルイスのCDを買いに行ったのですが、コレがまた、見事に売ってねぇンです。あんだけ一世を風靡したのにねぇ。(風靡されたのは日本でない地域ですが)
と、そんなことを思いながら数ヶ月。
したっけ、昨日、渋谷のタワレコでコレを見つけまして。
フランキー・ルイス(Frankie Ruiz)
『Serie Top 10』
もぉ、素晴らしくフニャけたベスト盤だと言うことがすぐ分かる、最高に適切なジャケにワタシの目はペグ・アタッチよ。いや、釘付けよ。
で、値段もフニャけてまして、なんと税込みで1,250円です。
当然、速攻でゲットです。
で、聴きましたが、意外とフニャけてません。
勿論、ロマンティカっすから、強烈に前のめりでグルーヴするというもんじゃナイですし、緊張感ビシビシという線でも無くって、当たり前に甘口サルサなんですが、案外と大甘じゃないんですね。
キラキラ・シンセによる味付けもないし。
サルサだから当然リズムはシャキっとしてるし。
まぁ、でもやっぱりキャッチーなサビとかイントロが、らしいと言えばらしい、ですなぁ。ホーンの響きがソフトなのも、ロマンティカなんでしょうなぁ。とか思いつつ、あっと言う間に聴き終わりまして、コレはコレで中々に良いモノであるなぁと思いましたが、やはり、もっとフニャけたサルサを改めて探さねばならないと、一方ではココロに誓った一日と相成りました。
ハイ、本日はココまで。
ぢゃ。
そうだ!フニャけたサルサを聴こう!
ある日、そう思い立ちまして、ある時期のフニャけたサルサ(その筋の専門用語では「サルサ・ロマンティカ」と言います)の代表的シンガー、フランキー・ルイスのCDを買いに行ったのですが、コレがまた、見事に売ってねぇンです。あんだけ一世を風靡したのにねぇ。(風靡されたのは日本でない地域ですが)
と、そんなことを思いながら数ヶ月。
したっけ、昨日、渋谷のタワレコでコレを見つけまして。
フランキー・ルイス(Frankie Ruiz)
『Serie Top 10』
もぉ、素晴らしくフニャけたベスト盤だと言うことがすぐ分かる、最高に適切なジャケにワタシの目はペグ・アタッチよ。いや、釘付けよ。
で、値段もフニャけてまして、なんと税込みで1,250円です。
当然、速攻でゲットです。
で、聴きましたが、意外とフニャけてません。
勿論、ロマンティカっすから、強烈に前のめりでグルーヴするというもんじゃナイですし、緊張感ビシビシという線でも無くって、当たり前に甘口サルサなんですが、案外と大甘じゃないんですね。
キラキラ・シンセによる味付けもないし。
サルサだから当然リズムはシャキっとしてるし。
まぁ、でもやっぱりキャッチーなサビとかイントロが、らしいと言えばらしい、ですなぁ。ホーンの響きがソフトなのも、ロマンティカなんでしょうなぁ。とか思いつつ、あっと言う間に聴き終わりまして、コレはコレで中々に良いモノであるなぁと思いましたが、やはり、もっとフニャけたサルサを改めて探さねばならないと、一方ではココロに誓った一日と相成りました。
ハイ、本日はココまで。
ぢゃ。











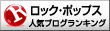









































 」というヒトにはあんまり向かない。理由は、渋くて長い曲が前半に入っているから。
」というヒトにはあんまり向かない。理由は、渋くて長い曲が前半に入っているから。

















