『船場』に内側から迫るシリーズ(笑)第2弾、本日は船場を舞台にした小説のご紹介です。
先日のブログでも書きましたが、山崎豊子氏の『ぼんち』を読み終えました。これは市川崑監督、市川雷蔵主演で映画化されていて、そちらは何度か観ています。(雷サマだから )
)
ひと言で言ってしまえば、船場の河内屋という老舗足袋問屋の旦那が、女と放蕩にふけりまくる話なのですが、初めて映画を観た時は、雷蔵サマがこの作品の映画化に熱心だった理由も、そもそも硬派な女性であるはずの山崎氏が、なぜこんなやわらかい男の話を書きたいと思ったのかも非常に不可解だったのを覚えています。
小説を読んで、その理由がやっと分かった気がしました。何百年にもわたって培われてきた『船場』という風俗を残したかったんですね。
そもそもぼんちとは何ぞや。
小説のあとがきから引用しますと、
「大阪では、良家の坊ちゃんのことを、ぼんぼんと言いますが、根性がすわり、地に足がついたスケールの大きなぼんぼん、たとえ放蕩を重ねても、ぴしりと帳尻の合った遊び方をする奴には”ぼんち”という敬愛を籠めた呼び方をします。
そんな大阪らしいニュアンスをもったぼんちは、現在の大阪(小説が書かれたのは昭和35年)から次第に姿を消しつつあるようです。それだけに、ぼんちという特異な人間像を、今、書き留めておきたいというのが、この小説を書いた私の大きな出発点です」(新潮社『ぼんち』あとがきより)
時代は大正から昭和、女系家族の中に生まれ、姑と母に押され、商い以外では家の中での居場所をなくした喜久治が外に女性を求める過程は、決して自堕落な理由だけではなく、存在するための切実さを感じます。何百年と続く旧家を守り抜くために生まれた澱のようなものが家の中に漂っていて、喜久治はその中でもがきながら必死に生きようとしているのです。ぼんちは間違いなく、船場という町が生み出した稀有な人間像です。
実際に大阪の旧家出身である山崎氏の手によって、船場でのさまざまなしきたりが小説の中に出てきます。見栄えを気にする商人らしく、訪問着や下駄の種類やら更衣(ころもがえ)の季節、火事にあった船場の商家を助けるために一番乗りしてきた近隣の商家は、その後、被災した商家が立ち直るまで、できる限りの援助をする・・・。昨今のアメリカ式の強い企業がどんどん小さい企業を吸収合併していくのとは違って、狭い船場の中で共存していくためのルールは、実はとても日本的です。そしてあの独特なイントネーションで紡ぎだされる言葉はとても美しい。
面白いのは、人間の実存的な欲求をすべて肯定していること。そもそも人間の欲望を刺激して商売をしているわけですから、彼らの夢や目標はとても実際的なんですね。例えば、「海を超えて広い世界を見てみたい」とか「人間とはなんぞやを芸術で表現してみたい」とかそういう虚な部分には興味がない。女性のぜいたくは綺麗な着物を着て、美味しいもの食べて、芝居見物。男性はそれプラスお茶屋遊びなんです。
遊びが本気になってお妾さんができるなんていうのも自然なこと。むしろ、甲斐性ある男だと名を挙げる理由になったりする。そこは全然否定しないんだけども、妾が商売に口を出したり、跡目争いでもめたりしないよう、本妻と妾の格付けはきっちりと線を引き、子供が絡むトラブルの根を断つためには、非情なこともする。四方を川に囲まれた狭い地域では、隠し事をするのも難しかったんでしょう。だったら、ルール(しきたり)を決めて、しっかり交通整理をしておけば、みなさん客商売だからみてみぬふりをしてくれる。人間の業を理解した、見事な解決方法です。
小説の中では、お妾さんが本宅にあいさつに行ったり(着物や挨拶の仕方まで決まってます!)、妾に子供が生まれたら、男の子料5万円、女の子料1万円の手切れ金を渡してすぐ、里子に出させる。その時は忘れずにへその緒をもらってこいとまで、喜久治は姑に指図され愕然とします。
読んでいて、なんてひどいと思うこともしばしば。気に染まない嫁をいびり出すところなど正直ドン引きでしたが、それぐらいしないと家は守れなかったんでしょうね。そう考えるとむげにもできない、と思うあたり、私も大人になりました(笑)。
第一次大戦後の恐慌、それに続く銀行恐慌、そして第二次世界大戦と、繁栄を誇った河内屋も時代の波に翻弄されていきます。小説は、喜久治の明るくはない未来を暗示して終わります。
映画はさらに一歩踏み込み、冒頭とラストに老年の喜久治が出てきますが、そのシーンが山崎氏の怒りを買って映画『ぼんち』は山崎氏のお気には召さなかったそうです。正直私も、そこの部分は不可解であまり好きではないのですが、映画と小説は違う媒体ですから、落としどころとしてのシーンは必要だったんでしょう。
映画には、大正時代の花街から喜久治の家へ向かう西横堀川の橋の風景が出てきますし、大阪育ちの雷蔵サマは大阪のぼんぼん、という風情がぴったりで、それはそれで見ごたえがあります。現在、西横堀川は埋め立てられ、数回に及ぶ大阪大空襲で町は半分以上焼けてしまい、現在も残っている建物は少ないですが、区画はほとんど変わってないので、今回見直していて、現在の町の風景が感じ取れるような気がしました。立派な建物の銀行も出てきて、しかもばんばん潰れて(笑)、ああ、こういうのがカフェになったりしてるのね~と納得です。
印象的だったのが、確かお妾さんの一人が亡くなったシーンで、一報を受けた喜久治こと雷サマが着物の帯を結びながら慌てて出かけようとするところ。何でもない仕草なんだけど、雷サマの帯さばきのスムーズさと動きの美しさに、思わずため息が出てしまいました。こういう日本独特の風俗はどんどん消えていきますね・・・。
山崎豊子氏には他に『女系家族』などの船場シリーズがあるそうです。こうした商家での人間模様が、のちに『華麗なる一族』や『白い巨塔』での利害関係のある組織での物語に発展していくんだなと思うと、山崎氏のルーツとしても興味深い作品です。
今日は、字だらけになってしまいました。明日は写真を載せたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう










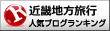

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます