ユーキャンの今年の流行語の候補に「AI」が入っていたっぽい。
もちろん人工知能のことである。
けどね。
いまさらAIなんてダサくないですかい?
そもそもAIなんて言葉は1960年代にはすでにあった。たぶん。
1980年代になると、
「〇〇のとき△△する。〇〇でないとき□□する」
といった手続き型でAIを作るのがはやったことがある。
それをエキスパートシステムと当時言っていた。
たとえば、飯を炊くのに、窯をどういうタイミングでどれだけ加熱すればうまい飯になるかを知っているエキスパートと同じレシピになるよう、内蔵タイマーと温度センサを使ってマイコンでマネして炊飯する装置ができた。
それをマイコンジャーといい、たしか1980年代末くらいに爆発的に普及した。
マイコンジャーはエキスパートシステムであり、したがってマイコンジャーはAIであり、なんとすでに各家庭の台所に1台はAIが入っているのである。
だがもはやこれはあたりまえすぎて死語。
いまさらエキスパートシステムなどと言う場合は、一見するとディープラーニング(後述)のように見えるけどディープラーニングではなく中身はエキスパートシステムだということを強調する場合にしか使われない。
そのあと人間の脳細胞をマネた方式のAIが登場した。
これをニューラルネットワークという。
あらかじめエキスパートがあらゆる規則を記述しないと使い物にならないエキスパートシステムとは違い、人間が学習するように勝手に学習させることができたり何なりという点で注目をあびた。
だが思ったより大したことができなかったため死語と化した。
さいきんディープラーニングというものが登場した。
日本語で深層学習ということもある。
中身が4段以上あるニューラルネットワークをディープラーニングという。
なぜ4段かというと、逆誤差伝播法という、かつてはやった調整方法を使うと現実的な時間内には収束しないほど段数がディープな(深い)ネットワークだという意味である。
このディープなニューラルネットワークを使いこなせる方法が確立したことで、とつぜんディープラーニングが注目を浴びるようになったということだ。
本屋にいってみるといい。
タイトルに人工知能やAIと銘打ってある本のほとんどは、だれでも読める的な超入門書か、数学が大嫌いな文科系ビジネスパーソン向けかのどちらかである。
よしじゃあワシも作ってみようかいな…というレベルのガチ勢予備軍が読むような本のほとんどは、タイトルにディープラーニングや深層学習と書いてあり、中身は行列など数式が満載である。
人工知能(AI)というと、すでにレガシーな感じがして何となくダサいと思わないだろうか?
ようはOVA全盛期(80年代後半~90年代前半)ごろのSFによくあった、意識にめざめた人工知能が暴走して人間と核戦争するみたいな創作が一世を風靡した、そんな古き良き時代のイメージが強いからだ。
じっさい、ガチ勢はAIとは言わずディープラーニングと言っている。
あえてAIという場合はディープラーニングといっても伝わらない一般人に対して説明する場合だけだ。
さあ、あなたも意識高い系またはガチ勢予備軍と思われたいなら、明日からAIとは言わずディープラーニングと言おう。
ただ、ホンモノのガチ勢が寄ってきて濃ゆい話をふってきてボロが出るかもしれんけどね(笑)。
もちろん人工知能のことである。
けどね。
いまさらAIなんてダサくないですかい?
そもそもAIなんて言葉は1960年代にはすでにあった。たぶん。
1980年代になると、
「〇〇のとき△△する。〇〇でないとき□□する」
といった手続き型でAIを作るのがはやったことがある。
それをエキスパートシステムと当時言っていた。
たとえば、飯を炊くのに、窯をどういうタイミングでどれだけ加熱すればうまい飯になるかを知っているエキスパートと同じレシピになるよう、内蔵タイマーと温度センサを使ってマイコンでマネして炊飯する装置ができた。
それをマイコンジャーといい、たしか1980年代末くらいに爆発的に普及した。
マイコンジャーはエキスパートシステムであり、したがってマイコンジャーはAIであり、なんとすでに各家庭の台所に1台はAIが入っているのである。
だがもはやこれはあたりまえすぎて死語。
いまさらエキスパートシステムなどと言う場合は、一見するとディープラーニング(後述)のように見えるけどディープラーニングではなく中身はエキスパートシステムだということを強調する場合にしか使われない。
そのあと人間の脳細胞をマネた方式のAIが登場した。
これをニューラルネットワークという。
あらかじめエキスパートがあらゆる規則を記述しないと使い物にならないエキスパートシステムとは違い、人間が学習するように勝手に学習させることができたり何なりという点で注目をあびた。
だが思ったより大したことができなかったため死語と化した。
さいきんディープラーニングというものが登場した。
日本語で深層学習ということもある。
中身が4段以上あるニューラルネットワークをディープラーニングという。
なぜ4段かというと、逆誤差伝播法という、かつてはやった調整方法を使うと現実的な時間内には収束しないほど段数がディープな(深い)ネットワークだという意味である。
このディープなニューラルネットワークを使いこなせる方法が確立したことで、とつぜんディープラーニングが注目を浴びるようになったということだ。
本屋にいってみるといい。
タイトルに人工知能やAIと銘打ってある本のほとんどは、だれでも読める的な超入門書か、数学が大嫌いな文科系ビジネスパーソン向けかのどちらかである。
よしじゃあワシも作ってみようかいな…というレベルのガチ勢予備軍が読むような本のほとんどは、タイトルにディープラーニングや深層学習と書いてあり、中身は行列など数式が満載である。
人工知能(AI)というと、すでにレガシーな感じがして何となくダサいと思わないだろうか?
ようはOVA全盛期(80年代後半~90年代前半)ごろのSFによくあった、意識にめざめた人工知能が暴走して人間と核戦争するみたいな創作が一世を風靡した、そんな古き良き時代のイメージが強いからだ。
じっさい、ガチ勢はAIとは言わずディープラーニングと言っている。
あえてAIという場合はディープラーニングといっても伝わらない一般人に対して説明する場合だけだ。
さあ、あなたも意識高い系またはガチ勢予備軍と思われたいなら、明日からAIとは言わずディープラーニングと言おう。
ただ、ホンモノのガチ勢が寄ってきて濃ゆい話をふってきてボロが出るかもしれんけどね(笑)。










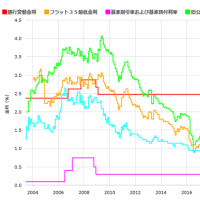
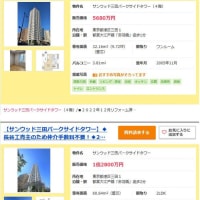
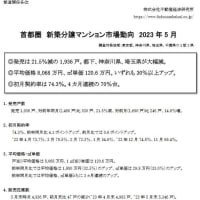
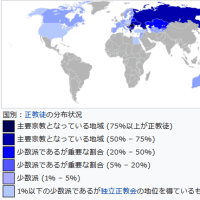











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます