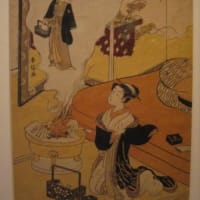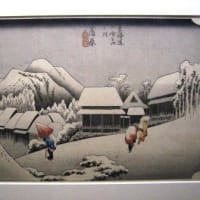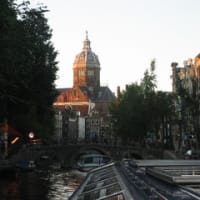モダン・パラダイス
大原美術館+東京国立近代美術館 東西名画の饗宴
2006年8月15日~10月15日
東京国立近代美術館
大原美術館と東京国立近代美術館の所蔵作品による、夢のコラボレーション。
TAKさんのBLOGで予習をして、戦々恐々として東京国立近代美術館に向かいました。
I.光あれ
菱田春草《四季山水》(ca.1909)(T):明るいカラフルな四季山水。樹木の細かい表現が繊細。
このほかの東京国立近代美術館の作品では、写真の作品に目がいく
山中信夫《東京の太陽(4)》《マンハッタンの太陽(31)》(1980-81)
杉本博司《カリブ海 ジャマイカ》(1980)、《日本海 隠岐》(1987)
大原美術館の作品は、豪華絢爛。
アンリ・マティス《エトルター川下の絶壁》(1920)
ブリジット・ライリー《花の精》(1976);カラフルな線がすこし波を打って画面いっぱいに拡がります。
児島虎二郎《ベゴニアの畠》(1910);日本人にとって西欧の夏の光は眩しいという感覚でしょうか?
カミュー・ピサロ《りんご採り》(1886);ほのかな光を木陰に見つける。
ジョバンニ・センガンティーニ《アルプスの真昼》(1892);Bunkamuraで開催された「スイス・スピリッツ 山に魅せられた画家たち」は見にいきませんでしたので、センガンティーニの作品は多分はじめて。
ポール・シニャック《オーヴェルシーの運河》(1906)
アルベール・マルケ《マルセイユの港》(1916);
マルケ(1875-1947)は、Wikipediaによれば、「19世紀~20世紀のフランスの画家。ギュスターヴ・モローの指導を受ける。ここで同窓生のマティス、ルオーらと知り合った。 後にフォーヴィスムのグループに加わるが、マルケの作風は激しいデフォルメや非現実的な色彩を用いない穏健なものである。派手さや革新性はないが、グレーや薄い青を基調とした落ち着いた色彩と穏やかなタッチで、パリの街や港の風景などを描いた。」とのこと。
Ⅱ.まさぐる手・もだえる空間
白木ゆり《Sonic(A)》(1998)《Sound-28》(2000); この展覧会でなければ見逃していたかもしれません。白地に細い灰黒色の線で画面を覆っています。白木ゆり氏(1966-)の作品には、日本人の女性的な感覚が画面を覆っているというのが、この展覧会の「まさぐる手・もだえる空間」という視点で見た感想。でもよく考えてみれば、平安以来の料紙の模様・感覚です。今年のはじめにも日高理恵子さんに魅せられたましたが、私は女性的な感覚の作品が好きだということでしょうか?
李禹煥Lee Ufan《線より》カラフルな線が縦縞に描かれます。上は着色、下は色が消えます。この作品は、李禹煥の作品ではじめて好きになりました。
ピエール・スーラージュ《絵画》(1959)
横山操《塔》(1957)
黒で力強さを表したとき、書跡の表現と重なってきます。でもこれらのモダンアートでは、力強さしか表現できないのではと、ちょっと疑問。
ここまで来てハタと納得。まさぐる手って書跡と同じ。もっとシンプル?書跡では、画面を切り裂いたりはしませんが。
Ⅲ.こころの形
このパートは、東京国立近代美術館と大原美術館の作品の饗宴。代表作が対になって展示されています。
高村光太郎 《腕》(1917-19、大原)《手》(1918)
関根正二《三星》(1919)《信仰の悲しみ》(1918、大原)
中村彝《エロシェンコ氏の像》(1920)《頭蓋骨をもてる自画像》(1923、大原);キリスト教への信仰を感じさせます。
堂本右美 Kanashi-11(2004);不思議な感覚の表現です。青色の世界に「未知との遭遇」のような円盤が描かれています。なぜ、この作品がこの部屋に展示されているのか。
小出樽重《ラッパを持てる少年》(1923)
岸田劉生 《麗子肖像(麗子五歳之像)》(1918)
アンリ・マティス《画家の娘-マティス嬢の肖像》(1917-18、大原);8月にやはり1917年のマティスの肖像画を鑑賞しました。マティスのこの頃は、肖像画が多いのでしょうか?
IV.夢かうつつか?
ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ《幻想》(1866、大原);この2月にパリのオルセーで見ていらいファンです。
ギュスターブ・モロー《雅歌》(1893、大原)
ジョルジョ・デ・キリコ《ヘルクトールとアンドロマケーの別れ》(1918、大原)
古賀春江《深海の情景》(1933、大原)
イブ・タンギー《聾者の耳》(1933)
戦争画が何点か。藤田嗣治《決戦ガタルカナル》はこの間藤田嗣治展で見たばかりでしたし、靉光は常設展でよく眺めている。TAKさんやとらさんのBLOGで予習をしていたので、ジャン・フォートリエやフルーデンスライヒ・フンデルトワッサー(百水さん)も成る程と思いながら鑑賞することができました。フルーデンスライヒ・フンデルトワッサーは、カラフルですね。戦争画が主題かは、ぱっと見ただけでは判らないですね。
国吉康夫《飛び上がろうとする頭のない馬》(1945、大原)
ジャン・フォートリエ《人質》(1944、大原)
パブロ・ピカソ《頭蓋骨のある静物》(1942、大原)
藤田嗣治《決戦ガタルカナル》(1944)
フルーデンスライヒ・フンデルトワッサー《血の雨の中の家々-あるオーストリア・ユダヤ人を慟哭させた絵》(1961、、大原)
靉光《眼のある風景》(1938)
V.楽園へ
ワリシー・カンディンスキー《突端》(1920、大原)
ジョアン・ミロ《夜のなかの女たち》(1946、大原)
東松照明《「光る風・沖縄より」小浜島》(1977)、《「光る風・沖縄より」波照間島(1979)、《「光る風・沖縄より」阿嘉島(1973)》
など
ピエール・オーギュスト・ルノワール《泉による女》(1914、大原)
土田麦僊《湯女》(1918);
ポール・ゴーギャン《かぐわしき大地》(1892、大原)
萬鉄五郎《裸体美人》(1912)
トーマス・シュトゥルート《パラダイス13屋久島日本》(1999)
岡村桂三郎《黄象05-1》(2005)
など
終わってみれば、大原美術館名品展+現代絵画入門+菱田春草《四季山水》+土田麦僊《湯女》が一緒に楽しめる展覧会といったところでしょうか。もう一度訪問したいと思います。
大原美術館+東京国立近代美術館 東西名画の饗宴
2006年8月15日~10月15日
東京国立近代美術館
大原美術館と東京国立近代美術館の所蔵作品による、夢のコラボレーション。
TAKさんのBLOGで予習をして、戦々恐々として東京国立近代美術館に向かいました。
I.光あれ
このほかの東京国立近代美術館の作品では、写真の作品に目がいく
大原美術館の作品は、豪華絢爛。
マルケ(1875-1947)は、Wikipediaによれば、「19世紀~20世紀のフランスの画家。ギュスターヴ・モローの指導を受ける。ここで同窓生のマティス、ルオーらと知り合った。 後にフォーヴィスムのグループに加わるが、マルケの作風は激しいデフォルメや非現実的な色彩を用いない穏健なものである。派手さや革新性はないが、グレーや薄い青を基調とした落ち着いた色彩と穏やかなタッチで、パリの街や港の風景などを描いた。」とのこと。
Ⅱ.まさぐる手・もだえる空間
黒で力強さを表したとき、書跡の表現と重なってきます。でもこれらのモダンアートでは、力強さしか表現できないのではと、ちょっと疑問。
ここまで来てハタと納得。まさぐる手って書跡と同じ。もっとシンプル?書跡では、画面を切り裂いたりはしませんが。
Ⅲ.こころの形
このパートは、東京国立近代美術館と大原美術館の作品の饗宴。代表作が対になって展示されています。
IV.夢かうつつか?
戦争画が何点か。藤田嗣治《決戦ガタルカナル》はこの間藤田嗣治展で見たばかりでしたし、靉光は常設展でよく眺めている。TAKさんやとらさんのBLOGで予習をしていたので、ジャン・フォートリエやフルーデンスライヒ・フンデルトワッサー(百水さん)も成る程と思いながら鑑賞することができました。フルーデンスライヒ・フンデルトワッサーは、カラフルですね。戦争画が主題かは、ぱっと見ただけでは判らないですね。
V.楽園へ
など
など
終わってみれば、大原美術館名品展+現代絵画入門+菱田春草《四季山水》+土田麦僊《湯女》が一緒に楽しめる展覧会といったところでしょうか。もう一度訪問したいと思います。