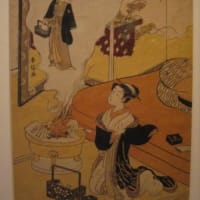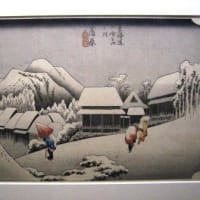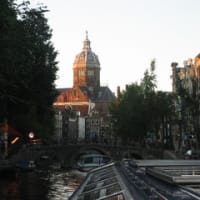国宝 法隆寺伝来 細字法華経
この1点が見たいがために年末の24日に慌てて、東博の法隆寺宝物館の建物に向かった。「長安宮廷写経」の絶品である敦煌経「妙法蓮華経巻第二」(675)などを三井記念美術館(記録はこちら)で拝見して、唐代の写経の別のものが見たくなった。こちらは聖徳太子所持との伝来。細字で32文字を一行に書く様は見事だが、やはり、少し時代が下るためかそれほど謹厳ではない。また経筒も拝見できたが竹製の筒であった。竹製ものが千年以上も伝来していることを目の前にすると感慨深い。(木簡など例は多いのだが)
国宝 細字法華経 唐時代・長寿3年(694) N-7
国宝 経筒 唐時代・7~8世紀 N-7付属
展示期間 2006/10/24~ 2006/12/24(終了)
http://www.tnm.jp/jp/servlet/Con?pageId=B07&processId=00&event_id=2576&event_idx=1&dispdate=2006/10/24
e国宝から(
http://www.emuseum.jp/cgi/pkihon.cgi?SyoID=3&ID=w098&SubID=s000)
中国・魏晋南北時代の鳩摩羅什(くまらじゅう 344-413)が、406年に訳した法華経を、唐時代の694年に李元恵(りげんけい)が書写したものである。李元恵は長安の人であるが、伝記の詳細は不明。
麻の繊維をすいた麻紙(まし)39枚を継ぎ、1紙56行に淡い墨の罫線を引き、1行32字詰に1部7巻を書写している。全長は20メートルに及ぶ。文字は、背をやや低くした細字で、書き出しは精細で謹直だが、巻がすすむにつれて速写となり、字体はくずれる。唐代の書写年代の判明すること、細字で法華経全巻を1部に写したものとして貴重である。
撥(ばち)形の軸首に碧玉をはめ込み、香木を二つ割りして内側をくりぬいた経箱に納められていた。永く法隆寺に伝来し、聖徳太子所持と伝えられ、「御同朋経」(ごどうぼうきょう)という俗称がある。太子は中国の高僧慧思禅師(えしぜんじ)の生まれ変わりで、前世に中国の寺院の仲間(同朋)が用いていたこの経典を、使いを派遣して取り寄せた、という伝説に基いている。
この1点が見たいがために年末の24日に慌てて、東博の法隆寺宝物館の建物に向かった。「長安宮廷写経」の絶品である敦煌経「妙法蓮華経巻第二」(675)などを三井記念美術館(記録はこちら)で拝見して、唐代の写経の別のものが見たくなった。こちらは聖徳太子所持との伝来。細字で32文字を一行に書く様は見事だが、やはり、少し時代が下るためかそれほど謹厳ではない。また経筒も拝見できたが竹製の筒であった。竹製ものが千年以上も伝来していることを目の前にすると感慨深い。(木簡など例は多いのだが)
国宝 細字法華経 唐時代・長寿3年(694) N-7
国宝 経筒 唐時代・7~8世紀 N-7付属
展示期間 2006/10/24~ 2006/12/24(終了)
http://www.tnm.jp/jp/servlet/Con?pageId=B07&processId=00&event_id=2576&event_idx=1&dispdate=2006/10/24
e国宝から(
http://www.emuseum.jp/cgi/pkihon.cgi?SyoID=3&ID=w098&SubID=s000)
中国・魏晋南北時代の鳩摩羅什(くまらじゅう 344-413)が、406年に訳した法華経を、唐時代の694年に李元恵(りげんけい)が書写したものである。李元恵は長安の人であるが、伝記の詳細は不明。
麻の繊維をすいた麻紙(まし)39枚を継ぎ、1紙56行に淡い墨の罫線を引き、1行32字詰に1部7巻を書写している。全長は20メートルに及ぶ。文字は、背をやや低くした細字で、書き出しは精細で謹直だが、巻がすすむにつれて速写となり、字体はくずれる。唐代の書写年代の判明すること、細字で法華経全巻を1部に写したものとして貴重である。
撥(ばち)形の軸首に碧玉をはめ込み、香木を二つ割りして内側をくりぬいた経箱に納められていた。永く法隆寺に伝来し、聖徳太子所持と伝えられ、「御同朋経」(ごどうぼうきょう)という俗称がある。太子は中国の高僧慧思禅師(えしぜんじ)の生まれ変わりで、前世に中国の寺院の仲間(同朋)が用いていたこの経典を、使いを派遣して取り寄せた、という伝説に基いている。