簿記用語の一つに「諸口」というのがあります。
どう読むと思いますか?
ショコウ(音読み)、モロクチ(訓読み)。どちらも不正解。重箱読みをして「ショクチ」と読みます。「残高」も重箱読みですね(あれ、「音読み」自体が重箱読みじゃないですか)。
この諸口、取引を仕訳帳に記入する方法のところで扱いますので、簿記の授業では、比較的最初の方で出てくると考えてもいいでしょう。(ややレベルが上がると特殊仕訳帳というところで、また出てきます。)
取引を仕訳帳に記入する場合に、勘定科目が2つ以上あるときには、勘定科目の上に諸口と書きます。
たとえば、次のような具合です。
「3月5日 商品5,000円を仕入れ、代金のうち、2,000円は現金で支払い、残額は掛とした。」
仕訳帳に記帳しないで、仕訳だけを書く場合には次のような仕訳になりますね。
(借方)仕 入 5,000 (貸方)現 金 2,000
買掛金 3,000
ところが、これを仕訳帳に記帳するときには、次のように書くことになっています。
(仕 入) 5,000 諸 口
(現 金) 2,000
(買掛金) 3,000
もっとも、仕訳だけを書く場合にも「諸口」を使ってもいいと思われますが、そのように教えることは、まずありません。
では、なぜ仕訳帳にはこのように書くのか。
実は、明確な根拠はないようです。いえることは「簿記教育の慣習だから・・・。」
ちょっと気になって手もとにある簿記の本をいろいろ読んでみたのですが、やっぱり明確な根拠は見あたりませんでした。
中村忠先生は、比喩を使って次のように説明しています。
「これは、貸方勘定が複数であることを注意させるために書かせるのである。ちょうど電車の運転士が発車のときに『出発進行』と唱えるように。」(中村忠『簿記の考え方・学び方(五訂版)』税務経理協会、2006年、p.134)
中村先生がいうには、アメリカにはこういった用語も処理もなく(p.125)、そのルーツはイギリスにあるといわれるが、イギリスの書物をあたってもそれらしきものは出てこないと述べています(p.135)。そして「こんな目印はなくても一向に困らないのであるから、なくしてしまったほうがよいと私は考える。」(p.135)とさえ、述べています。
思えば、最初に簿記を勉強したとき、「この諸口というのは勘定科目なのかどうか」悩んだことがあります。しかも「どんなとき諸口を付けるのか」ということも悩んだ記憶があります。(講義を聴いていない証拠ですね。苦笑)
新年度に向けて講義録を作成していますが、今日は、ちょうど諸口を使う内容の講義録をまとめていましたので、改めて考えてしまいました。
どう読むと思いますか?
ショコウ(音読み)、モロクチ(訓読み)。どちらも不正解。重箱読みをして「ショクチ」と読みます。「残高」も重箱読みですね(あれ、「音読み」自体が重箱読みじゃないですか)。
この諸口、取引を仕訳帳に記入する方法のところで扱いますので、簿記の授業では、比較的最初の方で出てくると考えてもいいでしょう。(ややレベルが上がると特殊仕訳帳というところで、また出てきます。)
取引を仕訳帳に記入する場合に、勘定科目が2つ以上あるときには、勘定科目の上に諸口と書きます。
たとえば、次のような具合です。
「3月5日 商品5,000円を仕入れ、代金のうち、2,000円は現金で支払い、残額は掛とした。」
仕訳帳に記帳しないで、仕訳だけを書く場合には次のような仕訳になりますね。
(借方)仕 入 5,000 (貸方)現 金 2,000
買掛金 3,000
ところが、これを仕訳帳に記帳するときには、次のように書くことになっています。
(仕 入) 5,000 諸 口
(現 金) 2,000
(買掛金) 3,000
もっとも、仕訳だけを書く場合にも「諸口」を使ってもいいと思われますが、そのように教えることは、まずありません。
では、なぜ仕訳帳にはこのように書くのか。
実は、明確な根拠はないようです。いえることは「簿記教育の慣習だから・・・。」
ちょっと気になって手もとにある簿記の本をいろいろ読んでみたのですが、やっぱり明確な根拠は見あたりませんでした。
中村忠先生は、比喩を使って次のように説明しています。
「これは、貸方勘定が複数であることを注意させるために書かせるのである。ちょうど電車の運転士が発車のときに『出発進行』と唱えるように。」(中村忠『簿記の考え方・学び方(五訂版)』税務経理協会、2006年、p.134)
中村先生がいうには、アメリカにはこういった用語も処理もなく(p.125)、そのルーツはイギリスにあるといわれるが、イギリスの書物をあたってもそれらしきものは出てこないと述べています(p.135)。そして「こんな目印はなくても一向に困らないのであるから、なくしてしまったほうがよいと私は考える。」(p.135)とさえ、述べています。
思えば、最初に簿記を勉強したとき、「この諸口というのは勘定科目なのかどうか」悩んだことがあります。しかも「どんなとき諸口を付けるのか」ということも悩んだ記憶があります。(講義を聴いていない証拠ですね。苦笑)
新年度に向けて講義録を作成していますが、今日は、ちょうど諸口を使う内容の講義録をまとめていましたので、改めて考えてしまいました。










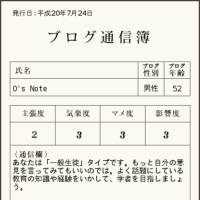

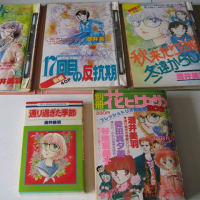






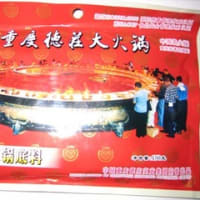
じゃないんですね