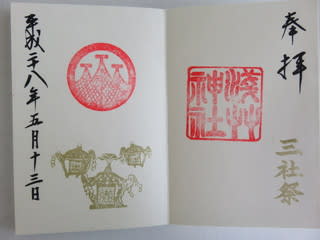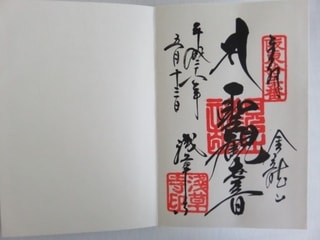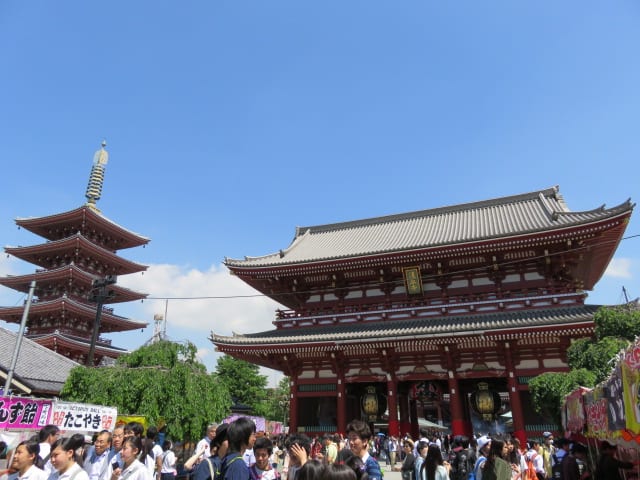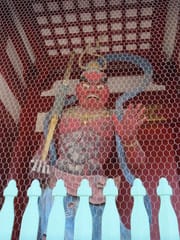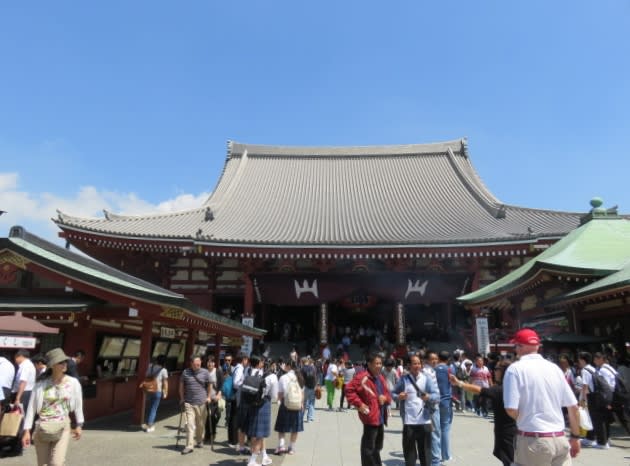浅草寺の隣りの 「浅草神社」にも寄ってきました。
東京のお祭り「三社祭」の名は聴いたことがありますが
偶然、「三社祭」が始まっていて、しかも浅草神社のお祭りだとか
周りを見れば、なるほど提灯や幟が上がってます。


その提灯の中に、聞き覚えのある名前が
「三浦布美子」さん、テレビで見たことあります、確か。

ポスターによると、13日は
☆大行列
☆びんざさら舞奉納 (都指定無形民俗文化財)
☆各町神輿神霊入れの儀
があるとか

神輿庫
お隣の浅草寺の御本尊は 「聖観世音菩薩」 ですが、
この観音様を宮戸川(隅田川)から網で引き揚げた漁師兄弟と
その観音様を篤く供養した郷司、
この方達が浅草神社に祀られている三神です
土師真中知命(はじのなかとものみこと)
桧前浜成命(ひのくまはまなりのみこと)
桧前竹成命(ひのくまたけなりのみこと)
「三社様」 と親しみを込めて呼ばれているそうです。
また、浅草神社には東照宮(徳川家康)と大国主命が合祀されています

拝殿 (重要文化財)
現存の社殿は徳川家光の寄進で慶安2年(1649)に完成したもので
昭和36年に拝殿・幣殿・本殿が国の重要文化財に指定されました。

拝殿内部 、と言っても外から撮ってます
拝殿の幕に入っている紋がとても気になりました

臨時のテントにくっきりと見えます
「三網紋」
アレッ?
” 三社祭三網になるスカイツリー ”
ここでまた漁師と観音様の話になりますが
推古天皇36年(628)早朝、漁師の浜成、竹成兄弟が宮戸川(隅田川)で
漁をしていました
その日は魚は全く網にかからず、途方に暮れていると、
はからずも一体の人型像が網にかかり、
川に戻し場所を変えて網を打つものの、また網に…、
それで、人型像を持ち帰り槐(えんじゅ)の切り株に安置し、
その後、郷土の文化人土師中知に相談しました
この像は聖観世音菩薩であることを知り、
土師中知は自宅を寺とし僧となり観音像を生涯供養しました
明治維新以降寺社分離となりましたが
浅草寺と浅草観音は深い縁があるのです
あ、三網紋のことでした!
これは観音様を引き上げた漁の網の模様です(干し網)
真ん中の背の高いのが土師中知
両側が浜成、竹成で、ちょっと背の高い方が兄の浜成を表しているそうです
向かって右が高いですか?

神楽殿
この舞台で「びんさざら舞」が奉納されていたのですが
その時、御朱印頂くのに並んでいて見てないのです(ーー;)
予め、調べておけばよかったと、今回も後悔…
これがほんとの、後の祭り…

(参考写真)
びんさざらとはこんな形をしてるんですね
(何枚かの板を合わせ両側を紐で止めてある楽器)
それから、浅草は川柳発祥の地だとか
三社祭に合わせ川柳の大賞を発表していました
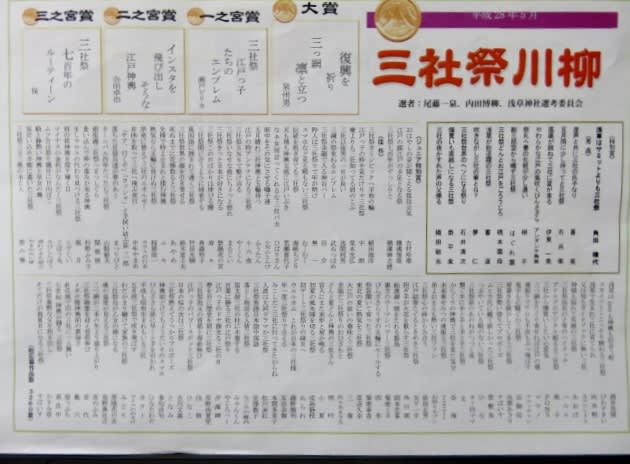
大賞
” 復興を祈り三つ網凛と立つ ” 泉州男
一之宮賞
” 三社祭江戸っ子たちのエンブレム ” 瀬戸ピリカ
二之宮賞
” インスタを飛び出しそうな江戸神輿 ” 会田卓也
三之宮賞
” 三社祭七百年のルーティーン ” 保
受賞の川柳でした
川柳は江戸時代、柄井川柳(八右衛門)が始めたとあります(からいせんりゅう)
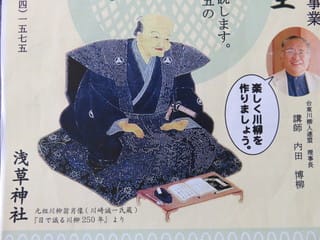 ()
()
元祖 柄井川柳
福助さんみたいですね
俳句とは違う点が幾つかありそうです
びんさざら舞の鑑賞を棒に振って頂いた御朱印
三社祭限定だそうです
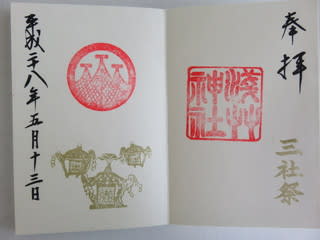
浅草神社(三社様)の御朱印
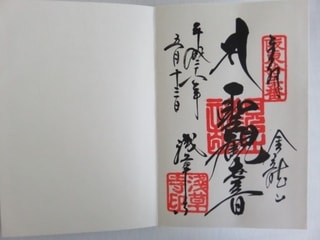
こちらは浅草寺
御朱印帳がいっぱいになり、2冊目は浅草寺で買いご朱印もここのを一番に
良い所で買えてよかった~
さて、ざっとですが古刹を訪ねました
そして、気になるものがチラチラ見えるのです

何もかも初めてのことで、上手く行けますかどうでしょう
観光マップを見る
スマホで検索する
近くに居る人に片っぱしから尋ねる
こんな風に当たって砕けてきました




















































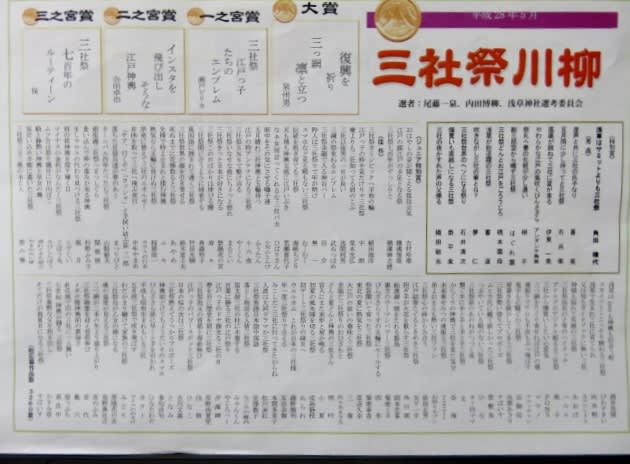
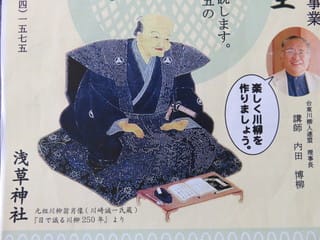 ()
()