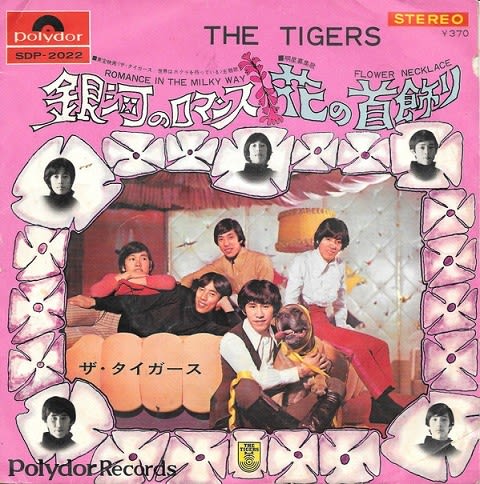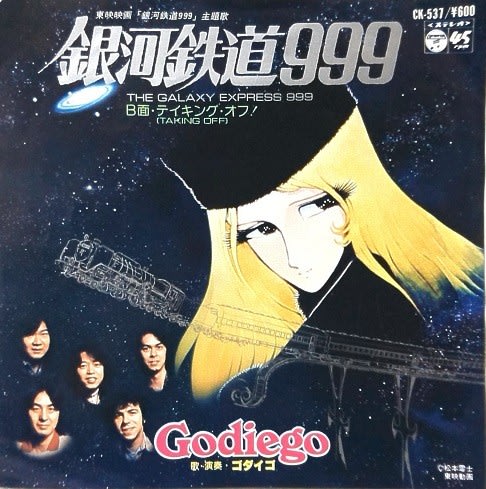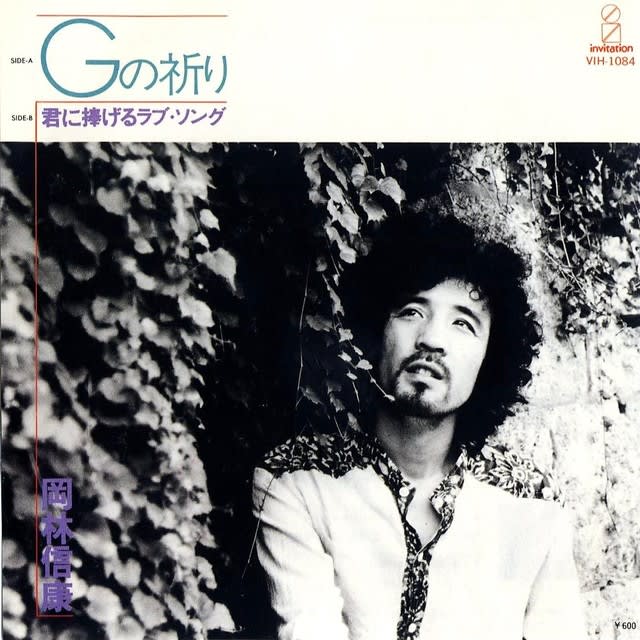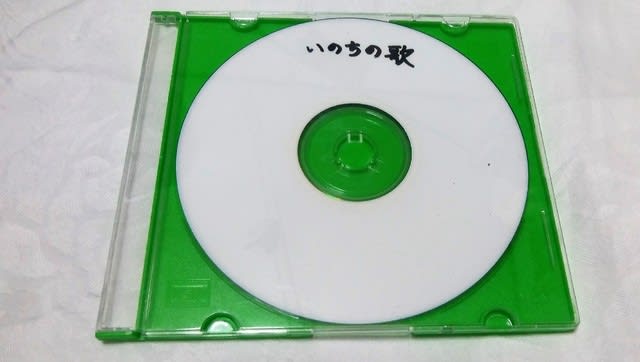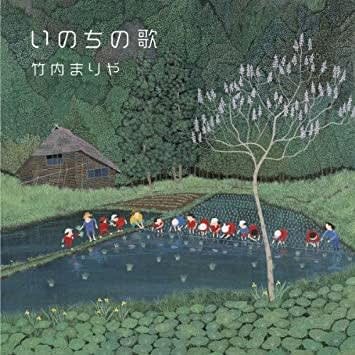最寄りのTSU…YA書店で、レンタルCDの中古品販売をやっていた。
あまりいいモノはないが、1枚300円で、5枚で1000円だという。
これは、ラッキー!と2枚組や3枚組のベスト物のCDとともに、ファンキーモンキーベイビーズの10周年記念ベスト盤「YELL」も買った。
購入理由は、今度楽天に復帰した田中将大投手の、あのころの登板ソング「あとひとつ」を聴きたくなったからだ。
気持ちよくその歌を聴いていたら、終わって次の曲になった。
そこに入っていたのが、「ヒーロー」という曲である。
最寄り駅の改札抜ければ いつもよりちょっと勇敢なお父さん…
で、1番も2番も3番も始まる歌。
それが、ファンキーモンキーベイビーズが歌った「ヒーロー」という歌。
この歌は、日本中の働くお父さんに贈られるエールのように聞こえる。
1番の詞の中には、こんな文句が続く
昨夜の疲れとアルコールがまだ残った午前6時OH
暗いニュース野菜ジュースで流し込み朝から全力疾走
きっと今日も七転八倒 でも鳴らすな10カウント
家族にとってのヒーローになる為 転んでも立ち上がるんだぜ
別に家族のヒーローになる為ではないが、転んでも立ち上がらないといけない毎日には変わりがない。
ただ、励ましてもらっていることは分かる。
2番の詞は、こんなふうになる。
毎日おんなじ時間に起きてはテレビのニュースを見る父さん
はたから見たって一見そんなに冴えない普通のサラリーマン
だっていつも家族の為 人知れずに一人で戦ってる
照れくさくって言いづらいけど がんばっているのはわかる
これ、ちょっとうれしい。
自分の子どもは、自分のことをさえないサラリーマンと思っているのだろうなあ…と思うお父さんは多いことだろう。
だが、「照れくさくって言いづらいけど がんばっているのはわかってる」なんてことを聞くと、心の中でニコニコしてしまうだろう。
3番になると、
カカア天下のお茶の間 第三のビールで乾杯しよう
明日の見えない日本の夜に それでも陽は昇るんだ
…こんなことを歌われると、見抜かれてる!と思うじゃないか。
さて、歌全体を通して、元気付けられる部分はまだあるけれど、働く父親としては、子ども側からすべてを見抜いてくれて、ありがとう!と言いたい気分になりそうだ。
今まで、父親賛歌のような歌。
浜田省吾は、「I am a Father」という歌で、父親であることの自覚と責任を歌っていたけれども、あれも父親賛歌の一つだと思う。
この歌は、息子が賛美してくれている歌だから、余計にうれしいかもしれない。
働くお父さんだという皆さん、この歌聴いて、元気出していきましょう!
あまりいいモノはないが、1枚300円で、5枚で1000円だという。
これは、ラッキー!と2枚組や3枚組のベスト物のCDとともに、ファンキーモンキーベイビーズの10周年記念ベスト盤「YELL」も買った。
購入理由は、今度楽天に復帰した田中将大投手の、あのころの登板ソング「あとひとつ」を聴きたくなったからだ。
気持ちよくその歌を聴いていたら、終わって次の曲になった。
そこに入っていたのが、「ヒーロー」という曲である。
最寄り駅の改札抜ければ いつもよりちょっと勇敢なお父さん…
で、1番も2番も3番も始まる歌。
それが、ファンキーモンキーベイビーズが歌った「ヒーロー」という歌。
この歌は、日本中の働くお父さんに贈られるエールのように聞こえる。
1番の詞の中には、こんな文句が続く
昨夜の疲れとアルコールがまだ残った午前6時OH
暗いニュース野菜ジュースで流し込み朝から全力疾走
きっと今日も七転八倒 でも鳴らすな10カウント
家族にとってのヒーローになる為 転んでも立ち上がるんだぜ
別に家族のヒーローになる為ではないが、転んでも立ち上がらないといけない毎日には変わりがない。
ただ、励ましてもらっていることは分かる。
2番の詞は、こんなふうになる。
毎日おんなじ時間に起きてはテレビのニュースを見る父さん
はたから見たって一見そんなに冴えない普通のサラリーマン
だっていつも家族の為 人知れずに一人で戦ってる
照れくさくって言いづらいけど がんばっているのはわかる
これ、ちょっとうれしい。
自分の子どもは、自分のことをさえないサラリーマンと思っているのだろうなあ…と思うお父さんは多いことだろう。
だが、「照れくさくって言いづらいけど がんばっているのはわかってる」なんてことを聞くと、心の中でニコニコしてしまうだろう。
3番になると、
カカア天下のお茶の間 第三のビールで乾杯しよう
明日の見えない日本の夜に それでも陽は昇るんだ
…こんなことを歌われると、見抜かれてる!と思うじゃないか。
さて、歌全体を通して、元気付けられる部分はまだあるけれど、働く父親としては、子ども側からすべてを見抜いてくれて、ありがとう!と言いたい気分になりそうだ。
今まで、父親賛歌のような歌。
浜田省吾は、「I am a Father」という歌で、父親であることの自覚と責任を歌っていたけれども、あれも父親賛歌の一つだと思う。
この歌は、息子が賛美してくれている歌だから、余計にうれしいかもしれない。
働くお父さんだという皆さん、この歌聴いて、元気出していきましょう!