京都二十四節気 立春
春の気配が感じられる頃 新暦二月四日~十八日(頃)
梅(立春の自然)

春、花の中でもっとも早く咲く梅は、「百花の魁(ひゃっかのさきがけ)」や「春告草(はるつげぐさ)」と呼ばれ、昔から日本人に親しまれてきました。漢文の「梅開早春」という言葉は、「梅、早春 “に”開く」と読まれることが多いようですが、禅の世界では、「梅、早春“を”開く」と読みます。「春が来たら梅が咲く」のではなく、「梅が咲くから春が来る」と考えているのです。これを人に当てはめれば、人もどう生きるかで人生が決まる、ということなのかもしれません。梅の花のように、周りを春に変えるような生き方は、理想でもあります。
初午(立春の暮らし)

2月最初の午の日は「初午」と呼ばれ、全国各地の稲荷神社で「初午祭」が営まれます。この祭りは、奈良時代の和銅4(711)年2月初午の日に、伏見稲荷大社の祭神・稲荷大神が稲荷山の三ヶ峰にご鎮座されたことにちなんだもので、昔から老若男女を問わず多くの人々が、参詣に出かけました。初午詣は「福まいり」とも呼ばれ、ご神木「しるしの杉」を受け、商売繁盛や家内安全を祈る習わしがあります。伏見稲荷大社は、平成23(2011)年、「稲荷大神ご鎮座1300年」という節目の年を迎えます。
コンセプト
四季のある国、日本。
桜が咲くこと、雨が降ること、紅葉が散ること、そして雪が降ること。
日本人は、その美しい自然の変化を、つい百年前まで、二十四の季節に分け見つめてきました。
私たち日本人が使ってきた旧暦の中では二十四の季節に沿った年中行事や風習と共に、風雅な暮らしを楽しむ工夫や知恵がありました。
それと同時に、永遠にめぐる四季の中で移ろい変わっていくものと、その変化の裏にある不変のものを感じとってきたのです。
新しいものがあふれていく現代社会のなかで古くから日本にある伝統を見つめなおすこと、それは、移ろう季節のなかから不変のものをみつけだすことと似ています。
ますます季節感が失われていくなかで、二十四節気の暦をつうじて自然の変化を敏感に感じとれる繊細な感性と伝統の素晴らしさとそれとともにある大切な文化を伝えていきたいと思います。
その四季折々の美しさに触れるとき、自然のなかから生まれてくるこの国の美しさを改めて見つめ、「美」と「伝統」にめぐり逢える誇りとよろこびを共にしていきたいと思います。
春の気配が感じられる頃 新暦二月四日~十八日(頃)
梅(立春の自然)

春、花の中でもっとも早く咲く梅は、「百花の魁(ひゃっかのさきがけ)」や「春告草(はるつげぐさ)」と呼ばれ、昔から日本人に親しまれてきました。漢文の「梅開早春」という言葉は、「梅、早春 “に”開く」と読まれることが多いようですが、禅の世界では、「梅、早春“を”開く」と読みます。「春が来たら梅が咲く」のではなく、「梅が咲くから春が来る」と考えているのです。これを人に当てはめれば、人もどう生きるかで人生が決まる、ということなのかもしれません。梅の花のように、周りを春に変えるような生き方は、理想でもあります。
初午(立春の暮らし)

2月最初の午の日は「初午」と呼ばれ、全国各地の稲荷神社で「初午祭」が営まれます。この祭りは、奈良時代の和銅4(711)年2月初午の日に、伏見稲荷大社の祭神・稲荷大神が稲荷山の三ヶ峰にご鎮座されたことにちなんだもので、昔から老若男女を問わず多くの人々が、参詣に出かけました。初午詣は「福まいり」とも呼ばれ、ご神木「しるしの杉」を受け、商売繁盛や家内安全を祈る習わしがあります。伏見稲荷大社は、平成23(2011)年、「稲荷大神ご鎮座1300年」という節目の年を迎えます。
コンセプト
四季のある国、日本。
桜が咲くこと、雨が降ること、紅葉が散ること、そして雪が降ること。
日本人は、その美しい自然の変化を、つい百年前まで、二十四の季節に分け見つめてきました。
私たち日本人が使ってきた旧暦の中では二十四の季節に沿った年中行事や風習と共に、風雅な暮らしを楽しむ工夫や知恵がありました。
それと同時に、永遠にめぐる四季の中で移ろい変わっていくものと、その変化の裏にある不変のものを感じとってきたのです。
新しいものがあふれていく現代社会のなかで古くから日本にある伝統を見つめなおすこと、それは、移ろう季節のなかから不変のものをみつけだすことと似ています。
ますます季節感が失われていくなかで、二十四節気の暦をつうじて自然の変化を敏感に感じとれる繊細な感性と伝統の素晴らしさとそれとともにある大切な文化を伝えていきたいと思います。
その四季折々の美しさに触れるとき、自然のなかから生まれてくるこの国の美しさを改めて見つめ、「美」と「伝統」にめぐり逢える誇りとよろこびを共にしていきたいと思います。















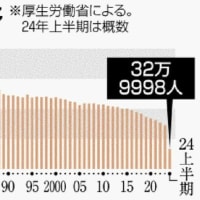
心地の良い風景でした。日本には
二四の季節がある。半月ごとの計
算になりますが、なんとなくわか
るような気がします。このことは
日本の本来の気候のお陰とも言え
ましょう。周囲を海に囲まれ、
元来海洋性の気候でありつつ、大
陸の影響を強く受ける位置関係。
その両者の糸が縦横に複雑に絡み
合って成りたっています。
このことはたぶん諸外国の方々に
は奇跡のような変化に見られる事
でしょう。
さて、今朝は肌寒い佐渡です。日
中の気温は二十度を超えることも
なさそうです。
万葉集に続く新しいシリーズです。
当然24回シリーズです。
楽しみです。
確かに外国の方には奇跡のような変化と映るかもしれないですね。
今日は久しぶりの晴れ間で、現在の気温が20度を超えています。