こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。
今朝、教室に来るとき、運動会の太鼓の音や花笠音頭が聞こえてきました。秋晴れとはいきませんが、雨にならずに良いことです。
中2の英語では、 “that”、 “when”、 “if”、 “before”、 “after” などの従属接続詞を勉強します。その従属接続詞で従属節が構成されるのですが、従属節の動詞の時制が主節の動詞の時制との関係で決まることを「時制の一致」と呼びます。
例えば、 “I know that he is busy.”(私は彼が忙しいことを知っています) の主節の動詞 “know” を過去形の “knew” にすると、従属節の動詞 “is” を過去形 “was” にして、 “I knew that he was busy.”(私は彼が忙しいことを知っていた)となります。
ところが、上に挙げた2つの例文の従属節の和訳部分は、2つとも 「彼が忙しいこと」となっていて違いはありません。(もっとも、“I knew that he was busy.” を 「私は彼が忙しかったことを知っていた」と訳して従属節の時制を和訳に反映させることもできますが)
それでは、従属接続詞 “before” の例をみてみると、例えば、 “Before I went to New York,I studied English.”(ニューヨークに行く前に、私は英語を勉強した)では、「ニューヨークに行った前に、私は英語を勉強した」とは言いません。
日本語の場合、「前」(“before”)に対しては「いく」(現在形)、 「後」(“after”)に対しては「行った」(過去形)という言い方が普通で、これは英語との大きな違いです。
この理由をマーク・ピーターセン著「日本人の英語」では、英語が「時」のことばかり気にするのに対して、日本語は「時」自体に関しては特に気にせず、いつも「相」のことを気にしているからと述べています。
これを言い換えると、英語にとっては行動と状態の時が最も大事なのに対して、日本語にとっては行動と状態の完了の程度が最も大事であるということです。
つまり、先の例文で、“Before ~”(前) であれば、~した行動の時を問わず、未だ始まらない状態を言っているので、「~した前」にはならない訳で、 “After”(後)であれば、行動の時を問わず、もう終わった状態を言っているので、「~する後」にはならないという訳です。
高校では勉強する時制も増えて、また時制の一致の例外なども勉強することになるので楽しみにしてください。
今朝、教室に来るとき、運動会の太鼓の音や花笠音頭が聞こえてきました。秋晴れとはいきませんが、雨にならずに良いことです。
中2の英語では、 “that”、 “when”、 “if”、 “before”、 “after” などの従属接続詞を勉強します。その従属接続詞で従属節が構成されるのですが、従属節の動詞の時制が主節の動詞の時制との関係で決まることを「時制の一致」と呼びます。
例えば、 “I know that he is busy.”(私は彼が忙しいことを知っています) の主節の動詞 “know” を過去形の “knew” にすると、従属節の動詞 “is” を過去形 “was” にして、 “I knew that he was busy.”(私は彼が忙しいことを知っていた)となります。
ところが、上に挙げた2つの例文の従属節の和訳部分は、2つとも 「彼が忙しいこと」となっていて違いはありません。(もっとも、“I knew that he was busy.” を 「私は彼が忙しかったことを知っていた」と訳して従属節の時制を和訳に反映させることもできますが)
それでは、従属接続詞 “before” の例をみてみると、例えば、 “Before I went to New York,I studied English.”(ニューヨークに行く前に、私は英語を勉強した)では、「ニューヨークに行った前に、私は英語を勉強した」とは言いません。
日本語の場合、「前」(“before”)に対しては「いく」(現在形)、 「後」(“after”)に対しては「行った」(過去形)という言い方が普通で、これは英語との大きな違いです。
この理由をマーク・ピーターセン著「日本人の英語」では、英語が「時」のことばかり気にするのに対して、日本語は「時」自体に関しては特に気にせず、いつも「相」のことを気にしているからと述べています。
これを言い換えると、英語にとっては行動と状態の時が最も大事なのに対して、日本語にとっては行動と状態の完了の程度が最も大事であるということです。
つまり、先の例文で、“Before ~”(前) であれば、~した行動の時を問わず、未だ始まらない状態を言っているので、「~した前」にはならない訳で、 “After”(後)であれば、行動の時を問わず、もう終わった状態を言っているので、「~する後」にはならないという訳です。
高校では勉強する時制も増えて、また時制の一致の例外なども勉強することになるので楽しみにしてください。










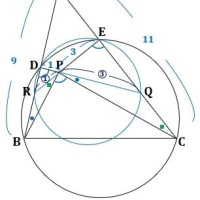
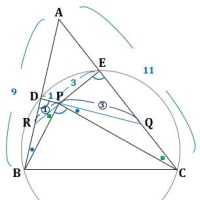
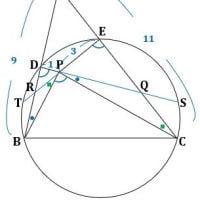
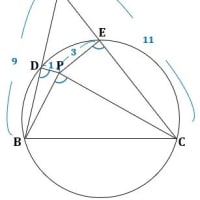



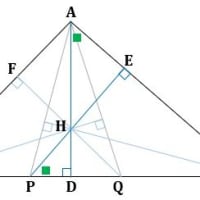
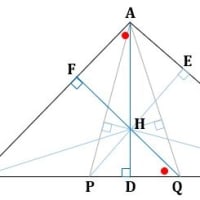
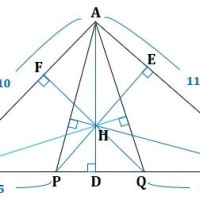
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます