都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画」 国立西洋美術館
国立西洋美術館(台東区上野公園7-7)
「ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画」
2/28-6/14
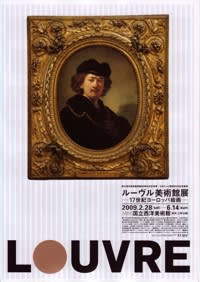
感想が遅くなりましたが、珍しくも初日に参戦してきました。国立西洋美術館で開催中の「ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画」へ行ってきました。
副題の通り、ルーヴル所蔵の17世紀絵画(約70点)を俯瞰する展覧会です。うち60点が日本初公開とのことで、毎年の如く開催されるルーヴル展に食傷気味な方も、また新鮮であったのではないでしょうか。以下、惹かれた10点を挙げてみました。

アンブロシウス・ボスハールト(父)「風景の見える石のアーチの中に置かれた花束」(1619-21)
遠景には広い海辺を望むアーチに置かれた花束が精緻なタッチで表されている。爛れるように咲くチューリップの色鮮やかな表現、もしくは少し枯れ始めた葉、さらにはアーチの上にのる昆虫などの描写は極めて写実的。また古くなったのだろうか、花瓶の中の水が仄かな緑色を帯びていた。ちなみに油彩ながらもやや光沢感のある画肌は、支持体が銅板であるからなのかもしれない。

ル・ナン兄弟「農民の家族」
何ら変哲のない農民の姿が、まるで聖家族を思わせるほどに厳粛な雰囲気をたたえている。まるで舞台を飾るように横一線に並び、憂いをたたえた視線を前へ向ける様は、こちらの心をぐさりと突き刺してきた。彼らは一体、何を訴えているのだろうか。
17世紀スペイン派「法悦の聖フランチェスコ」(1650)
痛みをこらえつつ、激しいエクスタシーにも襲われる聖フランチェスコ。充血して虚ろな目の先には神が見えるのだろうか。ドクロや聖書などは比較的細かく描かれているが、突き刺して破けた衣服や背景のグレーはかなり荒削りだった。まるでエル・グレコのよう。
ペーテル・パウル・ルーベンス「トロイアを逃れる人々を導くアイネイアス」(1602-04)
ルーベンスの壮年期の大作も一点(ユノに欺かれるイクシオン)出ているが、より興味深かったのは画家が25歳の頃に描いた本作。左奥には炎上するトロイアを望み、森の手前の中央には逃れてきた人々が、そして右手には夕陽に染まる帆船が並んでいる。ルーベンスらしからぬ地味な配色と、決して量感に過ぎない人物表現がむしろ魅力的だった。

クロード・ロラン「クリュセイスを父親のもとに返すオデュッセウス」(1644)
ビロードのようにも輝く光が全体を覆う美しい一枚。イリアスに由来するドラマがロランの得意とする舞台的な港町に見事に描かれている。船から一筋の光が差し込んで来る様は神々しいほど。また両側に立ち並ぶ古典的な建築も堂々として立派だった。ちなみにオデュッセウスは船の前にいるそうだが、その辺の記載も会場キャプションにあればなお良かったかもしれない。
ヤーコプ・ファン・ライスダール「嵐」(1670)
暗雲漂う空の下、力強くうねる波に今にも呑み込まれようとする寒村が表されている。雲の合間から差す光は、もう間もなく嵐が終わることを暗示しているのだろうか。波に洗われた岸辺の草むらの激しいタッチは、まるでブラマンクの描く葦のようだった。
アドリアーン・コールテ「5つの貝殻」(1696)
大小様々な貝が暗がりに透き通る台の上に丁寧に並べられている。貝の表面の凹凸まで示した描写は実に細やかだが、やはりこれらの貝は貴重なものだったのだろうか。意味ありげにひび割れたグレーの台との対比が、静物画らしからぬ緊張感を絵に呼び込んでいた。
ヘリット・ダウ「歯を抜く男」(1630-35)
偽歯医者が大仰な様子にて男の歯を抜いている。大口を開けながら脚を踏ん張る男は、やはり痛みに耐えているからなのだろうか。もちろんダウと言えばこうした人物表現よりも、細部を顕微鏡で伺うほど精緻に描かれた事物の方が面白い。前に置かれたかごの表面の質感は、西美所蔵の「シャボン玉を吹く少年」と同様にリアルだった。

カルロ・ドルチ「受胎告知 天使」/「聖母」(1653)
ドルチの聖母を見るのは西美、東博所蔵のそれに続いて三作目。軽やかなブロンドの髪をなびかせ、ややあどけない様子にて手を前にやる天使と、ドルチカラーならぬ抜けるように澄み渡った青いスカーフを纏い、ひたすらに敬虔な趣にて受け止める聖母の美しさは甲乙付け難い。本展示のハイライト。

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール「大工ヨセフ」(1642)
イエスの左手を透かす蝋燭からもれる明かりが、この父子に表される慈愛を祝福する。ヨセフの逞しい腕や潤んだ瞳に、彼の父としての力強さを見る思いがした。ラトゥール展の記憶もよみがえった方も多いのではなかろうか。
以上です。
なおこの手の大型展では要注意の混雑状況ですが、これまでのところ土日の午後、とりわけ14時から15時前後に10分から20分程度の入場待ちの行列が出来ているそうです。明日からの三連休以降、また会期中盤へ向けて間もなく迎える桜のシーズン、そして大型連休中には激しい混雑となるのかもしれません。
ロングランの展覧会です。6月14日まで開催されています。
「ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画」
2/28-6/14
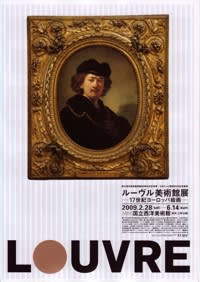
感想が遅くなりましたが、珍しくも初日に参戦してきました。国立西洋美術館で開催中の「ルーヴル美術館展 17世紀ヨーロッパ絵画」へ行ってきました。
副題の通り、ルーヴル所蔵の17世紀絵画(約70点)を俯瞰する展覧会です。うち60点が日本初公開とのことで、毎年の如く開催されるルーヴル展に食傷気味な方も、また新鮮であったのではないでしょうか。以下、惹かれた10点を挙げてみました。

アンブロシウス・ボスハールト(父)「風景の見える石のアーチの中に置かれた花束」(1619-21)
遠景には広い海辺を望むアーチに置かれた花束が精緻なタッチで表されている。爛れるように咲くチューリップの色鮮やかな表現、もしくは少し枯れ始めた葉、さらにはアーチの上にのる昆虫などの描写は極めて写実的。また古くなったのだろうか、花瓶の中の水が仄かな緑色を帯びていた。ちなみに油彩ながらもやや光沢感のある画肌は、支持体が銅板であるからなのかもしれない。

ル・ナン兄弟「農民の家族」
何ら変哲のない農民の姿が、まるで聖家族を思わせるほどに厳粛な雰囲気をたたえている。まるで舞台を飾るように横一線に並び、憂いをたたえた視線を前へ向ける様は、こちらの心をぐさりと突き刺してきた。彼らは一体、何を訴えているのだろうか。
17世紀スペイン派「法悦の聖フランチェスコ」(1650)
痛みをこらえつつ、激しいエクスタシーにも襲われる聖フランチェスコ。充血して虚ろな目の先には神が見えるのだろうか。ドクロや聖書などは比較的細かく描かれているが、突き刺して破けた衣服や背景のグレーはかなり荒削りだった。まるでエル・グレコのよう。
ペーテル・パウル・ルーベンス「トロイアを逃れる人々を導くアイネイアス」(1602-04)
ルーベンスの壮年期の大作も一点(ユノに欺かれるイクシオン)出ているが、より興味深かったのは画家が25歳の頃に描いた本作。左奥には炎上するトロイアを望み、森の手前の中央には逃れてきた人々が、そして右手には夕陽に染まる帆船が並んでいる。ルーベンスらしからぬ地味な配色と、決して量感に過ぎない人物表現がむしろ魅力的だった。

クロード・ロラン「クリュセイスを父親のもとに返すオデュッセウス」(1644)
ビロードのようにも輝く光が全体を覆う美しい一枚。イリアスに由来するドラマがロランの得意とする舞台的な港町に見事に描かれている。船から一筋の光が差し込んで来る様は神々しいほど。また両側に立ち並ぶ古典的な建築も堂々として立派だった。ちなみにオデュッセウスは船の前にいるそうだが、その辺の記載も会場キャプションにあればなお良かったかもしれない。
ヤーコプ・ファン・ライスダール「嵐」(1670)
暗雲漂う空の下、力強くうねる波に今にも呑み込まれようとする寒村が表されている。雲の合間から差す光は、もう間もなく嵐が終わることを暗示しているのだろうか。波に洗われた岸辺の草むらの激しいタッチは、まるでブラマンクの描く葦のようだった。
アドリアーン・コールテ「5つの貝殻」(1696)
大小様々な貝が暗がりに透き通る台の上に丁寧に並べられている。貝の表面の凹凸まで示した描写は実に細やかだが、やはりこれらの貝は貴重なものだったのだろうか。意味ありげにひび割れたグレーの台との対比が、静物画らしからぬ緊張感を絵に呼び込んでいた。
ヘリット・ダウ「歯を抜く男」(1630-35)
偽歯医者が大仰な様子にて男の歯を抜いている。大口を開けながら脚を踏ん張る男は、やはり痛みに耐えているからなのだろうか。もちろんダウと言えばこうした人物表現よりも、細部を顕微鏡で伺うほど精緻に描かれた事物の方が面白い。前に置かれたかごの表面の質感は、西美所蔵の「シャボン玉を吹く少年」と同様にリアルだった。

カルロ・ドルチ「受胎告知 天使」/「聖母」(1653)
ドルチの聖母を見るのは西美、東博所蔵のそれに続いて三作目。軽やかなブロンドの髪をなびかせ、ややあどけない様子にて手を前にやる天使と、ドルチカラーならぬ抜けるように澄み渡った青いスカーフを纏い、ひたすらに敬虔な趣にて受け止める聖母の美しさは甲乙付け難い。本展示のハイライト。

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール「大工ヨセフ」(1642)
イエスの左手を透かす蝋燭からもれる明かりが、この父子に表される慈愛を祝福する。ヨセフの逞しい腕や潤んだ瞳に、彼の父としての力強さを見る思いがした。ラトゥール展の記憶もよみがえった方も多いのではなかろうか。
以上です。
なおこの手の大型展では要注意の混雑状況ですが、これまでのところ土日の午後、とりわけ14時から15時前後に10分から20分程度の入場待ちの行列が出来ているそうです。明日からの三連休以降、また会期中盤へ向けて間もなく迎える桜のシーズン、そして大型連休中には激しい混雑となるのかもしれません。
ロングランの展覧会です。6月14日まで開催されています。
コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )
| « 「ジョアン・... | 「小杉放庵と... » |










何点か印象に残った絵画がダブっていました。
17世紀というくくりは結構面白いくくりだと思いましたが、展覧会側としても展覧会テーマをどうもってくるかに苦心したのだろうなぁと思ったもの確かです。
これからどんどん混雑しそうですね。。。桜の季節は上野には近寄れないかも。
>展覧会側としても展覧会テーマをどうもってくるかに苦心したのだろうなぁと思ったもの確か
そうでしたね。
見る側としてはルーブルなので名品展のつもりで行ってしまうのですが、
構成が意外と手が込んでいて驚きました。
>上野には近寄れない
同感です。来週末がピークでしょうね。しばらくは遠慮したいところです…。
はろるどさんの10選、興味深く思いました。
わたしと共通する作品が少ないところが、とても面白かったです。
ドルチの青は本当に綺麗でしたね。
それに天使がとても女性的な美貌で、そこにも惹かれました。
「風景の見える石のアーチの中に置かれた花束」
この絵はなんとなくマグリットを思い出してました。
シュールな雰囲気だと感じたのです。
写実的な筆致で、そのくせ現実感がないからそう感じるのかもしれませんが。
>10選、興味深く思いました。わたしと共通する作品が少ないところ
ありがとうございます。皆さんが思い思いに挙げられているのがまた面白いですね。趣向のカラーが良く出ます。
>マグリットを思い出してました。シュールな雰囲気
なるほどそうですね。花束と窓枠の向こうに広がる景色のアンバランスな対比がまた非現実な感じがします。
当時はどう受け止められたのでしょうね。
三連休の初っ端、朝一番に出かけました。
私は静物画が好きなので、「風景の見える石のアーチの中に置かれた花束」や「五つの貝殻」、
双眼鏡を持って、離れた場所から
じっと眺めていました。
カロル・ドルチ「受胎告知 天使」は初めてで
息をのむような美しさにうたれました。
「聖母」もすばらしい! そうだ帰りに常設に
あるのを見ようと、行ったのですが、もう違う
絵に変わっていて残念でした。東博でも秋にみま
したけど、このルーヴルのは圧巻でした。
こんばんは。コメントとTBをありがとうございます。
>静物画が好き
私も好きです。花の絵があったりするとなおさら見入ってしまいます。アーチの作品はどこかシュールでした。
>離れた場所
混雑していると近くでずっと見るのは叶いませんが、
双眼鏡があると便利かもしれませんね。
私も単眼鏡をそろそろ新調したいのですが…。
@すぴかさん
こんばんは。
>東博でも秋
このところドルチを見る機会が多いですよね。
一体何枚の作品があるのかも気になりました。
国内では無理かもしれませんが、ドルチの画業を回顧する展覧会というのもいつか見てみたいです。
見応えある作品を多数揃え、他のルーブル展と一線を画すという意気込みが伝わってくる内容でした。
それに引っ張られるのか、人出も順調ですね。
今度は如何にして空いてる頃合を探すかが悩みどころです。
>他のルーブル展と一線を画す
そろそろ新美のルーヴルも始まりますね。
そちらとの比較もまた面白そうです。
>空いてる頃合
やはり金曜夜間でしょうか。とりあえず今週末は避けた方が良さそうです。
事前にチラシで全作品を見せてしまうのですから
出展作品に自信を持っていた証。
フェルメール、ラ・トゥールら17世紀の画家たちを
「ヨーロッパ」という大きな枠組みで捉えようとする
ある種大胆な発想の展覧会でした。
混雑避け今一度。
>大胆な発想の展覧会
そうでしたね。賛否両論あれども、構成はかなり意欲的でした。
ルーヴルももう名品展はしたくないのかもしれませんね。
>混雑避け
同感です。