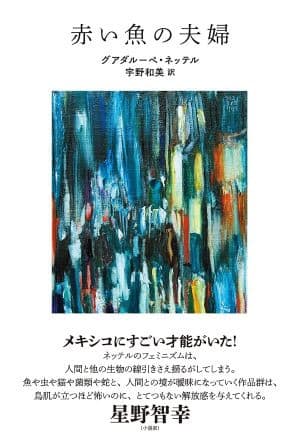新年度もみなさまに喜んでいただけるような講座をお届けしよう! そんな思いを胸に、私たちボランティアスタッフは、年初から事務局と共に企画を練っていたのですが、新型コロナウイルスの流行に阻まれ、仕方なく4月に予定していた講座を中止し、以降も開催を見合わせていました。いつになったらまた講座ができるのだろうと気になっていた今夏、ついに事務局から「オンラインで講座を再開しよう!」とのうれしい連絡があり、意気込んで準備を始めました。初めての試みとあって、開催にこぎつけるまでには、事務局の方々は大変苦労したようですが、私たちも微力ながらお手伝いし、当日は、自宅にて共同ホストとしてバックアップすることになりました。
9月19日、開始時刻15分前、無事に進行するかどきどきしつつ、参加者のみなさまが続々と入室していらっしゃるのをお迎えしました。今回、申し込んでくださったのはなんと141名! しかもそのうち80名が初参加で、海外から参加してくださる方も多くいました。そんな「洋書の森」の歴史を塗り替えるようなすごいイベントが始まるのだと興奮しながら、画面を見守っていると、講師の酒寄進一さんとゲストの吉川美奈子さんが登場し、事務局から開会の挨拶があり、いよいよ講座がスタートしました。
今回の講座のタイトルは『文芸翻訳♡字幕翻訳~ふたつの顔をもつ物語をめぐって』。初めは、ドイツ語の文芸翻訳をされている酒寄先生の講演です。文芸翻訳家になるまでの過程や、翻訳家になってからどんなことを心がけているかについてお話ししていただきました。文芸翻訳家になるにあたっては、大学の卒論のテーマがグリム童話だったことが役立ったそうで、「そうした引き出しがあったからこそ文芸翻訳の仕事をもらえた。みなさんも、本をたくさん読んだり言葉をいっぱい学んだりして、いろいろな引き出しを作っておこう」というアドバイスをいただきました。実際に翻訳家になってからのお話で特に興味深かったのは「持ち込み」についてです。大変ありがたいことに、後半の対談でも話題となる『キオスク』のレジュメの一部を披露してくださいましたし、「企画を持ち込んで断られても、出版社やラインアップと合わなかっただけかもしれないからあきらめずに温めておくように」とのお言葉には、筆者自身、とても励まされました。
次に、ドイツ語の字幕翻訳をされている吉川先生の講演です。まずは、「字幕翻訳とは」といったテーマで、どんな作業をするか、どんなルールがあるかについてわかりやすく説明してくださいました。字幕翻訳をするにあたっては黒子に徹するのが大事で、常に「透明な訳文」を心がけていらっしゃるそうです。仕事を得るには、出版と違って持ち込みはないので、やりたい作品があれば、「来い、来い」とひたすら念じるのが効果的なのだとか。これならすぐにでも実践できそうですね。そして、「これまでの翻訳稼業をふりかえる」というテーマで、字幕翻訳家になるに至った経緯についてもお話ししてくださいました。字幕翻訳の仕事をするうえで何よりも心がけているのは、「締め切り厳守・誠実であること」だそうです。簡単なようで難しいことかもしれません。
後半は、酒寄先生と吉川先生の対談です。フェルディナント・フォン・シーラッハの『コリーニ事件』、ローベルト・ゼーターラーの『キオスク』(映画の邦題は『17歳のウィーン フロイト教授 人生のレッスン』)という二つの作品を、「原作の翻訳」と「映画の字幕翻訳」という異なる形で手がけたお二方に、どんな思いでこの作品に向き合い、どんな工夫をされたのか、じっくり語り合っていただきました。そして、翻訳者にとって永遠のテーマともいえる「役割語」「時制」などについても触れていただきました。お二方のお話は尽きそうもなく、いつまでもうかがっていたいと思うほど楽しい時間が続きましたが、残念ながら終了時刻が迫り、最後は受講している方々に向けて、お二方から「作品に愛ある訳を。作品を好きになって訳せば、その作品にとっても自分にとっても幸せだから」というすてきなメッセージをいただきました。そんな作品を見つけたいものです。
酒寄先生、吉川先生、こうした状況にもかかわらずすばらしい講義をしていただき、ほんとうにありがとうございました。そして受講してくださったみなさまにも改めてお礼申し上げます。お見苦しいところもあったかと思いますが、この反省点を生かし、次回の開催に向けて準備を進めてまいりますので、またご参加いただけるとうれしいです。
次回は、今年4月に登壇していただくことになっていた夏目大先生をお招きする予定です。開催日時は11月28日(土)15時より。引き続きオンライン開催となります。詳細が決まり次第ご案内いたしますので、ご予定を空けてお待ちください。
今後もみなさまに楽しく学んでいただけるようなイベントを企画していくつもりですので、再始動した「洋書の森」をどうぞよろしくお願いいたします。